| はやし浩司のメインHP | 電子マガジン総合INDEX |
| 2009年 10月号 |
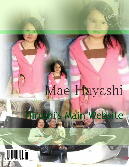 |
 |
| |
|
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 30日号
================================
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page028.html
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●毎日数万個!(脳の謎)
++++++++++++++++++
毎日、数万個の神経細胞(ニューロン)が、
死滅しているという。
数万個だぞ!
……といっても、人間の脳の中には、1000億個もの
ニューロンがあるので、あわてて心配しなくてもよい。
仮に、100年生きたとしても、
数万x365x100=数万x約4万で……?
サッと暗算できなくなった。
私の神経細胞も、かなり減ってきたらしい。
で、指を折りながら計算してみると、約10億個という数字が出てきた。
1000億個もあるのだから、10億個くらい減っても、どうということはない。
少し安心したところで、つぎの話。
++++++++++++++++++
●再生しない神経細胞(ニューロン)
脳の神経細胞は死滅する一方で、再生しない。
もちろん、ふえることもない。
理由は簡単。
再生したり、ふえたりしたら、たいへんなことになる。
再生したり、ふえたりするたびに、その人の神経細胞は新しくなり、人格そのものまで変
化してしまうかもしれない。
「10年前と今年では、まるで別人のよう」では、困る。
(実際、そうなる人もいるには、いるが……。)
つまり脳は、その人の同一性を保つために、神経細胞を再生したり、ふえたりしないよ
うにしている。
●が、もしふえたら……
が、もしふえたら……。
ここからが私の得意分野。
もし神経細胞がふえたら、どうなるか?
そんな仮定を頭の中でしてみる。
が、脳は頭蓋骨によって取り囲まれているから、容量には限界がある。
約1000億個が限度ということになる。
そういう脳が、神経細胞をふやすとしたら、古い神経細胞から順に、除去していかなけ
ればならない。
しかしこのとき同時に、古い神経細胞がもっていた、もろもろの情報は、そのまま失われ
ることになる。
再生するばあいも、同じ問題が起きる。
●電話回線
たとえば電話回線で考えてみよう。
現在、053−452−xxxxへ電話をかければ、私の事務所につながる。
日本中のどこからかけても、つながる。
電話回線網が、できあがっている。
が、もしそのときある地域の、ある一部の電話回線網を切り取ってしまったとしたら、
どうだろうか。
その地域の電話が不通になることはもちろん、その地域を経由している電話回線も、すべ
て不通になってしまう。
そこで「再生」ということになるが、電話回線のばあいは、工事屋の人たちが配線図を
見ながら、新しく電話回線網をつなぎ合わせてくれる。
しかし人間の脳の中には、そういう機能は、ない。
へたをすれば、そのまま混線してしまうかもしれない。
●神経細胞がふえたら……
新しい神経細胞がふえたばあいも、同じ問題が起きる。
先にも書いたが、脳の容量には限界がある。
古い神経細胞が除去されるたびに、電話回線のつなぎ合わせのようなことをしなければな
らない。
もしそれをしなかったら、新しい神経細胞は新しい情報を蓄え、独自の働きをするように
なる。
つまり脳の中が、メチャメチャになってしまう。
新しくピアノを弾くことができるようになるかもしれないが、それまでに蓄えた、文を
書く能力を失ってしまうかもしれない。
あるいは楽譜をアルファベットを使って書くようになってしまうかもしれない。
だから脳は、一方的に、神経細胞を死滅させるしかない。
となると、ここで重大な疑問が生ずる。
毎日数万個というが、脳はどういう基準に従って、その数万個を選んでいるのか?……
という疑問である。
またどういう神経細胞が、死滅していくのか?
そのメカニズムがわかれば、逆に死滅するのを阻止することもできるはず。
もしそれができれば、人間は、生涯、1000億個の神経細胞を保持することができるは
ず。
またそれは可能なのか?
(疑問1)どういう神経細胞が死滅するのか。
(疑問2)死滅していく神経細胞を阻止する方法はないのか。
●死滅する神経細胞
常識的に考えれば、「使わない神経細胞は死滅する」ということになる。
しかし使わない神経細胞は、いくらでもある。
人によっては、脳の大部分を使っていない人もいる。
そういう人の神経細胞は、どうなるのか。
1日、数万個ではなく、数10万個の神経細胞が死滅していく人だっているかもしれない。
恐らく脳科学者たちは、そのあたりのことを知っているかもしれない。
たとえば「古い神経細胞から、死滅していく」とか、など。
(このばあいも、つぎの疑問が生まれる。
人間のばあい、乳幼児期にすでに1000億個の神経細胞をもつと言われている。
もしそうなら、「古い」とか「新しい」とかいう言葉すら、意味をもたなくなる。)
この世界は、おもしろい。
本当におもしろい。
今夜は高校生たちが私の教室に来るので、こんな話を余談の中でしてみたい。
そうそうついでに付記するなら、辺縁系の中にある海馬(かいば)の中の神経細胞だけは、
生涯、ふえつづけるのだそうだ。
海馬といえば、短期記憶の中枢部。
それについては、また別の機会に調べてみたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 神経細胞 ニューロン 神経突起 シナプス)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【走馬灯】(ぼくの少年時代)(My Boyhood Days)
●ゴム靴
ぼくの少年時代は、あのゴム靴で始まる。
黒いゴム靴で、歩くとキュッキュッという音がした。
子どもながらに安物ということが、よくわかった。
しばらく歩いていると、足の皮がこすれて、むけた。
ぼくが小学2年生か、3年生ころのことではなかったか。
やがてその靴ははかなくなったが、どういうわけか、「少年時代」という言葉を聞くと、あ
のゴム靴を思い出す。
当時は、靴下をはいている子どもは、ほとんどいなかった。
それでよけいに、はきにくかったのではなかったか。
●蛍光灯
そのゴム靴をはいて、近くの先生の家に遊びに行った。
当時としてはハイカラな家で、引き戸を開けて中へ入ると、そこにソファが置いてあった。
白い布製のカバーが、かかっていたように思う。
で、そのときは蛍光灯を見に行った。
「熱くない電気がある」と言うから、みなで、それを確かめに行った。
当時は、「電気」つまり、「電灯」というと、裸電球が当たり前で、そのときぼくは、はじ
めて蛍光灯というのを見た。
その蛍光灯は、家の一番奥にあった。
記憶はそこでやや途絶えるが、ぼくは触っても熱くない電気に驚いた。
それに明るく、色も白かった。
そのときゴム靴をはいていったから、ゴム靴をはいたのは、小学2年生のときというこ
とになる。
その先生というのが、ぼくが小学1年生と2年生のときの担任の先生だった。
名前を高井先生と言った。
●遊び場
あのころの町の様子は、よく覚えている。
目を閉じただけで、あのころの街並みが、走馬灯のように見えてくる。
ぼくたちの遊び場は、近くにある円通寺という寺だった。
当時のぼくには、広い境内に見えた。
その境内を出ると、角にお好み焼き屋があった。
靴屋もあった。
その横が菓子屋で、つづいて床屋・・・。
ぼくの家は、1ブロック離れた角にあった。
見る角度のよって、立派に見えたり、反対にみすぼらしく見える、不思議な家だった。
しかし寺の境内から帰る道から見るぼくの家は、それなりに立派に見えた。
●女たらし
当時のぼくたちは、女の子とは遊ばなかった。
女の子と遊ぶヤツは、「女たらし」と呼ばれて、仲間に軽蔑された。
ぼくも軽蔑した。
だから、女の子と遊ぶときは、内緒で遊ぶか、ずっと年上の女の子と、ということになる。
その年上の女の子というか、女の人に、「けいちゃん」という人がいた。
当時、高校生くらいではなかったか。
けいちゃんは、いつもぼくを自転車に乗せて、あちこちへ連れていってくれた。
ぼくの家のはす向かいにあった、薬屋の女の子だった。
今でもアルバムの中には、けいちゃんの写真は、何枚か、残っている。
●喧嘩
ぼくは、外では、明るく朗らかな子というイメージで通っていた。
よくしゃべり、よくはしゃぎ、よく笑った。
そうそう喧嘩もよくした。
気が小さく、弱いくせに、そのときになると、肝っ玉がすわる。
今でもそうだが、何か気になることがあると、即、解決しないと気がすまない。
それでよく喧嘩をした。
どんな形であれ、決着は早くつける。
それが今でも処世術として、ぼくの身についている。
だからみな、こう言った。
「林の浩ちゃん(=ぼく)と喧嘩すると、こわい」と。
ぼくは一度喧嘩を始めると、とことん、した。
相手を、相手の家の奥まで追いつめて、した。
●さみしがり屋
それだけぼくの心は荒れていたことになる。
ぼくに対して好意的な人に対しては、明るく、朗らかに・・・。
しかしそうでない人に対しては、容赦しなかった。
どこか独裁者的な子どもを想像する人もいるかもしれないが、事実は反対。
ぼくは、さみしがり屋だった。
自分でもそれがはっきりとわかるほど、さみしがり屋だった。
寝るときも、母のふとんの中にもぐりこんだり、祖父のふとんの中にもぐりこんで寝て
いた。
あるいはいつもだれかそばにいないと、不安だった。
だからだれに対しても、シッポを振った。
相手に合わせて、その場で、自分を変えた。
●集団教育
そういうぼくだから、その分だけ、気疲れをよく起こした。
多分、そのころのぼくを知る人には信じられないかもしれないが、ぼくは集団教育が苦手
だった。
運動会にしても、遠足にしても、集団で同じように行動するということが、苦手だった。
嫌いではなかったが、居心地はいつも悪かった。
が、先にも書いたように、だからといって、ひとりでいることもできなかった。
心理学の世界には、「基本的信頼関係」という言葉がある。
その基本的信頼関係の構築ができなかった子どもということになる。
わかりやすく言えば、人に対して、心を開くことができなかった。
もっと言えば、人を信ずることができなかった。
いつも相手の心の裏を見た。
やさしい人がいたとしても、それを素直に受け入れる前に、その下心を疑った。
●粗製濫造
原因は、「母子関係の不全」ということになる。
しかしこんな言葉は、ずっとあとになってから知ったことで、当時のぼくに、それがわか
るはずもなかった。
またそれが原因で、当時のぼくがそうなったなどとは、知る由もなかった。
ぼくはぼくだったし、母は、母だった。
あえて言うなら、当時は、そういう時代だった。
戦後の混乱期で、家庭教育の「か」の字もなかった。
あるにはあったのだろうが、今とは比較にならなかった。
たとえば家族旅行にしても、ぼくの家族のばあい、家族旅行などといったものは、ただの
1度しかなかった。
小学6年生のときで、みなで伊勢参りをしたのが、最初で最後。
粗製濫造というか、ぼくたちは、戦後のあの時代に、濫造された。
ひらたく言えば、ほったらかし。
それがよかったのか、それとも悪かったのか・・・?
ぼくも含めて、当時の子どもは、みな、そうだった。
●父の酒
つぎに少年時、代というと、「酒」の話になる。
父は、酒癖が悪く、酒を飲むと、人が変わった。
これについては、もう何度も書いた。
が、おかしなもので、当時のぼくを知る従兄弟たちはこう言う。
「浩君(=ぼく)の家庭は、たいへん幸福そうに見えた」と。
そう言われるたびに、ぼくは、「フ〜ン?」とか、「そうかなあ?」とか、思う。
まわりの人たちには、そう見えたかもしれない。
しかしあの時代をいくら思い起こしても、明るく楽しい思い出は、ほとんど浮かんでこな
い。
理由は、やはり「酒」ということになる。
父は、数日おきくらいに酒を飲み、家の中で大声を出したり、暴れたりした。
それがぼくが、5、6歳のころから、中学3年生くらいまでつづいた。
●兄弟
ぼくには、当時、1人の兄と、1人の姉がいた。
もう1人、兄がいたが、ぼくが3歳くらいのときに死んだ。
日本脳炎が原因だった。
母が言うには、暑い夏の日に、父が荷台に兄を乗せ、自転車で数時間もかけて母の在所
へ行ったのが原因ということだった。
ぼくが覚えているのは、その日、つまり葬式の日、土間に無数の下駄や靴が、散乱してい
たということだけ。
兄との思い出は、まったくといってよいほど、ない。
歳が離れていたこともある。
だから今でも兄弟と言えば、兄と姉ということになる。
●家族
兄弟との接触も少なかったが、父や母との接触は、もっと少なかった。
こんな話をしても、だれも信じないかもしれないが、生涯において、ぼくはただの一度も
父に抱かれたことがない。
手を握ってもらったこともない。
結核を患ったこともあるが、ほかにも深刻な理由があった。
しかしそれをここに書くことは、できない。
その代わり、祖父がぼくの父がわりなってくれた。
祭りに行っても、祖父は、最初から最後まで、ずっと、一度もぼくの手を放さなかった。
・・・ということで、何からなにまで、おかしな家族だった。
しかしそれがぼくの家族であり、ぼくは、ほかに家族を知らなかった。
家族というのは、そういうものと思っていた・・・というよりは、(それ)を、ぼくは受け
入れるしかなかった。
それがぼくの家族だった。
●子ども時代
今でもときどき、不思議に思うことがある。
とくに10歳とか、12歳の子どもを見ると、そう思う。
「ぼくにも、同じような時代があったはずだが・・・」と。
当時のぼくは、当然のことながら、(子ども)だった。
しかし記憶のどこをさがしても、(子どもとしてのぼく)が、浮かび上がってこない。
子どもらしく、父や母に甘えたという記憶も、ほとんどない。
父や母が、ぼくを子どもとして、扱ってくれたという記憶も、ほとんどない。
あるのは、ぼくをいつも子ども扱いしたこと。
(子ども扱い)というのは、ぼくを人間としてではなく、言うなればペットのようにしか
扱ってくれなかったこと。
あるいはモノ?
道具?
ぼくの意思や人格など、父や母の前では、腸から出るガスのようなものだった。
父や母が、ぼくの話に静かに耳を傾けてくれたことは、ほとんどなかった。
家族の談話など、そういうものがあることさえ知らなかった。
だからぼくにとって父や母は、一方的に命令するだけの存在だった。
口答えすれば、・・・というより、当時のぼくの家庭では、子どもが親に口答えするなどと
いうことは、考えられなかった。
親は、いつも絶対だった。
とくにぼくの父と母は、G県に本拠を置く、M教という、(親絶対教団)の熱心な信者だっ
た。
母ですら、ぼくが何かを口答えをすると、「親に向かって、何てことを言う!」などといっ
て、叱った。
「親に歯向かうと、地獄へ落ちる」と、よく脅された。
ぼくにとって、親というのは、そういう存在だった。
●恩着せ
父や母の子育ての基本は、(恩着せ)だった。
ことあるごとに、父や母は、ぼくにこう言った。
「産んでやった」「育ててやった」「言葉を教えてやった」と。
ぼくはそういう言葉を、耳にタコができるほど聞かされた。
が、何よりも恐ろしい言葉は、「〜〜をしなければ、自転車屋を継げ」というものだった。
ぼくは兄を見て育っているから、自転車屋というのは、恐怖以外の何ものでもなかった。
兄は、まるで奴隷のように、家の中では扱われていた。
「自転車屋になる」ということは、ぼくも、その奴隷になることを意味した。
●ぼくの夢
ぼくにもいくつかの夢があった。
「夢」と実感したというわけではなかったが、ぼくは、パイロットになりたかった。
いつも模型の飛行機を作って遊んでいた。
もう少し幼いころには、ゼロ戦のパイロットになりたかった。
が、中学校へ入学するころから近視が始まり、断念。
「近視の者はパイロットにはなれない」というのが、当時の常識(?)だった。
つぎにぼくはいつしか、大工になることを考えるようになった。
ものづくりは好きだったし、木工には、かなりの自信があった。
学校から帰ってくると、店の中で、木材を切ったり、金槌で叩いたりして、いろいろなも
のを作った。
小学5年生か、6年生のときには、組み立て式ボートというのを、作ったことがある。
手先も器用だった。
中学生になるころには、そこらの大工よりも、のこぎりや、かんなを、うまく使いこなす
ようになっていた。
だからぼくの身のまわりには、大工道具が、いつも一式そろっていた。
●ドラマ
こうした断片的な記憶は、無数にある。
しかしそれをつなげるドラマというのが、ない。
ドラマらしきものはあるが、どれも中途半端。
映画でいうような結末がない。
ないまま、終わっている。
子ども時代の思い出というのは、そういうものか。
いや、そのつど小さなドラマはあったのかもしれない。
クラス一の乱暴者グループと、ひとりで対決した話。
円通寺という小さな山をはさんで、山向こうの子どもたちと戦争ごっこをした話。
ほとんど毎日、学校から帰るときは、寄り道をして遊んだ話、などなど。
書き出したらキリがない。
しかしドラマはない。
こま切れになった映画のフィルムのよう。
言い換えると、ぼくは、あの当時、街角のどこにでもいるような、1人の子どもに過ぎな
かった。
よごれた下着を着て、当て布をした半ズボンをはいて、ジャイアンツのマークの入った野
球帽をかぶった、1人の子ども。
何か特別なことをしたわけでもない。
そんな子どもに過ぎなかった。
●母の在所
そんなぼくにも、楽しみはあった。
夏や冬、春などの休みのときは、母の在所(=実家)に行った。
そこはぼくにとっては、別天地だった。
従兄弟たちと山の中を歩き、川で泳いだ。
夜は、伯父たちの話す昔話に耳を傾けた。
今でもそんなわけで、「故郷」というと、自分が生まれ育ったあのM町ではなく、母の在
所のあった、I村のほうを先に思い出す。
川のせせらぎの音、近くの水車が、粉をつく音、それに風の音。
つんとした木々が放つ芳香も、好きだった。
夕方になると、ご飯を炊くにおいがする。
魚の缶詰を切る音がする。
ぼくたちは、いつも腹をすかしていた。
だから、何を食べてもおいしかった。
もちろん最高のぜいたくは、川でとれた鮎(あゆ)。
ときどきウナギもとれた。
当時は、アマゴ(=やまめ)や、ウグイには、目もくれなかった。
川魚といえば、鮎。
鮎の塩焼き!
●父
父の酒乱は、ぼくが高校生に入るころまでつづいた。
そのころ父は肝臓を悪くし、思うように酒を飲めなくなった。
たぶん悪酔いをするようになったのだと思う。
酒の量が減った。
家で暴れることも、少なくなった。
しかし父は、もともと体の細い人だったが、ますますやせていった。
一度だが、そんな父と殴り合いの喧嘩をしたことがある。
ぼくが中学3年生のときのことである。
体は、すでにぼくのほうが大きかった。
家の中で暴れる父に向かって、無我夢中で頭から体当たりをしていった。
そのあとのことは、よく覚えていない。
どこをどうしたという記憶はないが、あとで聞いたら、父はそのため肋骨を何本か、追っ
たということだった。
もちろんぼくには、罪の意識はなかった。
が、その日を境に、父は、ぼくの前ではおとなしくなった。
ぼくを恐れるようになった。
●みな、同じ
おとなになって、いろいろ話を聞くと、ぼくの家庭だけが、特別だったということでも
ないようだ。
当時は、その程度の話は、どこの家庭にもあった。
たとえばぼくの祖父母は、今で言う、「できちゃった婚」で、結婚した。
祖父には、たがいに結婚を約束した女性がいた。
が、ある日、祖父は別の女性と遊び、子どもができてしまった。
それがぼくの祖母であり、そのときできたのが、ぼくの父だった。
それがぼくの家の原点だったかもしれない。
祖父母の夫婦喧嘩は絶えなかった。
父は父で、不幸な家庭で生まれ育った。
そしてあの戦争。
終戦。
その2年後の昭和22年、ぼくは生まれた。
●ふつうでない家系
「林家」と「家」をつけるのも、おこがましい。
が、ぼくの家は、それでも、ふつうではなかった。
それから62年。
振り返ってみると、父方の「林家」にしても、母方の「N家」にしても、それぞれが例外
なく、深刻な不幸を背負っている。
ぼくの家も、長男が日本脳炎で死去。
つづいて兄、Jが生まれ、姉、Mが生まれた。
そのあともう一人兄が生まれたが、(流産)ということで、処理されてしまった。
ぼくはそのあと生まれた。
この程度の話なら、どこの家系にもある話だが、ぼくの家系はちがう。
例外なく、どの親族も、みな、深刻な不幸を背負っている。
が、それについてはここには詳しく書けない。
それぞれがそれぞれの不幸を懸命に隠しながら、あるいはその苦しみと闘いながら、今で
もがんばっている。
●少年時代
ときは今、ちょうど秋。
稲刈りのシーズン。
郊外を車で走ると、すずめの集団が、ザザーッと空を飛ぶ。
言うなれば、あの集団。
あの集団こそが、ぼくの少年時代ということになる。
個性があったのか、なかったのか。
どこに(ぼく)がいたかと聞かれても、その(形)すら、よく見えてこない。
近所の人たちにしても、そうだろう。
学校の先生にしても、そうだろう。
ひょっとしたら、父や母にしても、そうだったかもしれない。
ぼくは、すずめの集団の、その中の一羽に過ぎなかった。
当時は、そういう時代だったかもしれない。
町のどこを歩いても、子どもの姿があった。
通りでは、どこでも子どもたちが遊んでいた。
子どもの声が聞こえていた。
……一度、ここで走馬灯の電源を切る。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 「ぼくの少年時代」 少年時代 はやし浩司の少年時代)
●巨大な台風
+++++++++++++++++
超巨大な台風が、現在、この日本に
向かって進行中!
昨日の報道によれば、中心部の気圧は
何と910ヘクトパスカル!
+++++++++++++++++
異常気象は、日本以外の国の話かと思っていた。
が、とうとうこの日本にもやってきた。
それが今度の台風18号。
昨夜ネットで調べてみたら、中心部の気圧は、何と910ヘクトパスカル!
「910」!
「910」という数字は、私の記憶の中にはない。
「950」とか「960」とかいう数字までなら、聞いたことがある。
が、「910」はない。
常識をはずれている!
その上、予想進路を見て、ドキッ!
昨夜の予想によれば、紀伊半島あたりから上陸し、東海地方を横断するコース。
もしそうなら、伊勢湾台風並みの、あるいはそれ以上の被害が心配される。
何とか東へそれてくれればよい。
今日は、10月6日。
10月8日、つまりあさっての午後9時ごろ、予想通りなら、東海地方を直撃。
今日と明日は、その対策で忙しくなりそう。
みなさんも、くれぐれも、ご注意ください。
Hiroshi Hayashi++++++++Oct. 09+++++++++はやし浩司
●「スティグマ」
++++++++++++++++++
今朝は、「スティグマ」という言葉について
学習した。
差別につながる、その人の客観的な属性を、
「スティグマ」という。
たとえば街の中を歩いてみる。
いつもと変わりない風景。
そこへ少し見慣れない一行が歩いてやってくる。
彼らの話す言葉を聞いて、彼らが、中国人で
あることを知る。
とたん、ちょっとした緊張感が走る。
彼らに対する緊張感もあるが、同時に、彼らも
また私を見て、同じような緊張感をもつに
ちがいない。
それが逆に、私の心に伝わる。
私も、若いころ、香港や台湾で、私はいろいろな経験を
した。
だまされたことも多い。
意地悪されたこともある。
「中国人」というだけで、いろいろなイメージが
心に浮かぶ。
ばあいによっては、それが差別意識となってはねかえってくる。
その「中国人」というのが、客観的属性ということになる。
「スティグマ」というのは、体につけられた「刻印」を
いう。
昔、ギリシアでは、その人を社会的に差別するために、
その刻印を体に焼いてつけた。
一度その刻印をつけられると、その人のあらゆる部分まで
合わせて、否定されてしまう。
それが「差別」ということになる。
たとえば以前、手鏡を使って女性のスカートの下をのぞいた大学の
教授がいた。
行為そのものは許されないものだが、しかしそのためその
教授は、「変質者」という刻印を焼きつけられてしまった。
ほかのすぐれた部分まで、否定されてしまった。
「スティグマ」というのは、それをいう。
+++++++++++++++++++++
●実験
2009年10月6日、私は「スティグマ」について学習した。
いくつかの文献を読み、自分なりに解釈し、理解した。
しかしこの知識は、いつまで記憶に残るだろうか?
それが今日の実験ということになる。
今までの経験では、1、2か月ぐらいなら、何とか記憶に残るだろう。
しかし半年は、もたない。
半年後に、「スティグマって、何?」と聞かれたら、たぶん、私はこう答えるだろう。
「何だったけなア? 聞いたことがある言葉だな」と。
自分で自分の脳みそが、信用できない。
考えてみれば、これは深刻な問題である。
●刻印
「スティグマ(刻印)」という言葉を学んで、私は別の心で、『ダラカ論』に似ていると
感じた。
スティグマ、イコール、『ダカラ論』ではない。
しかし『ダカラ論』も、人にラベルを張ることによって、差別する道具として、よく使わ
れる。
「お前は、男だから……」「お前は、本家の息子だから……」と。
「ダカラ論」は、そのあと、「〜〜スベキ」「〜〜のハズ」と、『ベキ論』『ハズ論』へと
つながっていく。
ばあいによっては、それが「差別」となることもある。
実のところ、私も、長い間、この『ダカラ論』に苦しんだ。
(苦しんだというより、いじめられた?)
差別という差別ではないが、しかし私はそのつど、こう反発した。
「だからといって、それがどうしたの?」と。
●中身を見る
日本人は元来、地位や肩書によって、相手を判断する。
あるいは少し昔前までは、家柄によって判断した。
今でも、この日本は、その延長線上にある。
たとえば上下意識。
マスコミの世界では、知名度によって、上下関係が決まる。
そのまま「上」になって、国会議員や知事になっていく人さえいる。
つまり日本人に何が欠けているかといえば、(相手を中身を見て判断する)という能力では
ないか。
「スティグマ」という言葉を使うなら、「スティグマ」だけで、相手を判断する。
そしてその人のもつ、よい面まで、否定してしまう。
●文化性の問題
要するに相手を、中身を見て判断できるかどうかは、その国民の文化性の問題というこ
とになる。
文化性が高ければ高いほど、その国民は、相手の中身を見ることができる。
そうでなければそうでない。
表面的な部分だけを見て、判断する。
あるいは自分の経験だけをもとに、相手を判断する。
言い換えると、私やあなた自身が、いかに相手の中身まで見ることができるかという問
題につながる。
それができる人のことを、文化性の高い人といい、そうでない人を、低い人という。
が、これは簡単なことではない。
どうしてもスティグマに左右されてしまう。
つまり、自分の文化性を高めようと考えるなら、スティグマと闘う。
そういう努力を怠ってはいけない。
……ということで、スティグマの話はここまで。
さて、この記憶はいつまでつづくか。
実験開始!
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 スティグマ 刻印 刻印論 人間の価値 中身)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
MMMMM
m | ⌒ ⌒ |
( ̄\q ・ ・ p
\´(〃 ▽ 〃) /〜〜
\  ̄Σ▽乃 ̄\/〜〜/
\ : ξ)
┏━━┻━━━━┓
┃来月もよろしく┃
┃はやし浩司 ┃
┗━━━━━━━┛
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 28日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page027.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
***************************************
HAPPY BIRTHDAY TO ME, Hiroshi! I am 62 years old now!
******************************************************************************
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【人間の多様性について】
●人間の弱さ
+++++++++++++++++
欲望と理性が真正面からぶつかったら、どうなるか。
ふつう、理性に、勝ち目はない。
欲望はそれほどまでに強力で、根が深い。
とくに性欲においては、そうである。
どんな高徳な聖職者でも、あるいは高邁な
哲学者でも、たとえば性欲の前では、ひとたまりもない。
それなりの仮面をかぶることはできても、
仮面は仮面。
他人の目を気にした、仮面。
「私はそういうことには興味はありません」というような
顔をしているだけ。
……こう断言するのは、たいへん危険なことかもしれない。
中には、「私はそうでない」と反論する人もいるかも
しれない。
しかしそういう人は、まず、自分の肉体と精神の健康を
疑ってみたほうがよい。
あなたの肉体と精神が健康であるなら、もう一度、改めて、ここに
断言する。
欲望と理性が真正面からぶつかったら、どうなるか。
ふつう、理性に、勝ち目はない。
++++++++++++++++++++++++++++
●脳の構造
もし前頭連合野の働きが、脳全体をコントロールできるとするなら、
うつ病も含めて、もろもろの精神病は、そのまま解決する。
アルコール中毒も、ニコチン中毒も、そのまま解決する。
依存症もなければ、うまくいけば、人と人との争いもなくなる。
逆説的に考えるなら、そうでないから、そうでない。
前頭連合野のもつ力は、それほど強くない。
アルコール中毒ひとつとっても、それから抜け出るのは容易なことではない。
それがそのまま人間の精神力の限界ということになる。
前頭連合野の限界ということになる。
が、それにもし、性欲が理性でコントロールできるようなものであるとするなら、
人類は、とっくの昔に絶滅していたということになる。
人間がもつ臓器の中で、あれほどまでに不潔で、悪臭の漂う場所はない。
いくらその異性が好きになったとしても、もし理性のコントロールが働いているなら、
あの部分だけは、手で触れるとしても、最後の最後。
できるなら、見るのも避けたい。
そんな場所に、何と、種族存続のための、最重要器官が集まっている。
快楽の中心点になっている。
●「魔が差す」
少し前、手鏡を使って、女性のスカートの中をのぞいていた、どこかの教授が
いた。
それで有罪になったと思っていたら、今度は、電車の中で痴漢行為を働いたという。
その前にも、何かの事件で、一度、逮捕されている。
何もその教授の行為を弁護するつもりはない。
ないが、しかしどこのだれが、そういう教授を、「石をもって、打てるか」?
またそういうことをしたからといって、その教授がもつ、ほかのすぐれた部分
まで、否定しまうのも、どうかと思う。
その教授にしても、99・99%の時間は、教授として、師弟の指導に
尽力していたにちがいない。
すばらしい才能と能力に、恵まれていた。
彼が説いていた経済理論は、一級のものであった。
が、残りの0.01%の部分で、「魔が差した」。
●私だって……
「私だって……」という言い方をすると、誤解があるかもしれない。
しかし私は、けっして聖人ではない。
ふつうにスケベだし、スケベなこともたくさんしている。
頭の中は、この年齢になっても、スケベでいっぱい。
むしろ私は、生まれも育ちも、よくない。
動物的で、野蛮。
「魔が差す」という言葉からもわかるように、ほんの一瞬のスキが、私の
人生を狂わすということも、私のばあい、ありえないことではない。
たとえば私は、よくこんなことを考える。
●もし政治家だったら……
私が政治家だったとする。
その私のところへ、1人の土建業者がやってきた。
そして机の上に、1000万円の現金を積んだとする。
そしてこう言った。
「X町の土木部長に、よろしく」と。
そのときのこと。
だまってうなずけば、そのお金は自分のものになる。
土建業者は、何も言わず、その場を去る。
私なら……?
この先のことは書かないが、多分、みなさんと同じような行動を取ると思う。
●欲望
人間が本来的にもつ弱さというのは、人間自身がもつ、欠陥と考えてよい。
あるいは、本来、人間というのは、そういう(動物)であるという前提で、考えたらよい。
つまり人間は知的な意味で、格段の進化を遂げたが、その一方で、それ以前の
動物的な部分を残してもっている。
それが悪いというのではない。
それがあるからこそ、人間は、子孫を後世に残すことができる。
誤解してはいけない。
性欲といっても、もろもろの(欲望)のひとつにすぎない。
が、そうした欲望を、すべて否定してしまったら、残された道はただひとつ。
人類は、そのまま絶滅する。
●欲望のない世界
子どもは人工授精によって生まれ、それ以後は人工飼育器の中で育てられる。
欲望は否定される。
もちろん人間は、去勢され、性欲そのものを失う。
……話が少し極端になってきたが、欲望を否定した世界では、そうした形で、
子孫を残すしかない。
すべての人間は平等で、競争もなければ、もちろん争いもない。
手鏡で、女性のスカートの下をのぞく人もいなくなるが、同時に、経済の研究を
する学者もいなくなる。
話が入り組んできたが、平たく言えば、善があるから悪があり、悪があるから善が
あるということ。
その2つがつねにぶつかりあうから、そこからドラマが生まれる。
人間がなぜ生きているかといえば、そこにすべての目的が集約される。
●人間の中味
犯罪にもいろいろある。
それによって起こる事件にも、いろいろある。
しかし私は、最近、こんな経験をした。
故郷のM町の民芸館の中を見て回っているときのこと。
そこにどこか顔なじみに男がいた。
中学時代の同級生である。
彼のことは、よく知っている。
親しくはなかったが、よく知っている。
彼は中学を卒業するとしばらくして、どこかの暴力団に入り、そのあと、
10年近く、刑務所で暮らしている。
同窓会に出るたびに、彼の話がよく出た。
が、である。
私はその男の温厚さに驚いた。
ふつうの温厚さではない。
体の芯からにじみ出るような、温厚さである。
人間的な深い暖かみも感じた。
私のことはよく覚えていて、たがいに話がはずんだ。
そのあと、ボランティアの案内人として、町の中を、観光客を案内するということだった。
別れてからワイフに、その男の過去を話すと、ワイフはたいへん驚いていた。
「そんな人には、ぜんぜん、見えないわね」と。
●罪を憎んで、人を憎まず
法律の世界には、『罪を憎んで、人を憎まず』という言葉がある。
そこに犯罪者がいたとしても、悪いのは、その「罪」であって、「人」ではないという
考え方である。
まさにそのとおりで、手鏡でスカートの下をのぞいたことは悪いとしても、だからと
いって、その人のすべてを否定してはいけない。
同じように、若いころ、刑務所にいたからといって、その後の彼の人生のすべてを
否定してはいけない。
その区別というか、境界をしっかりと引く。
それが『罪を憎んで、人を憎まず』の意味ということになる。
●魔が差す
考えてみれば、人間は、社会的動物である以上、いつも「悪」にさらされて生きている。
今、「私はだいじょうぶ」と考えている人にしても、明日のことはわからない。
それは事故のようなもの。
ふと油断したようなとき、悪の餌食になる。
『魔が差す』というのは、それをいう。
言い換えると、だれしも、そういうときはある。
私にもあるし、あなたにもある。
冒頭にあげた(欲望)というのは、そういうもの。
(理性)の緊張感がゆるんだ、その一瞬をついて、その人を狂わす。
だからといって、そういう人を擁護するつもりはない。
が、一方的にそういう人を、否定してしまってはいけない。
私は、それを書きたかった。
Hiroshi Hayashi++++++++Oct. 09+++++++++はやし浩司
●多様性について
+++++++++++++++++++++++++++
知人、友人が、健康を害していくのを見るのは、つらい。
見た目には同じようでも、「今、○○病と闘っているよ」と
言われると、そのつど、ドキッとする。
同じように、知人、友人が、ボケていくのを見るのは、つらい。
明らかに頭の回転が鈍くなっている。
話し方も、かったるい。
会話から繊細さが消え、ぶっきらぼうな言い方をする。
たいていは、血栓性の脳障害(脳血管性認知症)によるもの。
独特の話し方をする。
それが最近は、素人の私にも、判断できるようになった。
+++++++++++++++++++++++++++
●意識
私たちがもっている(意識)ほど、あてにならないものはない。
「私は私」と思っている部分についても、では、脳の中で、どの部分がそう思っているか
となると、それがどうもよくわからないらしい。
たとえば理性の中枢部として、前頭連合野がある。
額の裏側にある脳である。
しかしその「前頭」と言われている部分についても、左脳と右脳に分かれている。
仕事を分担している。
(最近、とくに注目されている部分が、第46野と言われている部分だが、それについて
は、最後のところで書く。)
が、もちろん別々の仕事をしているわけではない。
「脳梁(のうりょう)」と呼ばれる、太い配線で結ばれている。
が、全体として、(1つ)ということではない。
脳は、そのときどきにおいて、いろいろな組み合わせを繰り返しながら、別人格を作りあ
げる。
一説によれば、8人格。
私の計算によれば、9人格。
さらには32人格まであると説く人もいる。
それぞれがそれぞれの人格のとき、別の意識をもつ。
今、「私は私」と思っている部分は、その中のひとつにすぎない。
●脳の奥で作られる無意識
たとえば「ジュース」という言葉を見たとする。
左脳の言語中枢は、それを「ジュース」と読み、読んだ言葉を、右脳に伝える。
右脳はその信号をとらえて、コップに入った黄色い飲み物を具体的に映像化する。
このとき、右脳は、すでに脳の中に格納された情報から、ジュースの情報を引き出し、「冷
蔵庫の中に、昨日買ってきた、オレンジジュースが残っているはず」と判断する。
が、もしここで、「マイロ」という言葉を見たとしたら、どうだろうか。
オーストラリアの飲み物である。
日本では、N社から、「ミロ」という商品名で、売りに出されている。
しかしオーストラリアに住んだことのない人は、「マイロ」と読んでも、意味がわからな
い。
右脳に情報を送っても、それがどんなものであるか、具体的に頭の中に浮かんでこない。
言葉だけは脳のあちこちをかけめぐるが、そのつど脳の壁に当たって、はね返されてしま
う。
「ジュース」という言葉を見たときには、それが具体的な映像となって、意識を動かす。
「飲みたい」という意識につながる。
が、「マイロ」という言葉を見たときには、具体的な映像は浮かんでこない。「飲みたい」
という意識は、当然、生まれない。
●操られる意識
ところが、「マイロ」について、だれかがこう説明したとする。
「ココアに似た味の、おいしい飲み物」と。
すると好奇心がわいてくる。
その好奇心が、「飲みたい」という意識を引き出す。
しかもそのとき、同時に、脳の別の部分では、別の意識が活発に動き出す。
「どこへ行けば手に入るか」
「値段は、いくらくらいか」
「どうやって飲むのか」などなど。
このときほとんどの意識は、意識されない世界、つまり無意識の世界で動き出す。
さらに脳の頭頂部あたりでは、「どんなカップに、どのようにして溶かして飲むか」まで考
えるかもしれない。
そこであなたは、「マイロ」について、調べる。
人に聞く。
最終的には、日本でも、N社から、「ミロ」という名前で売りに出されていることを知る。
で、あなたは近くの店に行き、それを手に入れる……。
●意識は、氷山の一角
こうした一連の意識活動で重要なことは、私たちが(意識している意識)というのは、
海に浮かんだ氷山の一角のようなものにすぎないということ。
一角どころか、「一微」と書いた方が、正確かもしれない。
で、そのあと、あなたは店へ行く。
店員に、「ミロはありますか?」と聞く。
それを見つけて、カートに入れる。
お金を払う。
家に帰って、飲む……。
そのつどあなたは、「私は、自分の意思で、そうしている」と思うかもしれない。
しかし実際には、それ以前、つまりあなたが「マイロ」という名前を読んだとき、脳の別
の部分が決めた行動に従って、そうしているにすぎない。
「意識」としては、意識できなかっただけ、ということになる。
これはほんの一例だが、私たちがもっている意識というのは、そういうものと考えてよ
い。
つまりアテにならない。
●多様人格
こうして考えていくと、どこからどこまでが「私」なのか、わからなくなってくる。
さらにその「私」にしても、冒頭に書いたように、脳の組み合わせによって、いくつもの
パターンに分かれる。
すばらしい映画を観たあとなどは、神々(こうごう)しい気持ちになる。
反対に殺伐とした暴力映画を観たあとなどは、イライラしたり、怒りっぽくなったりする。
どちらも「私」なのだが、どちらが本物の私で、どちらがそうでないかという判断をくだ
すのは、正しくない。
「神々しい私の方が、私」と思いたい気持ちはわかるが、それがすべてではない。
ときには、サスペンス映画、戦争映画、スリラー映画も、観たくなる。
SF映画も楽しい。
……となると、ますます訳が分からなくなる。
が、こうなったときの鉄則は、ひとつ。
ここは居直るしかない。
つまり私たちは、「常に(1人の私)ではない」と、考える。
1人の私に限定するから、話に無理が生じてくる。
自己矛盾に悩む。
脳の構造についていうなら、前頭前野の第46野が、「私」を作っている中枢部らしいと
いうことまでわかってきた。
その第46野は、簡単に言えば、3層(カラム)になっている。
それが左右の両方に、ひとつずつあるわけだから、組み合わせの数で言えば、3×3=9の、
9通りということになる。
9通りということになる。
つまり私たちは、単純に計算すれば、いつも9通りの「私」をもっていることになる。
(もちろんどれが優勢か、劣勢かということはあるが……。
とくに優勢なのを、「主人格」という。)
ひとつにこだわらなければならない理由は、ない。
つまり多重人格であるのが、当たり前。
「多重人格」という言葉に抵抗があるなら、「多様人格」という言葉を使ってもよい。
私たちは、そのつど、時と場合に応じて、多様な意識をもって、ものを考えたり、行動
したりする。
学者のときは、学者。
父親のときは、父親。
酒が入ったときには、友人。
妻と裸で接するときは、スケベ人間……。
つまり「意識はアテにならない」と考えるのではなく、「どれも意識」と考える。
「どれも私」と考える。
さらに言えば、この多様性があるからこそ、その人のもつ(おもしろさ)が生まれる。
少し前、手鏡で女性のスカートの中をのぞいた大学教授の話を書いた。
が、それも人間が本来的にもつ、多様性のひとつとも考えられなくもない。
(だからといって、そういう行為を容認しているのではない。
ただ、ほかのすぐれた部分まで、いっしょくたに否定してしまってはいけないと書いてい
る。
誤解のないように!)
この考え方は、今後、変わるかもしれない。
しかし今は、これが私の意識についての結論ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 意識論 多様人格 人間の多様性 多重人格 はやし浩司の意識論)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●今日も終わった……(改)
●人を愛する
ぼくは、子どものころから、人を愛することができなかった。
愛することで、自分が傷つくのが、こわかった。
今も、そうで、人を愛しそうになると、その一歩手前で、立ち止まってしまう。
ぼくは、臆病者。
気が小さく、心が狭い。
いつも自分の殻(から)に閉じこもり、小さな穴から、外をのぞいている。
もちろん人を愛することのすばらしさは、知っている。
しかし同時に、人を愛することのきびしさも、つらさも知っている。
だから人を愛しそうになると、自分から先に逃げてしまう。
結婚してからもそうだった。
ぼくは心を開けなかった。
すべてをさらけ出して、妻に、「愛している」とは言えなかった。
そんなぼくを、妻は、いつもさみしく思っていたにちがいない。
この年齢になっても、また40年も連れ添っていても、
ぼくは自分が、こわい。
そう、ぼくはすべてをさらけ出すことができない。
いつも仮面をかぶって、自分の心をごまかしている。
裏切られるのがこわくて、先に、相手を裏切ってしまう。
つまらない人間ということも、よく知っている。
なさけない人間ということも、よく知っている。
しかしそんな自分を、どうすることもできない。
●徘徊
ぼくは、いやなことやつらいことがあると、よく徘徊する。
あてどもなく、ただひたすら、道に沿って歩く。
だれも通らない、細い道を選んで歩く。
そんなとき、妻はぼくを心配して、ぼくをさがす。
が、妻の運転する車を見ると、ぼくは、隠れてしまう。
助けてほしいのに、体は、別のほうを向いてしまう。
いじけた心。
ゆがんだ心。
すなおになりたくても、もう1人のぼくがいて、それをじゃまする。
もう残りの人生のほうが、はるかに短い。
ぼくは、ぼくらしく生きたい。
しかしそれができない、そのもどかしさ。
ときどき妻は、こう言う。
「あなたって、かわいそうな人ね」と。
自分で孤独を作って、その孤独の中で、もがき苦しんでいる。
「その人はどこにいるの?」と、1人の少女が、そう歌う。
昔、キングスクロスの劇場で観た、「ヘアー」の中でのことだった。
「私を導き、私を教えてくれる人は、どこにいるの?」と。
その少女は、つづけて、こう歌う。
「なぜ、私たちは生まれ、なぜ死ぬのか」
「私たちは、それを知るために、どこへ行けばいいの?」と。
話がそれたが、ぼくはなぜ歩くか。
理由は、簡単。
歩いているときだけ、ぼくは自分を忘れることができる。
●10月3日
静かな夜。
満月の夜。
心地よい、夜の冷気が、つんとぼくの乾いた心を包む。
洗い物をする妻のうしろ姿。
テーブルにころがった、もうひとつのメガネ。
その横には、小さな薬箱。
何でもない光景だが、それが今夜は、ひときわ動きを止めている。
息をひそめて、ぼくが何をするか、それを待っている。
が、ぼくは、ただそれをぼんやりとながめているだけ。
「時」だけが、こうして流れてきた。
今も、流れている。
これからも、流れていく。
人を愛することのできない、もどかしさ。
自分らしく生きられない、もどかしさ。
今のときを、自分の手でつかむことができない、もどかしさ。
みんなそうなのだろうか?
それともぼくだけが、そうなのだろうか?
あるいは、みんなは、こういうとき、どうしているのだろうか?
10月3日は、もうそろそろ終わる。
時刻は、午後10時30分。
ああ、今日も、何もできなかった……。
Hiroshi Hayashi+++++++Oct. 09++++++はやし浩司
●自殺論
++++++++++++++++++++++
自殺というのは、それを考えない人には、
遠くにある。
「自殺するヤツは、バカ」と、平気で言う。
しかしそれを考える人には、手をのばせば
すぐそこにある。
その気になれば、いつでも死ねる。
自殺というのは、それを考えない人には、
恐怖かもしれない。
しかしそれを考える人には、最後の救い。
「死ぬことによって、自分の魂を解放させることができる」と。
死に向かって、迷わず、歩いていく。
+++++++++++++++++++++++
●絶望
絶望の恐ろしさは、絶望を味わったものでないとわからない。
すべての光が消えて、すべての目的が形を失う。
すべてのものが動きを止め、時間さえも、そのまま止まってしまう。
自分の人生の無意味さを思い知らされることくらい、恐ろしいことはない。
すべてのものが、色あせ、すべての人から、見放される。
そのとき「死」が、薄い氷の下で、手招きをして、ぼくを呼ぶ。
絶望こそが、死の魔手。
それがこわくて、人は、それがどんなに小さなものであっても、
希望に明日への命をつなぐ。
庭の芝生?
栗の木の上に造った、ハトの巣。
それとも明日の天気?
今、妻が、衣服を着替えながら、ぼくに微笑みかけた。
洗面所でいつものように顔を洗い、やがてこの居間にもどってきて、血圧を測る。
床につく時刻がやってきた。
明日こそは、妻を暖かい陽だまりで包んでやろう。
明日こそは、「今日はいい一日だった」と言えるようにしよう。
明日こそは……。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 詩 はやし浩司の詩)
Hiroshi Hayashi+++++++Oct. 09++++++はやし浩司
●10月4日(日曜日)
++++++++++++++++
遅い朝食をとっていると、ワイフが、こう言った。
「どこかへ行かない?」と。
で、「お前が決めろ」と言うと、ワイフは、
「浜名湖電車に乗りたい」と。
そこで急きょ、外出することにした。
++++++++++++++++
●浜名湖鉄道(天竜浜名湖鉄道)
ネットで時刻表を調べると、金指(かなさし)発、1時6分というのがあった。
それに乗ることにした。
言い忘れたが、「浜名湖鉄道」というのは、浜名湖の北を、掛川から、新所原(しんじょは
ら)まで、浜名湖を取り囲むようにして走っている電車である。
折しもフラワーパークでは、「モザイカルチャー博覧会」というのをやっていた。
が、日曜日ということもあって、やめた。
人が混雑したところを歩くのは、好きではない。
●1時6分発
途中、市内のパソコンショップに寄ったのが、まずかった。
時計を見ると、12時45分。
いくら急いでも、金指駅までは、20分はかかる。
とても間に合いそうにない。
が、こういうときは、(運命)に、身をゆだねる。
間に合うときには、間にあう。
間に合わないときには、間に合わない。
ジタバタしても、仕方ない。
ワイフの時計は、2、3分、進んでいた。
私の時計は、電波時計に合わせておいたから、正確。
「もうだめだね」と言いながら、駅に着くと、電車はそこで待っていた!
駅員さんに、車から降りながら、ちょっとだけ待ってくださいと声をかけると、「いいです
よオ!」と。
こういうところが、ローカル線。
人間の暖か味がちがう。
ワイフは、空き地に車を止め、ハーハーと息を切らしながら、駅へ走ってきた。
●森町でおりる
1日周遊券というのを買うと、1500円で乗り放題。
私たちはそれを買った。
しばらく、窓の外の景色を見る。
見慣れた景色だが、それだけに、ほっとする。
私はミニパソコンを取りだして、文を書き始める。
ワイフは、途中の駅で買った駅弁を開いて、それを食べる。
のどかな1日。
で、私たちは森町でおりることにした。
「森の石松」で有名な、森町である。
駅を出たところに案内所があって、そこの男性が、ていねいにいろいろと教えてくれた。
私たちは、蓮華寺と、その隣の民俗資料館を目指すことにした。
時間的に余裕があれば、その近くの町営浴場にも入ることにした。
●民俗資料館
もともとは役所だったという。
木造の二階家だった。
中にぎっしりと、農機具などが展示されていた。
私が子どものころ、どこかで見たようなものばかりだった。
なつかしいというより、どれも、小さいのに驚いた。
「ぼくが子どものころには、これはぼくの背丈より大きかった……」と話しながら、案内
人の案内を受けながら、館内を回った。
楽しかった。
で、そのあと、蓮華寺へ。
小さな寺だったが、住職がちょうど勤行(ごんぎょう)を始めるところだった。
私たちはその後ろ姿を見ながら、小銭を賽銭箱に入れた。
天井からつりさげられた鐘を鳴らした。
●町営浴場
このところ毎週のように、大きな浴場で風呂に入っている。
それもあって、帰りに、町営浴場へ入ることにした。
が、玄関を入ったとたん、Uターン。
ここから先は、森町の悪口になるから、慎重に書きたい。
私たちは、どうしてUターンをしたか?
入浴しないで、どうしてそのまま外へ出たか?
実は、玄関を入ると、通路をはさんで、左側が、デイサービスセンターになっていた。
独特の老臭と消毒臭。
右側が大浴場。
その右側には、広いロビーが、昼下がりの日光をさんさんと受けて明るく輝いていた。
が、見ると、80〜90歳の老人たちが、椅子に座って、そこで休んでいた。
車椅子に座っている老人もいた。
よたよたと杖をついて歩いている老人もいた。
みな、腰の部分が不自然にふくらんでいる。
だから、Uターン。
老人を介護したことのある人なら、その理由を、みな、知っているはず。
●掛川へ
森町から、今度は掛川へ。
のどかな田園風景が、ゆっくりと流れるようにつづく。
私はパソコンのバッテリーを気にしながら、思いついたことを書きとめる。
こういうときというのは、書きたいことがつぎつぎと思い浮かんできて、頭の中がパニック状態
になる。
になる。
で、掛川へ。
あちこちを歩いて、通りのそば屋に入った。
ほかの店は、どこも休息中だった。
味は、ふつう。
が、値段は高かった。
ざるそばが、850円!
店を出ると、そのまま駅へ。
みやげは、葛(くず)湯。
掛川名物。
そのときワイフが万歩計を見ると、9000歩近くを示していた。
つまり目的は達した。
家に着くころには、とっぷりと日が暮れていた。
私はネットで、新しいミニパソコンを注文した。
ワイフは、DVDを見始めた。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 天竜浜名湖鉄道 浜名湖鉄道 浜名湖 浜松市 浜名湖)
Hiroshi Hayashi++++++++Oct. 09+++++++++はやし浩司
●文章
「文」というのは、生き物。
しばらく時間をおいて読み直してみると、まったく別の文になっている。
そんなことは、よくある。
そこで私のばあいは、文を一度書くと、しばらくそのままにしておく。
そのあと時間をおいて、再び、読み直す。
そのとき、できるだけ、声を出して読むようにしている。
たとえば昨日、私は、「人を愛する」というのと、「絶望論」というのを、書いた。
それを今朝、読み直してみた。
が、どこかヘン?
ぎこちない?
リズムが乱れている。
書いているときは気がつかなかったが、意味不明のところさえある。
だから改めて、書き直す。
だから楽しい。
だからおもしろい。
文を書くと言うのは、文という生き物を相手にすること。
……ということで、今週も始まった。
がんばろう!
10月5日、月曜日!
Hiroshi Hayashi++++++++Oct. 09+++++++++はやし浩司
●満62歳
++++++++++++++++++++
もうすぐ満62歳になる。
62歳だア!
その62歳が近づいて、うれしい報告がひとつある。
私は、ずっとこう考えていた。
「健康というのは、維持するもの」
「不可逆的に悪化するもの」と。
だから「現状維持ができるだけも、御の字」と。
ところが、である。
これがどうも、そうでないということがわかった。
まず体重を、68キロから60キロに減らした。
3か月ほどかけて、少しずつ減らした。
しばらくは、それまでに経験したことのない体の不調に
悩まされた。
体重が減ったのだから、その分、体は軽くなったはず。
が、それはなかった。
かえって、体を重く感ずるようになった。
抵抗力が落ちたせいか、皮膚病(とくに結膜炎)も含めて、風邪をひきやすく
なった。
ショックだったのは、いつもなら自転車でスイスイと登れる
坂が、登れなくなったこと。
筋肉そのものまで、萎(な)えてしまった。
で、それからさらに2か月あまり。
体重を60キロに維持したまま、運動量を多くした。
それに加えて、3週間ほど前から、ウォーキング・マシンを
購入し、暇を見つけてはそれを使い始めた。
1日、40〜50分を目標にしている。
速度も時速6キロ前後に設定し、できるだけ、つま先で
歩くようにしている。
こうすると、軽いジョギングをしているような格好になる。
10〜20分も使っていると、全身から汗が噴き出してくる。
こうした努力が功を奏したのか、最近では、自分の健康を、
はっきりと自覚できるようになった。
体も軽い。
睡眠も深くなった。
もちろんあの坂も、再び、スイスイと登れるようになった。
さらにうれしいことに、頭がサクサクと動くようになった。
朝起きたとき、それがよくわかる。
文章を書いていても、思ったことを、そのまま表現できる。
人と話していても、言葉が、なめらかに出てくる。
だから、こう書きたい。
「みなさん、還暦と言われて、あきらめてはいけない」
「60歳を過ぎても、健康は、じゅうぶん、増進できる」
「健康は維持するものではない。努力によって造るもの」と。
少し前、私の友人がこう言った。
「男がね、いちばん仕事ができるのは、60代だよ」と。
その友人は、日本でも最大手のペンキ会社の監査役をしていた。
私は、その友人の言った言葉を、信ずる!
花の60代!
我ら、ヤング・オールド・マンなのだア!
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 健康論 健康増進)
+++++++++++++++++++++++++はやし浩司
●エピソード記憶
++++++++++++++++
●もの忘れ
昨日の昼に、何を食べたか。
おととい観た映画の題名は何だったか。
隣の息子の名前は何だったか。
そういうことを忘れるということは、よくある。
俗に言う、「ど忘れ」というのが、それ。
しかしその程度の(もの忘れ)は、むしろ正常なのだそうだ。
脳には、そういう機能がある。
それによって、脳はいつも脳への負担を軽くし、つぎの記憶に備える。
パソコンにたとえるなら、「クリーンアップ」ということか。
無駄な情報を消去して、メモリーを軽くする。
が、食べたことそのものを忘れてしまうのは、よくない。
映画を観たという事実を忘れてしまうのは、よくない。
自分の家の住所を忘れてしまうのは、よくない。
アルツハイマー型の痴呆症になると、記憶といっても、エピソード
(物語)そのものが記憶から抜けてしまい、それを忘れてしまうという。
実は、私の知人(現在60歳)も、この問題で、困っている。
6歳年上の姉がいるのだが、その姉が、最近、「私は相続放棄をした覚えは
ない」と言って、騒ぎ出したという。
ことのいきさつは、こうだ。
●知人のケース
知人の父親は、5年ほど前に他界した。
そのとき家を継いでいた知人が、何百万円かの現金を渡して、姉に相続を
放棄してもらった。
それに基づいて、知人は、土地、家屋の名義を、その知人のものに書き換えた。
で、それから5年。
変化が生じた。
知人の家の近くが、土地整理区画に指定された。
とたん、土地の価格が大暴騰。
どうしようもない荒地と思っていた土地が、住宅地になった。
姉が「相続放棄をした覚えはない」と言い出したのは、そのときのことだった。
で、知人は、当時の書類を姉に見せた。
それには、「協議により、全財産を兄、○○に譲ります」とある。
もちろん姉自身の実印による押印、直筆による署名もある。
「全財産」という箇所の上にも、実印による押印してある。
これについて、知人は、「とくに重要な箇所だから、あえて押印してもらった」
と言っている。
しかしその「協議書」を、姉は、「そんなものを書いた覚えはない」と。
で、知人が私に相談してきた。
一応、私は、元法学部の学生。
成績も悪くなかった。
それに専門は、民事訴訟法。
念のため、M市で弁護士をしている友人に、電話で確かめた上で、
知人にこう言った。
私「やりたいようにさせ、あとは無視したらいいですよ」
知「無視ですか?」
私「何か言うと、そういう人ですから、言葉尻をつかまれますよ」
知「姉というより、姉の娘が騒いでいるのですね。今年、40歳になるかな」
私「最近、そういうケースがたいへん多いですよ。弁護士をしている友人も
そう言っていました」と。
つまり当の本人(=相続権をもった相続権者)ではなく、その子ども
(=相続権をもたない息子や娘)が、「親の取り分が少ない」と言って騒ぐ。
●エピソード記憶
が、知人の姉のケースは、もう少し深刻である。
法務局でコピーを見せつけられたにもかかわらず、「私は書いてない」
「印鑑を押してない」と、がんばっているという。
さらには、「その協議書は、偽造されたもの」とまで、言い出した。
しかし偽造ということはありえない。
印鑑証明書にしても、本人以外は、取り寄せることさえできない。
実印にしても、そうだ。
筆跡をまねるとしても、限界がある。
さらに協議書の「全財産」という箇所の上に、実印が押印してある。
(実印の上に、「全財産」という文字が上書きしてあるなら、偽造という
こともありえるが……。)
……などなど。
が、知人の姉は、知人の話によれば、とぼけているとか、ウソをついているとか、
そういう雰囲気は、まるでないという。
まったく、シラフというか、本気で、そう信じこんでいるといったふう、と。
あるいは騒いだ分だけ、引っ込みがつかなくなってしまったのかもしれない(?)。
どうであるにせよ、話は、アルツハイマー病へと進んだ。
●アルツハイマー型認知症
知人の姉がその病気というわけではない。
しかし話の内容を総合すると、その心配は、ある。
あるいは私がその女性の夫なら、まずそれを疑う。
現在、満65歳をすぎると、アルツハイマー病の有病率は急激にふえることがわかってい
る(新潟大学脳研究所※)。
他の認知症も含めると、約10%の人が、そうなる。
で、アルツハイマー型の認知症のこわいところは、ここにある。
記憶の一部だけではなく、ある部分の記憶が、スッポリと抜けたかのように、
消えてしまう。
部分的に覚えているということもない。
たとえば夕食を食べたあと、しばらくすると、「私は夕食を食べていない」とか
言って騒ぎ出す。
さらに知人が困っているのは、電話。
数日おきに、姉から電話がかかってくるという。
(知人は、ナンバーディスプレイ装置を使って、姉からの電話には
出ないようにしているというが……。)
その電話というのが、高姿勢。
高慢。
留守番電話に向かって、言いたい放題。
妙に慇懃無礼な言い方をしたかと思うと、つぎの電話では、ギャンギャンと
怒鳴り散らす、など。
私「やはり、無視するしかないですね」
知「そうですね」
私「どうせ、あなたの姉さんは、何もできませんから」
知「しかし残念なのは、夫や娘も含めて、まわりの人たちがみな、姉を
たきつけていることです」
私「相続がからむと、そうみたいですよ」と。
認知症というと、とかく当の本人だけの問題と考えられがちである。
しかしそういう病気であると、まわりの人たちがわかっていればよい。
わからないから、その人に、振り回される。
予期せぬトラブルに巻き込まれていく。
不愉快な思いをする。
(教訓)
今ではこの病気も、早期発見が、第一。
治るということはないそうだが、進行を遅らせるという方法はある。
それに家族のだれかがそうなったら、できるだけ早く、周囲の人にそれを
伝えたほうがよい。
知人の姉のばあいは、かなりの電話魔らしく、夫の目を盗んでは、あちこちに
電話をかけまくっている。
そういう事実を、夫は知らない。
また「おかしい?」と気づいても、たいていのばあい、夫は、それを自ら
否定しようとする。
それを認めることは、夫にとっても、つらい。
が、こうした姿勢が、友人関係、近隣関係、親戚関係を破壊する。
アルツハイマー型痴呆症には、そういう問題も隠されている。
(注※)「65歳以上の認知症平均有病率は約10%である」
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 アルツハイマー 認知症 もの忘れ)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 26日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page026.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【子どもを叱る】
++++++++++++++++++++++
総論
(1)親子(母子)の密着度が強すぎる。
(2)子どもを、1人の人格者として認めていない。
(3)1人の人間(親であれ)、別の人間を叱るということは、
たいへんなことだという、自覚が乏しい。
(叱る側に、哲学、倫理、道徳観がなければならない。)
各論
(1)威圧、恐怖感を与えない。
(2)言うだけ言って、あとは時間を待つ
(3)自分で考えさせる。
+++++++++++++++++++++
●叱る
++++++++++++++++++++
子どもであれ、相手を「叱る」ということは、
たいへんなこと。
叱る側に、それなりの道徳、倫理、哲学が
なければならない。
しかもその道徳、倫理、哲学は、相手をはるかに
超えたものでなければならない。
自分の価値観を押し付けるため、あるいは自分の
思い通りに、相手を動かすために、相手を叱るというのは、
そもそも(叱る)範疇(はんちゅう)に入らない。
いわんや自分が感ずる不安や心配を解消するために、
相手を叱ってはいけない。
そういうのは、自分勝手という。
わがままという。
+++++++++++++++++++++++
●私のばあい
簡単に言えば、私は忘れ物をしてきた生徒を、叱ったことがない。
ときどきはあるが、それでもめったにない。
理由は、簡単。
私自身がいつも忘れ物をするからである。
同じようなことだが、こんなことがある。
よく子どもに向かって、「サイフを拾ったら、おうちの人か、交番に届けましょう」と
教える。
しかし私はそのたびに、どうも居心地が悪い。
私は団塊の世代、第一号。
戦後のあのドサクサの中で生まれ育った。
家庭教育の「か」の字もないような時代だったといえる。
そういう時代だったから、たとえば道路にお金やサイフが落ちていたとしたら、
それは見つけた者のものだった。
走り寄っていって、「もら〜い」と声をかければ、それで自分のものになった。
そういう習慣が今でも、心のどこかに残っている。
一度身についた(悪)を、自分から消すのは容易なことではない。
だから居心地が悪い。
実際、今でも、サイフを道路で拾ったりすると、かなり迷う。
迷いながら、近くの店か、交番に届ける。
この(迷い)は、60歳を過ぎた今も、消えない。
そんな私がどうして、子どもたちに向かって、堂々と、「拾ったサイフは、
交番へ届けましょう」と言うことができるだろうか。
●親の身勝手
ほとんどの親は、ほとんどのばあい、自分の身勝手で、子どもを叱る。
たとえば自分では、信号無視、携帯電話をかけながら運転、駐車場でないところへ
駐車しておきながら、子どもに向かって、「ルールを守りなさい」は、ない。
自分では一冊も本を読んだことさえないのに、子どもに向かって、「勉強しなさい」は、
ない。
……となると、「しつけとは何か」と疑問に思う人も多いかと思う。
しかし(しつけ)は、叱って身につけさせるものではない。
(しつけ)は、子どもに親がその見本を見せるもの。
見せるだけでは足りない。
子どもの心や体の中に、しみこませておくもの。
その結果として、子どもは、(しつけられる)。
親がぐうたらと、寝そべり、センベイを食べながら、「机に向かって、
姿勢を正しくして勉強しなさい」は、ない。
●子どもの人格
私が子どものころでさえ、女性と子どもは、社会の外に置かれた。
「女・子ども」という言い方が、今でも、耳に残っている。
つまり「女や子どもは、相手にするな」と。
戦後、女性の地位は確立したが、(それでも不十分だが……)、子どもだけは、
そのまま残された。
今でも、子どもは、(家族のモノ)、あるいは、(親のモノ)と考えている人は
少なくない。
子どもに向かって、「産んでやった」「育ててやった」という言葉をよく使う人は、
たいていこのタイプの親と考えてよい。
だから叱るときも、モノ扱い(?)。
子どもの人格を認める前に、頭ごなしにガミガミと叱る親は、いくらでもいる。
人が見ている前で、ガミガミと叱る親は、いくらでもいる。
子どもの意見を聞くこともなく、ガミガミと叱る親は、いくらでもいる。
『ほめるのは公に、叱るのは密やかに』と言ったのは、シルスだが、子どもの
人格を平気で無視しながら、無視しているという意識さえない。
●日本人の民族性
一般論として、日本人は、子どもを叱るのが、へた。
その原因の第一として、日本人がもつ民族性があげられる。
先にも書いたように、この日本では、伝統的に、子どもは、家のモノ、
あるいは親のモノと考える。
つまりその分だけ、親子、とくに母子関係において、親子の密着度が強い。
たとえば私が教師という立場で、子どもを叱ったとする。
私は子どもを叱ったのだが、親は、自分が叱られたように感じてしまう。
さらには、自分の子育てそのものが、否定されたかのように感じてしまう。
この一体性が強いため、自分の子どもでありながら、自分の子どもを
客観的にながめて、子どもを叱ることができない。
●欧米では……
一方、欧米では、もちろんイスラム教国でも、伝統的に子どもは神の子
として考える。
それが長い歴史の中で熟成され、独特の子ども観をつくりあげている。
つまりあくまでも比較論だが、欧米では、親と子どもの間に、まだ距離感がある。
そのひとつの例というわけではないが、私が子どものころには、たとえば家族の
中に障害をもった子どもが生まれたとすると、親は、それを「家の恥」と
考えた。
そういう障害をもった子どもを、世間から隠そうとした。
今では、そんな愚かな親はいないが、しかしまったくそういう考え方が
なくなったというわけではない。
今も、日本は、その延長線上にある。
つまりこうした日本人独特の民族性が、子どもの叱り方の中にも現れる。
それが、ぎこちなさとなって現れる。
子どもだけを見て、子どものために、子どもの人格を認めてしかるのではない。
ときとして、自分のために叱っているのか、子どものために叱っているのか、わからなく
なる。
わかりやすく言えば、自信をもって、子どものために、子どもを叱ることができない。
●子どもを叱れない親
実際、子どもが、小学校の高学年くらいになると、子どもを叱れない親が
続出する。
「子どもがこわい」という親がいる。
「子どもに嫌われたくない」という親もいる。
親が、子どもに依存性をもつと、さらに叱れなくなる。
こうなってくると、子どもの問題というよりは、親の問題ということになる。
親自身の精神的な未熟さが原因ということになる。
子どもというのは、ある一定の年齢に達すると、(小学3、4年生前後)、親離れ
を始める。
その親離れを、うまく助けるのも、親の務めということになる。
が、このタイプの親は、それができない。
そればかりか、自分自身も、子離れできない。
そんな状態で、では、どうして親は、子どもを叱ることができるのかということに
なる。
●モンスターママ
数日前、インターネット・サーフィンをしていたら、こんな記事が目についた。
何でも自分の息子(中学生)が、万引きをして、店の責任者から、警察に通報された
ときのこと。
母親がその責任者に向かって、こう言ったという。
「いきなり警察に通報しなくてもいいではないか。まず子どもを諭すのが先だろ」と。
つまりその母親は、自分の子どもが万引きしたことよりも、店側が警察にそれを
通報したことを、怒った。
何かがおかしい。
どこかが狂っている。
だから日本人は、子どもの叱り方がへたということになる。
●では、どうするか
(1)自分の子どもといえども、1人の人間、もしくは、「友」として叱ること。
(2)叱る側が、それなりの哲学や倫理感、道徳を確立すること。
(3)親のエゴイズムに基づいて、子どもを叱らないこと。
……こう書くと、「それでは子どもを叱れない」と思う親もいるかもしれない。
そう、(叱る)ということは、それほどまでに、むずかしいことである。
その自覚こそが、子どもを叱るとき、何よりも重要ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 子どもの叱り方 子供の叱り方 子供を叱る 子どもを叱る 叱り方
ほめ方 はやし浩司 叱り方の原則)
(補記)
●叱り方・ほめ方は、家庭教育の要(かなめ)
子どもを叱るときの、最大のコツは、恐怖心を与えないこと。「威圧で閉じる子どもの耳」
と考える。中に親に叱られながら、しおらしい様子をしている子どもがいるが、反省して
いるから、そうしているのではない。怖いからそうしているだけ。親が叱るほどには、効
果は、ない。叱るときは、次のことを守る。
(1)人がいうところでは、叱らない(子どもの自尊心を守るため)、(2)大声で怒鳴
らない。そのかわり言うべきことは、繰り返し、しつこく言う。「子どもの脳は耳
から遠い」と考える。聞いた説教が、脳に届くには、時間がかかる。(3)相手が
幼児のばあいは、幼児の視線にまで、おとなの体を低くすること(威圧感を与え
ないため)。視線をはずさない(真剣であることを、子どもに伝えるため)。子ど
もの体を、しっかりと親の両手で、制止して、きちんとした言い方で話すこと。
にらむのはよいが、体罰は避ける。特に頭部への体罰は、タブー。体罰は与えるとしても、
「お尻」と決めておく。実際、約50%の親が、何らかの形で、子どもに体罰を与えてい
る。
次に子どものほめ方。古代ローマの劇作家のシルスも、「忠告は秘かに、賞賛は公(おお
やけ)に」と書いている。子どもをほめるときは、人前で、大声で、少しおおげさにほめ
ること。そのとき頭をなでる、抱くなどのスキンシップを併用するとよい。そしてあとは
繰り返しほめる。
特に子どもの、やさしさ、努力については、遠慮なくほめる。顔やスタイルについては、
ほめないほうがよい。幼児期に一度、そちらのほうに関心が向くと、見てくれや、かっこ
うばかりを気にするようになる。実際、休み時間になると、化粧ばかりしていた女子中学
生がいた。また「頭」については、ほめてよいときと、そうでないときがあるので、慎重
にする。頭をほめすぎて、子どもがうぬぼれてしまったケースは、いくらでもある。
叱り方、ほめ方と並んで重要なのが、「励まし」。すでに悩んだり、苦しんだり、さらに
はがんばっている子どもに向かって、「がんばれ!」はタブー。ムダであるばかりか、かえ
って子どもからやる気を奪ってしまう。「やればできる」式の励まし、「こんなことでは!」
式の、脅しもタブー。結果が悪くて、子どもが落ち込んでいるときはなおさら、そっと「あ
なたはよくがんばった」式の前向きの理解を示してあげる。
叱り方、ほめ方は、家庭教育の要であることはまちがいない。
【コツ】
★子どもに恐怖心を与えないこと。
そのためには、
子どもの視線の位置に体を落とす。(おとなの姿勢を低くする。)
大声でどならない。そのかわり、言うべきことを繰り返し、しつこく言う。
体をしっかりと抱きながら叱る。
視線をはずさない。にらむのはよい。
息をふきかけながら叱る。
体罰は与えるとしても、「お尻」と決める。
叱っても、子どもの脳に届くのは、数日後と思うこと。
他人の前では、決して、叱らない。(自尊心を守るため。)
興奮状態になったら、手をひく。あきらめる。(叱ってもムダ。)
+++++++++++++++++
子どもを叱るときは、
(1)目線を子どもの高さにおく。
(2)子どもの体を、両手で固定する。
(3)子どもから視線をはずさない。
(4)繰り返し、言うべきことを言う。
また、
(1)子どもが興奮したら、中止する。
(2)子どもを威圧して、恐怖心を与えてはいけない。
(3)体罰は、最小限に。できればやめる。
(4)子どもが逃げ場へ逃げたら、追いかけてはいけない。
(5)人の前、兄弟、家族がいるところでは、叱らない。
(6)あとは、時間を待つ。
(7)しばらくして、子どもが叱った内容を守ったら、
「ほら、できるわね」と、必ずほめてしあげる。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●酒乱
++++++++++++++++++++
私の父がそうだったが、酒が入ると、人が変わった。
ふだんは静かなおとなしい人だった。
が、今から思うと、それがよくなかった。
つまりその分だけ、心の中に別室を作ってしまった。
心理学の世界には、「抑圧」という言葉がある。
防衛機制のひとつにもなっている。
つまり人は何か、不愉快なことが慢性的につづくと、
心の中に別室を作り、その中に、それを押し込んでしまう。
そうして心の平和を保とうとする。
「心の別室」という言葉は、私が考えた言葉だが、
「抑圧」という現象を説明するのには、たいへん便利な
言葉である。
こうして人は、自分の心が崩壊したり、傷ついたりするのを防ぐ。
だから「防衛機制」という。
++++++++++++++++++++
●心の別室
できるなら、心の別室は作らない方がよい。
そのつど、自分を、素直に外へ吐き出すのがよい。
いやだったら、はっきりと「いや」と言うなど。
が、それができないと、心の中に別室を作り、その中に、不愉快なことや、不平、不満を
押し込んでしまう。
そのため、見た目には、心は落ち着く。
しかしそれで問題が解決するわけではない。
折に触れて、「お前は、あのとき!」と、心の別室にあったものが、外に向かって爆発する。
この爆発がこわい。
●上書きのない世界
抑圧され、心の別室に入った、不平や不満は、いわば心の世界から隔離された状態にな
る。
だからワープロの世界でいうような、(上書き)という現象が起きない。
その間に、いくら楽しい思い出があったとしても、一度爆発すると、そのまま過去へと戻
ってしまう。
それこそ10年前、20年前にあったできごとを、つい先頃のことのように思い出して、
爆発する。
子どもの世界でも、よく見られる現象である。
たとえば高校3年生の男子が、母親に向かってこう叫ぶ。
「お前は、あのとき、オレに、こう言って、みなの前で恥をかかせた!」と。
母親が恥をかかせたのが、10年前であっても、またそれ以後、いくら楽しい思い出が
あったとしても、心の別室に入った思い出は、影響を受けない。
そのまま(時)を超えて、外に出てくる。
●時間のない世界
そういう点では、心の別室では、時間は止まったままになる。
止まったまま、時間が、そこで固定される。
だからふつうなら、とっくの昔に忘れてしまってよいようなことを蒸し返して、爆発させ
る。
「お前は、あのとき!」と。
私の父がそうだった。
酒が入ると別人のようになり、暴れ、大声で叫んだ。
そして10年前、20年前の話を思い出して、母を責めた。
こんなことがあった。
●父の心
母がはじめて父と、母の実家へ行ったときのこと。
道の向こうから、母の友人が数人、並んでやってきた。
そのとき母は、何を考え、何を感じたかは知らないが、父に向かってこう言ったという。
「ちょっと隠れていて!」と。
母は父を、橋のたもとにある竹やぶに、父を押し倒した。
父は言われるまま、(多分、訳も分からず)、竹やぶの中に身を潜めた。
が、それが父には、よほど、くやしかったのだろう。
それ以後、5年とか、10年を経て、父は酒を飲むたびに、それを怒った。
「お前は、あのとき、オレを竹やぶに突き倒した!」と。
母は母で、気位の高い人だったから、やせて細い父を、恥ずかしく思ったのかもしれな
い。
母は、よく「かっぷく」という言葉を使った。
太り気味で、腹の出た人を、「かっぷくのいい人」と言った。
母は、また、そういう人を好んだ。
●うつ病
酒乱とうつ(鬱)は、たがいに深くからみあっている。
そのことは、うつ病の人が、緊張状態を爆発させる状態を見ると、よくわかる。
そのときも、(もちろん酒は入っていなくても)、心の別室にたまった、不平や不満が、同
じような形で爆発する。
うつ病も初期の段階では、心の緊張感が取れず、ささいなことにこだわり、悶々と悩ん
だりする。
そこへ不安や心配が入り込んでくると、心の状態は、一気に不安定になり、爆発する。
「爆発」というより、錯乱状態になる。
大声で叫び、ものを投げつける。
ものを壊す。
私の父も、ひどいときには、食卓に並んだ食事類を、食卓ごとすべて土間に投げ捨てて
しまった。
ガラスを割ったり、障子やふすまを破ったりするようなことは、毎度のことだった。
そういう父を、当時は理解できず、私はうらんだが、父は父で、大きな心の傷をもって
いた。
父は、戦時中、出征先の台湾で、アメリカ軍と遭遇し、貫通銃創を受けている。
今にして思えば、その傷が、父をして、そうさせたのだと理解できる。
●子どもへの影響
家庭騒動は、親の酒乱にかぎらず、子どもの心に大きな傷をつける。
恐怖、不安、心配……。
そんなどんな傷であるかは、私自身が、いちばんよく知っている。
子ども自身の心が、二重構造になる。
いじけやすく、ひがみやすくなる。
何かいやなことがあると、やはり心の別室に入り、その中に閉じこもってしまう。
そして自分では望まない方向に自分を追いやってしまう。
ときとして、それが自虐行為につながることもある。
わざと罪のない人に、つらく当たったり、身近な人に冷たくしたりする。
わかりやすく言えば、子どもの心から、すなおさが消える。
心の動きと、行動、表情が、不一致を起こすようになる。
私のばあいも、子ども時代の私をよく知る人は、みな、こう言う。
「浩司は、明るくて、朗らかな子だった」と。
しかしそれはウソ。
そう見せかけていただけ。
私は、そういう形で、いつも自分をごまかして生きていた。
●アルコール中毒
そんなわけで、アルコール中毒と酒乱は分けて考える。
アルコール中毒イコール、酒乱というわけではない。
酒を飲んで、かえって明るく朗らかになる人は、いくらでもいる。
しかしその中の一部の人が、(これはあくまでも私の推測だが)、うつ、もしくはうつ病
と結びついて、酒乱になる。
だから治療となると、この2つは分けて考えたほうがよい。
さらに、私の父のケースのように、その背景に、何らかのトラウマが潜んでいることもあ
る。
異常な恐怖体験が原因で、酒に溺れるようになることだってある。
●みんな十字架を背負っている
先にも書いたが、私は、そういう父を、ある時期恨んだ。
父が死んだときも、涙は、一滴も出なかった。
しかし私自身が、40代、50代になると、父に対する考え方が変わった。
父が感じたであろう孤独、さみしさがよく理解できるようになった。
と、同時に、父に対する恨みも消えた。
そんな私の心情を書いたのが、つぎの原稿。
54歳、つまり8年前に書いた原稿である。
++++++++++++++++
●心のキズ
私の父はふだんは、学者肌の、もの静かな人だった。しかし酒を飲むと、人が変わった。
今でいう、アルコール依存症だったのか? 3〜4日ごとに酒を飲んでは、家の中で暴れ
た。大声を出して母を殴ったり、蹴ったりしたこともある。あるいは用意してあった食事
をすべて、ひっくり返したこともある。
私と六歳年上の姉は、そのたびに2階の奥にある物干し台に身を潜め、私は「姉ちゃん、
こわいよオ、姉ちゃん、こわいよオ」と泣いた。
何らかの恐怖体験が、心のキズとなる。そしてそのキズは、皮膚についた切りキズのよ
うに、一度つくと、消えることはない。そしてそのキズは、何らかの形で、その人に影響
を与える。が、問題は、キズがあるということではなく、そのキズに気づかないまま、そ
のキズに振り回されることである。
たとえば私は子どものころから、夜がこわかった。今でも精神状態が不安定になると、夜
がこわくて、ひとりで寝られない。あるいは岐阜の実家へ帰るのが、今でも苦痛でならな
い。帰ると決めると、その数日前から何とも言えない憂うつ感に襲われる。しかしそうい
う自分の理由が、長い間わからなかった。
もう少し若いころは、そういう自分を心のどこかで感じながらも、気力でカバーしてしま
った。
が、50歳も過ぎるころになると、自分の姿がよく見えてくる。見えてくると同時に、「な
ぜ、自分がそうなのか」ということがわかってくる。
私は子どものころ、夜がくるのがこわかった。「今夜も父は酒を飲んでくるのだろうか」
と、そんなことを心配していた。また私の家庭はそんなわけで、「家庭」としての機能を果
たしていな
かった。家族がいっしょにお茶を飲むなどという雰囲気は、どこにもなかった。だから私
はいつも、さみしい気持ちを紛らわすため、祖父のふとんの中や、母のふとんの中で寝た。
それに私は中学生のとき、猛烈に勉強したが、勉強が好きだからしたわけではない。母に、
「勉強しなければ、自転車屋を継げ」といつも、おどされていたからだ。つまりそういう
「過去」が、今の私をつくった。
よく「子どもの心にキズをつけてしまったようだ。心のキズは消えるか」という質問を
受ける。が、キズなどというのは、消えない。消えるものではない。恐らく死ぬまで残る。
ただこういうことは言える。心のキズは、なおそうと思わないこと。忘れること。それに
触れないようにすること。
さらに同じようなキズは、繰り返しつくらないこと。つくればつくるほど、かさぶたをめ
くるようにして、キズ口は深くなる。
私のばあいも、あの恐怖体験が一度だけだったら、こうまで苦しまなかっただろうと思う。
しかし父は、先にも書いたように、3〜4日ごとに酒を飲んで暴れた。だから54歳にな
った今でも、そのときの体験が、フラッシュバックとなって私を襲うことがある。「姉ちゃ
ん、こわいよオ、姉ちゃん、こわいよオ」と体を震わせて、ふとんの中で泣くことがある。
54歳になった今でも、だ。心のキズというのは、そういうものだ。決して安易に考えて
はいけない。
++++++++++++++++++++++
●父のうしろ姿(中日新聞に書いたコラムより)
私の実家は、昔からの自転車屋とはいえ、私が中学生になるころには、斜陽の一途。私
の父は、ふだんは静かな人だったが、酒を飲むと人が変わった。二、三日おきに近所の酒
屋で酒を飲み、そして暴れた。大声をあげて、ものを投げつけた。そんなわけで私には、
つらい毎日だった。プライドはズタズタにされた。友人と一緒に学校から帰ってくるとき
も、家が近づくと、あれこれと口実を作っては、その友人と別れた。父はよく酒を飲んで
フラフラと通りを歩いていた。それを友人に見せることは、私にはできなかった。
その私も五二歳。一人、二人と息子を送り出し、今は三男が、高校三年生になった。の
んきな子どもだ。受験も押し迫っているというのに、友だちを二〇人も呼んで、パーティ
を開くという。「がんばろう会だ」という。土曜日の午後で、私と女房は、三男のために台
所を片づけた。
片づけながら、ふと三男にこう聞いた。「お前は、このうちに友だちを呼んでも、恥ずかし
くないか」と。すると三男は、「どうして?」と聞いた。理由など言っても、三男には理解
できないだろう。私には私なりのわだかまりがある。私は高校生のとき、そういうことを
したくても、できなかった。友だちの家に行っても、いつも肩身の狭い思いをしていた。「今
度、はやしの家で集まろう」と言われたら、私は何と答えればよいのだ。父が壊した障子
のさんや、ふすまの戸を、どうやって隠せばよいのだ。
私は父をうらんだ。父は私が三〇歳になる少し前に死んだが、涙は出なかった。母です
ら、どこか生き生きとして見えた。ただ姉だけは、さめざめと泣いていた。私にはそれが
奇異な感じがした。が、その思いは、私の年齢とともに変わってきた。四〇歳を過ぎるこ
ろになると、その当時の父の悲しみや苦しみが、理解できるようになった。
商売べたの父。いや、父だって必死だった。近くに大型スーパーができたときも、父は「J
ストアよりも安いものもあります」と、どこか的はずれな広告を、店先のガラス戸に張り
つけていた。「よそで買った自転車でも、パンクの修理をさせていただきます」という広告
を張りつけたこともある。しかもそのJストアに自転車を並べていたのが、父の実弟、つ
まり私の叔父だった※。叔父は父とは違って、商売がうまかった。父は口にこそ出さなか
ったが、よほどくやしかったのだろう。戦争の後遺症もあった。父はますます酒に溺れて
いった。
同じ親でありながら、父親は孤独な存在だ。前を向いて走ることだけを求められる。だ
からうしろが見えない。見えないから、子どもたちの心がわからない。ある日気がついて
みたら、うしろには誰もいない。そんなことも多い。ただ私のばあい、孤独の耐え方を知
っている。父がそれを教えてくれた。客がいない日は、いつも父は丸い火鉢に身をかがめ
て、暖をとっていた。あるいは油で汚れた作業台に向かって、黙々と何かを書いていた。
そのときの父の気持ちを思いやると、今、私が感じている孤独など、何でもない。
私と女房は、その夜は家を離れることにした。私たちがいないほうが、三男も気が楽だ
ろう。いそいそと身じたくを整えていると、三男がうしろから、ふとこう言った。「パパ、
ありがとう」と。そのとき私はどこかで、死んだ父が、ニコッと笑ったような気がした。
(注※)この部分について、その実弟の長男、つまり私の従兄から、「事実と違う」という
電話をもらった。「その店に自転車を並べたのは、父ではなく、私だ」と。しかし私はその
叔父が好きだったし、ここにこう書いたからといって、叔父や従兄弟をどうこう思ってい
るのではない。別のところでも書いたが、そういう宿命は、商売をする人にはいつもつい
て回る。だれがよい人で、だれが悪い人と書いているのではない。ただしその従兄に関し
ては、以後、印象は、180度変わった。以後、断絶した。誤解のないように。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●憎むvs恨む
人を恨んだり、憎んだりするのも、たいへん。
ものすごいエネルギーを消耗する。
だったら、恨んだり、憎んだりするのは、やめたらよい。
反対に、その人のために、祈ってやる。
「どうか、心を平安に」と。
というのも、恨まれたり、憎まれるような人は、そういう人。
放っておいても、自ら墓穴を掘っていく。
定められた運命に沿って、自らの道を選んでいく。
私やあなたが、どうこうしたところで、その運命は、変えられない。
あとのことは、その人自身の運命に任せればよい。
●相手にしない
こういう私の意見に対して、ワイフはこう言う。
「憎むも、恨むもないわよ。何も考えなければいいのよ」と。
つまりあれこれと気を回すから、こちらも疲れる。
まったく忘れてしまえば、それでよい、と。
ワ「話しあったところで、何も解決しないでしょ」
私「そうだね」
ワ「どうせわかる相手でないし……」
私「そう。そういう限界は、このところよく感ずる」
ワ「そうよ」と。
●人生のドラマ
人生にはいろいろなことがある。
その(いろいろなこと)が、無数のドラマを作り、それが人生を楽しくする。
みながみな、聖人でも、この世の中は、つまらない。
(悪人でも、困るが……。)
あっちで衝突し、こっちで衝突し、そうした(衝突)の中から、ドラマが生まれる。
もっとも当事者は、とことん神経をすり減らすが……。
それに人とのトラブルは、できるだけ避けたい。
平凡は、それ自体が、美徳。
だから……。
あなたの身の回りに、恨んだり、憎んだりしなければならないような人がいたら、
無視すればよい。
ただひたすら、無視。
あとはワイフが言うように、忘れる。
忘れて、自分の心の平安を大切にする。
Hiroshi Hayashi++++++++Oct. 09+++++++++はやし浩司
●相続問題
++++++++++++++++++++++
相続問題が、これほどまでに厄介なものとは、
思わなかった。
人間の欲得には、際限がない。
その際限のなさが、相続問題を、こじらせる。
++++++++++++++++++++++
●額には関係なし
数億円の相続財産があるというのなら、まだわかる。
争うだけの価値は、ある(?)。
しかし実際には、わずか数百万円の財産を取りあって、兄弟姉妹が、骨肉の争いを
繰り返す。
そんな例は、いくらでもある。
金銭問題がこじれると、とかく人間関係はこじれやすい。
そこへ相続問題がからむと、さらにこじれる。
たいてい泥沼化し、やがて悪臭を放つようになる。
●1円ももらえなかった
A子さん(現在60歳)の父親が亡くなって、もう20年になる。
A子さんは、現在、85歳の母親と、2人暮らしをしている。
そのA子さんが、こんな話をしてくれた。
「歳をとればとるほど、人はお金に執着するようになる」と。
85歳になった母親が、毎日、お金の話ばかりしているという。
やや認知症ぽいところはあるが、その年齢の女性にしては、平均的とのこと。
●20年も前の話
A子さんの母親は、今でもことあるごとに、こう言うという。
「私は、(亡くなった夫の)実家から、遺産分けをしてもらっていない」と。
亡くなった……といっても、先にも書いたように、それからもう20年になる。
その夫には、2人の兄弟がいた。
(亡くなった夫も含めて、3人。
うち2人は、すでに他界。現在は、末の三男が郷里の実家に住んでいる。)
亡くなった夫は、その中の二男だった。
たいした財産ではなかった。
G県の山奥の、もとはと言えば、小作農。
しかも夫が生きている間は、夫婦喧嘩ばかりしていた。
そんな妻であっても、亡き夫の相続財産に執着し、「私たちは、遺産相続を
してもらえなかった」「1円ももらっていない」と。
●兄弟関係
こだわる人は、こだわる。
こだわらない人は、こだわらない。
それが相続問題である。
「親の財産など、最初からアテにしないこと」とは言うが、その年齢が
近づいてくると、何かと気になる。
日ごろから、兄弟姉妹関係が良好なら、まだ救われる。
が、関係がおかしくなると、とたん、相続問題が浮上する。
「判を押す」「押さない」がこじれて、裁判沙汰になるケースも少なくない。
●便利な『ダカラ論』
義兄はこう話してくれた。
「ぼくにも、2人の妹がいるが、あいつら、ときとばあいに応じて、ダカラ論を
うまく使い分ける」と。
お金を払う話になると、「私らは女だから」「家を出た身分だから」と言う。
つまり「払わない」「払う必要はない」と。
しかしこと遺産相続の話になると、「私らも、子どもだから」と。
「子どもだから、分け前にもらう権利がある」と。
つまり自分の都合に応じて、『ダカラ論』を、うまく使い分ける、と。
相続問題がからんでくると、その『ダカラ論』が、がぜん、多くなる。
●遺言
こうした問題が起きないようにするには、親自身が、自分の死後をしっかりと
見つめながら死ぬしかない。
親の威光(?)がまだそれなりの力がある間は、こうした問題は、地下にもぐっている、
しかし親の威光が鈍り始めたとたん、表に顔を出す。
冒頭に書いたように、「額」の問題ではない。
(もちろん相続財産が巨額であれば、問題は起きやすいが……。)
そこで「遺言」ということになる。
しかしこれは公正証書として、文書化しておく必要がある。
というのも、私の母もそうだったが、そのつど世話になる人に向かって、
「あの家はお前にやる」「この家はあなたにあげる」などと言ったりする。
それを聞いた人は、その言葉を真に受けてしまう。
それが騒動の原因になる。
●協議分割
財産分与の仕方には、いろいろある。
一般的には、兄弟に、遺産相続放棄をしてもらうという方法がある。
が、最近、よく使われるのが、「協議分割」という方法。
これは当事者どうしがあらかじめよく話しあい、それぞれの取り分を
数値で示しておくという方法。
もし長男がすべてを相続するというのであれば、分割割合のところに、「全財産」と
明記しておけばよい。
あとは相手方の、印鑑証明と実印の捺印、それに住民票があればよい。
●伏兵
が、この段階で、別の問題が起きることがある。
親が死ぬころというのは、息子も、娘も、その年齢になる。
平均的な家族で考えれば、60〜70歳。
そのころになると、認知症の心配も出てくる人もいる。
そのときはよく納得して判を押したとしても、数か月、あるいは数年も
すると、「私は知らない」「判を押した覚えはない」と言って、騒ぎ出す。
そういうケースも、たいへん多い。
たいていは、その子孫がそれに同調する。
「書類が偽造された」「おやじは、叔父に財産を横取りされた」と言って、騒ぎ出す。
●無知
しかし民法の世界では、とくに不動産関係の世界では、「書類」がすべて。
書類に始まって、書類に終わる。
その書類に不備がなければ、よほどのことがないかぎり、(事実)がひっくり返る
ということは、ない。
不動産は、つぎつぎと転売されていくことが多い。
分割されることも多い。
その途中で、「契約無効」ということになると、それ以後の社会生活に深刻な
影響を及ぼす。
ここでいう「よほどのこと」というのは、公文書偽造のような犯罪性のある行為をいう。
(が、それでも一度動いた権利関係を、もとに戻すのはむずかしい。)
で、ある女性(64歳)は、法務局の窓口で、「私はこんな書類に判を押した覚えはない」
「署名した覚えはない」と言って、泣き叫んだという。
しかし印鑑は、その女性の実印。
署名したのは、その女性自身。
直筆。
結局、その女性は、一度は、相続放棄はしたものの、あとになって、惜しくなったらしい。
それで腹を立てて、異議を申し立てた
が、こんな道理は、この世界は、通用しない。
そのあと弁護士に相談したというが、もちろん、門前払い。
●孫が相続権を争う?
司法書士をしている友人のM氏は、こう話してくれた。
「今では、遺産相続権者である当の本人というよりは、さらにその下の
息子や娘が、騒ぐケースがふえている」と。
たとえば実の親が死ねば、その息子や娘が、相続権者ということになる。
で、そういう相続権者が、相続を争うのは、まだ話がわかる。
が、実際には、さらにその息子や娘、つまり相続権のない息子や娘(=死んだ
実の親の孫たち)が、遺産相続をめぐって争うケースがふえているという。
M「つまりね、孫たちが、親にも取り分があるといって、親をたきつけて、
騒動を大きくするんだね」
私「……なるほど。孫の代になると、人間関係も希薄になっているから、その分だけ、
騒ぎやすいというわけか」
M「そうなんだよな。もらえるべきものは、もらうべきという、おかしな平等意識
ばかり、強くてね」と。
●教訓
繰り返すが、こと遺産相続に関しては、書類に始まって、書類に終わる。
その書類を、しっかりと整えておくこと。
さらに土地の権利関係においては、書類がすべてを物語る。
これは鎌倉時代の、地頭の時代からの常識。
ずっとあとになって、「そんなつもりはなかった」と言っても、
それこそ、「あとの祭り」。
実印を捺印するときはもちろん、署名するときも、それなりの覚悟と
確認をしっかりとすること。
遺産相続問題がからんでいるときは、なおさらである。
●付記
こうして兄弟姉妹が、バラバラになっていくケースは、たいへん多い。
ざっと私の周辺をながめてみても、すんなりとこうした問題が片づいていくケースは、
10に、1、2もない。
言い換えると、兄弟姉妹に幻想はもたないこと。
甘えはもたないこと。
その(甘え)が、騒動を大きくする。
だからくしくも昔の人はこう言った。
『兄弟は、他人の始まり』と。
まさに核心をついた言葉である。
Hiroshi Hayashi++++++++Oct. 09+++++++++はやし浩司
●認知症
+++++++++++++++++++++
認知症は、こわい!
昨日、こんな話をワイフから聞いた。
何でもその女性の義母(68歳くらい)が、
毎晩のように、こう叫ぶという。
「ワシ(=私)のサイフを、嫁(=その女性)が盗んだ!」
「嫁が、夕飯を食わせてくれない!」
「嫁が、土地を勝手に処分してしまった!」と。
68歳と言えば、まだ若い。
ワイフは、「若年性アルツハイマー病らしいわね」と言ったが、
その可能性は、高い。
そういう話は、よく耳にする。
で、その母親には、3人の娘がいる。
その3人の娘が、義母の話を真に受けて、その女性に対して、
よくない印象をもち始めているという。
つまり、疑いの目で、その女性を見始めているという。
「私がきちんと説明しても、横目で、『そうかしら?』と、
いかにも疑っていますという顔で、私を見つめるのね」と。
で、その女性が夫(=母親の実子、長男)に、「お母さん、おかしいから、
病院へ連れていってみたら?」と声をかけるのだが、この夫が、また
たいへんなマザコン。
そのつど、「母は、何ともない」「お前がしっかりしろ」と、
反対に怒鳴り返されてしまうという。
で、こうなると、打つ手なし。
3人の娘たちは娘たちで、「自分の相続の取り分が少なくなる」と、もう、今から
そんな心配をしているという。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 23日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page025.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
休みます
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●決別
++++++++++++++++++++++++
すでに、5、6年前のこと。
すでに心に、そう決めていた。
私は、母が死に、兄が死に、実家を片づけたら、
古里のM町からは縁を切ろうと。
だから兄が死に、母が死んだときも、その一方で、
「あと少しのがまん」と、自分で、自分に言って聞かせた。
もちろんだからといって、兄や母の死を喜んだというわけではない。
待ち望んでいたというのでもない。
母や兄と言うよりは、「実家」。
つまり私にとって、実家は、それほどまでに重いものだった。
この60年間、1日とて、心の晴れた日はなかった。
そうでない人には、信じられないような話かもしれないが、
私には、そうだった。
が、昨年の8月、兄が他界した。
つづいて10月、母が他界した。
葬儀だ、法事だと、あわただしく日々が過ぎた。
が、それも一段落すると、私は、すぐ実家の売却を計画した。
そのときすでに空家になって、5年になっていた。
M町の中でも、一等地(?)にあるということで、税金の負担も大きかった。
といっても、私はその税金を、30年以上、払いつづけてきた。
今さら負担という負担ではなかったが、放っておいても、朽ちるだけ。
おまけに市の伝統的建造物に指定され、壊したり、改築することもできなかった。
私は、親類には、ハガキで、こう知らせた。
「母の一周忌前後には、実家を売却を予定します。あらかじめご了承ください」と。
母の四九日の法要の連絡のときのことである。
+++++++++++++++++++++++++
●心の整理
数年単位の、時間が必要である。
心の整理が必要である。
「今日決めたから、明日、売却」というわけにはいかない。
古い柱、一本一本に、思い出がしみ込んでいる。
一歩、外に出れば、街の人たちの顔もある。
みな、顔なじみ。
「縁を切る」というのは、そういう人たちとの決別も意味する。
●決別
こう書くと「決別まで……!」と驚く人も多いかもしれない。
しかしあの街には、私のゴミのようなものが、山のようにたまっている。
母の時代から、私は、あの街では、悪者だった。
「親を捨て、浜松の女性と結婚した」
「親の財産を、全部、自分のものにした」
「勝手に仏壇を、浜松に移した」
「親の葬儀を浜松でした」などなど。
先日も実家へ帰り、近くの店に宅配便を届けたときも、その店の女性にこう言われた。
「あなた、親類の断りもなく、仏壇を浜松へ移したんだってねエ……」と。
イヤミたっぷりの、不愉快な言い方だった。
その言葉を聞いたとき、M町への思いが、ふっ切れた。
●売却
実家の売却は、簡単なものだった。
買い主がお膳立てしてくれた銀行にみなが集まり、そこで書類に判を押して、それでおし
まい。
買い主の女性が、何度も「ありがとうございます」と頭をさげるほど、格安の価格だった。
が、価格など、問題ではない。
あの実家に貢いだ現金だけでも、その20倍以上はある。
が、それよりも、私の人生の大半は、あの実家のために犠牲になってしまった。
そうした(損害?)と比べたら、家の価格など、何でもない。
今さら、わずかな金額を手にして、それでどうなる?
私の心が、どう癒される?
私の人生が、どう戻ってくる?
●離縁
「縁を切るというのは、こういうことだね」と、ワイフに話した。
心の中を、からっぽにする。
未練を残さない。
あっても、きれいさっぱり、それを忘れる。
掃除をして、心の外に掃き出す。
私はその日、家の中に残っていた家財道具を、道路に並べた。
ビニールシートを敷き、その上に並べた。
花瓶、火鉢、食器類、掛け軸、棚、電気製品、家具などなど。
本うるしの漆器も数百個あったが、それも並べた。
で、ゆっくりと張り紙をした。
「長い間、お世話になりました。
使っていただけるものがあれば、どうぞ、使ってください。
ご自由に、お持ち帰りください」と。
やがてすぐ、何10人もの人たちが集まり、それぞれが、それぞれを家にもって帰った。
中には、漆器類を、袋につめて帰る人もいた。
●未練
少しおおげさな言い方になるかもしれないが、人は、死ぬときも、そうではないか。
つまり心の整理をする。
未練を消す。
心がきれいさっぱりしたところで、この世に別れを告げる。
「告げる」といっても、相手はいない。
自分の心に告げる。
一方、「私」にこだわっているかぎり、平安な日々はやってこない。
「私の財産」「私の地位」「私の名誉」と。
そういうものをすべて捨てる。
捨てて、身のまわりから、何もかも消す。
そのとき人は、さばさばとした気持ちで、「死」を、迎え入れることができる。
●9月3日
翌朝、長良川のほとりにある緑風荘という旅館で一泊したあと、そのまま浜松へ帰って
きた。
一度、実家に立ち寄り、「最後に……」と思って、外から実家をながめた。
実家は、そのままそこにあった。
父が手作りで書いた看板だけが、強く印象に残った。
「林自転車店」と、それにはあった。
「家は残るとしても、看板はどうなるんだろう?」とふと、そんなことを考えた。
が、長くはつづかなかった。
私とワイフは、ほとんど立ち止まることなく、そのまま駅の方に向かって歩き出した。
ゆるい坂道だった。
白い朝日が、まぶしかった。
私「二度と、この町に来ることはないね」
ワ「二度と……?」
私「何か、特別な用事でもないかぎりね……。でも、もう来ないよ」と。
すべてが終わった。
本当に、すべてが終わった。
2009年9月3日のことだった。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●ルーム・ウォーカー
毎日、40〜50分は、ルーム、ウォーカーで、歩いている。
当初は、10分とか、1キロに設定していたが、
最近は、20分とか、2キロに設定している。
(使用時間か、距離数で設定できるようになっている。)
それはそれでよいのだが、……というか、やはり
20分はしないと、汗は出てこない。
有酸素運動ということになれば、20分以上は、したほうがよい。
10月からは、1回につき、30分に挑戦してみる。
ところが、である。
予期しなかった現象が出てきた。
伏兵というのである。
実は、昨日、道路を歩いていて、2度もころびそうになった。
一度は、階段を上がるとき。
もう一度は、何と、深々としたジュータンの上を歩くとき。
理由はやはり、ルーム・ウォーカーにあることがわかった。
ルーム・ウォーカーでは、歩くとき、膝をほとんどあげないで歩く。
(いざり歩き)というか、足裏をベルトにほとんどこすりつけるようにして歩く。
それがクセになり、そのままの歩き方で、道路を歩く。
ちょっとしたことで、つまずくようになった(?)。
そこで私は考えた。
ルーム・ウォーカーに、ハードル競技のような、小さなハードルをとりつけることにした。
足でひっかけてもよいように、厚紙のようなものでつくればよい。
まだ実行していないが、このあと朝食が終わったら、さっそく、やってみよう。
そうすれば歩くのに合わせて、膝をあげるようになる。
うまくいけばよいのだが……。
ところでその分だけ、このところサイクリングをする回数が減っている。
居間でいつでも運動ができる……という思いが、サイクリングを減らす理由になっている。
便利なことはよいのだが、ルーム・ウォーカーにも、いろいろ問題があるようだ。
●ミニパソコン
ミニパソコンを、現在、3台使っている。
HP社のもの、MSI社のもの、それにACER社のもの。
それぞれに一長一短があって、どれがよいということにはならない。
が、今の私には、ACER社のものが、いちばん使い勝手がよい。
「ASPIRE ONE」という機種である。
ただし画面が8インチしかない。
で、現在、10インチのものに交換しようしている。
が、どこの店も、「下取りはしません」とのこと。
しかたないので、ネットで、新しいのを注文しようと考えている。
価格は、どんどんさがって、今では、3万4000円前後。
最初に買ったときの、約半額!
どうしようか?
●芝生
秋になったせいなのか、芝生の一部が枯れ始めた。
水不足かもしれない。
この数か月間で、まとまった雨が降ったのは、2回だけ。
これでは芝生も、根を張ることさえできない。
で、昨日、近くの店で、肥料を買ってきた。
全体にまいて、その上にたっぷりと水をかけてやった。
今は、その芝生の先端に、無数の種らしきものができている。
そのため芝刈り機で、芝を刈ることもできない。
今しばらく様子を見て、……つまりもう少し芝が伸びるのを見届けてから、芝を刈るつも
り。
●ハトの巣
居間の前の栗の木に、ドバトが巣を作り始めた。
が、今朝見たら、巣は、からっぽ!
「どうしたんだろ?」とワイフに話しかけたら、ワイフが、「リスよ」と。
リスが出没するようになって、もう10年近くになる。
当初は、餌まで買ってきて歓迎したが、それはまちがいだった。
リスのおかげで、野鳥が巣を作らなくなってしまった。
前にも書いたが、リスは、地上のネズミ。
長いシッポの生えた、ネズミ。
あんなリスを見て、「あら、かわいい」と喜んでいる人の気がしれない。
(今日は9月27日、日曜日)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●エネルギー
++++++++++++++++++
大学時代の友人のこと。
数か月前、その友人が、
交通事故訴訟で、やっと結審を迎えた。
長い裁判だった。
4〜5年もかかった。
本来なら、もっと早く片づくべき裁判
だった。
が、保険会社がごねた。
この不況下ということもある。
保険会社は、支払い保険金をできるだけ安く
すませようする(?)。
そこで結果的には、裁判は、東京高裁にまで
もちこまれた。
しかし裁判をつづけるにも、それなりの
エネルギーがいる。
長くて、苦しい闘いがつづく。
いくら「勝つ」とわかっている裁判でも、
「裁判をする」ということ自体、不愉快。
裁判所へ足を運ぶということだけでも、
たいへん。
気が滅入る。
膨大なエネルギーを消耗する。
その日が来るたびに、重苦しい気分に
包まれる。
++++++++++++++++++
●不正の追及
正義を貫くには、それほどの努力はいらない。
それなりに自分を守れば、それですむ。
たいへんはたいへんだが、しかし悪の追及と比べたら、何でもない。
とくに力関係に差があるときは、そうである。
たとえば(個人)と(組織)。
個人が、組織の悪と対峙したようなばあいを考えてみよう。
個人のもつ財力、人脈には限界がある。
一方、組織には、財力も人脈もある。
冒頭に書いた友人の交通事故裁判にしても、そうだ。
訴えるのは、個人。
相手は巨大組織。
地裁という下級審においても、3〜4年の歳月を要した。
裁判をつづけながら、友人は、その一方で、週に3〜4回、病院へ通わねばならなかった。
「首の骨のズレは、交通事故によるものではない。老化によるもの」というのが、保険会
社の言い分だった。
ほかにもいろいろある。
いろいろあって、そのつど難ぐせをつけ、保険会社は、保険金の支払いをしぶった。
保険会社という大企業にとっては、裁判といっても、事務手続きのひとつにすぎない。
しかし被害者である個人にとっては、そうではない。
そうでないことは、裁判を経験したことがある人なら、みな、知っている。
裁判でなくても、家庭裁判所の調停でもよい。
あのイヤ〜ナ気分には、独特のものがある。
●トラブル
それがどんなトラブルであるにせよ、人は、できるだけトラブルに巻き込まれるのを避
けようとする。
わずらわしい。
本当に、わずらわしい。
いわんや、裁判をや!
私も、20年近く前、貸金の返還請求というのをしたことがある。
たいした額ではなかったが、相手の男の不誠実な態度が許せなかった。
それで最終的には、民事調停ということになったが、あのとき感じた、イヤ〜ナ気分は、
今でも忘れない。
それを知っているから、友人も、さぞかし不愉快な思いをしたにちがいない。
その友人は、こう言っている。
「林君、保険に入るとしても、民間の保険会社とは契約してはいけないよ。
公的な機関の保険に加入したほうがいいよ」と。
私も、それまでに、30年近く民間の生命保険会社と契約を結んでいたが、10年ほど
前、解約した。
一度、何かのことで保険金を請求しようと電話を入れたら、窓口の女子店員に、門残払い
をされてしまった。
私の話すら、じゅうぶんに聞いてくれなかった。
「病気になり、後遺障害が残ったら、保険金の支払いの対象になるとあるではないか」と
迫ったが、だめだった。
相手にされなかった。
不信感がつのり、そのまま解約。
それにしても、裁判だけで、4〜5年。
最後は、東京高裁!
こんなバカげた保険会社が、どこにある!
そうそう友人は、こうも言った。
「あいつら、とにかく保険金を払わない。
だから『裁判で争おう』と、しっかりと言うことだ。
そうすれば、払ってくれる」と。
●本漆(ほんうるし)
実家を処分したとき、古い家財が、ごっそりと出てきた。
その中でも、価値があると思われるのは、本漆(ほんうるし)の食器類。
たいはんは、近所の人たちに無料で分けてやった。
残ったのは、この浜松へ持ち帰った。
が、何と言っても量が多い。
そこで毎晩のように、仲のよいいとこたちに電話をかけ、それを分けてやっている。
みんな、喜んでくれている。
で、昨夜、改めて箱を見たら、「大正11年」と書いてあった。
今から100年近くも前の漆器である。
「古いもの」とは思っていたが、そこまで古いとは、思っていなかった。
ズシリと重い。
塗りが厚いので、深みがまるでちがう。
しかも本漆。
スポンジで洗っただけで、そのまま新品のような光沢を放つ。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●ニッポン放送「石原良純のピーカン子育て日和」
+++++++++++++++++++++
10月1日(木曜日)午後2:15〜ごろから、
ニッポン放送「石原良純のピーカン子育て日和」
にて、「子どもの叱り方」について話します。
興味のある方は、どうか、聴いてください。
+++++++++++++++++++++
●12月13日・秋田県・秋田県庁で講演します。
10:00〜12:00ごろです。
読者の中で、秋田県の方がいらっしゃれば、ご一報
ください。
招待いたします。
++++++++++++++++++++
●帰すう本能(The Last Home)
+++++++++++++++++++
晩期の高齢者たちは、ほとんど例外なく、みな、こう言う。
「〜〜へ帰りたい」と。
母もそうだったし、兄もそうだった。
母は、自分が生まれ育った、K村の実家に、
兄は、やはり自分が生まれ育った、M町の実家に。
それぞれが、「帰りたい」と、よく言った。
私の30年来の友人も、昨年(08年)に亡くなったが、
その友人も、九州の実家に帰りたいと、いつも言っていた。
こうしたことから、みな、人は死が近づくと、自分の
生まれ育った実家に帰りたがるようになると考えてよい。
それをそのまま「帰すう本能」と断言してよいかどうかは、
私にもわからない。
あえて言えば、正確には、「原点回帰」ということか。
しかしこんな言葉は、私が考えたもので、辞書にはない。
つまり「死ぬ」ということは、(生まれる前の状態)に戻ること。
だから死が近づけば近づくほど、人はみな、原点に回帰するようになる。
その願望が強くなる。
原点で安らかな死を迎えるために……。
++++++++++++++++++++++++++
●私の場合は、どうか?
私もあと10〜15年もすると、そうした老人の仲間入りをする。
これは可能性の問題ではない。
確実性の問題である。
そのときうまく特別養護老人ホームに入居できればよし。
そうでなければ、独居老人となり、毎日悶々とした孤独感と闘いながら、暗い日々を送る
ことになる。
そのときのこと。
私は、どこへ帰りたいと言うだろうか?
理屈どおりに考えれば、私は、生まれ育ったM町の実家に帰りたいと言い出すにちがい
ない。
記憶というのは、新しいものほど、脳から消えていく。
そのためM町の記憶しか残らなければ、そうなる。
が、私は子どものころから、あのM町が、嫌いだった。
今でも、嫌い。
そんな私でも、その年齢になったら、「M町に戻りたい」と言いだすようになるのだろうか。
●放浪者
私は基本的には、放浪者。
ずっと放浪生活をつづけてきた。
夢の中に出てくる私は、いつも、あちこちをさまよい歩いている。
電車に乗って家に帰るといっても、今、住んでいるこの浜松市ではない。
この家でもない。
もちろん実家のあるM町でもない。
ときどき「これが私の家」と思って帰ってくる家にしても、今のこの家ではない。
どういうわけか、大きな、ときには、大豪邸のような家である。
庭も広い。
何百坪もあるような家。
見たこともない家なのに、どういうわけか、「私の家」という親近感を覚える。
で、たいていそのまま、目が覚める。
が、夢の中に出てくる家は、そのつど、いつもちがう。
つぎにまた見るときは、今度は別の家が、夢の中に出てきたりする。
つまり私は基本的には、放浪者。
無宿者。
根なし草。
●M町の実家
が、ここ5、6年は、ときどき、M町の実家が夢の中に出てくることがある。
表の店先のほうから中へ入ると、そこに母がいたり、兄がいたりする。
祖父や、祖母がいたりすることもある。
先日は、家に入ると、親戚中の人たちが集まっていた。
みんな、ニコニコと笑っていた。
もちろんいちばん喜んでくれるのが、私の母で、「ただいま!」と声をかけると、うれしそ
うに笑う。
兄も笑う。
が、私は、実家ではいつも客人。
みなは、私を客人として迎えてくれる。
私の実家なのだが、実家意識は、ほとんど、ない。
●徘徊老人
こう考えていくと、私はどうなるのか、見当がつかない。
認知症になり、特別養護老人センターに入居したとする。
そんなとき、私は、どこへ帰りたいと言うだろうか。
それをワイフに話すと、ワイフは、こう言った。
「あなたは、まちがいなく、徘徊老人になるわよ」と。
つまりあてもなく、あちこちをトボトボと歩き回る老人になる、と。
そうかもしれない。
そうでないかもしれない。
しかしその可能性は、たいへん高い。
先にあげた友人にしても、九州出身だったが、いつも浜松市内を徘徊していた。
距離が遠いから、まさか九州まで歩いて帰るということはなかった。
しかし気持の上では、九州まで歩いて帰るつもりではなかったか。
今にして思うと、友人のそのときの気持ちが、よく理解できる。
●さて、あなたはどうか?
さて、あなたはどうか?
そういう状況になったとき、あなたなら、どこへ帰りたいと言いだすだろうか。
たいていの人は、自分が生まれ育った実家ということになる。
確たる統計があるわけではないが、90%以上の人が、そうなるのではないか。
が、残り10%前後の人は、帰るアテもなく、浮浪者のように、そのあたりをさまよい
歩く。
ところで徘徊する老人は多いが、そういう老人をつかまえて、「どこへ帰るの?」と聞く
と、ほとんどが、「うちへ帰る」と答えるという。
たぶん、私も、「うちへ帰る」と答えるだろうが、その「うち(=家)」とは、どこのこと
を言うのだろうか。
帰りたい家があり、その家が、あなたをいつまでも暖かく迎えてくれるようなら、そん
なすばらしいことはない。
しかし現実には、住む人の代もかわり、家そのものもないケースも多い。
こう考えただけでも、老後のさみしさというか、悲哀が、しみじみとよくわかる。
「老人になることで、いいことは何もない」。
そう断言してもよい。
そういう時代が、私のばあいも、もうすぐそこまで来ている。
(付記)
最近、ワイフとよく話し合うのが、「終(つい)の棲家」。
で、結論は、終の棲家は、この家の庭の中に建てよう、である。
街の中のマンションも考えた。
病院やショッピングセンターに近いところも考えた。
しかし、私たちの終の棲家は、どうやらこのまま、この場所になりそう。
今、別のところに移り住んでも、私たちは、そこには、もうなじめないだろう。
頭の働きが鈍くなってきたら、きっと私も、今のこの家に帰りたいと、だだをこねるよう
になるだろう。
だったら、終の棲家は、ここにするしかない。
・・・というのが、今の私たちの結論になりつつある。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW 終の棲家 帰すう本能 帰趨本能 徘徊 徘徊老人)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●9月30日(水曜日)
++++++++++++++++++++
今日で、9月もおしまい。
昨夕、G町の従兄弟が送ってくれた、鮎(あゆ)を、
塩焼きにして食べた。
「少し、塩をつけつぎたかな?」ということで、
今朝は、胃の中が、どうもすっきりしない。
いつもならご飯を1杯ですますところを、昨夕は、
2杯も食べてしまった。
で、その直後体重計を見たら、何と、61・5キロ!
たった1日で、1・5キロもふえてしまった。
怖しいことだ!
木曽川のタタリじゃア!
++++++++++++++++++++
●明日から10月
明日から10月。
とくに大きな予定は、ない。
いくつか講演の仕事が入っている。
そのレジュメ(概要)を、今日中に作成しよう。
それから秋田県のほうから講演依頼があった。
実のところ先月までは、遠方のは、すべて断ってきた。
が、今月から、心境が大きく変化した。
講演先で温泉に入る楽しみを、覚えてしまった。
それで変化した。
秋田といえば、湯沢温泉。
片道、7時間半の長旅になるが、かえってそれが楽しみ。
「講演をして、お金を稼ごう」という意識が、ほとんどなくなったせいもある。
かわって、「元気なうちに、できることをやっておこう」という意識が生まれた。
だから秋田県へ行く。
最高の講演をしてくる。
浜松人の心意気を、見せてやる。
「やらまいか」ということで、喜んで引き受けた。
●ニッポン放送
明日、ニッポン放送で、話す機会をもらった。
電話による応答番組だが、肝心のスタジオがない!
時間的に、市内の事務所を使うことになるが、目下、隣地は工事中。
終日、ユンボ類が、ガーガー、ゴーゴーと音を出している。
雑音が入ってはいけない……ということで、昨日、炊事室を急きょ、スタジオに改造。
電話線を延長して、電話機を炊事室へ。
マットをドアにあてる。
昨日テストしてみたが、「これならいけるわ」とワイフ。
全国放送。
あまり気負わないで、気楽に話そう。
●指が痛い!
右手中指の先端がパンパンに腫れている。
ささくれを指でちぎったのが、悪かった。
中で化膿した。
何とかこうしてごまかしてキーボードを叩いているが、痛い。
となりの薬指が軽くあたっただけで、キリキリと痛む。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●TK先生より
++++++++++++++
4月に人工関節の手術を受けた。
そのTK先生から、メールが
届いていた。
今は、ニンジンジュースがよいとか。
さっそく我が家でも、昨日から、
ニンジン料理をふやした。
++++++++++++++
林様:
膝の方は出来るだけ街まで歩くようにしています。往復して四、五千歩で一日に七,
八千歩になっています。手術のお蔭で、歩く時の痛さはなくなりましたが、未だヨタヨタ
歩きで、普段片道15分のところを23分ぐらいかかって、歩いています。普通になるま
で一年はかかるそうです。しかし手術以前は歩くのが辛くて、歩かないと全身が老化しま
すので、先が短いのを承知でも、手術をしてよかったと思っています。
この二ヶ月間始めたのは野菜の生ジュースです。夜ベッドに入るとしばらくして胃が
痛くなり、睡眠剤を服用しても眠り難かったのですが、ある本に胃が良くない時はキャベ
ツのジュースを飲めと書いてありましたので、(市販にキャベジンもありますが)、飲み始
めましたら悪くないようです。
尤も眠くならないので睡眠薬を続けていますが。出来るだけ種類を違えて取り換えながら
していますが。その本の著者は毎日朝ニンジンのジュースを飲んで結構元気だと言ってい
ます。その人がスイスの病院に留学している時、その病院では世界中からの難病、奇病の
患者がやって来るのに、毎朝ニンジンのジュースを飲ませていると言います。
何故ニンジンかと院長さんに聞きましたら、ニンジンにはすべての必要なビタミン
とミネラルが含まれているから、との答えでした。リンゴ一つのコマ切れに野菜ジ
ュースを加えてジューサーでジュウスを作り、それに、ニンジン二本のコマ切れを
加えてジュースを作るのです。一つの例でしかありませんからあまり誇張すること
はいけないと思うのですが、生野菜ですから悪くはなさそうです。
ご招待のものもう少し待ってから、様子次第で決めます。差し当たり別に困っていま
せんから、面倒くさそうなのは億劫です。 お元気で。
TK
+++++++++++++++++++++++++++
●TK先生
先生は、もう85歳になるのでは?
いまだに文科省や日本化学会の仕事で、あちこちを飛び回っている。
その間に原稿も書き、講演もしている。
その前向きな生き方は、いつも私に新鮮な驚きと喜びを与える。
そう、先生が後ろ向きになるのは、若くして亡くなった奥様の話と、やはり若くして亡く
なった、三女のお嬢さんの話のときだけ。
いつも日本の未来と日本の教育の心配ばかりしている。
その前向きのエネルギーのものすごさというか、生き方のすばらしさというか、世の老人
たちは、みな、見習ったらよい。
もちろん私も見習っている。
若い時から、ずっと、見習っている。
研究の分野では、すでに神の領域に入った人である。
先日も、水を光分解して、水素と酸素を取りだすニュースが世界中を駆け巡った。
かけた熱量よりも多くのエネルギーの水素と酸素に分離することができた。
その偉業を成し遂げたのが、先生の一番弟子と言われる、DI教授である。
先生は、いつもDI教授の自慢をしている。
そのときもらったメールには、こうあった。
++++++++++++++++++++++
林様:
太陽光を使って水を水素と酸素に分解する反応の世界のトップ研究者の一人は、私
のインタビューの最後に載っている写真の中のDI君です。私の研究室にいたころ
からいわゆる「光触媒」の研究に打ち込んでいました。インチキ記事よりも私のホ
ームページにDI君との共著があります。取り敢えずお知らせまで。
TK
+++++++++++++++++++++++
そこでその原稿をさがしてみた。
TK先生のHPに公開されているので、そのまま紹介させてもらう。
+++++++++++++++++++++++
【太陽エネルギーを用いる水からの水素製造】
DI TK先生
化石資源の消費、枯渇からもたらされるエネルギー問題と二酸化炭素発生などによる地球
環境問題は、我々が直面する深刻な課題である。これらの問題は、放っておけばいつか解決
するという類のものではない。我々の生活に直結しており、我々自身で積極的に取りくん
でいかねば決して解決しない問題である。この問題の本質は、現代の人類の生活が多量の
エネルギーを消費する事によって維持されているという点である。しかも現在そのエネル
ギーを主に担っている化石資源は、有限な資源であり必ず枯渇するだけでなく、それを使
い続ける事は地球環境を破壊する危険性が高い。
もともと石油や石炭などの化石資源は、光合成によって固定された太陽エネルギーを
何億年もかけて地球が蓄えてきたものであり、それとともにわれわれの住みやすい地球環
境が形成されてきたはずである。我々はそのような地球が気の遠くなるような時間をかけ
てしまいこんできたエネルギーを「かってに」掘り出し、その大半を20世紀と21世紀の
たった200年程度で使い切ってしまおうとしている。したがって現在の時代を後世になっ
て振り返れば、人類史上あるいは地球史上極めて特異な浪費の時代と映っても不思議では
ない。かけがえのない資源を使い切ってしまいつつある時代に生きる我々は、それについ
て微塵も罪の意識を持っていないが、少なくともわれわれにとっては地球環境を破壊しな
い永続的なエネルギー源を開発することは、後世の人々に対する重大な義務である。その
為には、核融合反応や風力などいくつかの選択肢があろう。なかでも太陽エネルギーをベ
ースにしたエネルギー供給システムは、枯渇の心配のない半永久的でクリーンな理想的な
エネルギー源であろう。
太陽光を利用する方法もいくつかの選択肢がある。例えば最も身近な例は太陽熱を利
用した温水器である。また太陽電池を用いて電気エネルギーを得る方法も既に実用化して
いる。しかし、これですぐにエネルギー問題が解決するわけでない事は誰でも実感してい
る事であろう。
ここで太陽エネルギーの規模と問題点について少し考えてみる。太陽は、水素からヘリウ
ムを合成する巨大な核融合反応炉であり、常時莫大なエネルギー(1.2 x 1034 J/年)を宇
宙空間に放出している。その中の約百億分の一のエネルギーが地球に到達し、さらにその
約半分(3.0 x 1024 J/年)が地上や海面に到達する。一方、人間が文明活動のために消費し
ているエネルギーは約3.0 x 1020 J/年であり、地球上に供給される太陽エネルギーの約
0.01 %である。ちなみにそのうちの約0.1 %、3.0 x 1021 J/年、が光合成によって化学物
質、食料などの化学エネルギーに変換されている。また、地球上にこれまで蓄えられた石
油や石炭などの化石資源がもつエネルギー量は、もし地球上に降り注ぐ太陽エネルギーを
全て固定したとすれば約10日分にすぎない。このように考えれば太陽エネルギーは我々の
文明活動を維持するには十分な量であることがわかる。
では、なぜ太陽エネルギーの利用が未だに不十分なのであろうか。理由は太陽光が地球全
体に降り注ぐエネルギーであることである。したがって太陽光から文明活動を維持するた
めの十分なエネルギーを取り出すためには数十万km2(日本の面積程度)に展開できる光エ
ネルギーの変換方法を開発しなければならない。ただしこの面積は地球上に存在する砂漠
の面積のほんの数%程度であることを考えれば我々は十分な広さの候補地を持っているこ
とになる。その様な広大な面積に対応できる可能性をもつ方法の一つが人工光合成型の水
分解による水素製造である。もし太陽光と水から水素を大規模に生産できれば人類は太陽
エネルギーを一次エネルギー源とする真にクリーンで再生可能なエネルギーシステムを手
にすることができる。水素の重要性は、最近の燃料電池の活発な開発競争にも見られる様
に今後ますます大きくなってくることは間違いない。しかしながら現在用いられている水
素は化石資源(石油や天然ガス)の改質によって得られるものがほとんどである。これは
水素生成時に二酸化炭素を発生するのみでなく、明らかに有限な資源であり環境問題やエ
ネルギー問題の本質的な解決にはならない。
もし、太陽光の中の波長が600nmより短い部分(可視光、紫外光)を用いて、量子収率30%
で、1年程度安定に水を分解できる光触媒系が実現すると、わが国の標準的な日照条件下1
km2当たり1時間に約15,000 m3(標準状態)の水素が発生する。この時の太陽エネルギー
全体の中で水素発生に用いられる変換効率は約3%程度であるが、この水素生成速度は現
在工業的にメタンから水素を生成する標準的なリフォーマーの能力に匹敵する。したがっ
てこの目標が達成されれば研究室段階の基礎研究から太陽光による水からの水素製造が実
用化に向けた開発研究の段階に移行すると考えられる。
現在、水を水素と酸素に分解するための光触媒系として実現しているのは、固体光触媒を
用いた反応系だけである。他にも人工光合成の研究は数多く行われているが、以下、不均
一系光触媒系に話を限定する。水を水素と酸素に分解する為に必要な熱力学的条件は、光
触媒として用いる半導体あるいは絶縁体の伝導帯の下端と価電子帯の上端がH+/Hおよび
O2/OH-の二つの酸化還元電位をはさむような状況にあればよい。個々の電子のエネルギー
に換算すると、1.23 eVのエネルギーを化学エネルギーに変換すればよい。また、光のエネ
ルギーで1.23 eVは波長に換算するとほぼ1000 nmであり、近赤外光の領域である。つま
り、全ての可視光領域(400nm 〜 800nm)の光が原理的には水分解反応に利用できる。ただ
しこれらの条件はあくまで熱力学的な平衡の議論から導かれるものであるから、実際に反
応を十分な速さで進行させるためには活性化エネルギー(電気化学的な言葉でいえば過電
圧)を考慮する必要があるので、光のエネルギーとして2 eV程度(光の波長で600nm程度)
が現実的には必要であろう。
固体酸化物を用いた水の光分解は、1970年頃光電気化学的な方法によって世界に先駆けて
我が国で初めて報告され、本多―藤嶋効果と呼ばれている。この実験では二酸化チタン(ル
チル型)の電極に光をあて、生成した正孔を用いて水を酸化し酸素を生成し、電子は外部
回路を通して白金電極に導き水素イオンを還元し水素を発生させた。このような水の光分
解の研究は、その後粒径がミクロンオーダー以下の微粒子の光触媒を用いた研究に発展し
た。微粒子光触媒の場合、励起した電子と正孔が再結合などにより失活する前に表面ある
いは反応場に到達できるだけの寿命があればよい。さらに微粒子光触媒の場合、通常電極
としては用いることが困難な材料群でも使用できるメリットがあるため、多くの新しい物
質の研究が進んでいる。現在では紫外光を用いる水の分解反応は50%を超える量子収率
で実現できる。
しかしながら太陽光は550nm付近に極大波長をもち、可視光から赤外光領域に広がる幅広
い分布をもっているが、紫外光領域にはほんの数%しかエネルギー分布がない。つまり太
陽光を用いて水を分解するためには可視光領域の光を十分に利用できる光触媒を開発する
ことが必要である。しかしながら、これまでに開発された水を効率よく分解できる光触媒
は全て紫外光領域の光あるいはほんの少しの可視光領域で働くものである。
最近になって新しく可能性のある物質群が見出され始めている。それらは、d0型の遷
移金属カチオンを含み、アニオンにO2-だけでなくS2-イオンやN3-イオンをもつ材料群で
ある。例えばSm2Ti2O5S2やTa3N5、LaTiO2Nなどのようなものであり、オキシサルファイ
ド、ナイトライド、オキシナイトライドと呼ばれる物質群である。これらの材料では価電
子帯の上端はO2p軌道よりも高いポテンシャルエネルギーを持ったS3p軌道やN2p軌道で
できている。しかし、このような物質はまだ調製が容易ではないが、酸化剤や還元剤の存
在下では水素や酸素を安定に生成することが確認されており、これまで見出されていなか
った、600nm付近までの可視光を用いて水を分解できるポテンシャルを持った安定な物質群
であることがわかってきた。したがって、このような物質の調製法の開発および類似化合
物の探索によって、太陽光を用いる水からの水素生成が、近い将来実現する可能性も十分
にある状況になっている。安価で安定な光触媒を広い面積にわたって水と接触させて太陽
光を受けることにより、充分の量の水素を得るのも夢ではない。 このような触媒の開発に
成功し、大規模な応用が可能となれば、21世紀の人類が直面する大きな課題であるエネル
ギー問題と環境問題に化学の力で本質的な解決を与える可能性がある。
++++++++++++++++++++++++
●水を分解
水を酸素と水素に分解すれば、人類は、無尽蔵かつクリーンなエネルギーを手にするこ
とができるようになる。
夢のような話だが、今、その実現に向けて、研究が一歩ずつ進んでいる。
「20〜30人規模の大がかりな研究チームを作ってがんばっているので、成果が出るの
は時間の問題です」と、TK先生が話してくれたのを、覚えている。
もしそれが成功し、実用化されたら、ノーベル賞ですら、ダース単位で与えられる。
同時に、世界の政治地図も一変するだろう。
「産油国」という言葉すら、消える。
少なくとも排気ガスによる地球温暖化の問題も解決される。
クリーンな光エネルギーによって、深夜の野菜栽培も可能になる、などなど。
私たちの生活環境は、劇的に変化する。
「太陽光を使って、水を分解する」という話は、そういう話である。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 21日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page024.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●草食男子
++++++++++++++++++++
だれがつけた名前かは知らないが、「草食男子」という
言葉がある。
あちこちで耳にする。
「肉食男子」に対する言葉として、「草食男子」という。
ヤギとかウサギのような草食動物のように、おとなしく、ハキがなく、穏やかで、やさし
い。
そういう男性を、「草食男子」という。
「性欲も淡白な傾向が見られる」(Life、10月号)とか。
性欲も淡白?
そのほかの特徴としては、
(1)恋愛に消極的
(2)家庭的
(3)繊細
(4)優しそう
(5)協調性が高そう(同書)とある。
全体的に見れば、マザコンタイプの男性ということになる。
本来なら、父親が、母子関係の中に割って入り、男児の女性化を修正しなければならない。
が、その父親の存在感が薄い。
あるいは父親自身が、マザコン的。
子どもがそうであっても、それに気づかない?
あるいはそのまま受け入れてしまう?
本来、男性というのは、「肉食的」。
女性とくらべても、肉食的。・・・のはず。
●性欲
たとえば視床下部に性欲を司る部位がある。
「内側視索前野」と呼ばれる部分だが、別名、「第一性欲中枢」とも呼ばれている。
ここから「セックスをしたい」という指令が発せられる。
この内側視索前野は、男性のそれは、女性のそれの2倍ほどの大きさがある。
つまり男性のほうが、その分だけ性欲に対する欲求が、はげしいということになる。
大きいから、それだけ「はげしい」と短絡的に結びつけることはできないが、長い進化
の過程でそうなったと考えるのが、妥当。
もし男性も女性も、同じように攻撃的になってしまったら・・・。
あるいは反対に、男性も女性も、同じように受動的になってしまったら・・・。
その時点で、人類は、滅亡していたことになる。
つまり本来、育て方で、男児が女性化するということはあっても、性欲まで「受動的」
になるということは、ありえない。
(それとも育て方次第で、内側視索前野が萎縮するとでもいうのだろうか?)
私が書きたいのは、「草食男子」であっても、こと性欲については、ふつうの男子と、と
くに大きなちがいはないということ。
●肉食女子
「草食男子」に呼応して、「肉食女子」という言葉も、流行っている。
男性に対して、攻撃的で積極的な女性をいう。
ネーミングとしては、おもしろいが、やはりこと性欲に関していえば、女性は女性。
ただ、私は食べ物によって、男性も、女性も、性欲に関しては、ある程度の影響を受ける
のではないかと考えている。
たとえばニンニクがある。
私はニンニクを食べると、そのあとなどは、いつも、(いつもより)、強力な性欲を感ずる。
そういうことはある。
が、肉食女子というから、性欲面においても、攻撃的で積極的ということにはならない。
ただ女性のばあい、セックス中枢が、満腹中枢(食欲中枢のひとつ。食欲中枢には、満
腹中枢と摂食中枢がある)に近いため、満腹度によって大きく影響を受けるとされる。
これに対して男性のばあいは、セックス中枢が、摂食中枢、つまり空腹感を覚える中枢に、
より近いところにあるため、空腹感によって大きく影響を受けるとされる。
●女性化する男子
男子の女性化は、すでに20年近くも前から、指摘され、問題になっている。
その中でもとくに注目されているのが、環境ホルモン説。
以前、私が書いた原稿をさがしてみた。
つぎのは、10年ほど前に書いた原稿である。
++++++++++++++++++++
【環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)と、男児の女性化】
小学校の低学年児について言えば、いじめられて泣くのは男の子、いじめるのは女の子
という、図式がすっかり定着してしまっている。それについて、以前書いた原稿を、先に
転載する。
++++++++++++++++++++++++
●進む男児の女性化(中日新聞に掲載済み)
この話とて、もう15年近くも前のことだ。花柄模様の下敷きを使っている男子高校生
がいたので、「おい、君のパンツも花柄か?」と冗談のつもりで聞いたら、その高校生は、
真顔でこう答えた。「そうだ」と。
その当時、男子高校生でも、朝シャンは当たり前。中には顔面パックをしている高校生
もいた。さらにこんな事件があった。市内のレコードショップで、一人の男子高校生が白
昼堂々と、いたずらをされたというのだ。その高校生は店内で5、6人の女子高校生に囲
まれ、パンツまでぬがされたという。こう書くと、軟弱な男子を想像するかもしれないが、
彼は体格も大きく、高校の文化祭では一人で舞台でギター演奏したような男子である。私
が、「どうして、声を出さなかったのか」と聞くと、「こわかった……」と、ポツリと答え
た。
それ以後も男子の女性化は明らかに進んでいる。今では小学生でも、いじめられて泣く
のはたいてい男児、いじめるのはたいてい女児、という構図が、すっかりできあがってい
る。先日も一人の母親が私のところへやってきて、こう相談した。「うちの息子(小2)が、
学校でいじめにあっています」と。話を聞くと、小1のときに、ウンチを教室でもらした
のだが、そのことをネタに、「ウンチもらしと呼ばれている」と。母親はいじめられている
ことだけを取りあげて、それを問題にしていた。が、「ウンチもらし」と呼ばれたら、相手
の子どもに「うるさい!」と、一言怒鳴ってやれば、ことは解決するはずである。しかも
その相手というのは、女児だった。私の時代であれば、相手をポカリと一発、殴っていた
かもしれない。
女子が男性化するのは時代の流れだとしても、男子が女性化するのは、どうか。私はな
にも、男女平等論がまちがっていると言っているのではない。男子は男子らしく、女子は
女子らしくという、高度なレベルで平等であれば、それはそれでよい。しかし男子はいく
らがんばっても、妊娠はできない。そういう違いまで乗り越えて、男女が平等であるべき
だというのは、おかしい。いわんや、男子がここまで弱くなってよいものか。
原因の一つは言うまでもなく、「男」不在の家庭教育にある。幼稚園でも保育園でも、教
師は皆、女性。家庭教育は母親が主体。小学校でも女性教師の割合が、60%を超えた(9
8年、浜松市教育委員会調べ)。現在の男児たちは、「男」を知らないまま、成長し、そし
ておとなになる。あるいは女性恐怖症になる子どもすら、いる。しかももっと悲劇的なこ
とに、限りなく女性化した男性が、今、新時代の父親になりつつある。「お父さん、もっと
強くなって、子どもの教育に参加しなさい」と指導しても、父親自身がそれを理解できな
くなってきている。そこでこういう日本が、今後、どうなるか。
豊かで安定した時代がしばらく続くと、世相からきびしさが消える。たとえばフランス
は第一次大戦後、繁栄を極めた。パリは花の都と歌われ、芸術の町として栄え、同時に男
性は限りなく女性化した。それはそれでよかったのかもしれないが、結果、ナチスドイツ
の侵略には、ひとたまりもなかった。果たして日本の未来は?
++++++++++++++++++++++++
●環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)
こうした男児の女性化について、環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)原因説がある。
ここでいう「環境ホルモン」という言葉は、NHKが放送番組用に作った言葉で、正確に
は「内分泌かく乱化学物質」という。
この環境ホルモンは、ホルモンそのものではない。「生体のホルモン受容体に作用するな
どして、ニセのホルモンとして働いたり、その反対に、ホルモン受容体をブロックするこ
とで、ホルモン本来の作用を妨げたりする化学物質」(福島章著「子どもの脳が危ない」・
PHP新書)ということになる。
その結果、環境ホルモンは、さまざまな影響を、体におよぼす。そのうちでも、近年、
問題になっているのが、生殖機能への影響である。福島章氏の「子どもの脳が危ない」に
書かれている事例を、ここにあげてみる。
●多摩川のコイの7割が、メスであった(91年)。しかもオスの精巣の発達が不完全であ
り、雌雄同体のコイも発見された。原因は洗剤などに含まれる、ノニルフェノールだと言
われている。
●イギリスでは、ニジマスやローチという魚のオスの精巣がやはり不完全であった。原因
はやはりノニルフェノールと言われているが、ピルに含まれている女性ホルモンという説
もある。
●カナダのセントローレンス川では、白鯨のオスがメス化して、メスの妊娠率が低下した
だけではなく、ガンが多発していることがわかった。
●アメリカでは、ハクトウワシの孵化率が低下した。アジサシやカモメなどの鳥類では、
オスのメス化が進んでいる。
●フロリダ州のミッシシッピーワニのペニスが小さくなり、精巣機能が低下し、血中のテ
ストステロン(男性ホルモン)が低下しているのがわかった。
さらに人間に与える影響としては、「男子の精子数が減少しているだけでなく、元気がな
くなった」という報告も、多いという。たとえば、「91年に、デンマークのスキャケベッ
ク博士は、ここ50年の間に、男性の1回の射精に含まれる精子数が、1ミリリットルあ
たり、1億1000万から、6000万に、42%も減少し、さらに受胎に必要な精子数
2000万以下の男性は、この間に3倍に増加した」(同書)そうだ。
こうした影響からか、人間についても、男性の性衝動が弱くなったという報告もある。
男児の女子化が、その流れの中にあるとしたら、これはたいへん深刻な問題と考えてよい。
そこで私たち親は、この問題に対して、どう対処したらよいかだが、とりあえず注意す
べきことは、食器や調理道具から、プラスチック製品を取り除くということ。とくにプラ
スチック製品が、何らかの形で、熱湯とふれるようなときが、危険だという。環境ホルモ
ン、つまり内分泌かく乱化学物質の大半は、これらのプラスチック製品から溶けでるとい
う。カップヌードルなども、発泡スチロールの容器の中から一度、陶器の茶碗などに移し
てから、熱湯をかけるとよい。
なお女性のばあい、最近若い人の乳がんがふえているが、その原因も、ここにあげたノ
ニルフェノールではないかと言われている。注意するにこしたことはない。
(02−11−26)
●世の男性諸君よ、スケベであることを喜ぼうではないか。もっともっとスケベになって、
妻たちを、ハッピーにしてあげようではないか。種族を後世に残すために。
+++++++++++++++++++++++
●終わりに
「草食男子」……これからこの名前は、あちこちで使われるようになるだろう。
しかし一言。
動物の世界のことをよく知っている人なら、こう反論するだろう。
「草食動物がおとなしいというのは、ウソ」と。
草食動物が、草食動物的に見えるのは、あくまでも人間の目に、そう見えるだけ。
一方、肉食動物が、肉食動物的に見えるのは、あくまでも人間の目に、そう見えるだけ。
食べる餌が、動くか動かないかのちがい。
食べる餌が動かないから、草食動物は、はげしく動き回る必要はない。
が、食べる餌が動けば、肉食動物は、それに応じて、はげしく動かねばならない。
それが(見た目のちがい)となっている。
その時期になれば、草食動物だって、雌を取り合って、はげしい闘争を繰り返す。
肉食動物だって、おとなしいときには、おとなしい。
さらに、こと性欲に関して言えば、草食男子も肉食男子も、ちがいはない。
同じように、肉食女子も、草食女子も、ちがいはない。
ちがいはないが、もし本当に「性欲も淡白」(同書)ということであれば、ことは深刻。
環境ホルモンだけが原因とは言えないが、何らかの原因が、だれにもわかる程度に、この
10年で人間にも影響が出始めたとも考えられる。
で、もしそういう男性を、「草食男子」というのなら、ただ単なる言葉の遊びとしては、す
まされなくなる。
繰り返すが、ことは深刻!
(はやし浩司 草食男子 草食男性 肉食女子 性欲 男女の性欲 視床下部 内側視索
前野 環境ホルモン はやし浩司 内分泌かく乱化学物質 食欲中枢 満腹中枢 摂食中
枢 はやし浩司 男児の女性化)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●加齢と精神の完成度
+++++++++++++++++
加齢とともに、精神的に完成度が高くなる
ということは、まっかなウソ!
むしろ加齢とともに、精神的にガタガタに
なる。
そういう人のほうが、多い。
何かの精神的な病(やまい)をもてば、なおさら。
定番のうつ病(失礼!)のほか、パニック障害、
もろもろの人格障害、精神障害などなど。
何かの認知症になれば、なおさら。
何かの身体的な病気をかかえると、それがきっかけで、
ガタガタになる人も少なくない。
そういう人たちを身近に見ながら、
このところ「じょうずに老いるには、どうしたら
よいか」。
そんなことをよく考える。
+++++++++++++++++
●気力と精神病
骨だけでは、身体を支えることはできない。
筋肉があって、はじめて、私たちは身体を支えることができる。
同じように、精神力だけでは、私たちの精神を支えることはできない。
「気力」があって、私たちは精神を支えることができる。
たとえば何か困難な場面に遭遇したとする。
肉親の死や事故など。
そういうとき精神力だけで、自分の精神を支えることは難しい。
「乗り切ってやろう」という気力が必要である。
●仮面
私たちはみな、仮面をかぶって、生きている。
仕事をしている。
仮面をかぶることが悪いというのではない。
ショッピングセンターの女性店員ですら、仮面をかぶって仕事をしている。
穏やかでやさしそうな笑みを浮かべて、「いらっしゃいませ」と言って頭をさげる。
そういう姿を見て、「この女性は、人間的にすぐれた人格者」などとは思ってはいけない。
医師だって、政治家だって、企業家だって、みな、仮面をかぶっている。
もちろん私だって、仮面をかぶっている。
その仮面を裏から支えるのが、気力ということになる。
●持病
同じように、だれしも、何らかの持病をかかえている。
私のばあいも、上から、左耳の難聴。
右の上腕痛。
便秘。
それに脚痛など。
しかし今はまだ体力があるから、それらを何とか、カバーしている。……できる。
上腕痛は、2か月ほどまで、草刈機を使ったときから、起こるようになった。
便秘は、自分でセンナ茶を煎じて、何とかしのいでいる。
脚痛については、体重を減らしたり、運動量をふやしたりして対処している。
が、加齢とともに、体力そのものが弱くなる。
とたん、持病が表に出てくる。
●気力
精神疾患にも似たようなところがある。
私は元来、いじけやすい性格をもっている。
何かのことでつまずいたりすると、そこでいじけてしまう。
が、仕事の上で、いじけることはできない。
いつも先生面(づら)して、偉そうなことを言っている。
それをカバーするのが、気力ということになる。
持病をカバーする、体力。
精神的もろさをカバーする、気力。
これら両者の関係は、たいへんよく似ている。
つまり加齢とともに、気力も弱くなり、その下に隠れていた精神的もろさ、つまり人間
性が、表に出てくる。
●自分の「地」
わかりやすく言えば、若いときというのは、いい人ぶるのは、簡単なこと。
それらしい顔をして、それらしいことを言えばよい。
それを支えるのに、じゅうぶんな、気力がある。
が、加齢とともに、その気力が弱くなる。
長つづきしなくなる。
とたん、自分の「地」が、表に出てくる。
こんな話を耳にした。
●ある男性(75歳)
その男性は、現役時代は、XX局の副長をしていた。
人望もあり、統率力もあった。
晩年は、全国の関係機関を回り、その指導を繰り返していた。
が、それは(表)の顔。
晩年になると、とくに家の中では、様子がまったく違った。
夜中じゅう起きていて、大声で家人を呼びつけていた。
「水、もってこい!」「背中が痛いから、湿布薬を張れ!」と。
そのため妻や、息子夫婦は、みな、ノイローゼになってしまった。
とくに息子の妻(=嫁)は、痛々しいほどまでに体重を落としてしまった。
が、である。
仮面をかぶる気力がまったくなくなってしまったかというと、そうでもない。
弟夫婦が、遠方から訪ねてきたりすると、別人のように穏やかで、やさしい父親を演じて
みせていた。
そんなキャリアをもつ人でも、そうなる人は、そうなる。
●人間性
加齢とともに体力は落ちる。
同じように気力も、落ちる。
仮面を維持できなくなる。
そのときその人のもつ人間性が、そのまま(表)に出てくる。
その人間性がよいものであれば、問題ない。
加齢とともに、ますます円熟味に磨きがかかる。
が、そうでなければ、そうでない。
へたをすれば、邪悪な性格、醜い人間性が、そのまま表に出てくる。
これがこわい。
●人間性
その人の人間性は、10年とか20年とか、長い年月を経て、熟成される。
それも健康論に似ている。
先日、ワイフの友人(男性)が、98歳という年齢で亡くなった。
その男性は、92歳を過ぎても、テニスのコーチとして活躍していた。
いくつかの会場をもっていて、遠いところだと、20キロ近くもある。
その会場へ、毎週、自転車で通っていた。
その男性は、若いときからテニスが好きで、そのテニスを通して、体を鍛えていた。
同じように、人間性もまた、日々の鍛錬のみによって、熟成される。
難しいことではない。
(1)ウソをつかない、(2)約束は守る、(3)ルールに従う。
この3つだけでよい。
この3つだけを守ればよい。
それが10年、20年という年月を経て、その人の人格となり、人間性となって表に表れ
てくる。
●ズルイ人
一方、ズルイ人は、ズルイ。
何かにつけて、ズルイ。
一事が万事。
小細工に小細工を重ねる。
小細工を重ねているという意識がないまま、重ねる。
そうした行為が、ごく日常的なことして、できる。
だからしばらくつきあっていると、何がなんだか、訳が分からなくなる。
ウソとホントが、ごちゃ混ぜになり、ウソを指摘すると、そのつど巧みに、その場を逃げ
たりする。
あるいはとぼける。
さらに追及すると、興奮状態になったりする。
が、こういう生き方を、10年、20年とつづけていると、その人の人間性が狂ってく
る。
そしてそれがそのままその人の人間性となって、定着してしまう。
●有終の美
こうして考えてみると、老人になると、その人の人間性が、そのまま出てくると考えて
よい。
しかしこれが、先にも書いたように、こわい。
このことは、まわりにいる老人たちを観察してみると、それがわかる。
老人のなり方は、千差万別。
千人いれば、みな、ちがう。
そこにその人の、それまで歩んできた人生が、すべて凝縮される。
好ましい人格者の人もいれば、もちろんそうでない人もいる。
だからといって、つまりどういう老人であれ、人、それぞれ。
その老人がそれでよいと思っているなら、それはそれでよい。
が、これだけは言える。
どうせたった1回しかない人生。
自分の納得いく人生を送り、最後は、有終の美を飾って、死んでいきたい。
……というのが、今の目標。
自信はないが、その目標に向かって、今日も精進(しょうじん)あるのみ。
がんばろう。
2009年9月22日、火曜日。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●雑感・あれこれ
+++++++++++++++++++++++
●もう9月も20日
昨日から、市内の鴨江寺で、秋の彼岸会が始まっている。
「秋だなア」と思うと同時に、「今年1年も、あと3カ月・・・」と
思ってしまう。
本当に月日のたつのは早い。
昨日、昔世話になったKさん(男性)を見舞った。
今年79歳になるという。
この5月に敷居でころんで以来、車椅子の生活になったという。
10年ほど前に、一度、すい臓がんを患ったが、そちらのほうは、治ったようだ。
見た目には元気そうだった。
子どもの世界を見ていると、10年単位で、どんどんと変わっていく。
同じように、老人の世界も、10年単位で、どんどんと変わっていく。
●クリスマス
日本人は、昔から「神様」には、おおらか。
「八百万(やおよろず)の神」というほどで、そのまま読めば、800万人の神様がいる
ことになる。
野にも山にも、小川にも家の中にも・・・。
だから神様なら、何でもよいということになる。
ある女性(当時、50歳くらい)は昔、私にこう言った。
「人がいいと言っていることは、何でもやったらいいのです」と。
・・・ということで、その女性は、複数(5、6)の信仰団体に出入りしていた。
仏教もキリスト教も、日本人にとっては、その一部でしかない。
だから仏教徒でありながら、クリスマスを祝ったところで、何ら違和感を覚えない(?)。
神様に対するおおらかさが、ちがう。
寛大さが、ちがう。
9月も終わりに近づくと、もうクリスマスが気になる。
年賀状が気になる。
その年賀状。
今年から、年賀状を再開。
虚礼を廃して、本当に大切にしたい人だけと交換することにした。
●天国
仏教には、「天国」という考え方はない。
ないものはないのであって、どうしようもない。
「天上」という言葉はあるが、それは釈迦以前からインドにあった、「先天(しょうてん)
思想」をいう。
それが釈迦仏教に混入した。
「天上」というのは、いうなれば「理想郷」をいう。
「生前、よい行いをすれば、その理想郷で生まれ変わることができる」(「哲学」宇都宮
輝夫・PHP)と。
実際、釈迦自身は、「来世(=あの世)」などという言葉など、一度も使っていない。
来世思想が混入したのは、釈迦入滅後のこと。
「前世」「来世」と言うようになったのは、ヒンズー教の輪廻転生思想の影響によるもので
ある。
そういう点では、釈迦は、たいへん現実的なものの考え方をしていた(法句経)。
たとえば『苦行では、悟りは得られない』と教え、「中正」という生き方を導く。
わかりやすく言えば、ごくふつうの人間として、ふつうの生活をしながら、その中で自分
を磨いていくことこそ、大切、と。
私はキリスト教徒ではないので、私には「天国」はない。
入りたくても、入れない。
まっ、ここはあきらめるしかない。
「メリークリスマス!」と言いながら、神の国を、横目で見るしかない。
●「我」
仏教では、「我」を認めない。
わかりやすく言えば、「私」を認めない。
これが「私」と思っているものでも、玉ねぎの皮のようなもの。
一枚ずつ、どんどんとめくっていくと、最後には、何も残らない。
「私は私」と思っているのは、ただの意識にしか過ぎない。
が、意識こそ、まさに「無」。
だから仏教では、「我」、つまり「私という意識」からの解脱を説く。
「解脱」というのは、「私という執着から、自らを解放すること」をいう。
その「私」に執着すかぎり、安穏たる日々は、ぜったいにやってこない。
そこから「一切皆苦(一切行苦)」という言葉も生まれた。
平たく言えば、「私の名誉」「私の地位」「私の財産」・・・などと、「私」にこだわってい
るかぎり、安穏たる日々は、やってこないということ。
が、その「私という意識」から解放されれば、そこは恐ろしく広くて、心静かな世界。
四法印で説く、『涅槃静寂(ねはんせいじゃく)』というのは、そういう世界をいう。
●孤独な世界
来世思想を否定すれば、そこに待っているのは、「孤独」という無間地獄。
・・・と考えていたが、このところ、私の考え方が、少し変化してきた。
大切なことは、「私という意識」をどうとらえ、どう解釈するかということ。
「私という意識」を、「私の肉体」に閉じ込めてしまえば、たしかに、そこに待っているの
は、「孤独」ということになる。
しかし「私という意識」には、連帯感をもたせることもできる。
たとえば今、この文章を読んでくれる人がいたとする。
多少の時間差、地域差はあるかもしれないが、(そんなものは、何でもない)、その瞬間、
私の意思と、その人の意思が、この文章を介して、つながる。
つまりこうして「私の意思」を、他人に伝えていけば、仮に肉体は滅びても、意思は残
る。
それを「生」ととらえれば、私は不滅ということになる。
孤独にならなければならない理由すら、ない。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●ルーム・ウォーカー使用記
++++++++++++++++++++++
ルーム・ウォーカーを使用するようになって、1週間が過ぎた。
いろいろなものを買ってきたが、これほど役に立ったものはない。
・・・と言えるほど、現在のところ、役に立っている。
毎日、計40分前後は、ルーム・ウォーカーの上で歩いている。
汗をかいている。
それが楽しい。
終わったあとは、気分もよい。
そのルーム・ウォーカーを使っていて、いくつか気づいた点がある。
これから買う人のために、メモの形で、残しておきたい。
++++++++++++++++++++++
(1)手はできるだけさげた姿勢で歩くのがよい。
取っ手が前と前上部についているが、それにつかまっていると、
だれかに引っ張ってもらいながら歩いているような感じになる。
これでは、運動の目的が半減する。
そのため手はできるだけさげた状態、つまり取っ手の下のほうに、
手を軽くあてているだけといったふうに、歩いたほうがよい。
(2)顔は45度くらい上を向けて歩く
最初のころは、どうしても顔が下向きになる。
姿勢が悪くなる。
だから顔を45度くらい上に向けながら、歩く。
姿勢がまっすぐ伸びて、その分だけ、足が前方にさっさと出るようになる。
(3)音に注意
これは自分でしてみて気がついたことだが、右足と左足が作る足音の質が異なる
ときがある。
たとえば、パタ・ペタ・パタ・ペタ……と。
利き足とそうでない足のちがいかと思ったが、そうではない。
原因は歩き方。
歩き方が、まずい。
そこで自分の足音を聞きながら、どうすれば同じような足音になるかを調整する。
まっすぐ、交互に同じように力を入れてあるくと、パタ・パタ……と同じような
音になる。
これで自分の歩きかたを、矯正することができる。
(4)歩き方
右足と左足の流れを平行にして歩く……これを「平行歩き」という。
右足と左足が一直線になるよう歩く……これを「直線歩き」という。
右足が、左足ラインを、左足が右足ラインを歩くようにして歩く……これを「ちどり足歩
き」という。
ほかに「小また歩き」「大また歩き」など。
自分でいろいろな歩き方を試してみた。
うしろ歩きに歩く方法試してみた。
横歩きに歩く方法も、試してみた。
私の印象では、上記の「ちどり足歩き」というのは、美容効果もあるのではないか。
腰部がそのつど、ぐいぐいとひねられるような感じになる。
ただし長くつづけるのは、無理。
そのうち歩くだけで精一杯といったふうになり、汗がジワリと出てくるようになると、
いろいろな歩き方を試す余裕がなくなってくる。
今は、1回、20分が限度。
もう少し先になったら、30分はつづけてみたい。
テレビを見ながら、あるいは雑誌を読みながら歩くのもよい。
そんなわけでメーカーに一言。
雑誌を読みながらできるように、雑誌を置けるような、パネルのようなものを取りつけて
ほしい。
(補記)60歳を過ぎて、「健康を取り戻すなんて無理」と考えている人へ
自分でやってみて気がついたが、60歳すぎても、健康は増進できる。
今回のルーム・ウォーカーもそうだが、毎回、回を重ねるごとに、足腰が軽くなっていく
のを実感できる。
あきらめてはいけない!
現在、体重は、60キロ。
数か月前までは、68キロ台もあった。
苦しい闘いがつづいたが、今は、その状態で、以前と同じような生活ができる。
足の裏の痛みも、かなり楽になった。
頭の働きも快調になった。
だから、あきらめてはいけない!
まだまだ、人生、これから!
(はやし浩司 ルーム・ウォーカー ルームウォーカー ルーム・ランナー
ウォーキングマシン ウォーキング・マシン ランニング・マシン ランニング
マシーン)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●前頭連合野
+++++++++++++++++++++++++++++++
前頭連合野は、言うなれば、知性と理性のコントロール・センター。
その働きを知るためには、ひとつには、「夢」の内容を知るという方法
がある。
夢を見ているときには、前頭連合野は、働いていない。
そのため、人は、支離滅裂な、前後に脈絡のない夢を見る。
言い換えると、もし前頭連合野の働きが弱くなれば、私たちの思考は、
ちょうど夢を見ているような状態になる。
もしそうなれば、自分でも、何をどう考えているか、さっぱりわからなく
なるだろう。
もちろん自分の考えをまとめることさえできない。
電車に乗り遅れる夢を見るように、ただあわてふためくだけで、それで
終わってしまう。
いつもの私の夢が、そうだ。
+++++++++++++++++++++++++++++++
●前頭連合野
人間の脳みその、約3分の1は、前頭連合野と呼ばれる部分だそうだ。
人間は、とくにこの部分が発達している。
そのため、猿やチンパンジー、古代人の骨格と比べても、人間の額は大きく、広い。
言うなれば、知性と理性のコントロール・センター。
それがこの前頭連合野ということになる。
が、もしこの前頭連合野の働きが鈍くなったら・・・。
私たちの思考は、ちょうど夢を見ているときのような状態になると考えられる。
というのも、人間が眠っている間というのは、前頭連合野も、眠った状態になっている。
反対に、そのことから、前頭連合野の働きを、私たちは知ることができる。
●今朝の夢
実のところ、今朝の夢というのは、よく覚えていない。
夢というのは不思議なもので、半日もたつと、それが今朝の夢だったのか、それとも何日
も前に見た夢だったのか、わからなくなる。
が、今朝見た夢は、こんなものだった。
山の中の、どこかの駅に向かっている。
新幹線の中のようだが、窓がなく、貨物室のようになっている。
それが川沿いを走ったり、山の中を走ったりしている。
ところどころ線路が切れているが、新幹線は、そのまま走り続けている。
が、やがて、森のようなところをぐるりと回ったところで、新幹線は止まる。
中央にプラットフォームがあって、その向こうには、別の電車が待っている。
ローカル線である。
切符を買うために、駅舎へ向かうが、料金がわからない。
長野を通って、仙台へ行く・・・というようなことを、私は話している。
途中、高い山を電車は越えるらしい。
山の途中には、ひなびた温泉街がいくつも並んでいる・・・。
●小鳥の思考
理屈で考えれば、矛盾だらけの夢である。
夢の内容に連続性がない。
それに非合理。
そこで私は、ふとこう考えた。
前頭連合野がまだ未発達だったころの人間は、こうした思考方法を、日常的にしていたの
ではないか、と。
もちろん目の前に見える(現実)に対しては、現実的な行動をする。
餌となる食べ物があれば、それを口にするまでの行動を開始する。
危険が迫れば、それを回避するための行動を開始する。
しかしこと(思考)ということになると、それをまとめあげ、合理的に判断し、前後を論
理的につなげる能力はない。
恐らく、目を閉じたとたん、私たち人間が夢を見ているときのような状態になるのではな
いか。
ミミズが地面をはっている。
その横に、大きな木の枝がある。
木の枝の中には、おいしそうな種がいっぱいつまっている。
それを高い空を飛びながら、上から見ている、と。
小鳥なら、きっとそんな光景を思い浮かべるかもしれない。
もちろん言葉もないから、それを的確に、別の鳥に知らせることもできない。
●理性の源泉
が、人間のばあいは、目を閉じても、それで前頭連合野の活動がそこで停止するわけで
はない。
目を閉じていても、言葉を使って、ものごとを論理的に考え、理性的な判断をくだすこと
ができる。
それがしっかりとできる人のことを、理性的な人といい、そうでない人を、そうでない人
という。
程度の差は、当然、ある。
言うなれば、神に近いほど、理性的な人もいれば、反対に、動物に近いほど、そうでない
人もいる。
その(ちがい)は何によって生まれるかといえば、結局は行きつくところ、(日々の鍛錬)
ということになる。
このことは幼児期前期の子どもたちを見れば、よくわかる。
エリクソンが、「自律期」と名づけた時期である。
●自律期
年齢的には、満2歳から4歳前後ということになっている。
実際には、乳幼児期を脱し、少年少女期へ移行する、その前の時期までということになる。
この時期の子どもは、親や先生に言われたことを忠実に守ろうとする。
この時期をとらえて、うまく指導すると、いわゆる(しつけ)がたいへんしやすい。
が、この時期に、(いいかげんなこと)をしてしまうと、子どもはやがて、ドラ息子、ドラ
娘化する。
ものの考え方が享楽的になり、自己が発する欲望に対して、歯止めがきかなくなる。
わがままで、自分勝手。
感情のコントロールさえ、ままならなくなる。
つまりこの時期に、前頭連合野の働きが活発になり、ある程度の形がその前後に形成さ
れると考えてよい。
もちろんそれ以後も、前頭連合野の形成は進むだろうが、原型は、その前後に形成される
と考えてよい。
●夢と前頭連合野
そこでこう考える。
夢の中でも、前頭連合野を機能させることはできないものか、と。
しかしそれでは、睡眠が妨げられることになる。
ただ、ときどき、ほとんど起きがけのころだが、夢と現実が混濁するときがある。
そういうときというのは、かなり理性的な判断(?)ができる。
「これは夢だぞ」と、自分で、それがわかるときさえある。
あるいはこんなこともあった。
この話は少し前にも書いたが、こんな夢を見たことがある。
歩いていて、その男女の乗った車に、体をぶつけてしまった。
中から男が出てきて、ワーワーと大声を出して、私に怒鳴った。
で、私は目を覚ましたが、そのときのこと。
私はそれが夢だったと知り、もう一度、夢の中に戻りたい衝動にかられた。
夢の中に戻って、その男女の乗った車を、足で蹴飛ばしてやりたかった。
が、このとき、脳のほとんどは覚醒状態にあったが、前頭連合野だけは、まだ半眠の状
態であったと考えられる。
前頭連合野が正常に機能していたら、「蹴飛ばしてやる」ということは考えなかったかもし
れない。
それ以前に、「夢は夢」と、自分から切り離すことができたはず。
・・・などなど。
前頭連合野の働きをわかりやすく説明してみた。
今度の高校生のクラスで、こんな話を、子どもたちにしてみたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW 前頭連合野 前頭前野 理性の府 夢と理性)
Hiroshi Hayashi++++++++SEP.09+++++++++はやし浩司
●帰すう本能(The Last Home)
+++++++++++++++++++
晩期の高齢者たちは、ほとんど例外なく、
「〜〜へ帰りたい」と、よく言う。
母もそうだったし、兄もそうだった。
母は、自分が生まれ育った、K村の実家に、
兄は、やはり自分が生まれ育った、M町の実家に。
私の30年来の友人も、昨年(08年)に亡くなったが、
その友人は、九州の実家に帰りたいと、いつも言っていた。
こうした現象から、みな、人は死が近づくと、自分の
生まれ育った実家に帰りたがるようになると考えてよい。
それをそのまま「帰すう本能」と断言してよいかどうかは、
私にもわからない。
というのも、記憶と言うのは、加齢とともに、新しく
記銘された分から、先に消えていく。
古い記憶ほど、脳の奥深くに刻まれている。
そのため歳をとればとるほど、子ども時代、さらには
幼児期の記憶のみが残るようになる。
だから「帰る」となると、幼児期に育った世界へ、となる。
++++++++++++++++++++++++++
●私の場合は、どうか?
私もあと10〜15年もすると、そうした老人の仲間入りをする。
うまく特別養護老人ホームに入居できればよし。
そうでなければ、独居老人となり、毎日悶々とした孤独感と闘いながら、暗い日々を送る
ことになる。
そのときのこと。
私は、どこへ帰りたいと言うだろうか?
理屈どおりに考えれば、私は、生まれ育ったM町の実家に帰りたいと言い出すにちがい
ない。
M町の記憶しか残らなければ、そうなる。
が、私は子どものころから、あのM町が、嫌いだった。
今でも、嫌い。
そんな私でも、その年齢になったら、「M町に戻りたい」と言いだすようになるのだろうか。
●放浪者
私は基本的には、放浪者。
ずっと放浪生活をつづけてきた。
夢の中に出てくる私は、いつも、行くあてもなく、あちこちをさまよい歩いている。
電車に乗って家に帰るといっても、今、住んでいるこの浜松市ではない。
この家でもない。
もちろん実家のあるM町でもない。
ときどき「これが私の家」と思って帰ってくる家にしても、今のこの家ではない。
どういうわけか、大きな、ときには、大豪邸のような家である。
庭も広い。
何百坪もあるような家。
見たこともない家なのに、どういうわけか、「私の家」という親近感を覚える。
が、たいていそのまま、目が覚める。
が、その家は、いつもちがう。
つぎにまた見るときは、今度は別の家が、夢の中に出てきたりする。
つまり私は基本的には、放浪者。
●M町の実家
ここ5、6年は、ときどき、M町の実家が夢の中に出てくることが多くなった。
表の店のほうから中へ入ると、そこに母がいたり、兄がいたりする。
祖父や、祖母がいたりすることもある。
先日は、家に入ると、親戚中の人たちが集まっていた。
みんな、ニコニコと笑っていた。
もちろんいちばん喜んでくれるのが、私の母で、「ただいま!」と声をかけると、うれしそ
うに笑う。
兄も笑う。
が、私は、実家ではいつも客人。
私の実家なのだが、実家意識は、ほとんど、ない。
●徘徊老人
こう考えていくと、私はどうなるのか、その見当がつかない。
認知症になり、特別養護老人センターに入居したとする。
そんなとき、私は、どこへ帰りたいと言うだろうか。
それをワイフに話すと、ワイフは、こう言った。
「あなたは、まちがいなく、徘徊老人になるわよ」と。
つまりあてもなく、あちこちをトボトボと歩き回る老人になる、と。
しかしこの意見には、異論がある。
先にあげた友人にしても、九州出身だったが、いつも浜松市内を徘徊していた。
距離が遠いから、まさか九州まで歩いて帰るということはなかった。
しかし気持の上では、九州まで歩いて帰るつもりではなかったか。
今にして思うと、友人のそのときの気持ちが、よく理解できる。
●さて、あなたはどうか?
さて、あなたはどうか?
そういう状況になったとき、あなたなら、どこへ帰りたいと言いだすだろうか。
たいていの人は、自分が生まれ育った実家ということになる。
確たる統計があるわけではないが、90%近くの人が、そうなるのではないか。
が、残り10%前後の人は、帰りたい場所もなく、浮浪者のように、そのあたりをさま
よい歩く。
ところで徘徊する老人は多いが、そういう老人をつかまえて、「どこへ帰るの?」と聞く
と、ほとんどが、「うちへ帰る」と答えるという。
たぶん、私も、「うちへ帰る」と答えるだろうが、その「うち(=家)」とは、どこのこと
を言うのだろうか。
帰りたい家があり、その家が、あなたをいつまでも暖かく迎えてくれるようなら、そん
なすばらしいことはない。
しかし現実には、住む人の代もかわり、家そのものもないケースも多い。
こう考えただけでも、老後のさみしさというか、悲哀が、しみじみと心の中にしみ込ん
でくる。
「老人になることで、いいことは何もない」と、断言してもよい。
そういう時代が、私のばあいも、もうすぐそこまで来ている。
(付記)
最近、ワイフとよく話し合うのが、「終(つい)の棲家」。
で、結論は、終の棲家は、この家の庭の中に建てよう、である。
街の中のマンションも考えた。
病院やショッピングセンターに近いところも考えた。
しかし、私たちの終の棲家は、どうやらこのまま、この場所になりそう。
今、別のところに移り住んでも、私たちは、そこには、もうなじめないと思う。
頭の働きが鈍くなってきたら、きっと、今のこの家に帰りたいと、だだをこねるように
なるだろう。
だったら、終の棲家は、ここにするしかない。
・・・というのが、今の私たちの結論になりつつある。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW 終の棲家 帰すう本能 帰趨本能 徘徊 徘徊老人)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 19日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page023.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●「実家」離れ
++++++++++++++
「親離れ」「子離れ」という言葉がある。
同じように「実家離れ」というのもある。
50歳を過ぎても、60歳を過ぎても、
「実家」「実家」と、何かにつけて、
実家に入り浸りになる。
背景には、未熟な精神性があるのだが、
マザコンというケースも少なくない。
概して、女性に多い。
(「マザコン」というと、男性だけの問題
と考える人も多いが、女性にも多い。
同性であるだけに、外からは、わかりにくい。)
+++++++++++++++++
●嫁ぎ先?
Mさん(現在55歳、女性)は、結婚してすでに30年以上になる。
夫は公務員で、代々つづいた「家」を守っている。
しかしMさんにとっては、自分の生まれ育った実家が、「家」。
傍から見ていると、そんな感じがする。
ことあるごとに実家に足を運び、実家を守る弟氏(現在50歳)に、あれこれと指示す
る。
冠婚葬祭は言うに及ばず、実家の母親(実母)の世話の仕方にまで、口を出す。
墓参りにしても、嫁ぎ先の墓参りよりも、実家の墓参りの回数のほうが多い。
ときどき弟氏が、「お前は、H家に嫁いだのだから、H家の人間だ」といくら諭しても、そ
れが理解できない。
理解できないばかりか、他人には、こう言う。
「N夫(=その女性の弟氏)は、私に頼ってばかりいる」「N夫は、自分では何もできない」
「先祖をきちんと供養していない」と。
●実家意識
「実家」意識の強い人は多い。
ことあるごとに「実家」という言葉をよく使う。
これも「家族自我群」の一種ということになる。
「家族」というしがらみが、無数に「私」にからんでくる。
その呪縛感を「家族自我群」という。
その家族との関係が良好な間は、家族自我群も、よい方向に作用する。
が、どこかでその歯車が狂う。
そういうケースも多い。
とたん家族自我群は、その人を苦しめる(責め具)として機能する。
「家」に縛られ、「家族」に縛られる。
その呪縛感の中で、もがき苦しんでいる人は多い。
●マザコン
Mさんのケースは、やや特殊である。
結婚して、H家に嫁いではみたものの、そのH家には同化できなかった。
もともと望んだ結婚ではなかった。
それもあった。
が、それ以上に、Mさんは、マザコンだった。
親を絶対視しながら、同時に親離れできないまま成人になった。
40歳を過ぎても、「母ちゃん」「母ちゃん」と言っては、実家に帰っていた。
50歳を過ぎても、「母ちゃん」「母ちゃん」と言っては、実家に帰っていた。
が、そういう自分を、「孝行娘」と誤解していた。
●特徴
このMさんというのは、架空の女性である。
いくつかの例を、ひとつにまとめてみた。
しかしこういう例は、多い。
地方の農村部へ行けば行くほど、似たような話を耳にする。
特徴としては、つぎのようなものが、あげられる。
(1)嫁いでも、嫁ぎ先と同化できない。
(2)嫁いでも、実家意識が強く、実家への帰趨(きすう)本能が強い。
(3)実家を絶対視する。
(4)ものの考え方が、権威主義的。
(5)家父長意識、上下意識が強く、「先祖」という言葉をよく使う。
本来なら、結婚し、相手の夫の側に籍を入れたら、少なくとも夫側の「家」と自分の実
家を同等にみる。
あるいは「家」意識そのものを、平等に否定する。
さらに言えば、親が子離れし、子どもが親離れするように、「家」離れをする。
その上で、親子という関係であっても、一対一の人間としての人間関係を築く。
●G・ワシントン
どうであるにせよ、今どき、「家」意識をもつほうが、おかしい。
江戸時代の昔ならいざ知らず。
今は、そういう時代ではない。
また人間が、「家」に縛られる時代ではない。
名前(姓)にしても、そうだ。
私の知人の中には、「ルーツさがし」と称して、家系図づくりに熱中している人がいる。
人、それぞれ。
しかしあの福沢諭吉は、アメリカで、こんなことに驚いている。
福沢諭吉が、G・ワシントンの子孫についてたずねたときのこと。
まわりにいた人たちが、みな、「知らない」と答えた。
当時の日本では考えられなかった。
今の日本でも、考えられない。
「G・ワシントンの子孫がどうなっているか、わからないだと!」と、まあ、福沢諭吉は、
そんなふうに驚いたにちがいない。
つまり日本の常識は、けっして世界の常識ではない。
ちなみに私の祖父は、百姓の出。
一度、祖父は私を、祖父の生家へ連れていってくれたことがある。
土壁むきだしの、窓もないような粗末な家だった。
私が小学6年生か、中学1年生のときのことである。
だからこれは私のひがみかもしれない。
家系を誇る人に出会うたびに、内心では、「ごくろうさま」と思う。
今、「私」がここにいる。
ここに生きている。
それでじゅうぶん。
Hiroshi Hayashi++++++++++Sep 09++++++++++++++はやし浩司
●自己認知力
+++++++++++++++++
自分を、自分で、評価する能力があるかないか。
その能力のことを、「自己認知力」という。
ピーター・サロベイの説く「社会適応性」、つまり
EQ論(人格の完成度論)でも、重要なキーワードの
ひとつになっている。
自分で自分を評価する能力の高い人を、自己認知力の
高い人という。
そうでない人を、低い人という。
が、一般的には、自分のもつよい能力を、正当に評価する
能力のことを、「自己認知力」という。
あるいは「私の能力はすぐれている」と信ずる能力のことを、
「自己認知力」という。
この自己認知力には、2種類ある。
(1)能力があり、それを評価する能力がある。
「自分にはどのような能力があるか」を知る能力をいう。
(2)能力がないのに、それを評価する能力がない。
「自分には、どのような能力がないか」を知る能力をいう。
ふつう「自己認知力」というときは、前者をいう。
が、後者のケースも少なくない。
最近、私は、こんな話を聞いた。
+++++++++++++++++
●ある葬儀で
義兄がある葬儀に参列した。
そこでのこと。
亡くなったのは、87歳の女性。
喪主は、その女性の長男、60歳。
ところが、である。
その長男の嫁(58歳)の様子が、異様だったという。
義兄は、こう話してくれた。
「だんなは昔から、静かな人だった。
そのこともあって、嫁が、ひとりではしゃいでいた」と。
私「はしゃいでいた?」
義「そう、はしゃいでいた。キャッキャッと笑ったり、大声で世間話をしていた。ハイに
なっていた。みな、眉をひそめていたよ」と。
●「私が主人公」
何かにつけ、自己中心性の強い人は、自分が目立たないと気がすまない。
俗にいう「目立ちたがり屋」というのが、それ。
義兄が言うには、その女性(嫁)が、そうだったという。
火葬場で火葬を待っているときも、三日目、初七日の法事のときも、「まるでクラブのホ
ステスのように、みなのところを回り、世間話を繰り返していた」と。
「ふつうなら、親(義母)の葬式だから、嫁というのは、しおらしくしているもの。
しかしその女性(嫁)は、まるでパーティでの主人公のように振舞っていました。
で、驚いたのは、火葬が終わって、一度祭事会館へ戻ったときのことです。
最後の焼香というところで、みなの前で、オロオロと泣き崩れてしまったのです。
あれには、みな、あっけに取られました。
というのも、亡くなった女性(姑)とその女性(嫁)とは、昔からうまくいっていなかっ
たことを、みな、知っていたからです」と。
●現実検証能力
「自分が今、どういう状況に置かれているか」「自分が今、みなに、どう思われているか」。
それを「現実検証能力」ともいう。
しかし「自己認知力」と「現実検証能力」の境目が、よくわからないケースも少なくない。
その女性(嫁)を例にあげて、考えてみよう。
その女性(嫁)の言動は、たしかに「ふつうではなかった」(義兄談)。
しかしその女性(嫁)は、自分が他人にどう思われているか、それが判断できなかった。
つまり自分を客観的に評価する能力に、欠けていた。
最後の焼香のところで、オロオロと泣き崩れてしまったときも、(横にいた夫が、体を支え
たが)、みなはあっけに取られ、言葉を失った。
が、そこは葬儀の場所。
現実を正確に知る能力があれば、態度ももっと別のものになっていたはず。
●まるで自分のことがわかっていない
「あの女性(嫁)はね、一族の中でも、変わり者ということになっていますよ」と、義
兄は話してくれた。
「ところが、自分では、よくできた嫁と思い込んでいるのですね。みなに好かれ、尊敬さ
れていると思い込んでいるのですね」とも。
そういう人は、少なくない。
まるで自分のことがわかっていない。
自己中心性が肥大化した人を、自己愛者という。
その自己愛者の症状とも似ている。
完ぺき主義で、他人の批判を許さない。
まちがいを指摘されると、それだけでパニック状態になってしまう。
ギャーギャーと泣きわめく。
あるいは激怒する。
他人に心を許さない。
許さない分だけ、心の中はいつも緊張状態。
ささいなことでカッとなりやすい。
●自己認知力
こういうケースも、「自己認知力」という能力で判断する。
自分にその能力がないのに、それを客観的に評価できない。
あとは思い込みと過信、独断と偏見だけで、ふつうではない行動を繰り返す。
この話をワイフにすると、ワイフはすかさず、こう言った。
「そういう人って、意外と多いわよ」と。
私「ぼくだって、そうかもしれない」
ワ「そうね、あなたにも、そういうところがあるわね」
私「だろ……」
ワ「ほら、学者とか、研究者と言われる人の中にも多いということよ」
私「そうだね。その分野のことはよく知っているけど、その外の世界を知らない。教師の
世界も、似たようなものだよ」と。
●では、どうするか
「自分は他人から、どう見られているか」。
それをいつも自分に問いかける。
(だからといって、他人に迎合しろということではない。誤解のないように!)
私も最近、こんな経験をときどきする。
「私のことを好意的に思ってくれているはず」と信じている人に、裏切られるようなケー
スである。
それに気づいて、「ああ、ぼくって、そんなふうに思われていたのだ」と、驚いたりする。
最近でも、生徒(中学生)に、こう言われたことがある。
「先生(=私のこと)って、キレやすい」と。
また反対に、意外な人に、高く評価されているということもある。
つまり自分が他人にどう見られているかを、的確に判断するのは、それくらい難しいこと
でもある。
●自己中心性
自己認知力は、このように一方で、その人の自己中心性と深く結びついている。
が、ある程度、自己認知力を高めるためには、ある程度、自己中心的でなければならない。
「私はすばらしい」という思い込みが、その人の自己認知力を高める。
その人を伸ばすということもある。
が、同じ自己認知力でも、「まるで自分のことがわかっていない」という自己認知力は、
いただけない。
自分に能力がないのに、それに気づいていない。
プライドばかり強くて、箸にも棒にもかからない。
さらに愚かなことをしながら、それを愚かなこととさえ気がつかない。
そういう人のことを、俗世間では、「バカ」という。
(「バカなことをする人を、バカという。頭じゃないのよ」(フォレスト・ガンプ)。)
【補記】
●加齢とともに……
私の印象では、加齢とともに、自己中心性が強くなっていく人と、反対に『老いては』
に従え』式に、自己中心性が弱くなっていく人がいるように感ずる。
そしてそれは、脳の働きとも、密接に関連している(?)。
たとえば認知症か何かになると、極端に自己中心性が強くなる人がいる。
人格そのものが、崩れるというか、変化する人も珍しくない。
心の余裕がなくなり、思慮深さが消える。
ささいなことでピリピリと反応し、ときに激怒したり、泣き叫んだりする。
要するに、これは習慣の問題ということになる。
能力ではなく、習慣。
日ごろから、考えるクセがあるかないかということ。
考えるクセが身についていれば、あえて「自己認知力」などという言葉は使わなくても、
自分のことを正当に評価できるようになる。
そうでなければ、そうでない。
その(ちがい)は、老齢期になると、さらにはっきりとしてくる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hay
ashi 林浩司 BW はやし浩司 自己認知力 自己評価力 人格の完成度 サロベ
イ EQ論)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●自己認知力
●子どもの社会適応性は、つぎの5つをみて、判断する(サロベイほか)。
(1)共感性
(2)自己認知力
(3)自己統制力
(4)粘り強さ
(5)楽観性
(6)柔軟性
これら6つの要素が、ほどよくそなわっていれば、その子どもは、人間的に、完成度の
高い子どもとみる(「EQ論」)。
順に考えてみよう。
(1)共感性
人格の完成度は、内面化、つまり精神の完成度をもってもる。その一つのバロメーター
が、「共感性」ということになる。
つまりは、どの程度、相手の立場で、相手の心の状態になって、その相手の苦しみ、悲
しみ、悩みを、共感できるかどうかということ。
その反対側に位置するのが、自己中心性である。
乳幼児期は、子どもは、総じて自己中心的なものの考え方をする。しかし成長とともに、
その自己中心性から脱却する。「利己から利他への転換」と私は呼んでいる。
が、中には、その自己中心性から、脱却できないまま、おとなになる子どももいる。さ
らにこの自己中心性が、おとなになるにつれて、周囲の社会観と融合して、悪玉親意識、
権威主義、世間体意識へと、変質することもある。
(2)自己認知力
ここでいう「自己認知能力」は、「私はどんな人間なのか」「何をすべき人間なのか」「私
は何をしたいのか」ということを、客観的に認知する能力をいう。
この自己認知能力が、弱い子どもは、おとなから見ると、いわゆる「何を考えているか
わからない子ども」といった、印象を与えるようになる。どこかぐずぐずしていて、はっ
きりしない。優柔不断。
反対に、独善、独断、排他性、偏見などを、もつこともある。自分のしていること、言っ
ていることを客観的に認知することができないため、子どもは、猪突猛進型の生き方を示
すことが多い。わがままで、横柄になることも、珍しくない。
(3)自己統制力
すべきことと、してはいけないことを、冷静に判断し、その判断に従って行動する。子
どものばあい、自己のコントロール力をみれば、それがわかる。
たとえば自己統制力のある子どもは、お年玉を手にしても、それを貯金したり、さらに
ためて、もっと高価なものを買い求めようとしたりする。
が、この自己統制力のない子どもは、手にしたお金を、その場で、その場の楽しみだけ
のために使ってしまったりする。あるいは親が、「食べてはだめ」と言っているにもかかわ
らず、お菓子をみな、食べてしまうなど。
感情のコントロールも、この自己統制力に含まれる。平気で相手をキズつける言葉を口
にしたり、感情のおもむくまま、好き勝手なことをするなど。もしそうであれば、自己統
制力の弱い子どもとみる。
ふつう自己統制力は、(1)行動面の統制力、(2)精神面の統制力、(3)感情面の統制
力に分けて考える。
(4)粘り強さ
短気というのは、それ自体が、人格的な欠陥と考えてよい。このことは、子どもの世界
を見ていると、よくわかる。見た目の能力に、まどわされてはいけない。
能力的に優秀な子どもでも、短気な子どもはいくらでもいる一方、能力的にかなり問題
のある子どもでも、短気な子どもは多い。
集中力がつづかないというよりは、精神的な緊張感が持続できない。そのため、短気に
なる。中には、単純作業を反復的にさせたりすると、突然、狂乱状態になって、泣き叫ぶ
子どももいる。A障害という障害をもった子どもに、ときどき見られる症状である。
この粘り強さこそが、その子どもの、忍耐力ということになる。
(5)楽観性
まちがいをすなおに認める。失敗をすなおに認める。あとはそれをすぐ忘れて、前向き
に、ものを考えていく。
それができる子どもには、何でもないことだが、心にゆがみのある子どもは、おかしな
ところで、それにこだわったり、ひがんだり、いじけたりする。クヨクヨと気にしたり、
悩んだりすることもある。
簡単な例としては、何かのことでまちがえたようなときを、それを見れば、わかる。
ハハハと笑ってすます子どもと、深刻に思い悩んでしまう子どもがいる。その場の雰囲
気にもよるが、ふと見せる(こだわり)を観察して、それを判断する。
たとえば私のワイフなどは、ほとんど、ものごとには、こだわらない性質である。楽観
的と言えば、楽観的。超・楽観的。
先日も、「お前、がんになったら、どうする?」と聞くと、「なおせばいいじゃなア〜い」
と。そこで「がんは、こわい病気だよ」と言うと、「今じゃ、めったに死なないわよ」と。
さらに、「なおらなかったら?」と聞くと、「そのときは、そのときよ。ジタバタしても、
しかたないでしょう」と。
冗談を言っているのかと思うときもあるが、ワイフは、本気。つまり、そういうふうに、
考える人もいる。
(6)柔軟性
子どもの世界でも、(がんこ)な面を見せたら、警戒する。
この(がんこ)は、(意地)、さらに(わがまま)とは、区別して考える。(がんこ)を考
える前に、それについて、書いたのが、つぎの原稿である。
+++++++++++++++++++
●子どもの意地
こんな子ども(年長男児)がいた。風邪をひいて熱を出しているにもかかわらず、「幼稚
園へ行く」と。休まずに行くと、賞がもらえるからだ。
そこで母親はその子どもをつれて幼稚園へ行った。顔だけ出して帰るつもりだった。しか
し幼稚園へ行くと、その子どもは今度は「帰るのはいやだ」と言い出した。子どもながら
に、それはずるいことだと思ったのだろう。結局その母親は、昼の給食の時間まで、幼稚
園にいることになった。またこんな子ども(年長男児)もいた。
レストランで、その子どもが「もう一枚ピザを食べる」と言い出した。そこでお母さん
が、「お兄ちゃんと半分ずつならいい」と言ったのだが、「どうしてももう一枚食べる」と。
そこで母親はもう一枚ピザを頼んだのだが、その子どもはヒーヒー言いながら、そのピザ
を食べたという。
「おとなでも二枚はきついのに……」と、その母親は笑っていた。
今、こういう意地っ張りな子どもが少なくなった。丸くなったというか、やさしくなった。
心理学の世界では、意地のことを「自我」という。英語では、EGOとか、SELFとか
いう。少し昔の日本人は、「根性」といった。(今でも「根性」という言葉を使うが、どこ
か暴力的で、私は好きではないが……。)
教える側からすると、このタイプの子どもは、人間としての輪郭がたいへんハッキリとし
ている。ワーワーと自己主張するが、ウラがなく、扱いやすい。正義感も強い。
ただし意地とがんこ。さらに意地とわがままは区別する。カラに閉じこもり、融通がき
かなくなることをがんこという。毎朝、同じズボンでないと幼稚園へ行かないというのは、
がんこ。また「あれを買って!」「買って!」と泣き叫ぶのは、わがままということになる。
がんこについては、別のところで考えるが、わがままは一般的には、無視するという方法
で対処する。「わがままを言っても、だれも相手にしない」という雰囲気(ふんいき)を大
切にする。
++++++++++++++++++
心に何か、問題が起きると、子どもは、(がんこ)になる。ある特定の、ささいなことに
こだわり、そこから一歩も、抜け出られなくなる。
よく知られた例に、かん黙児や自閉症児がいる。アスペルガー障害児の子どもも、異常
なこだわりを見せることもある。こうしたこだわりにもとづく行動を、「固執行動」という。
ある特定の席でないとすわらない。特定のスカートでないと、外出しない。お迎えの先
生に、一言も口をきかない。学校へ行くのがいやだと、玄関先で、かたまってしまう、な
ど。
こうした(がんこさ)が、なぜ起きるかという問題はさておき、子どもが、こうした(が
んこさ)を示したら、まず家庭環境を猛省する。ほとんどのばあい、親は、それを「わが
まま」と決めてかかって、最初の段階で、無理をする。この無理が、子どもの心をゆがめ
る。症状をこじらせる。
一方、人格の完成度の高い子どもほど、柔軟なものの考え方ができる。その場に応じて、
臨機応変に、ものごとに対処する。趣味や特技も豊富で、友人も多い。そのため、より柔
軟な子どもは、それだけ社会適応性がすぐれているということになる。
一つの目安としては、友人関係を見ると言う方法がある。(だから「社会適応性」という
が……。)
友人の数が多く、いろいろなタイプの友人と、広く交際できると言うのであれば、ここ
でいう人格の完成度が高い、つまり、社会適応性のすぐれた子どもということになる。
【子ども診断テスト】
( )友だちのための仕事や労役を、好んで引き受ける(共感性)。
( )してはいけないこと、すべきことを、いつもよくわきまえている(自己認知力)。
( )小遣いを貯金する。ほしいものに対して、がまん強い(自己統制力)。
( )がんばって、ものごとを仕上げることがよくある(粘り強さ)。
( )まちがえても、あまり気にしない。平気といった感じ(楽観性)。
( )友人が多い。誕生日パーティによく招待される(社会適応性)。
( )趣味が豊富で、何でもござれという感じ(柔軟性)。
ここにあげた項目について、「ほぼ、そうだ」というのであれば、社会適応性のすぐれた
子どもとみる。
(はやし浩司 社会適応性 サロベイ サロヴェイ EQ EQ論 人格の完成度)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●離脱と活動
+++++++++++++++++++++
先日、ある会場で、退職者を対象にした講演会があった。
その中で、講師(75歳くらい)が、こう言った。
「老後になったら、生活をコンパクトにすることが大切です」と。
「コンパクト」とは、つまり、「身辺の整理をし、住む世界を小さくしろ」ということ。
一理あるが、私は、ふと考えた。
「どうしてコンパクトにしなければならないのか」と。
つまりその講師の説いたのは、「離脱理論」のひとつということになる。
たしかにそういう部分はないわけではない。
行動範囲も狭くなる。
思考力も低下する。
運動能力も衰える。
それに合わせた環境づくりは、欠かせない。
+++++++++++++++++++++
●「老齢」と「老化」
私たちはみな、例外なく、歳をとる。
それを「老齢」という。
英語では、「エイジング(Aging)」という。
しかし「老齢」イコール、「老化」ではない。
歳をとったからといって、ジジ臭くなることはない。
ババ臭くなることはない。
そこで登場するのが、離脱理論と活動理論。
老齢期に入ったら、社会から離脱していく。
そのための理論が、「離脱理論」(カミング・ヘンリー)(「心理学用語」渋谷昌三)。
一方、老齢期に入っても、それまでと同じように、あるいはさらに活動的に生きていく。
そのための理論が、「活動理論」(フリードマン・ハヴィガースト)(「心理学用語」渋谷昌
三)。
日本でいう、「退職後は、庭いじりと孫の世話」というのは、まさに離脱理論ということ
になる。
●サクセスフル・エイジング
しかし老齢期に入ったら、どうしてそれまでの生き方を変えなければならないのか。
渋谷昌三氏の「心理学用語」の中に、こんな参考になる表現がある(同書・かんき出版)。
(1)サクセスフル・エイジング(Successful Aging)(成功した老齢期)
(2)プロダクティブ・エイジング(Productive Aging)(生産的な老齢期)
自分なりに、この2つを解釈してみたい。
老齢期は、それまでの人生の積み重ねの結果としてやってくる。
その(結果)をみれば、成功・失敗が、わかる。
(どういう状態を成功といい、どういう状態を失敗というかは、それぞれに、いろいろな
考え方がある。)
恐らくサクセスフル・エイジングというのは、それなりにのんびりと、優雅に暮らすこと
ができる老後をいうのだろう。
「老化の過程にうまく適応して、幸福な老後を送ること」(同書)とある。
それに対して、「老齢期こそ、もっと活動的に生きよう」というのが、プロダクティブ・
エイジングということになる。
●プロダクティブ・エイジング
プロダゥティブ・エイジングといえば、すぐさま頭に思い浮かぶのが、「統合性の確立」。
これについては、たびたび書いてきた。
で、今回は、それはさておき、もっと日常的なレベルで、プロダクティブ・エイジングを
考えてみたい。
つまりどうすれば、私たちは老齢期を、さらに生き生きと生きることができるか、と。
「高齢者が社会の中で、いかに生産的に生きるか」(同書)と。
少し前、日本のおバカ首相が、こう言った。
「高齢者は、働くしか才能がない」と。
恐らく、「高齢者は、働くしか能(のう)がない」と言うべきところを、「才能」と言った
のだろう。
あの人の国語力は、小学生程度(?)。
「才能」でも「能」でもよいが、これほど私たちの年代の者を怒らせた言葉はない。
私たち自身が、「働くしか能がないので……」と言うのは、構わない。
もっと言えば、「国民年金など、アテにならないから、死ぬまで働くしかない」。
しかしそれを他人、なかんずく首相に言われると、腹が立つ。
が、怒ってばかりいてはいけない。
私たちは、プロダクティブに生きてこそ、老齢期を乗り越えることができる。
●では、どうすればよいのか
重要なのは、「社会」と、接点を保つこと。
仕事をするのがいちばんよいが、ボランティア活動、近隣づきあい、地域活動などなど。
その中から、(自分ができること)(自分がすべきこと)を見つけながら、それを昇華させ
ていく。
私のばあいは、仕事第一に考えている。
「社会」というより、「子どもたち」との接点を失ったら、私は私でなくなる。
それが自分でもよくわかっている。
そのためにどうするか。
それが現在の思考、行動の原点になっている。
つまりその上で、原稿を書き、人生を考える。
こうしてパソコンに文章を叩き出すのも、そのひとつ。
書くのが楽しいというよりは、頭の中にあるモヤモヤを吐き出す。
吐き出したときの爽快感には、格別なものがある。
それにもうひとつ目標がある。
こうして書くことによって、脳みその健康を維持する。
同時に、「精進(しょうじん)」。
もともと私の素性はよくない。
自分でも、それがよくわかっている。
だからそういう自分に、言い聞かせるために書く。
「これをしろ」「これをしてはいけない」と。
一日でも油断すると、私の人間性は、即、後退に向かう。
こうした方法が、みなに効果的とは思わないが、しかしそれぞれがそれぞれの環境の中
で、プロダクティブ・エイジングを目指す。
そうすれば、若い人たちの私たちを見る目も変わってくるだろう。
同時に、社会に、大きく貢献できる。
けっして老齢イコール、老化と考えて、自分自身までコンパクトにしてはいけない。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 離脱理論 プロダクティブ エイジング 豊かな老後 老後論 はや
し浩司 活動理論)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●ルーム・ウォーカー使用感想
++++++++++++++++++++
昨日は、夜遅く、近くの温泉へ行ってきた。
帰りに、回転寿司を食べた。
ワイフと2人で、8皿。
で、そのあと家に帰ってから、ルーム・ウォーカー
に乗る。
心拍数、消費カロリーなどが表示される、すぐれモノ。
もともと散歩が好きだから、楽しい。
++++++++++++++++++++
●老後の必需品
ルーム・ウォーカーは、老後の必需品。
そう断言してよい。
老齢期になると、みな、膝や足を傷める。
それがそのまま持病となって、やがて歩けなくなる。
70歳で歩けなる人もいるし、80歳で歩けなくなる人もいる。
人それぞれだが、できるだけ末長く、健康でいたい。
そう願って、とうとう私も、ルーム・ウォーカーを購入した。
で、今朝も、すでに20分。
距離にして、1・5キロ前後を、歩いてみた。
(正確には、ルーム・ウォーカーを回してみた。)
軽い、さわやかな汗をかいた。
消費カロリーは、130キロカロリー前後か。
缶ジュース、2本分というところ。
これを使えば、危険な道路を歩くこともない。
雨の日でも、ウォーキングができる。
が、それだけではない。
私はルーム・ウォーカーを、テレビの前に設置した。
本も読めるようにした。
つまりテレビを見たり、本を読みながら、ウォーキングができる。
ハハハ、これが実に楽しい。
(いつまでつづくか、わからないが……。)
マッサージ機は、ルーム・ウォーカーのすぐ前に置いた。
疲れた足は、マッサージ機で、ほぐせばよい。
私も、いよいよジー様ぽくなってきた!
●映画『サブウェイ123』
+++++++++++++++++
おととい、仕事が終わってから、深夜劇場に
足を運んだ。
観た映画は、『サブウェイ123激突』。
矛盾だらけの、テロ映画。
星は、2つの、★★。
デンゼル・ワシントンと、ジョン・トラボルタ。
2人の名優の共演作ということで、かなり期待
していたが、がっかり。
観客も、私たちを入れて、たったの4人。
「ウルヴァリンにすればよかった」と、劇場を
出るとき、ワイフが、何度もそう言った。
+++++++++++++++++
●映画『サブウェイ123激突』
簡単に言えば、列車をハイジャックし、乗客を人質に、NY市から身代金を取るという
映画。
が、矛盾だらけ。
犯人たちは顔にマスクもつけていなかった。
今ではDNA捜査法というのもある。
あれだけ証拠をベタベタと残してしまったら、仮にそれがうまくいったとしても、即、逮
捕。
それに今では、地下鉄でも携帯電話は使えるはず。
パソコンのテレビ電話はそのまま使えるのに、どうして、みな、携帯電話を使わなかった
のだろう。
また私が監督だったら、地下鉄中の電源を落とし、真っ暗闇にしたあと、暗視スコープ
付きの銃で、犯人たちを射殺する。
映画のような回りくどいやり方は、しない。
「激突」というのは、要するに、地下鉄司令部勤務のデンゼル・ワシントンと、ハジジャッ
カーのジョン・トラボルタとの激突という意味(?)。
2人のやりとりが、映画の柱になっている。
しかしそれが、イマイチおもしろくない。
ネズミに足をかまれて、思わず発砲してしまう、SWAT。
現金を輸送するため、カーチェイス映画さながらに、車を走らせるパトカーなどなど。
最後は、あっけなく犯人たちが射殺されて、おしまい。
何とか時間を作って、今週中に、『ウルヴァリン』を見よう。
今は、そう考えている。
(090916)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●ニューロンとシナプス
+++++++++++++++++++++++
「脳のからくり」(茂木健一郎・新潮文庫)によれば、
脳の中には、1000億個のニューロン(神経細胞)があるという。
その1個ずつのニューロンから、細長いひものような神経突起が、
約1万本も伸びているという。
そしてその神経突起どうしが、「手をつないでいる部分」(同書)を、
シナプスという。
1000億個のニューロンが、1万本ずつの神経突起を伸ばしているから、
そのためシナプスの数は、なんと1000兆個にもなるという。
++++++++++++++++++++++++
(ニューロン)……(神経突起)……(シナプス)。
わかりやすくチャート化すると、こうなる。
それにしても、1000兆個というのは、すごい!
こうしたニューロンが私たちの知覚、行動、思考をコントロールしている。
で、興味深いことは、こうしたニューロンは、パソコンのメモリーと同じように、(プラ
ス)(マイナス)の単純なスイッチでできているということ。
そういう点では、脳の構造とパソコンの構造は、たいへんよく似ている。
そこで計算してみよう。
メモリーの基本的単位になっているのが、GB(ギガバイト)。
現在(2009)、2〜4GBのSDメモリーや、USBメモリーが、1000円前後で売
られている。
1GBは、約11億バイト(10億7374万1824バイト。
1GBは、1024メガバイト。
つまり10の9乗。)
数字が複雑なので、ここでは1GBを10億バイトとして計算してみる。
すると、人間の脳の中にあるシナプスの1000兆個を、10億個で割ってみると、人間
の脳は、100万GBということになる。
(1000万÷10で計算すればよい。)
100万GBというと、今では1テラバイト(=1000GB・10の12乗バイト)
のハードディスクさえ売りに出ているから、その1テラバイトのハードディスクで計算し
てみると、こうなる。
100万GB÷1000GB=1000!
つまり1テラバイトのハードディスクを、1000個つなげると、人間の脳の中にある
シナプスと同じ数になる!
この1000個を、多いとみるか少ないとみるか?
意見の分かれるところだが、私は、「いよいよここまで来たか!」と驚く。
1テラバイトのハードディスク(価格は、現在8000円前後)を、1000個つなげ
ると、人間の脳と同じになる!
1000個というと、たいへんな数だが、しかし不可能な数ではない。
あと5年もすれば、10テラバイト、さらに10年もすれば、100テラバイトの記憶媒
体が生まれるだろう。
そうなれば、小さな記憶媒体の中に、人間の脳をそのままコピーすることも可能になる。
もっとも人間の脳のばあい、すべてのニューロンが活動しているわけではない。
実際、活動しているのは、3分の1程度とも言われている。
さらに今、意識している部分についていえば、数10万分の1とも言われている。
だから、仮に100テラバイトの記憶媒体が生まれれば、それでじゅうぶんということに
なる。
もっとも神経突起は、言うなれば蜘蛛の巣状に脳の中で入り組んでいる。
それをひとつずつ取り出して、記憶媒体にコピーするというのには、別の問題もある。
しかしコンピュータに、人間の脳と同じ働きをさせることは、それで可能になる。
おもしろいというより、恐ろしい(?)。
『脳のからくり』を読みながら、本文とは別に、そんなことを考えた。
(090918)
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hay
ashi 林浩司 BW はやし浩司 シナプス ニューロン 1GB 1TB)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●Pay Forward(ペイ・フォワード)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
+
ハーレイ・J・オスメント(少年)主役の映画に、『ペイ・フォワード(Pay it Forward)』
(2000年作品)というのがあった。
1人の人が、それぞれ3人の人に、善意の行為を手渡していけば、世界が変わる、と。
1人の少年がそのアイディアを思いつく。
そして彼は、それを実行する。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
+
●ペイ・フォワード運動
「システムとしては、非常に単純明解なものです。つまり、人は他人から厚意を受けた
場合、その相手にお返しをしようとしますね。そうすると、その厚意は当事者間のみで
完結して終わってしまいます。しかし、この"厚意"を受けた相手に返すのではなくて、次
の人に別な形で『渡して』みたら、どうなるでしょう? それを、1人の人が別の新た
な3人に『渡して』いったとしたら・・・」(「ペイ・フォワード運動」HPの解説より、
転載」。)
●すばらしいこと
ハーレイ・J・オスメントといえば、同時期、『シクス・センス』という映画でも主演を
演じている。
もの静かで、それでいて理知的な演技が、見事だった。
映画『シクス・センス』から受けた衝撃は大きかった。
見終わったあと、頭の中で、バチバチと火花が飛んだ。
常識がひっくり返った、
そののち、この映画の(流れ)は、『マトリックス』、さらに最近の『ミラーズ』へと、つ
づく。
それはさておき、今日、私の周辺で、こんなすばらしいことがあった。
●山荘で
今日は土曜日。
午後からワイフと山荘へ向かった。
伸びすぎた梨の木を切り倒すためである。
このところ山荘周辺に、猿が出没する。
その猿が、いたずらをする。
雨どいを破壊したり、テレビアンテナを折ったりする。
そこで餌になるような実をつける木を切ることにした。
先日は、栗の木を切った。
で、今日は梨の木
●草刈り
驚いたことに、行ってみると、山荘周辺の雑草が、きれいに刈り取られていた。
明らかにプロの手さばき!
しかも刈り取った雑草まで、始末してあった。
私はだれが刈ってくれたか、すぐわかった。
親しくしている、Kさんである。
が、それだけではなかった。
●プロの手さばき
大通りをはずれたところから、山荘までつづく道は、500〜600メートルある。
細い一本道である。
しかし私たち以外は、ほとんどだれも使わない。
で、2週間ほど前のこと。
私は運動もかねて、この道の400〜500メートル分の道路わきの草を刈った。
草刈りは嫌いではない。
ストレス解消にもなる。
背丈の伸びた夏草を、草刈り機でバリバリ、ウィーン、バリバリと刈っていくのは、たい
へん気持よい。
爽快感すら、覚える。
それでそうした。
が、今日、その道を通ってみると、両側の草が、きれいに刈り取られていた。
こちらも見るからに、明らかにプロの手さばき!
●刈り残し
草刈りにも、じょうず、へたがある。
じょうずな人が草を刈ると、地面の小石だけを残したような草の刈り方をする。
全体に地面をなめるように、均一的な刈り方をする。
見た目にも美しい。
が、へたな人が草を刈ると、まるでぼさぼさのトラ刈りのようになる。
刈り残しが、いたるところで草の柱のようになる。
私は草刈りは嫌いではないが、いくら努力しても、うまく刈れない。
が、山荘のまわりの草が、きれいに刈り取られていた!
●みなが、草刈りをしてくれた!
先ほど「それだけではない」と書いたが、それだけではなかった。
500〜600メートルの道の両側の草も、きれいに刈り取られていた。
こうした農道は、いろいろな地権者が入り組んでいる。
Kさんの土地もあれば、Uさんや、Hさんの土地もある。
その中を、農道が通っている。
で、私はひまがあると、ときどき、その農道脇の草を刈っている。
私たち自身のためでもある。
放っておくと、両側から夏草が、道路をおおう。
車が通るのがやっとというほど、道が狭くなる。
●トラ刈り
けっして手を抜いているわけではない。
しかし私が草を刈ると、先にも書いたように、トラ刈りのようになる。
だから草を刈りながら、いつも、「Kさんたちが見たら、笑うだろうな」と思っていた。
まあ、笑われてもしかたないような刈り方しか、私にはできない。
が、私の行為が、農家の人たちに、別の形で伝わった。
もちろん私には、「みなのためにしている」とか、「してやっている」とかいう意識は、み
じんもない。
あくまでも私のため。
が、それを農家の人たちは、よいほうに解釈してくれた。
まずKさんが、自分の土地の中の草を刈った。
それを見て、Uさんや、Hさんたちが、草を刈った。
ついでにKさんは、私の山荘のまわりの草も刈ってくれた。
私はそれを知って、うれしくなった。
久しぶりに、胸の中がポーッと暖かくなった。
●ワイフと・・・
私「みんなが、山荘のまわりの草を刈ってくれたんだよ」
ワ「Kさんたちね」
私「そうだね」
ワ「それにしても、きれいね」
私「うん・・・」
ワ「お礼の電話でもしたら・・・?」
私「・・・しないよ。また近く、道路の草を刈って、返すよ」と。
家のまわりを見やりながら、私は、映画『ペイ・フォワード』を思い出していた。
1人の人の善意が、いつの間にか、他人の心を動かし、その輪がどんどんと広がっていく。
そして気がついてみたら、その輪が、いつの間にか、自分のところに戻ってくる。
戻ってきて、自分の心を暖かく包んでくれる。
私はきれいに刈り取られた山荘の周辺を見ながら、そう思った。
さわやかな、さわやかな、どこまでもさわやかな秋のはじめの乾いた風が、下の森から
やさしく吹いていた。
うれしかったプラス、たのしかった。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW Pay it forward ペイ・フォワード 夏の草刈り はやし浩司)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 16日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page022.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●娘の不登園
【N県のMさんより、はやし浩司へ】
はじめまして。年長の娘の登園拒否についての相談です。幼稚園に年中から入園して、一
週間後から1学期間登園拒否が続きました。
その後2学期以降はうそのように楽しく通園していたのですが、進級して年長になって夏
休み明けから再び登園拒否が始まりました。
習い事でも同様です。
夏休み後半には習い事でキャンプに出かけお友達とはじめて親元を離れてお泊りができ、
成長したなと思っていたところで、とてもショックでした。
頑張りすぎてしまったのかとも思いましたが、HPを拝見して、分離不安なのでは・・小
学生になって通えるのだろうか・・ととても不安です。
幼稚園では先生にも相談しています。先生は「一学期はとても頑張っていたんだと思いま
す。まだクラスに溶け込めていない感じがします。優等生タイプだと思います」「お友達と
遊んでいて自分の期待する答えが返ってこないといやみたいです」と話していました。娘
にも理由を聞いたりしていますが、その時々で違います。
幼稚園の帰りに友達と公園で遊んだり、近所の友達とは楽しく毎日遊んでいます。
娘は2歳から2年間幼児教室にも通っていたのですが、その時も始めだけは離れられなく
て毎回先生に抱っこでした。
どうしても嫌なら幼稚園お休みしてもいいんだよと言ってしまったこともありましたが、
明日はOOOがあるから行くと言います。でも幼稚園に入るとうつむいてしまい、離れる
ことができないのです。
どうしたらよいのでしょうか・・どうぞよろしくお願いいたします。
【はやし浩司より、Mさんへ】
M様へ
こんばんは
家族関係がよくわかりません。
相談のお嬢さんは、長女ですか?
下に弟か妹がいませんか。
分離不安かどうか、(赤ちゃん返りかどうか)、
そのあたりの症状がもう少し詳しくわかると、
適切なアドバイスができます。
それともうひとつは、あなた自身が、不安先行型の
子育てをしていないか。
過干渉気味ではないか。
過関心も疑われます。
子どもの問題というよりは、環境の問題と考えてください。
この際、不登園は、あきらめなさい。
まず子どもの心の問題を考え、子どもの心を守ることを
最優先します。
では、
返事をお待ちしています。
【Mさんより、はやし浩司へ】
早速返信いただきましてありがとうございます。
娘は長女で、一人っ子です。
外遊びの大好きな子供です。
朝から夕方までほんとに良く遊びます。
外で遊んでいるときの様子からは、とても想像がつきません。
私自身も一人っ子です。
そしてたしかに過干渉、過関心、不安先行型かもしれません。
口うるさく言ってしまう、怒ってしまっていると思います。
あまり言わないように・・と思っているのですが、
言わないと何もしない娘に、つい口が出てしまいます。
幼稚園行きたくない・・は正確には8月末の夏季保育から始まりました。
キャンプで最初の一日はお休みし、2日目から登園。
その日用事があり、預かり保育をして(迎えの時泣いていました)
そしてその翌日からのことでした。
2学期前日には奥歯が痛いと言い出し、歯科へ行きました。
原因はよくわからず、6歳臼歯のせいではないか・・といわれました。
そして今日まで行きたくない・・が続いています。
娘には幼稚園お休みしてもいいんだよ・・と言っています。
ただ明日はOO先生と約束しているから行かないと・・、
OOちゃんと約束しちゃったから・・と行こうとする気持ちもあるようです。
朝着替えのときになると、もじもじになってしまい、
幼稚園休むのは嫌だけど、でも行くのも嫌・・
今朝もその状態が続き、できるだけ話を聞いて、休むのが嫌だったら行ってみようか・・
と。
そして帰りは園に一番でお迎えに行く約束をして送りました。
教室の前まで送り、先生に引き離されてでした。
年中の時は始めての幼稚園で、泣いても仕方ないのかと休むことなく
連れて行き、夏休み明けからは楽しく行ってくれるようになりました。
今も行けば給食も花マル、運動会の練習も頑張っているようです。
娘は1歳のときくらいから、私がいないと、見えないとダメなタイプで、
公園に行っても離れられない子どもでした。
どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。
【はやし浩司より、Mさんへ】
●基本的信頼関係
返事が遅れて、ごめんなさい。
いろいろ心配さなっている様子は、よくわかります。
「不登園ならまだいいが、不登校児になったら、どうししょう?」と、悩んでおられる様
子もよくわかります。
が、全体的に判断すると、いわゆる(よくある問題)で、とくに子どもに問題があるとは
思われません。
で、このタイプの子どもは、(外の世界)でがんばる分だけ、(つまりそれだけ緊張感を解
放できない分だけ)、家の中では荒れるという症状が出てきます。
原因は、母子間の基本的信頼関係の構築に、やや失敗したかなというところです。
つまりその分だけ、外の世界でいい子ぶる、イコール、心を開いて、集団に溶け込めない
ということです。
さらにその原因はといえば、Mさん自身が、全幅に子どもに心を開いていない、開けない
という状態がつづいていると思います。
(詳しくは、「はやし浩司 基本的信頼関係」で検索してみてください。)
●家庭は休む場所
このタイプの子どもにとっては、「家庭は休む場所」と心得てください。
「うちの子は、外ではがんばっている」と思い直して、家の中では、うんと緩めます。
(1)暖かい無視と、(2)求めてきたときが与えどきを、大切にします。
生活態度がだらしなくなったり、ぞんざいになったりしますが、暖かくそれを無視する
ということです。
また子どもは、その瞬間、瞬間、あなたに愛着表示(愛情を求める行為)を繰り返します
が、そのつどすかさず、抱いてあげるなどの反応を示してあげます。
「待っていてね」「今、忙しい」は、禁句です。
すかさずしてあげれば、たいてい1〜2分で、子どもは満足し、あなたから体を離します。
●過負担
不登園というより、全体に過負担が疑われます。
私が40年前に、幼稚園の世界に入ったころには、1年保育が主流、2年保育がふえてき
たという状況でした。
幼稚園へ通わないで、小学校へ入る子どもも10%前後いました。
が、今は、3年、4年保育が主流(?)。
子どもの質が変わったというよりも、幼稚園経営の問題、さらには共働きをしなければな
らないという社会的状況が変わってきたためです。
オーストラリアでは、週3回の幼稚園があちこちにあります。
アメリカでは、4歳から子どもを、小学校内部のプレスクールで預かりますが、指導は、
きわめてゆったりとしたものです。
どうか日本の基準だけをみて、「幼児教育とはこういうもの」と考えないでください。
また現在の状況をみて、「小学校へ入ってから、心配」というのは、少し酷というものです。
もう少しおおらかに考えてあげてください。
先にも書いたように、この際、不登園はあきらめる。
子どもの心の回復を第一に考えて行動します。
●学校カルト
「幼稚園など、適当に行けばいいのです」と書くと、幼稚園の園長に叱られそうですが、
そういうおおらかさが必要な子どももいるのも事実です。
同じ集団教育でも、子どもによって受け取り方がちがうということです。
Mさんの子どもも、その1人です。
ですから、適当に休み、適当に様子を見て、子どもをゆとりのある目でながめてあげて
ください。
Mさんが、カリカリ、ギスギスしても、かえって逆効果です。
「幼稚園とは行かねばならないところ」「学校とは行かねばならないところ」と、もしあな
たが考えているなら、そのあたりの(学校神話)(学校カルト)を、ゆるめます。
一方で、そうした信仰は、子どもの心を圧迫します。
●母子分離不安
母子分離不安については、何らかの精神心的ショックが原因で起こります。
迷子、母親の入院、家庭騒動などなど。
が、これは過去の話。
基本的には、先にも書いたように、(心の緊張感)をほぐすことができない。
そこへ心配や不安が入り込んでくると、それを解消しようと、心の状態が一気に不安定に
なる。
グズグズしたり、ネチネチしたり、ベタベタしたりする。
で、そういうときは、(1)突き放すのではなく、(2)子どもの求めに、そのまま応じ
てあげます。
無理に引き離せば、いったんは症状が消えたかのように見えますが、(なおった)わけでは
ありません。
私は(潜る)という言葉を使っています。
症状はいったん、潜るだけです。
また同じような状況になったとき、同じような症状が出てきます。
しかし年齢的には、分離不安であれば、自立期に入っていますので、月ごとに症状は緩
和してきます。
自信を失っているようであれば、励まし、自信をもたせてあげます。
また食生活でも、情緒的に不安定な症状がつづけば、(1)白砂糖断ちをする。(甘い食品、
アイス、ジュース類、ジャンクフードを避ける)、(2)Mg、K、Caの多い食生活に心がけ
る(海産物を中心とした食生活にする)、(3)リン酸食品を避ける(インスタント食品類)
の3つに、心がけてみてください。
カルシウムを多くしただけで、子どもの情緒はみちがえるほど、安定してきます。
一度試してみてください。
●明るく、さわやかに
とにかく、今は、あまり深刻に考えないこと。
悪い面ばかりみて、取り越し苦労をすればするほど、あなたの(心配)は、そのまま子ど
もに伝わってしまいます。
心配そうに、あなたが、「幼稚園へは行きたくなかったら、行かなくてもいいよ」と言うの
ではなく、明るく、さわやかに、「お母さんと、今日は幼稚園をサボって、動物園へ行こう
か?」と話しかけてみます。
そうしたおおらかさが、子どもの心に、風穴をあけます。
どうして(子どもといっしょにいるという至極の時)を、粗末にしてしまうのでしょう
か。
今だけですよ。
楽しいのは!
小学3、4年生にもなると、子どもは、親離れをしていきます。
その時期は、あっという間にやってきます。
今の私なら、子どもたちを幼稚園など行かせないで、毎日、いっしょに遊びます。
(私の二男が、そういう教育方針をもっているようです。
HPを飾っている写真が、その孫たちです。)
とにかく今は、無理をしないこと。
泣いていやがる子どもを、無理に幼稚園へ引っ張っていくなどという行為は、少し乱暴す
ぎます。
1時間でも2時間でも、時間をかけて、ゆっくりと説得します。
根気との勝負と心得てください。
子どもの心を休めることだけを考えて、対処してください。
それができれば、不登園の問題は、(結果)として、解決します。
繰り返しますが、よくある問題で、それがトラウマになって……というような、深刻な問
題ではありません。
Mさん自身が、肩の力を抜いて、もっと子育てを楽しんでみてください。
あなたが楽しめば、子どもも楽しむようになります。
これは幼児教育のコツでもあります。
私も、みなさんの子どもを教えるときは、(教えよう)などという気持ちは捨てて、子ど
もたちといっしょに、楽しむつもりで教えています。
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
の「公開教室」をまた見てください。
子どもといっしょに見てくだされば、うれしいです。
では、今日は、これで失礼します。
メールの掲載許可に、感謝します。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 不登園 母子分離 分離不安 分離不安)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【ズル賢い人】
++++++++++++++
ズル賢い人は、多い。
小ズルイというか、一事が万事。
万事が一事。
ズルいという点で、あらゆることに
つながっている。
一貫性がある。
ズル賢い人は、意識的にそれをするという
というよりは、ごく自然な形で、それをする。
ズル賢く生きることが、その人の生き様に
なっている。
その手口を並べてみた。
++++++++++++++
●同情したフリして悪口を言う
「あの人はかわいそうですね。今度息子さんが事件を起こして、高校を退学に
なりました」などと、さも同情しているようなフリをして、その人の悪口を言いふらす。
ときに涙声になることもあるが、もちろん本物の涙は、一滴も出ない。
「本当は言いたくないのですが……」とか、「私はどちらでもいいと思っているので
すが……」とかいうような言い方も、よくする。
●小悪をバラして大悪を隠す
「こんなものが落ちていました」といって、どうでもよいようなものを届け出て、
その一方で、価値あるものを、自分のものにしたりする。あるいはささいな
失敗を告白して、さも自分は正直ということを、相手に売り込んだりする。
あらかじめ価値のないことを承知の上で、「こんなものがありました。価値を
調べていただけませんか」などと、どうでもよいようなものを、相手に渡すことも
ある。
●間に入って、たがいをモマす(トラブルを増幅させる)
「あの人がこう言っていましたよ」と、告げ口をしながら、あなたとその人の間に
トラブルを起こす。モメゴトを大きくする。そして自分は一歩退いたところから、
それを楽しむ。
●他人の目を気にして善行を見せびらかす
行為がわざとらしく、演技ぽい。不自然。病気の人を見舞ったりしながら、ことさら
おおげさに看病してみせるなど。「私はよくできた人間です」というような演技が
うまい。看病をしながら、「私は、近所の老人宅を回って、世話をしてあげているので
すよ」などと言ったりする。年季が入っているため、ふつうの人には、それが見抜けな
い。
●軽い会話に混ぜて承諾を得る
ペラペラと軽い会話をしながら、その間に、重要な会話を混ぜる。あとになって、
「あなたはOKと言ったはず」と、それを根拠にして、ものをいう。全体に口が
うまい。お世辞、へつらいもうまい。
●拡大解釈、縮小解釈がうまい
相手が言ったことを適当に拡大解釈したり、縮小解釈したりするのが、うまい。
つまり自分のよいように、相手の言葉を解釈し、相手に抗議されないようにする。
軽い気持ちで、「いいよ」などと言おうものなら、それをどんどんと拡大解釈して
しまう。
●その場だけをうまく言い逃れる
「1週間だけお願いします」などと最初は言ったりする。で、その1週間が過ぎる
ころになると、事情が少し変わったことなどを理由にして、そのままの状態を
つづける。約束は守らない。もちろん自分の言った言葉に、責任を取らない。
●トボけてその場をごまかす
自分に都合の悪いことがあると、最後はとぼけてすます。忘れたフリ、聞かなかった
フリをするのもうまい。さらに追及したりすると、ギャーギャーと泣き叫んだりして、
その場をごまかす。何かまずいことがあると、とりつくろい、ウソ、弁解を平気でする。
●言いにくいことは他人に言わす
相手に相槌を打たせて、今度はその人の言ったこととして、ほかの人に話を伝える。
「〜〜さんが、こう言っていましたよ」とか、など。だからこのタイプの人には、
安易に相槌を打ってはいけない。あなたが「私も、そう思います」などとでも言おう
ものなら、今度はそれを、あなたの言った言葉として他人に伝えてしまう。
●苦労話をしながら恩を着せる
「〜〜してやった」「〜〜で苦労した」と言いながら、相手に恩を着せる。「私は、
〜〜のことで、どれだけ苦労したかわからない」というような言い方をする。
自分の子どもに対しては、「産んでやった」「育ててやった」を、決まり文句にする。
会ったとたん、「あなたの家のゴミが、近所に散らかっていたので、掃除をしておきました」など
と言ったりする。
と言ったりする。
●他人をほめて相手に要求する
「義弟はすばらしい。毎年、年末になると、〜〜を送ってきてくれる」と言いながら、
言外で、相手に同じことをするよう要求したりする。このばあいも、義弟をほめる
という手段を使いながら、自分はそうされるにふさわしい人間であることを、言外に
におわす。「あのMさんは、すばらしい。毎年、冬になると、海産物を送ってくれる」
とかなど。
●先手を打って相手の言葉をつぶす
相手が願っていることを、先に言ってつぶす。「うちは貧乏で、このところ内職も
減りました」と先に言うことで、自分への負担を軽くしようとする。以前、こんな
ことを言った人がいた。みなで飲み食いが終わるころのこと。「悪いが、ビール代だけ
でも、私に払わせてほしい」と。
●事実にまぜてウソをつく
ズル賢い人の常套手段。1、2度、ボランティア活動をしただけなのに、それをもとに、
「毎週のように駆り出されて苦労しています」などと言う。あるいは1度しかして
いないボランティア活動を、角度を変えて、いろいろな話に仕立てる、など。そういう話術にたけ
ている。
ている。
ズル賢い人は、もともと小心で臆病。その上卑怯で、他人の批判、批評を許さない。
いつも人の目を盗んで、こまかい計算を重ねる。
で、こういうズル賢い人が近くにいたら、遠ざかること。
「いろいろな人と仲よくするのはいいこと」と言う人もいるが、ことズル賢い人に関して
言えば、遠ざかったほうがよい。
何かアクションがあっても、相手にしないこと。
反応したとたん、逆に利用されてしまう。
もともと口がうまいから、反感を買うと、今度はあなたの悪口が言いふらされる。
つきあっても、得るものは何もないばかりか、あなた自身も、その毒気に染まってしまう。
つまり人は、善人になるのは、難しい。
しかし悪人になるのは、簡単。
山登りに似ている。
上り坂は苦しいが、下り坂は楽。
私も一時期、そのズル賢い人と、親密につきあったことがある。
が、おかしなもので、そのときはその人が、ズル賢いということがわからない。
が、離れてみて、はじめて、それがわかる。
同時に、そのときの自分も、いかにズル賢かったかがわかる。
だから遠ざかるのがよい。
中には、ズル賢いことを自慢する人もいる。
あるいは自分の妻がズル賢いことを、自慢する夫さえいる。
「うちのカミさんは、値段を値切るのがうまいよ」とか、何とか。
(はやし浩司 ずるい人 ずる賢い人 小ずるい人 ずるい人間 ズルイ人間 ズルい人
ズル賢い 不誠実な人 はやし浩司 不誠実)
(補記)
●なぜ人はズル賢くなるか?
ズル賢い人を傍から観察してみると、第一に哲学のなさを感ずる。
一貫した哲学がない。
「一貫した」というよりは、「哲学の連続性」がない。
ものの考え方が享楽的で、その場その場で、哲学らしきものが、変化する。
もっと言えば、状況、あるいは相手に応じて、生きざまそのものが変化する。
金権教、あるいは親絶対教の信者であったりする。
ある女性(65歳くらい)は、何をどう誤解したか知らないが、私との会話の
中で、思わず、こう口走ったことがある。
「そんなことをしたら、貯金が減ってしまう」と。
たいていは金銭的な欲得感に支配され、その中でますますズル賢くなっていく。
が、それよりも気になるのは、自分で考える脳みそをもっていないこと。
ときに「ハッ」とするようなことを口にするが、たいていはだれかの受け売りに
すぎない。
少しでも自分の脳みそで考える習慣が身についていたら、ズル賢いことを、恥じるはず。
一見、利発だが、心に余裕がなく、小さな世界で動き回っているだけ。
その(狭小さ)が、それを見る者を不愉快にする。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●法事論
+++++++++++++++++++++++
今度、私自身が法事を執り行う立場になって、こんな
ことを知った。
「親の法事をしっかりとする人は、人格者である」という
考え方をする人が、意外と多いということ。
「親の法事もしないようなヤツは、子ども失格だね」と
言った人もいた。
私は、率直に告白するが、仏教式の法事には、意味を
認めない。
私の祖父も父も、墓参りをしたのを見たことがない。
(母は、ほとんど毎日、寺に足しげく通っていたが……。)
祖父や父が、仏壇に向かって、手を合わせている姿さえ、
記憶にない。
そういう私が、どうして、今、法事なのか?
+++++++++++++++++++++++
●法事
宗派にもよる。
寺にもよる。
住職にもよる。
しかし全体としてみると、日本の仏教は、カルト化している。
この問題に決着をつけないかぎり、日本の仏教には、明日はない。
現に若い人たちを中心に、仏教離れが急速に進んでいる。
法事にしても、おそらく、我が家に関していえば、私の代で最後になる。
長男はしないだろうし、二男は、クリスチャン。
三男は遠くに住んでいるし、考え方もちがう。
私の教育が悪かったのか。
3人とも、先祖の墓参りをしたことなど、数えるほどもない。
一方、私もワイフも、息子たちには、何も期待していない。
一応仏教徒ということになっているが、法事をしてくれなくても、一向に気にしない。
遺骨にしても、散骨でも何でもよい。
気が向いたときに、気が向いたように処分してくれればよい。
むしろ「法事など、するな」と遺言を残している。
「そんなヒマがあるなら、自分を磨け!」と。
●人それぞれ
信仰は教えに従ってするもの。
先にも書いたが、その(教え)をきちんとしている宗派もある。
寺もある。
住職もいる。
しかし今は、そのほとんどが儀式化し、宗教そのものが形骸化している。
本来、人々の魂の救済が目的である信仰が、金儲けの道具として利用されている。
それがだれの目にも、わかるようになっている。
で、その反動というわけでもないだろうが、おかしな占星術や、占い、カルトが
勢力を伸ばしている。
スピリチュアル(霊)・ブームもそのひとつ。
人々が、もともと救いにならないものを救いと思い込んで、右往左往している。
こうした愚劣な社会現象を引き起こしているのも、宗教、なかんずく仏教の責任と
考えてよい。
先頭に立って、そうした社会現象と戦うべき宗教が、だんまりを決め込んでいる。
で、私はある高校生(高1女子)に、こう聞いてみた。
「仏教をどう思うか?」と。
するとその高校生(女子)は、こう言った。
「仏教というと、古臭い感じがする」と。
今、古美術が、ボトム(最悪)状態にある。
古銭、古切手、古物が、二束三文どころか、むしろ引き取り料を請求されるほど、
売買が低迷している。
私の印象では、仏教も、同じ(流れ)の中にある。
現在は、その過渡期ということになるが、そのあとのことは、私にもわからない。
再び仏教ブームが来るのか。
それとも仏教は、このまま衰退していくのか。
しかしこれだけは言える。
それを大切な行事と思っている人は、それを大切にすればよい。
人、それぞれ。
私は干渉しない。
が、世の中には、そうした行事に意味を感じない人もいる。
いるが、だからといって、そういう人を、批判したり、「おかしい」という
レッテルを張るのは、やめてほしい。
自分の頭で考えて、そう言うのならまだしも、そうでないなら、やめてほしい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 B
W はやし浩司 日本の仏教 法事)
W はやし浩司 日本の仏教 法事)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●9月15日
●民主党政権(Our Next Cabinet of Japan)
「民主党の勝ちすぎ」という意見が、ネットをにぎわしている。
その一方で、AS首相(現在、まだ首相)が、「就任直後に選挙をしていたら、こんな
ベタ負けはしていなかったはず」と、おかしなことを言っている。
自民党がここまでベタまけしたのは、AS首相、彼自身に原因がある。
「AS首相だけには、勝たせたくない」という民衆の思いが、民主党の大勝利への
原動力となった。
で、たしかに民主党の勝ちすぎ。
その反動はやがて現れてくるはず。
現在、民主党は、HT代表が「代表」なのか、OZ氏が「代表」なのか、よくわからない。
「権力の二重構造」という言葉が、よく使われる。
HT代表は、OZ氏に対してだけは、敬語を使っている。
何か、おかしい?
●今、「反米」は、たいへんまずい!(Why now "Anti-US Policy"?)
I can understand the Minsyu-Party (Democratic Party) dislikes USA, but why now
"Anti-USA Foreign Policy"? We need USA and we do not need China for our safeties of
Japan. We don't have to open the back-door for a big lion, which wants to go away from
Japan now. Or why do we dare to do so now?)
民主党政権は、かねてより、「対米追従外交」に強く反対している。
首相顧問になった、TJ氏(私の三井物産時代の同僚)も、たびたび「対米追従外交」に
反対の論文を発表している。
しかし、今は、ま・ず・い!
親アジア、新中国も結構だが、まだそこまで時期が熟していない。
同時に、今、日本がアメリカに見放されたら、この先日本はどうやって国際外交を
展開していくつもりなのか。
すでにボスワースは、かねての予想通り、米朝直接交渉に動き出している。
もし米朝間で、「友好条約」(名称は何でも構わない)のようなものが結ばれたら、
日本はそのときこそ、万事休す。
日本は単独で、あのK国と対峙しなければならない。
アメリカの軍事力という後ろ盾を失う。
すでにK国は、中国を介して、戦後補償費を日本に打診してきている。
その額、驚くことなかれ、100兆円!
「払え! さもなければ戦争!」と、K国はしかけてくるはず。
そのとき日本は、どうするのか?
あえて日本側から、「反米」を唱えなくても、すでにアメリカは、日本を見捨てている。
こちらが「あなたが好きではありません」と言う前に、相手は、日本を見捨てている。
だったら、なぜ今、あえて火に油を注ぐようなことをするのか?
逃げようとしているライオンに、どうして裏門を開けてやるようなことをするのか?
鳩山外交の道筋がまだ見えてこないが、ここは慎重に!
「対米追従外交反対」を唱えるのは、K国が崩壊したあと。
今日本にとって重要なことは、ただの一発でも、K国のミサイルを、日本に
落とさせないこと。
もしそれでも「対米追従外交反対」を唱えるなら、日本中に、核シヘルターを用意し、
日本の子どもたち全員に防毒マスクを用意してからにしたらよい。
今の日本は、丸裸以上に丸裸。
鉄道や道路を使って、戦車や大砲の移動もままならない。
仮に一発でも、東京の中心に、ミサイル(核、生物、化学)が落とされたら、それだけで
日本の経済は、奈落の底へと叩き落とされる。
勇ましい好戦論にまどわされてはいけない。
政治、なかんずく国際政治は、(現実)が基本。
現実だけを見て、考える。
「卑怯だ」「おく病だ」と言われても、気にしてはいけない。
とくに戦争は、始めるのは簡単。
終えるのは、その100倍も、むずかしい。
今のイラク、アフガニスタンを見れば、それがわかるはず。
「反米親中」も結構だが、何も今、あえて「反米」を唱えなければならない理由は、
どこにもない!
頭を冷やせ、民主党!
頭を冷やせ、TJ氏!
私のことを覚えているか?
あなたは私のうしろの席にいて、よくいっしょに社内の英会話研修に通った。
あのときの「林」が、私だ。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●古里
++++++++++++++++++
古里と決別して、2週間が過ぎた。
心静かな日。
穏やかな日。
今は、記憶という電車に、
ゆらゆらと揺られて
ぼんやりと乗っている。
古里は日に日に遠ざかり、
昔の風景が、窓の外を流れる。
そこに60年という歳月があるはずなのに、
その厚みが、まるでない。
ぼんやりとした、陽炎(かげろう)のよう。
「だれのことだったのか?」
「本当に私のことだったのか?」
父が酒を飲んで暴れたこと。
学校から家に帰るのがいやで、
道草を食いながら、遊んで帰ったこと。
その一方で、祖父に手をつながれ、
夜祭の道を歩いたこと。
川で、みなと、泳いだこと。
そういった思い出が、つながりなく、
窓の外を流れていく。
すべてが終わった。
今ごろはあの家には、私の見知らぬ人が
出入りしているはず。
あの部屋、あの土間、あの階段。
父もいない。
母もいない。
祖父母もいない。
みんな、そのときは懸命に生きていた。
日々に新しいドラマを作り、
しゃべったり、笑ったりしながら生きていた。
それが、あとへあとへと、
どんどんと消えていく。
闇の中へと、どんどんと消えていく。
さみしい?
切ない?
しかしそれ以上に、私は今、解放感に
浸っている。
「家」から解放された、解放感。
心の鎖がはずされた、解放感。
そう、この軽快感。
いったい、あの家は何だったのか?
みなが懸命に守ろうとしていたものは、
何だったのか?
窓の外には、ぼんやりとした景色が
つぎつぎと現れては、また消える。
今はその景色を追いかける気力も弱い。
疲れた体をシートに沈め、
静かに心を休める。
そのうちこの電車も、どこかの駅に
着くだろう。
着いたら、そこで降りて、
またゆっくりと考えよう。
++++++++++++++++++
【思い込み論】
●200本のヒット数
アメリカのイチローが、9年連続で、200本のヒット数を記録したという。
その瞬間、試合を見ていた人たちは、総立ちになって、イチローを祝福したという。
「すばらしい」と書きたいが、ふと意地悪な心が顔を出す。
これは何も野球にかぎらないことだが、「たかが(失礼!)、棒で、ボールを叩いただけ
ではないか?」と。
「ひょっとしたら、私たちは、それをすばらしいことと思い込んでいるだけでは
ないのか?」と。
こんなことを書けば、この日本では、私のほうが袋叩きにある。
それはよくわかっている。
それに私は何も、イチローを批判しているわけではない。
「野球がつまらない」と書いているのでもない。
私自身、イチローのファンである。
先の日米戦では、私も、涙を流してイチローの活躍に感動した。
私が書きたいのは、その先。
つまり「思い込みについて」。
●思い込み
(思い込み)は、どんな世界にもある。
たとえば、「今、私はここに生きている」という(思い)ですら、(思い込み)
でしかない。
この光と分子の織りなす世界で、私は私と思っている。
本当は、私など、どこにもない。
脳みその中を行き交う、無数の信号。
その中で、私は私と思っているだけ。
それがわからなければ、あなた自身の手を見つめてみることだ。
「どうしてこれが私の手なのか?」と。
あなたは爪ひとつ、自分で作ったわけではない。
あなたの意思の命令によって指は動くかもしれないが、その指にしても、
あなたが自分で作ったわけではない。
「私の手」「私の指」と、あなたがそう思い込んでいるだけ。
が、(思い込み)が悪いわけではない。
人は、ものごとを思い込むことによって、それに価値を付加する。
野球にかぎらず、サッカーにしてもそうだ。
たかが(失礼!)、ボールの蹴りあいなのに、選手たちは、そこに命をかける。
観客もかける。
そうしたエネルギーの原点になっているのが、(思い込み)。
その(思い込み)が、人生を楽しくしている。
●たまごっち
こうした(思い込み)のプロセスは、子どもの世界をのぞいてみると、よくわかる。
たとえば1990年の終わりごろ、(たまごっち)というゲームが、大流行した。
小さなゲーム機器で、その中で、子どもたちは夢中になって、電子の生き物(?)を
飼育した。
そんなある日のこと。
1人の女の子(小学生)が、そのゲームをしていた。
で、私がそれを借りて、あちこちをいじっていたら、その生き物(?)が、死んで
しまった(?)。
それを知って、その女の子は、「先生が、殺しちゃったア!」と、大泣きした。
私は「これはゲームだよ」「死んではいないよ」「ごめんね」と何度も言ったが、
最後までその女の子は、私を許してくれなかった。
当時も、そして今も、こうした(思い込み)は、いたるところにある。
子どもの世界だけではない。
おとなの世界にもある。
私たちは、そうした(思い込み)の中で、生きている。
●論理
しかし(思い込み)には、いつもブレーキをかけなければならない。
(思い込み)だけで生きていると、それこそとんでもない世界に迷い込んでしまう。
占星術だの、心霊現象だの、などなど。
「カルト」と呼ばれる、狂信的な宗教団体を例にあげるまでもない。
そのブレーキの働きをするのが、「論理」ということになる。
映画『スタートレック』の中のミスタースポックの説くところの、
「ロジック(論理)」である。
野球を楽しむにしても、サッカーを楽しむにしても、ある(範囲)で楽しむ。
けっして、それをすべてと錯覚してはいけない。
錯覚したとたん、自分を見失う。
先にあげた、たまごっちを殺したと泣き叫んだ女の子も、その1人ということになる。
●世にも不思議な留学記
が、こうした(思い込み)は、いたるところにある。
私たちの仕事にしてもそうだ。
私たちはときとして、大切でないものを、大切なものと思い込んだり、
価値のないものを、価値あるものと思い込んだりする。
それだけですめばまだよい。
その一方で、大切なものを、大切でないと思い込んでしまうかもしれない。
価値のあるものを、価値のないものと思い込んでしまうかもしれない。
それがこわい。
それについて書いたのが、つぎの原稿である。
『世にも不思議な留学記』というのがそれ(中日新聞発表済み)。
(http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page195.html)
++++++++++++++
イソロクはアジアの英雄だった【2】
●自由とは「自らに由る」こと
オ−ストラリアには本物の自由があった。自由とは、「自らに由(よ)る」という意味だ。
こんなことがあった。
夏の暑い日のことだった。ハウスの連中が水合戦をしようということになった。で、一
人、2、3ドルずつ集めた。消防用の水栓をあけると、20ドルの罰金ということになっ
ていた。で、私たちがそのお金を、ハウスの受け付けへもっていくと、窓口の女性は、笑
いながら、黙ってそれを受け取ってくれた。
消防用の水の水圧は、水道の比ではない。まともにくらうと学生でも、体が数メ−トル
は吹っ飛ぶ。私たちはその水合戦を、消防自動車が飛んで来るまで楽しんだ。またこんな
こともあった。
一応ハウスは、女性禁制だった。が、誰もそんなことなど守らない。友人のロスもその
朝、ガ−ルフレンドと一緒だった。そこで私たちは、窓とドアから一斉に彼の部屋に飛び
込み、ベッドごと2人を運び出した。運びだして、ハウスの裏にある公園のまん中まで運
んだ。公園といっても、地平線がはるかかなたに見えるほど、広い。
ロスたちはベッドの上でワーワー叫んでいたが、私たちは無視した。あとで振りかえる
と、2人は互いの体をシーツでくるんで、公園を走っていた。それを見て、私たちは笑っ
た。公園にいた人たちも笑った。そしてロスたちも笑った。風に舞うシーツが、やたらと
白かった。
●「外交官はブタの仕事」
そしてある日。友人の部屋でお茶を飲んでいると、私は外務省からの手紙をみつけた。
許可をもらって読むと、「君を外交官にしたいから、面接に来るように」と。そこで私が「お
めでとう」と言うと、彼はその手紙をそのままごみ箱へポイと捨ててしまった。「ブタの仕
事だ。アメリカやイギリスなら行きたいが、99%の国へは行きたくない」と。彼は「ブ
タ」という言葉を使った。
あの国はもともと移民国家。「外国へ出る」という意識そのものが、日本人のそれとはま
ったくちがっていた。同じ公務の仕事というなら、オーストラリア国内のほうがよい、と
考えていたようだ。また別の日。
フィリッピンからの留学生が来て、こう言った。「君は日本へ帰ったら、軍隊に入るのか」
と。
「今、日本では軍隊はあまり人気がない」と答えると、「イソロク(山本五十六)の、伝統
ある軍隊になぜ入らない」と、やんやの非難。当時のフィリッピンは、マルコス政権下。
軍人になることイコ−ル、出世を意味していた。
マニラ郊外にマカティと呼ばれる特別居住区があった。軍人の場合、下から二階級昇進
するだけで、そのマカティに、家つき、運転手つきの車があてがわれた。またイソロクは、
「白人と対等に戦った最初のアジア人」ということで、アジアの学生の間では英雄だった。
これには驚いたが、事実は事実だ。日本以外のアジアの国々は、欧米各国の植民地になっ
たという暗い歴史がある。
そして私の番。ある日、一番仲のよかった友だちが、私にこう言った。「ヒロシ、もうそ
んなこと言うのはよせ。ここでは、日本人の商社マンは軽蔑されている」と。私はことあ
るごとに、日本へ帰ったら、M物産という会社に入社することになっていると、言ってい
た。ほかに自慢するものがなかった。が、国変われば、当然、価値観もちがう。
私たち戦後生まれの団塊の世代は、就職といえば、迷わず、商社マンや銀行マンの道を
選んだ。それが学生として、最良の道だと信じていた。しかしそういう価値観とて、国策
の中でつくられたものだった。私は、それを思い知らされた。
時、まさしく日本は、高度成長へのまっただ中へと、ばく進していた。
●作られる職業観
私はこの中で、私たちがもっている職業観すら、そのときどきの体制の中で作られる
ということを書きたかった。
軍事国家では、軍人になること。
経済国家では、経済人になること。
が、もちろんだからといって、そうした仕事がつまらないとか、意味がないとか、そんな
ことを書いているのではない。
私たちには、私たちの(思い込み)があった。
その(思い込み)によって、動かされた。
それをわかってもらいたくて、この原稿を抜き出してみた。
●問いかける
こうした(思い込み)と闘うには、つねに、自分に問いかけてみること。
意味のあるもの・ないもの。
価値のあるもの・ないもの、と。
この問いかけが、やがて論理へとつながっていく。
簡単な方法としては、「だから、それがどうしたの?」と問いかけてみるという
方法がある。
レストランで食事をした……だから、それがどうしたの?
電車で旅行をした……だから、それがどうしたの?
前からほしいと思っていたものを買った……だから、それがどうしたの?、と。
私がそれをいちばん強く感じたのは、大学の同窓生たちの会話を聞いたときのこと
だった。
今からもう30年以上も前のことである。
そのときすでに私は今で言う、フリーターをしていた。
A君(A銀行勤務)「君んとこは、35歳で課長か? いいなア」
B君(B銀行勤務)「君んとこは、何歳だ?」
A君「うちは、早くても、40歳にならないと、課長職には就けないよ」
B君「40歳かア……。遅いなア……。君んとこは、都市銀行だからなア」と。
私はその会話を横で聞きながら、「だから、それがどうしたの?」と考えていた。
彼らとて、日本の高度成長経済の中で、踊らされているだけ。
私はそう感じた。
その結果として今の日本があることは認めるが、同時に、その結果として、今の
彼らもある。
A君も、B君も、ともに50歳を過ぎるころには、リストラされ、さらに60歳を
過ぎた今、リストラ先でも、退職期を迎えつつある。
●脳の欠陥
こうした(思い込み)が起きる背景には、脳そのもの中に、欠陥があるためと
考えてよい。
たとえば今、同時に2つの問題が起きたとする。
わかりやすい例としては、(地球温暖化)と(相続問題)の2つを考えてみよう。
こういうとき人は、脳の中で、問題の軽重、大小を的確に判断できない。
より身近な問題を、重く、大きな問題として、とらえてしまう。
またひとつの問題が起きると、それによって脳内ホルモンが脳全体を満たし、
それがほかの問題にまで、影響を与える。
俗にいう『八つ当たり』という現象も、これによって説明される。
このことは、うつ病を患っている人の思考形態を観察してみると、よくわかる。
ささいな問題にこだわり、悶々と悩む。
悩むだけならまだしも、それが思考全般に影響を与える。
もちろんその反対の例もある。
イチローが200本目を打ったと聞いたときは、心も晴れ晴れとする。
気分もよくなり、「今日は、何かいいことが起きそうだ」と思ったりする。
これもつきつめれば、脳の欠陥による現象のひとつとも、考えられなくはない。
そこで問いかけてみる。
「だから、それがどうしたの?」と。
意地悪な見方かもしれないが、それがよきにつけ、悪しきにつけ、私たちを
(思い込み)から守る。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi
林浩司 BW はやし浩司 思い込み こだわり 錯覚)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●9月16日(情報格差)(The Second Industrial Revolution)
++++++++++++++++
昨日、ルーム・ウォーカー(ランナー)を
ネットで注文した。
ネットショップで注文すると、電気店で買うよりも、
1〜2割、安く買うことができる。
在庫があれば、即、配送してくれる。
それが今日中には、届くはず。
今日は、それが楽しみ。
これからは家の中にいて、散歩できる(?)。
++++++++++++++++
●ネット販売の時代
少し古い資料で恐縮だが、5年前ですら、ネットの広告販売高は、年間33%前後の
伸びを見せていた。
(eNネット)は、つぎのように書いている。
『米国におけるネット広告の業界団体Interactive Advertising Bureau (IAB)が、
4月28日発表した統計によると、2004年のインターネット広告販売高は前年比
33%増の96億ドルとなり、ドットコムブーム期の2000年を超える規模となった』と。
昨年(08年)には、この日本でも、デパートやショッピングセンター、商店街での
売上高よりも、ネットを通しての販売高のほうが高くなったと聞いている。
たとえばあの丸井も、ネット販売を始めたが、「2007年3月期の50億円に対して、
2009年3月期は3倍の150億円。今3月期は200億円の計画」という。
数字を見るかぎり、年々、倍々で販売高がふえているのがわかる。
つまりその分だけ、店で直接ものを買う客が減っているということ。
●ネットショップ
私も今回、ネットで、ルーム・ウォーカーを購入してみた。
簡単な登録するだけで、OK。
送料は無料。
値段を比較してみる。
J店内にあるC店(大型電気店)……10万9800円
最近できたK(大型電気店) ……12万9800円
ネット大手の、A・CO …… 9万0800円(+代引手数料など約500円)
値段を見ただけで、もう決まり。
近くの店で買うよりも、4万円近くも安い!
というより、店は、ただの陳列場。
客はそこで商品を見て、試しに使ってみる。
それをネットを通して、注文する。
一方、ネットショップは、店舗を構える必要がない分だけ、商品を安く売ることが
できる。
今ではそうしたネットショップが、都会の中心部にあるのではなく、長野県の山の中に
あったりする。
巨大な倉庫を構え、そこを拠点に、商品をネットで販売している!
●情報格差
そんなわけで、インターネットを使っている人と、使っていない人の間で、
大きな格差が生まれてくる。
インターネットをうまく使っている人は、より多くの情報を手に入れ、ものを買うとき
なども、より安く買うことができる。
一方、そうでない人は、そうでない。
それが(格差)となる。
称して「情報格差」。
今後、この情報格差は、拡大することはあっても、その反対はない。
ということは、これからは、インターネットをしていない高齢者は、ますます不利になる。
「不利」といっても、はっきりと目に見える不利ではないため、ことはやっかい。
「インターネットなど、なければないで、一向に困らない」と豪語する(?)人も
少なくない。
私の年齢以上の人に、そういう人が多い。
で、問題は、こうした高齢者たちを、どうフォローしていくかということ。
インターネットというより、パソコンという文明の利器は、使いこなせるようになるまで
が、たいへん。
その上での、インターネットである。
が、どうしようかと考えたところで、思考停止。
この問題だけは、本人がその気にならないかぎり、どうしようもない。
仮に……ということで、私の義兄(70歳代)たちを思い浮かべてみるが、キーボードを
叩くことにさえ、拒絶反応を示す。
最近も、こんなことがあった。
●「パソコンが動かない!」
ある女性(40歳)から電話がかかってきた。
「パソコンが動かないから、助けてほしい」と。
で、出かけてみると、新しくノートパソコンが、そこにあった。
(その横には、それよりも1、2年古いタイプのデスクトップパソコンが置いてあった。)
両方とも、電源を入れても、なかなか立ちあがらない。
その女性は、「中学生の息子がいじったから、動かなくなった」と言っていたが、
少し調べてみて、私は、絶望感を覚えた。
私「リカバリー(再セットアップ)するしかないです。ディスクはありますか」
女「そんなもの、ありません。もらってきたパソコンですから」
私「……」
女「これでテレビ電話(SKYPE)をしてみたいので、それをできるようにしてほしい」
私「ウィルス対策ソフトの期限が、とっくの昔に切れていますよ」
女「でも、ちゃんとソフトは、入っています」
私「毎年、お金を払って、更新しなければいけませんよ」
女「……」と。
ついでにIEの履歴から、息子氏がどんなところへアクセスしていたかを見てみた。
予想通り、そこにスケベサイトがズラリと並んだ。
私「このパソコンには、ウィルスやスパイボットが、きっと、ぎっしりと入っていますよ」
女「スパイボット?」
私「つまり、ばい菌だらけということです」
女「どうすればいいですか?」
私「だからここまでくると、リカバリーして、ソフトを新しく、インストールしなおす
しかないです」
女「先生、やっていただけますか?」
私「……。時間があれば、できますが、時間がないので、ごめんなさい」と。
あれほど重症のパソコンとなると、満足に使えるようになるまでに、5〜6時間は
かかる。
テレビ電話(SKYPE)などというのは、その後の後。
その女性は、パソコンを、テレビかラジカセのようにしか考えていない。
つまり、お手上げ!
こうした現状がわかればわかるほど、思考停止となってしまう。
●第二の産業革命
で、たった今、ネットで調べてみたら、「商品は、浜松市内現在配送中」と出てきた。
今では、ネットでそこまでわかるようになっている。
そこで宅配会社に電話を入れ、伝票番号を伝えると、「12時前後に配達の予定です」と
教えてくれた。
すごい!
これを第二の産業革命と言わずして、何と言う?
配送状況から、配達予定時刻までわかる。
私たちは人間の歴史に残る革命を、今、こうして目の当たりに、経験している!
2009年9月16日、水曜日。
100年後の人が、このエッセーを読んだら、どう思うだろうか?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 14日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page021.html
●まぐまぐプレミアの購読料は、月額300円です。よろしかったら、お願いします。
********安全は確認しています。どうか安心して、お読みください*****
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●子どもの叱り方(How to give a good scolding to Children)
++++++++++++++++
子どもの叱り方については、たびたび
書いてきた。
本の中でも書いてきたし、雑誌の中でも
書いてきた。
HPの中でも書いてきた。
で、ここでは、その先について書いてみたい。
++++++++++++++++
●なぜ、叱り方が問題になるのか
「子どもの叱り方がわからない」と悩んでいる親は、多い。
懇談会の席などでも、よく話題になる。
で、そのたびに私は、こう思う。
「どうしてそんなことが問題なるのか」と。
で、それについて書く前に、こんなことがある。
20年ほど前に、私が書いた子育て格言集の中に、『子どもは親の芸術品』という
のがある。
親というのは、自分の子どもを、自分自身の芸術品のように考える傾向が強い。
つまり子どもというのは、自分の(作品)というわけである。
こんな失敗をしたことがある。
ある日のこと。
ショッピングセンターの一角にあるレストランで、食事をしていたときのこと。
隣のテーブルに座った子ども(年齢は5歳くらい)が、自分の顔よりも大きな
ソフトクリームを食べていた。
おとなにはふつうの量でも、子どもにはそうでない。
そこで思わず、私はこう言ってしまった。
「そんなにたくさん、食べないほうがいいよ」と。
が、この言葉が、母親を激怒させた。
「いらんこと、言わんでください!」
「あなたの子じゃ、ないでしょ!」と。
私はその場を、平謝りに謝り、何とかやり過ごしたが、以後、そうしたお節介は
しないことにしている。
●なぜ母親は、激怒したか
なぜ、あの母親は、そのとき激怒したか?
私は親切心から、そうアドバイスしただけである。
当時、白砂糖の過剰摂取が、問題になり始めていた。
マウスの実験では、脳水腫を起こすことまでわかっていた。
理由をあれこれ考えてみた。
が、結局は、母親と子どもの間に、(壁)がないことが理由であることに気がついた。
このことは溺愛児と呼ばれる子どもをみると、よくわかる。
(溺愛児についても、たびたび書いてきたので、ここでは省略する。)
子どもを溺愛する親は多い。
とくに母親に多い。
私は勝手に「溺愛ママ」と呼んでいるが、溺愛ママの特徴のひとつに、親子の間に
壁がないことがあげられる。
密着度が高すぎて、親イコール子、子イコール親といった状態になる。
だからこのタイプの母親は、自分の子どもが批判されたり、けなされたりすると、
それに対して猛烈に反発する。
あたかも自分が批判されたり、けなされたかのように、激怒することも珍しくない。
子どもどうしの喧嘩でも、中へ割って入ってきたりする。
溺愛ママは別としても、日本人は、欧米人に比べて、親子の密着度が高い。
とくに母親と子どもの密着度が高い。
こうした日本人に対して、アメリカ人の親のばあい、「子どもは、神からの授かりもの」
という考え方をする。
つまり子どもから一歩退いて、子どもを見る。
そういう見方が、自然な形で身についている。
●親子の壁
親子の間に壁がないから、(あるいは密着度が高いから)、親は一歩退いたところで、
自分の子どもを見ることができない。
そのため子どもを叱ることに、自ら、ある種の抵抗感を覚える。
「子どものできが悪いのは、私の責任」と。
だから当然叱るべき場面になっても、自分でその責任をしょいこんでしまう。
こうした意識が、「子どもの叱り方がわからない」「どう叱ればいいのか」という
問題に、つながっていく。
●では、どうすればよいか
子どもの叱り方で悩んだら、まず、あなた自身が、自分の子どもをどう見ているかを
判断する。
先にも書いたように、密着度が高ければ高いほど、子どもを客観的に見ることができない。
それが(悩み)につながっている。
そういうケースは、たいへん、多い。
さらにこの問題は、日本人独特の民族性とも、深くからんでいるため、解決は容易で
ない。
子どもを(自分のモノ)と考える。
1人の独立した人間というよりは、モノと考える。
少なくとも欧米人と比べると、その傾向は強い。
その上さらに、日本人のばあい、父親の存在感が薄い。
その分だけ、母親の影響力が強い。
これらのことが、親子、とくに母子の密着度を高くする。
それが(叱り方)をむずかしくする。
が、反対に、子どもから一歩退いてみたらどうだろうか。
子どもの見方が一変するのみならず、叱り方の問題は、自然に解決する。
できれば、自分の子どもであっても、1人の独立した人間として見る。
それができれば、あとは自然体。
そして親は、人生のよき先輩として、また子どものよき友として、子どもを
励まし、ほめ、ときには叱る。
●補記
ついでに言うなら、(子どもを叱る)ためには、親側の方に、それなりの哲学
や倫理観がなければならない。
親が信号無視や駐車違反を平気でしながら、子どもに向かって、(叱る)は、ない。
が、むずかしいことではない。
親は、常にルールを守る。
約束を守る。
ウソをつかない。
この3つだけを、かたくなに守ればよい。
その積み重ねが、その親の人格を作る。
その人格がしっかりとしてくれば、親は、自然な形で、またそれほど考えることなく、
子どもを叱ることができるようになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hirosh
i Hayashi 林浩司 BW はやし浩司 子どもの叱り方 子供の叱り方 叱る方
法 はやし浩司 叱り方の基本 子供の叱り方について 子供をどう叱るか)
(追記)
要するに、自分が、叱られるべきようなことを多々しておきながら、子どもを
叱ろうというのは、ムシがよすぎるということ。
先にも書いたように、信号無視、駐車違反、運転中の携帯電話を平気でしておきながら、
子どもに向かって、「約束を守りなさい」「ルールを守りなさい」は、ないということ。
私の知人(女性、現在60歳くらい)に、こんな人がいる。
口がうまく、ウソばかりついている。
一事が万事、万事が一事。
ひとつのウソがバレそうになると、つぎのウソで塗りかためる。
あるいはバレると、とぼける。
その場だけの言い逃れをして、あとそれを既成事実化してしまう。
結果、どうなったかだが、家庭教育はメチャメチャ。
2人の息子がいたが、2人とも、よき家庭づくりに失敗し、今はどこに住んでいる
かさえもわからないという。
その女性だが、私が知るかぎり、子どもたちがまだ小さいころは、ガミガミ言って
ばかりいた。
つまり叱ってばかりいた。
が、2人の息子の方は、そういう母親を裏から見抜いていた。
ユングのシャドウ論を借りるまでもない。
その結果が、「今」ということになる。
親であることには、それなりのきびしさが伴う。
その(きびしさ)を乗り越えるのも、親の務めということになる。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●ショッピングセンターで
ワイフと散歩をしながら、ショッピングセンターへ行ってきた。
その電気店に、ランニングマシン(ルームランナー)が置いてあった。
試してみた。
時間、もしくは距離をインプットすると、それを表示しながら、床が回転する。
それに合わせて、歩いたり、ランニングしたりする。
値段は、6万円弱。
買うか、買わないか、迷った。
このところ紫外線を避けるため、散歩は、日没後と決めている。
しかしそのマシンがあれば、いつでも運動ができる。
で、ふと見ると、そのマシンの前に、こんな宣伝文句が張ってあった。
「リハビリに最適」と。
それを読んで、私はこう考えた。
「リハビリが必要になったら買った方が得なのか、それともそうならないよう、
予防のために買った方が得なのか」と。
たとえば事故や病気などで、リハビリが必要になったとする。
そのときこうしたマシンは、役に立つ。
それはわかる。
しかし同時に、同じマシンを使えば、健康を増進でき、その類の病気になるのを
未然に防ぐことができるかもしれない。
だから「どちらが得か」と。
・・・そのときのこと。
私の頭の中に、今まで考えたことがないことが、思い浮かんだ。
(そこに見える危機)と、(そこに見えない危機)というのが、それ。
「リハビリに最適」という文句は、(そこに見える危機)を言ったもの。
しかし私だっていつ、そのリハビリを必要とする体になるかもしれない。
そうしたマシンを否応なしに、買わなければならない立場になるかもしれない。
今はかろうじて健康だから、それ、つまり(リハビリをするという危機)が見えないだけ。
つまりそれが、(そこに見えない危機)ということになる。
少し長い前置きになったが、(そこに見える危機)と、(そこに見えない危機)に
ついて書いてみたい。
うまく自分の考えをまとめられるかどうか、自信はないが、書いてみる。
●そこに見える危機
+++++++++++++++++
何か不幸なできごとが起きたとする。
事故、病気、災難、何でもよい。
すると人は、そこを起点にものを考え始める。
しかしその不幸なできごとが、本来なら
起こったであろう、さらに大きくて、
不幸なできごとを防いでくれたかも
しれない。
禅問答のような話だが、未来はいつも、
その起点を基準に、プラスの方向か、
マイナスの方向のどちらかに向かう。
確率論的には、50%vs50%とみる。
つまり「フィフティ・フィフティ」。
たとえばあなたの息子が、学校へでかける
とき、玄関先で足をすべらせ、転倒したとする。
足の骨を骨折したとする。
するとあなたは息子の不注意をなじり、
学校へ行けなくなったことを、叱るかも
しれない。
しかしもしそのとき、いつものように
学校へでかけていたら、途中で、交通事故に
あって、障害が残るような大きなけがを
していたかもしれない。
そう考えれば、玄関先で転倒したことは、
むしろ幸運なできごとだったということになる。
するとあなたは、こう反論するかもしれない。
交通事故にあう確率は、ぐんと小さい。
そんなありえない話を前提に、玄関先で
転倒したことを幸運だったと思えと言われても、
それはできない、と。
++++++++++++++++++++
●そこに見える危機
私たちは常に、(そこに見える危機)と、(そこに見えない危機)の間で生きている。
(そこに見える危機)というのは、たいていはすでに起きた危機と考えてよい。
先の例で言うなら、息子が玄関先で転倒したような事故をいう。
が、もしそのとき、息子がいつもの時刻どおりに目をさましていたら、その事故は
起きなかったかもしれない。
たまたまその朝は、寝坊をしてしまった。
そのままでは遅刻してしまう。
そこで息子はあわてて玄関を飛び出した。
転倒した。
つまりすでに事故は、息子が寝坊をした段階で、(そこに見える危機)に向かって、
まっしぐらに進んでいたということになる。
が、そのときは、それがわからない。
つまりまだ(そこに見えない危機)だったということになる。
●健康論
このことは、健康論についても言える。
つぎのような例は、多い。
胃の調子が悪いと思って、たまたま病院で検査をしてもらったら、まったく
別のところに悪性腫瘍が見つかった、など。
このばあいは、胃の調子が悪いというのは、(そこに見える危機)ということになる。
が、そのときは、別のところに悪性腫瘍があるなどとは思っていない。
それが(そこに見えない危機)ということになる。
もっともこのばあいも、いつも(そこに見えない危機)があるわけではない。
たいていは胃薬を処方してもらい、それで胃の調子は、もとにもどる。
悪性腫瘍が見つかる・・・というより、悪性腫瘍がある確率は、ぐんと低い。
つまり(そこに見える危機)の向こうに、いつも(そこに見えない危機)が
潜んでいるわけではない。
●賢人と愚人
(そこに見える危機)と、(そこに見えない危機)。
賢者は、いつも(そこに見える危機)の向こうに、(そこに見えない危機)があること
を知る。
愚者は、(そこに見えない危機)が、(そこに見える危機)になってから、あわてふた
めく。
たとえば「今」というこのとき、あなたの身のまわりを静かに観察してみよう。
一見、平和でなにごともなく過ぎていく毎日だが、よくよく考えれば、身のまわりは、
(そこに見えない危機)だらけということがわかるはず。
それがわかると、(今の状態)が、きわめて恵まれた状況であることがわかってくる。
もう少し具体的に考えてみよう。
●二番底、三番底
子どもが非行化するときというのは、きわめて短時間でそうなる。
たとえばある夜、あなたの娘が、門限を破って、夜遅く帰宅したとする。
それが(そこに見える危機)ということになる。
そこであなたは娘を叱る。
「二度と門限を破ってはいけない」と強く、諭(さと)す。
が、その向こうには、(そこに見えない危機)が待ち受けている。
つぎにあなたの娘は、門限を破ったとき、叱られるのがいやで、そのまま外泊
してしまうかもしれない。
それが(そこに見えない危機)ということになる。
つまりこうしてあなたの娘は、あっという間に、二番底、三番底へと落ちていく。
(外泊)→(連泊)→(家出)と。
さらに進んで、異性と同棲、子どもの出産と進むかもしれない。
●では、どうするか
大切なことは、いつも(そこに見える危機)を、受け入れていくということ。
受け入れてしまうと、(そこに見えない危機)まで、見えてくるようになる。
冒頭の話について言えば、こうなる。
玄関先で転倒した子どもについて、「あわてて飛びだしたから、転倒した」と。
そしてなぜあわてて飛びだしたかについては、「寝坊をしたから」と。
もし同じような状態で、道路を横切っていたら、交通事故にあっていたかもしれない。
つまりそのとき、(そこに見えない危機)が、見えてくる。
門限を破ったあなたの娘についても、そうだ。
たぶんあなたは、「うちの娘にかぎって」とか、「まさか」と思っているかもしれない。
しかし対処の仕方によっては、最終的には、「家出」ということにもなりかねない。
つまりそこまで、(そこに見えない危機)が見えてくる。
●ランニングマシン
リハビリを必要とするようになってから買うよりも、それ以前から、つまりそうした
病気になる前から、予防のために買う方が、得。
そのほうが長く使える。
それに遅かれ早かれ、そういう時期は、やってくる。
70歳かもしれない。
80歳かもしれない。
やがて外の道路を歩くのも、つらくなる。
それがここでいう(そこに見えない危機)ということになる。
が、私は、ショッピングセンターで、ランニングマシンを見たとき、(そこに見えない
危機)を、見ることができた。
つまりこの段階で、(そこに見えない危機)が、(そこに見える危機)になった。
家に帰ってきてから、私はワイフにこう言った。
「あのマシンを買おう」「どうせ必要になるから」と。
で、ひとつの教訓を得た。
それが先に書いた教訓である。
賢者は、いつも(そこに見える危機)の向こうに、(そこに見えない危機)があること
を知る。
愚者は、(そこに見えない危機)が、(そこに見える危機)になってから、あわてふた
めく。
●終わりに
何ともまとまりのない、つまり焦点のボケたエッセーになってしまった。
要するに、私たちは、日常的に、(そこに見えない危機)に囲まれているということ。
そうした危機が、そこにあることを忘れてはいけないということ。
その上で、今、(そこに見える危機)を、見直してみるということ。
あるいは(そこに見えない危機)を基準に、現在の(そこに見える危機)を考える。
賢く生きるための、これはひとつの原則ではないだろうか。
Hiroshi Hayashi++++++++SEP.09+++++++++はやし浩司
●危機感vs道徳の完成度
+++++++++++++++
巨大な危機が人類というより、
地球全体を襲いつつある。
そうした危機に直面したとき、
それがあまりにも巨大すぎるためか、
危機感そのものがわいてこない。
どうしてだろう?
+++++++++++++++
●海面上昇
まず、つぎの毎日JPのニュースを読んでみてほしい。
この記事を読んで、あなたはそこにある危機を、どの程度強く感じ取ることが
できるだろうか。
『WWF:今世紀末、1メートル超の海面上昇 北極圏、温暖化で……報告書
北極圏での温暖化の影響で、今世紀末には1メートルを超える海面上昇が起こるとの報告
書を、環境保護団体の世界自然保護基金(WWF)がまとめた。「気候変動に関する政府間
パネル(IPCC)」が07年に予測した18〜59センチの海面上昇を大きく上回る。グ
リーンランドなどの氷床や各地の氷河の減少が、世界的な影響を及ぼすと分析している。
報告書によると、北極圏の気温は過去20年で、世界平均の2倍のペースで上昇し、氷
床や氷河の消失を招いた。また、永久凍土が溶けることにより温室効果ガスのメタンの放
出に拍車がかかり、温暖化を促進させているとしている』(09年9月13日)。
要点をまとめると、こうなる。
(1)IPCCは、今世紀末(2100年ごろ)には、海面上昇は、18〜59センチと
予想していた。
(2)しかしWWFがまとめた報告書によれば、1メートル近くになるという。
(3)北極圏の気温上昇は、世界平均の2倍のペースで上昇しつづけている、と。
韓国の海運業者(?)は、さっそく北極海経由の韓国→ドイツ航路を開始した。
インド洋→アフリカ経由の航路より、はるかに短時間で物資を輸送できる。
●危機感の喪失
もし海面が1メートルも上昇すれば、東京都全体が水没することになる。
この浜松市にしても、中心街の大半が、水没することになる。
「北極や南極の氷が溶けてしまえば、海面上昇は止まる」と考えている人も
いるかもしれない。
しかし海面上昇は、その後もつづく。
気温上昇によって、海水が膨張するからである。
海面上昇は、氷が溶けることによってではなく、海水の膨張によって起こる。
また「1メートルくらいなら、何とかなる」と考えてはいけない。
下水管などの生活インフラは、そのまま役に立たなくなってしまう。
台風などの高潮時には、さらに大きな被害が出るようになる。
それに、ここが重要だが、仮に予定通り排出ガスが規制されたとしても、
それで気温上昇(地球温暖化)が止まるわけではない。
仮に今世紀末は、何とかなっても、2200年には、どうなっているか
わからない。
不測の事態が、さらに不測の事態を引き起こし、二次曲線的に気温が上昇
するということも考えられている。
もしそうなれば、この地球の気温は、100年(たった100年だぞ!)を
待たずして、400度C近くにまで上昇するかもしれない。
もしそうなれば、「地球温暖化」ではなく、「地球火星化」ということになる。
●能力的欠陥
怖ろしいことを書いた。
読者のみなさんを不安にさせたかもしれない。
しかし私がここで書きたいのは、そのとき、ほんの少しでよいから、あなた自身の
心の中をのぞいてみてほしいということ。
あなたは(そこにある危機)を、どの程度深刻に感ずることができただろうか。
が、書いている私でさえ、ある種の不安感は覚えるが、そこまで。
それ以上の深刻さが、生まれてこない。
これはどうしたことなのか?
それとも私にだけ起こる、おかしな現象なのか?
深刻になる前に、「どうしようもない」とあきらめてしまうせいなのか?
つまり人は、そこにある小さな危機には、敏感に反応する。
しかし遠くにある巨大な危機に対しては、鈍感に反応する。
もし(危機の大きさ)(危機への距離感)によって、危機感が変化するとするなら、
それは人の、どういう能力的な欠陥によるものなのか。
またその能力的欠陥を克服するためには、どうしたらよいのか。
つまりこのあたりの能力的欠陥を克服しないかぎり、地球温暖化の問題は、
根本的には解決しない。
「北極海の航路が使えるようになった」と喜んでいる海運業者を、例にあげる
までもない。
さらに言えば、こうした問題に取り組んでいる研究者や、政府関係者にしても、
「形」だけの心配で終わってしまう可能性もある。
「立場上、地球温暖化を問題にしているだけ」と。
●触角
こう考えていくと、危機感の問題は、つまるところその人のもつ触角の長さに
よって決まるということになる。
触角が長ければ長いほど、より遠くにある危機を、自分のものとして実感できる。
そうでなければ、そうでない。
では、触角を長くするためには、どうしたらよいのか。
その前に、触角は長い方がよいのか、それとも短い方がよいのかという問題もある。
しかし道徳論でも、より視野の広い人ほど、道徳の完成度の高い人とみる(コールバーグ)。
それについては、こんな原稿を書いたことがある。
++++++++++++++
【子どもの道徳・道徳の完成度】
●地球温暖化
+++++++++++++
子どもたちほど、地球温暖化の
問題を真剣に考えているという
のは、興味深い。
他方、おとなほど、この問題に
関して言えば、無責任(?)。
「何とかなるさ」という言い方をする
おとな。「だれかが何とかしてくれ
る」とか、「私ひとりが、がんばって
も、どうしようもない」とか。
そんなふうに考えているおとなは、
多い。
+++++++++++++
道徳の完成度は、(1)いかに公正であるか、(2)いかに自分を超えたものであるか、
その2点で判断される(コールバーク)。
いかに公正であるか……相手が知人であるとか友人であるとか、あるいは自分がその立
場にいるとかいないとか、そういうことに関係なく、公正に判断して行動できるかどうか
で、その人の道徳的完成度は決まる。
いかに自分を超えたものであるか……乳幼児が見せる原始的な自己中心性を原点とする
なら、いかにその人の視点が、地球的であり、宇宙的であるかによって、その人の道徳的
完成度は決まる。
たとえばひとつの例で考えてみよう。
あなたはショッピングセンターで働いている。そのとき1人の男性が、万引きをしたと
する。男性は品物をカートではなく、自分のポケットに入れた。あなたはそれを目撃した。
そこであなたはその男性がレジを通さないで外へ出たのを見計らって、その男性に声を
かけた。が、あなたは驚いた。他人だと思っていたが、その男性は、あなたの叔父だった。
こういうケースのばあい、あなたなら、どう判断し、どう行動するだろうか。「叔父だか
ら、そのまま見過ごす」という意見もあるだろう。反対に、「いくら叔父でも、不正は不正
と判断して、事務所までいっしょに来てもらう」という意見もあるだろう。
つまりここであなたの公正さが、試される。「叔父だから、見過ごす」という人は、それ
だけ道徳の完成度が低い人ということになる。
またこんな例で考えてみよう。
今、地球温暖化が問題になっている。その地球温暖化の問題について、いろいろな考え
方がある。コールバークが考えた、「道徳的発達段階」を参考に、考え方をまとめてみた。
(第1段階)……自分だけが助かればばいいとか、自分に被害が及ばなければ、それでい
いと考える。被害が及んだときには、自分は、まっさきに逃げる。
(第2段階)……仕事とか、何か報酬を得られるときだけ、この問題を考える。またその
ときだけ、それらしい意見を発表したりする。
(第3段階)……他人の目を意識し、そういう問題にかかわっていることで、自分の立場
をつくったりする。自分に尊敬の念を集めようとする。
(第4段階)……みなでこの問題を考えることが重要と考え、この問題について、みなで
考えたり、行動しようとしたりする。
(第5段階)……みなの安全と幸福を最優先に考え、そのために犠牲的になって活動する
ことを、いとわない。日夜、そのための活動を繰りかえす。
(第6段階)……地球的規模、宇宙的規模で、この問題を考える。さらに、人類のみなら
ず生物全体のことを念頭において、この問題を考え、その考えに沿って、行動する。
この段階論は、子どもたちの意見を聞いていると、よくわかる。「ぼくには関係ない」と
逃げてしまう子どももいれば、とたん、深刻な顔つきになる子どももいる。さらに興味深
いことは、幼少の子どもほど、真剣にこの問題を考えるということ。
子どもも中学生や高校生になると、「何とかなる」「だれかが何とかしてくれる」という
意見が目立つようになる。つまり道徳の完成度というのは、年齢とかならずしも比例しな
いということ。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
子供の道徳 道徳の完成度 道徳 完成度 はやし浩司 道徳の完成度 コールバーク
道徳完成度 完成度段階説)
Hiroshi Hayashi+++++++++++はやし浩司
●道徳の完成度(2)
+++++++++++++++++++
道徳の完成度は、(1)いかに公正であるか、
(2)いかに自分を超えたものであるか、
その2点で判断される(コールバーク)という。
いかに公正であるか……相手が知人である
とか友人であるとか、あるいは自分がその立場
にいるとかいないとか、そういうことに関係なく、
公正に判断して行動できるかどうかで、その人の
道徳的完成度は決まる。
いかに自分を超えたものであるか……乳幼児
が見せる原始的な自己中心性を原点とするなら、
いかにその人の視点が、地球的であり、宇宙的
であるかによって、その人の道徳的完成度は決
まる。
+++++++++++++++++++
この2日間、「道徳の完成度」について、考えてきた。「言うは易(やす)し」とは、よ
く言う。しかし実際に、どうすれば自己の道徳を完成させるかということになると、これ
はまったく別の問題と考えてよい。
たとえば公正性についても、そのつど心の中で揺れ動く。情に動かされる。相手によっ
て、白を黒と言ってみせたり、黒を白と言ってみせたりする。しかしそれでは、とても公
正性のある人間とは言えない。
またその視野の広さについても、ふと油断すると、身近なささいな問題で、思い悩んだ
り、自分を取り乱したりする。天下国家を論じながら、他方で、近隣の人たちとのトラブ
ルで、醜態をさらけだしたりする。
コールバークの道徳論を、もう一度、おさらいしてみよう。
(1)「時、場所、そして人のいかんにかかわらず、公正に適応されるという原則」
(2)「個人的な欲求や好みを超えて、個人の行為を支配する能力」(引用文献:「発達心理
学」ナツメ社)。
そこで重要なことは、日々の生活の中での心の鍛錬こそが重要、ということになる。常
に公正さを保ち、常に視野を広くもつということ。が、それがむずかしい。ときとして問
題は、向こうから飛びこんでくる。こんな話を聞いた。
よくある嫁―姑(しゅうとめ)戦争だが、嫁の武器は、子ども。「孫がかわいい」「孫に
会いたい」という姑の心を逆手にとって、その嫁は、姑を自分のよいように操っていた。
具体的には、姑のもつ財産をねらっていた。
いつしか姑が、息子夫婦の生活費を援助するようになっていた。嫁の夫(=姑の息子)
の給料だけでは、生活が苦しかった。質素に生活すれば、できなくはなかったが、嫁には、
それができなかった。嫁は、派手好きだった。
そのうち、姑は、孫(=嫁の息子、娘)の学費、教育費まで負担するようになった。し
かし土地などの財産はともかくも、現金となると、いつまでもつづくわけではない。そこ
で姑が、支出を断り始めた。「お金がつづかない」とこぼした。とたん、嫁は、姑と息子と
娘(=姑の孫)が会うのを禁止した。
息子(小4)と娘(小1)は、「おばあちゃんに会いたい」と言った。
嫁は、「会ってはだめ」「電話をしてもだめ」と、自分の子どもにきつく言った。
姑は「孫たちに会いたいから、連れてきてほしい」と、嫁に懇願した。
嫁は間接的ながら、「お金がなかったら、土地を売ってお金をつくってほしい」と迫った。
……という話を書くのが、ここでの目的ではない。こういう話は、あまりにも低レベル
というか、あさましい。できるなら、こういう話は聞きたくない。話題にしたくもない。
が、現実の世界では、こうした問題が、つぎからつぎへと起きてくる。いくら道徳的に高
邁(こうまい)でいようとしても、ふと気がつくと、こうした問題のウズの中に巻き込ま
れてしまう。
言いかえると、道徳の問題は、頭の中だけで論じても、意味はないということ。この私
だって、偉そうなことなら、いくらでも言える。それらしい顔をして、それらしい言葉を
口にしていれば、それでよい。それなりの道徳家に見える。
しかし実際には、中身はガタガタ。私はその嫁とはちがうと思いたいが、それほどちが
わない。そこで繰りかえすが、「日々の生活の中での心の鍛錬こそが重要」ということにな
る。
私たちは常に試される。この瞬間においても、またつぎの瞬間においても、だ。何か大
きな問題が起きれば、なおさら。そういうときこそ、日々の鍛錬が、試される。つまりそ
の人の道徳性は、そういう形で、昇華していくしかない。
(道徳性について、付記)
高邁な道徳性をもったからといって、どうなのか……という問題が残る。たとえばこん
な例で考えてみよう。最近、実際、あった事例である。
あなたは所轄官庁の担当部長である。今度、遠縁にあたる親類の1人が、介護施設を開
設した。あなたは自分の地位を利用して、その親類に、多額の補助金を交付した。その額、
数億円以上。
そのあなたが、ある日、その親類から、高級車の提供をもちかけられた。別荘の提供も
もちかけられた。飲食して帰ろうとすると、みやげを渡された。みやげの中には、現金数
百万円が入っていた。
(お気づきの人もいるかと思うが、これは実際にあった事件である。)
こういうケースのばあい、あなたならどう判断し、どう行動するだろうか?
「私はそういう不正なことは、しません」と、それを断るだろうか。その勇気はあるだ
ろうか。また断ったところで、何か得るものは、あるだろうか。
私はそういう場に立たされたことがないので、ここでは何とも言えない。しかし私なら、
かなり迷うと思う。今の私なら、なおさらそうだ。いまだに道路にサイフが落ちているの
を見かけただけで、迷う。
不運にも(?)、この事件は発覚し、マスコミなどによって報道されるところとなった。
しかしこうした事例は、小さなものまで含めると、その世界では、日常茶飯事。それこ
そ、どこでも起きている。
つまり道徳性の高さで得られるものは、何かということ。それがこの世界では、たいへ
んわかりにくくなっている。へたをすれば、「正直者がバカをみる」ということにもなりか
ねない。
ところで、少し前、中央教育審議会は、道徳の教科化を見送ることにしたという。当然
である。
道徳などというものは、(上)から教えて、教えられるものではない。だいたい道徳を教
える、長の長ですら、あの程度の人物。公平性、ゼロ、普遍性、ゼロ。どうしてそんな人
物が、道徳を口にすることができるのか。
「学習指導要領の見直しを進めている中央教育審議会は、18日、道徳の授業を教科と
しない方針を固めた。政府の教育再生会議は、規範意識の向上を目的に、第二次報告で道
徳を『徳育』としたうえで、教科化するよう求めていた。もともと中教審の内部では、教
科化に慎重な意見も強かったが、安倍首相の辞任後、『教育再生』路線との距離の置き方も、
明確になった格好だ」(中日新聞)とある。
わかりやすく言えば、安倍総理大臣が辞任したこともあり、安倍総理大臣が看板にして
いた徳育教育(?)が、腰砕けしたということ。
閣僚による数々の不祥事。加えて、安倍総理自身も、3億円の脱税問題がもちあがって
きている。「何が、道徳か!」、ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
道徳 道徳教育 徳育 徳育教育 教育再生会議 中央教育審議会)
++++++++++++++++++++
●危機感について
触角の長さというのは、つまるところ、その人の道徳性の完成度と関係がある
ということになる(コールバーグ)。
道徳性の完成度の高い人ほど、触角が長くなり、遠くにある危機をも、そこに
ある危機として認識できる。
そうでなければ、そうでない。
日常のささいな問題に心を奪われ、その先を見ることができない。
加齢とともに、さらにこの傾向は強くなり、やがてそこらのオジチャン、オバチャンへと
変身していく。
そのひとつのバロメーターが、地球温暖化の問題ということになる。
私たちがこの問題に対して、いかに深く危機感をもちうるかによって、その一方で
自分の道徳の完成度を知ることができる。
私のように、「それがあまりにも巨大すぎるためか、危機感そのものがわいてこない」
というようであれば、道徳の完成度はまだまだ低いということになる。
(ついでに、補記)
●実家からの解放
話はぐんと私的になるが、私は60年を経て、やっと「実家」から解放された。
実に重苦しい、60年間だった。
実家を売り飛ばし、家財のほとんどを、近所の人たちに無料で配った。
そのあとのこと。
とたん、毎朝見る、夢の内容まで変わってしまった。
これには驚いた。
それをワイフに話すと、ワイフも驚いた。
私のこうした行為に対して、中には不満に思っている人もいるらしい。
すでにそういう話が、漏れ伝わってきている。
が、私が今感じている爽快感は、何物にも、替えがたい。
で、私はそれまで、(そこにある現実)に、毎日のように惑わされた。
心は地球、人類、教育へと、自由に駆け回るのだが、ふと気がつくと、そこに(実家)
がある。
あまりにも生々しく、毒々しい。
いくら自分では高邁(こうまい)であろうとしても、ふと油断すると、そこにある
(現実)に振り回されてしまう。
あの夏目漱石も、同じようなギャップに悩んだ。
小説『こゝろ』(こころ)が、それである。
最終的には、『こゝろ』の中の先生は、友人Kの自殺の罪悪感を克服することが
できず、明治天皇の崩御、乃木希典の殉死を契機に、自殺を決行する。
もちろん私は自殺などしないが、(実家)から解放されてはじめて、私の人生を
私のものにすることができた。
それはあまりにも生々しく、毒々しい自分との決別できた瞬間でもあった。
実家を、超安値の、破格価格で売り飛ばした。
が、価格など問題ではない。
私はそうすることで、実家そのものを、爆破したかのような爽快感を味わった。
事実、その翌朝、死んだ実兄が夢の中に現れた。
実兄は、私と腕を組みながら、うれしそうに笑っていた。
で、私が、「準ちゃん(=兄)、仇(かたき)は取ってやったぞ」と言うと、
実兄は、さらにうれしそうに笑った。
夢は夢だが、その夢が、私の深層心理にあったすべてを表現している。
●触角を長くするために
触角を長くするためには、いつも心を遠大な、宇宙の果てに置く。
そこにあまりにも生々しく、毒々しい世界があるなら、できるだけ早く、決別する。
自分の心から切り離す。
同時に2つの世界を経験すると、それこそ魂を切り裂かれるような苦痛を覚える。
自分の人格がバラバラになっていくように感じることさえある。
そうでなくても、おかしな緊張感が、じわじわと精神をむしばむ。
これは精神の健康にとっても、よくない。
私のばあいは、実家のことが頭の中を横切るたびに、情緒そのものが不安定になった。
ワイフに八つ当たりしたとことも、多い。
道徳の完成度を論ずるときの、ひとつの参考になれば、うれしい。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●9月13日
++++++++++++++++
ぽっかりとあいた、日曜日。
久しぶりの休日。
だれに会うという約束もない。
とくに予定もない。
昨日は、ワイフと散歩中、突然の
大雨に見舞われた。
そのため近くにあったレストランで、
雨宿り。
私はジュースを3杯も飲んだ。
ワイフは、コーヒーと紅茶を2杯も飲んだ。
久々の雨である。
私の記憶によれば、2か月ぶりの雨?
芝生の種をまいてからの、はじめての雨?
これから先、1日、1日と
秋らしくなっていく。
++++++++++++++++
●新しいHP
現在、新しいHPの開設を考えている。
カラフルで、楽しいものを考えている。
その構想を頭の中で練っているだけで、楽しい。
そうそう昨日、Twitterに登録してみた。
YOU STREAMも試してみた。
FACEBOOKも試してみた。
で、今度は、Twitter。
今のところ、残念ながら、それがどうしておもしろいのか、よくわからない。
現在Twitterを楽しんでいる人は、私をフォローしてみてほしい。
●携帯電話
Twitterのことを書いたので、携帯電話についても書いておかねばならない。
現在、多くの人が、携帯電話でHPを見たり、インターネットを楽しんでいる。
小説まで読んでいる人もいるという(G県のAさん)。
私も携帯端末機をもっているが、使うのは、旅行のときだけ。
それをふつうのパソコンにつなげば、モデムとしても使用できる。
やや不便だが、今のところ、それで満足している。
が、話を聞いていると、結構、おもしろそう。
小さなUSB端末をミニパソコンに装着すると、どこでもインターネットが
楽しめるようになるという。
「やってみたい」という思いは強いが、手を広げすぎるのもよくない。
そのうち収拾がつかなくなる。
(すでに今、収拾がつかなくなってきているが……。)
●WINDOW7が、待ち遠しい
10月下旬に、WINDOW7が、発売になる。
それに合わせて、パソコンメーカー各社から、新製品が発売になる。
楽しみ。
しかし……。
VISTAが発売になったとき、当時としては、最先端をいくパソコンを購入した。
が、今では、ノートパソコンでも、その程度の能力はもっている。
2、3週間前に買った、T社のノートパソコンにしても、そうだ。
がっかりしたというより、この世界の進歩の速さに驚く。
私の物欲エネルギーは、そういうわけで爆発寸前。
(1)WINDOW7搭載、64ビット最先端パソコン。
(2)カラーレザープリンター。
(3)24〜5インチクラスの、大型モニター。
この3つは、どうしてもほしい。
(現在、ワイフをあれこれと説得中!)
●近況
今朝、体重計に乗ってみたら、59・8キロ。
よかった!
(5日前には、62・5キロだった。)
で、昨夜、床に就く前に、猛烈な空腹感を覚えた。
視床下部にある血糖値センサーが、血糖値の低下を感知し、ドーパミンを
大量に放出した。
それが猛烈な空腹感を引き起こした。
さっそくワイフが、「カップヌードルでも食べたら?」と、私を誘惑。
が、それを口にしたら、おしまい。
またまたリバウンド。
「脳みそにだまされないぞ」と自分に言って聞かせて、歯を磨いた。
歯を磨いてしまえば、何も食べられない。
2度も歯を磨くのは、めんどうなこと。
だからそういうときは、先に、歯を磨いてしまう。
窓の外には、水色の空が広がっている。
白い筋雲が美しい。
朝食のあと、自転車で、佐鳴湖を一周してみよう。
……ということで、9月13日も、始まった。
全世界のみなさん、おはようございます!
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●価値観の転換(ライフサイクル論)
+++++++++++++++++
(したいこと)から(すべきこと)へ。
中年期から老年期の転換期における、
最大のテーマが、これ。
ユングは、満40歳前後を、『人生の
正午』と呼んだ。
この年齢を過ぎると、その人の人生は、
円熟期から、統合期へと向かう。
ユングは、『自己実現の過程』と位置
づけている。
それまでの自分を反省し、では自分は
どうあるべきかを模索する。
事実、満40歳を過ぎるころになると、
(したいこと)をしても、そこにある種の
虚しさを覚えるようになる。
「これではいけない」という思いが、より強く
心をふさぐようになる。
同時に老後への不安が増大し、死の影を
直接、肌で感ずるようになる。
青春時代に、「私とは何か」を模索するように、
中年期から老年期への過渡期においては、
「私の使命とは何か」を模索するようになる。
自分の命の位置づけといってもよい。
そして(自分のすべきこと)を発見し、
それに(自分)を一致させていく。
これを「統合性の確立」という。
この統合性の確立に失敗すると、老年期は
あわれで、みじめなものとなる。
死の待合室にいながら、そこを待合室とも
気づかず、悶々と、いつ晴れるともない
心の霧の中で、日々を過ごす。
ただ、中年期、老年期、その間の過渡期に
しても、年齢には個人差がある。
レヴィンソンは、『ライフサイクル論』の
中で、つぎのように区分している
(「ライフサイクルの心理学」講談社)。
45歳〜60歳(中年期)
60歳〜65歳(過渡期)
65歳〜 (老年期)
日本人のばあい、「自分は老人である」と自覚
する年齢は、満75歳前後と言われている。
また満60歳という年齢は、日本では、
定年退職の年齢と重なる。
「退職」と同時に発生する喪失感には、
相当なものがある。
そうした喪失感とも闘わねばならない。
そういう点では、こうした数字には、
あまり意味はない。
あくまでも(あなた)という個人に
あてはめて、ライフサイクルを考える。
が、あえて自分を老人と自覚する必要はないに
しても、統合性への準備は、できるだけ
早い方がよい。
満40歳(人生の正午)から始めるのが
よいとはいうものの、何も40歳にかぎる
ことはない。
恩師のTK先生は、私がやっと30歳を過ぎた
ころ、こう言った。
「林君、もうそろそろライフワークを
始めなさい」と。
「ライフワーク」というのは、自分の死後、
これが(私)と言えるような業績をいう。
「一生の仕事」という意味ではない。
で、私が「先生、まだぼくは30歳になった
ばかりですよ」と反論すると、TK先生は、
「それでも遅いくらいです」と。
で、私はもうすぐ満62歳になる。
「60歳からの人生は、もうけもの」と
考えていたので、2年、もうけたことになる。
が、この2年間にしても、(何かをやりとげた)
という実感が、ほとんど、ない。
知恵や知識にしても、ザルで水をすくうように、
脳みその中から、外へこぼれ落ちていく。
無数の本を読んだはずなのに、それが脳の
中に残っていない。
残っていないばかりか、少し油断すると、
くだらない痴話話に巻き込まれて、
心を無意味に煩(わずら)わす。
統合性の確立など、いまだにその片鱗にさえ
たどりつけない。
今にして、統合性の確立が、いかにむずかしい
ものかを、思い知らされている。
そこで改めて、自分に問う。
「私がすべきことは、何なのか」と。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 ユング 人生の正午 ライフサイクル論 統合性の確立 はやし浩司
老年期の心理
+++++++++++++++++
●計画
満65歳になったら、反カルト教団活動を再開するつもり。
私がもっている(もうひとつの顔)を、公表する。
そして宗教に名を借りて、人の心をもてあそんでいるような教団を、
片っ端から攻撃してやる。
この20年間、静かにしてきたが、もう遠慮はしない。
それまであと3年。
今は、静かにその準備を重ねている。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 12日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page020.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●柔軟性(理性vs欲望)
++++++++++++++++++
子どもの世界では、よく柔軟性が問題になる。
「頭のやわらかい子」「頭のかたい子」というような表現の仕方をする。
頭のやわらかい子どもは、融通性があり、機転がきく。
一方、頭のかたい子どもは、融通性がなく、機転がきかない。
「カタブツ人間」(「心理学用語がわかる本」渋谷昌三)
になると言われている。
頭のやわらかい子どものほうが、よいように思える。
が、柔軟性が強すぎてもよくない。
行動が衝動的になったり、ときに人格そのものが
支離滅裂になる。
+++++++++++++++++++++
●柔軟性
人は常に無意識の世界に支配されながら、考え、行動する。
その無意識の世界を分類すると、(イド)(自我)(超自我)ということに
なる(フロイト学説)。
「イドとは、無意識的、衝動的な側面で、心のエネルギーの貯蔵庫」(同書)。
「自我とは、パーソナリティの中の意識的な側面」(同書)という(以上、フロイト学説)。
つまり人は、イドと自我の間で、バランスを取りながら、自分をコントロールする。
イドが強すぎると、欲望に支配され、享楽的な生き方になる。
自我が強すぎると、融通がきかなくなる。
さらに「超自我」(「一般的に道徳心とか良心とよばれるもの」(同書))が強すぎると、
「柔軟性の欠けたカタブツ人間」(同書)になる。
●思考の柔軟性
子どもの柔軟性(=思考の柔軟性)は、2つに分けられる。
(1)思考の柔軟性
(2)行動の柔軟性
思考の柔軟性は、たとえば、ジョークを話したときなどに判断できる。
思考が柔軟な分だけ、おとなのジョークもよく理解する。
思考が柔軟でない子どもは、「カタブツ」という言葉で表現される。
言葉を額面通り、受け取ってしまう。
たとえばアスペルガー児などは、この思考の柔軟性が極端に失われた状態の
子どもと考えるとわかりやすい。
また行動の柔軟性は、たとえば、「がんこ」という言葉で表現される。
「青いズボンでないと、幼稚園へ行かない」とがんばったりする。
一方、行動に柔軟性のある子どもは、その場、その場で、臨機応変に行動を変える。
「これがだめなら、あれが、だめ。あれもだめなら、それにする」と。
一般的には、思考にせよ、行動にせよ、柔軟性のある子どものほうが、あとあと伸びる。
●自律期
3〜4歳の「自律期」(エリクソン)においては、一時期、子どもは、柔軟性に欠ける
ようになる。
おとなや先生が言ったことを、かたくなに守ろうとする。
この時期をうまくとらえて指導をすると、しつけがうまくいく。
またこの時期の子育てに失敗すると、子どもは、いわゆるドラ息子、ドラ娘になる。
わがままで自分勝手。
享楽的で、ルールを守れないなど。
で、その時期を過ぎると、今度は、「自立期」(エリクソン)へと入ってくる。
この時期に、思考が柔軟な子どもほど、あとあと伸びる。
好奇心が旺盛で、触角が四方八方に向いている。
天衣無縫というか、遊びにしても、自分でつぎからつぎへと発明していく。
反対に、いつも遊びは同じとか、遊び友だちは同じという生活は、子どもには、
好ましくない。
とくに変化の少ない、単調な生活は、子どもの知育の発育の大敵と思うこと。
ほどよい刺激を子どもの周辺に用意するのは、親の務めと考えてよい。
●「超自我」
超自我・・・いわゆる「理性」ということになる。
脳科学の世界では、人間の理性をコントロールするのは、大脳の中でも前頭前野という
ことになっている。
部位的には、額の部分。
額の奥に、前頭前野がある。
この部分が、人の心や行動をコントロールする。
しかし万能かというと、そうでもない。
たとえば思春期になると、子どものもつ性的エネルギー(フロイト)は、きわめて
強力になる。
大脳生理学的には、視床下部あたりの働きが活発になり、ドーパミンの分泌が旺盛に
なる。
ドーパミンというのは、欲望と快楽をつかさどる脳内ホルモンをいう。
こうした働きを、前頭前野だけで、コントロールするのはむずかしい。
むずかしいというより、不可能。
似たような反応に、アルコール中毒症やニコチン中毒症がある。
酒のにおいをかいだり、タバコのコマーシャルを見ただけで、酒を飲みたく
なったり、タバコを吸いたくなったりする。
これは条件反射反応といわれるものだが、意思の力で、それをコントロール
するのは、むずかしい。
●では、どうするか
要するに、(理性=善)と、(欲望=悪)との戦いということになる。
(ただし欲望イコール、悪ではない。念のため。)
こうした戦いは、何も子どもの世界だけの話ではない。
おとなになってからも、つづく。
老齢期になってからも、つづく。
だから子どもの問題として考えるのではなく、あなた自身の問題として考えるのがよい。
その結果、つまり「では自分はどうすればいいか」を考えながら、それを子どもの世界
へと、延長していく。
あるいはあなた自身の青春時代はどうであったかを、みるのもよい。
●精進(しょうじん)
結局は、「精進(しょうじん)」ということになる。
欲望という悪と戦うためには、日々に研鑚あるのみ。
これは健康論と似ている。
健康を維持するためには、日々に運動し、体を鍛錬するしかない。
それを怠ったとたん、健康は下り坂へと向かう。
同じように、日々の研鑚を怠ったとたん、心は欲望の虜(とりこ)となる。
私たちが生きているかぎり、健康に完成論がないのと同じように、理性や道徳に
完成論はない。
ただ幸いなことに、こと性欲に関しては、加齢とともに、弱体化する。
まったくなくなるわけではないが、若いときのように、四六時中・・・ということはない。
また時折泉から湧いてくるメタンガスのようなもので、湧いても、すぐ消える。
あるいは長つづきしない。
私もある時期、性欲から解放されてはじめて、性欲が何であったかを知った。
同時に、あのすがすがしい解放感を、今でも忘れることができない。
●限界
ということで、親として、あるいはおとなとして、子どもに対してできることにも
限界があるということ。
自分という親(=おとな)ですらできないことを、どうして子どもに求めることが
できるのか。
・・・と書くと、何のためのエッセーかということになってしまう。
そこで重要なのが、子どもの「自我の同一性」ということになる。
これについては、もう何度も書いてきた。
要するに、(自分のしたいこと)を、(生き生きと前向きにしている)子どもは、
それだけ心の抵抗力が強いということ。
心にスキがない。
ないから、悪をはねのけてしまう。
つまりそういう方法で、子どもの心を守る。
●私たちの問題
私たち親(おとな)も、また同じ。
理性や道徳の力に限界があるなら、それを補うためにも、(自分のしたいこと)を見つけ、
それに向かって(生き生きとする)。
もしあなたが老齢期にさしかかっているなら、(満40歳以後は老齢期だぞ!)、(自分の
すべきこと)を見つけ、それに向かって(生き生きとする)。
(自分のしたいこと)ではない。
(すべきこと)である。
しかもその(すべきこと)は、無私無欲でなければならない。
これを「統合性の確立」というが、打算や功利が混入したとたん、その統合性は霧散する。
そういう姿を、あなたの子どもが見て、またあなたをまねる。
結局は、それがあなたの子どもを伸ばすということになる。
●柔軟性とは
話が大きく脱線した。
柔軟性について書きたいと思っていた。
が、こんな話になってしまった。
しかし思考の柔軟性には、こんな問題も含まれている。
いくら柔軟性があっても、欲望のおもむくまま振り回されていたのでは、
どうしようもない。
一方、人は、自らが不完全であることを恥じることはない。
その(不完全さ)が、無数のドラマを生み、人生を潤い豊かに、楽しいものにする。
要はバランスの問題ということになる。
あるいはときに応じて、カタブツになったり、反対にハメをはずして遊ぶ。
その限度をわきまえる力が、「柔軟性」ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW イド 自我 超自我 はやし浩司 融通性 子どもの柔軟性 思考
の柔軟性 理性 カタブツ)
Hiroshi Hayashi++++++++SEP.09+++++++++はやし浩司
●山荘
++++++++++++++++++
今夜は、夜中に山荘にやってきた。
日時は、9月11日。
午後11時45分。
あと少しで、9月12日。
少し前、ワイフはチューハイを一缶飲んだ。
そしてそのまま床の中へ。
私は眠いが、こうしてパソコンを相手に、
文章を書いている。
真新しいパソコンで、キーを叩いているだけで、
気持よい。
TOSHIBAのTX66という機種である。
(パソコンのことを、「機種」と言うのかどうか
知らないが・・・。あるいは「型番」というのが、正しいのか?)
画面は16インチもある。
そのため持ち運びには不便だが、ひとたびデスクに
置けば、あとは楽。
ふつうのデスクトップのようにして、使える。
++++++++++++++++++++
●子どものやる気
++++++++++++++++
J君(小4)という、興味深い
子どもがいる。
毎週1時間30分、その子どもの学習を
みている。
が、1時間30分、勉強するわけではない。
最初の10〜20分は、コミック本を
読んで、時間をつぶす。
それから20〜30分は、だらだらと
勉強らしい勉強もせず、無駄話をして
すごす。
こうしてときに1時間あまり、時間を
無駄にしたあと、何かの拍子にふと
気が向くと、突然、勉強を始める。
が、一度始めると、猛烈な勢いで、
今度は「量」をこなす。
もともと頭の切れる子どもである。
あっという間に、計算問題だと、
40〜50問くらいは解いてしまう。
時間にすれば、20〜30分前後だが、
それでふつうの子どもなら、1時間
30分くらいはかかるような量を、
終えてしまう。
そしてそれが終わると、またいつもの
ように、だらだらし始める。
無駄話を始めて、時間をつぶす。
++++++++++++++++
●内発的か、外発的か?
子どものやる気をみるとき、それが内発的(自ら進んでやろうとしている)か、
外発的(親や先生に言われてやろうとしている)かを、みる。
内発的であれば、よし。
そうでなければ、そうでない。
たとえば子どもの学習の3悪に、(1)条件、(2)比較、(3)無理、強制がある。
条件というのは、「〜〜したら、〜〜を買ってやる」式の条件をつけること。
比較というのは、「〜〜さんは、もうカタカナが書けるのよ」と、子どもをほかの子ども
と比較すること。
無理、強制というのは、能力を超えた学習を子どもに押しつけたり、強制的に子どもを
勉強させることをいう。
こうした方法は、一時的には効果があっても、長つづきしない。
しないばかりか、それが日常化すると、子どもは、やる気そのものをなくす。
たとえば冒頭に書いたJ君の例で考えてみよう。
J君は、私の教室(BW教室)へは、小学1年生のときから来ている。
今年で、4年目になる。
当初は、そういうJ君の特性(?)に、戸惑った。
ときには条件をつけたり、あるいは無理に学習に向かわせようとした。
しかし効果はいつも、一時的。
そこである日から、(というのも、ガミガミ言うのは私のやり方ではないので)、
本人のやりたいようにさせることにした。
その結果が、冒頭に書いたようなやり方ということになる。
●特性
それぞれの子どもには、それぞれの特性がある。
勉強という(作業)をこなすときには、その特性が、大きくその子どもを左右する。
たとえば集中力についても、持続的に長時間保てる子どももいれば、そうでない
子どももいる。
極端なまでに集中力の欠ける子どもを、「集中力欠如型〜〜」とかというが、しかし
だからといって、それが問題というわけではない。
最近の調査によれば、チャーチルもモーツアルトも、そしてあのエジソンも、
アインシュタインも、その「集中力欠如型〜〜」(AD・HD児)だったと言われている。
とくにエジソンなどは、ここに書いた、J君とそっくりの特性を示していた。
●天才型
そういうJ君を指導しながら、よく「この子には、これでいいのだ」と、自分に言って
聞かせる。
あるいはときどき、もし父親が、そういうJ君を、この教室で見たら、どのような
判断をするだろうかと考えるときがある。
「怒って、やめてしまうだろうな」と。
幸い母親が理解のある人で、また愛情豊かな人のため、J君をおおらかに見ている。
会うたびに、「迷惑ばかりかけて、すみません」と言ってくれる。
本当は、迷惑と感じたことはない。
ただ私流の指導が思うようにできないため、私流にいらいらしているだけなのかも
しれない。
しかし考えてみれば、私自身にだって、私流の特性がある。
たった今も、この原稿を書いている途中で、ラジコンのヘリコプターの調整のため、
庭へ出て、それを飛ばしてきた。
集中力があるかないかということになれば、・・・というより、特性という点では、
私とJ君は、よく似ている。
若いときから、そうだった。
だらだらと一定の時間を過ごしたあと、仕事をするときは、一気にする。
それが私のやり方だった。
反対に、持続的にコツコツと勉強に取り組む子どもも、多い。
しかし期待するほど、効果はあがらない。
そこそこに勉強はできるようにはなるが、そこで止まってしまう。
「天才型」、あるいは、「才能発揮型」の子どもというのは、多くはJ君のような
特性を示す。
指導する側としては、(指導しにくいタイプ)ということになるが、長い目で見れば、
むしろこのタイプの子どものほうが、好ましいということになる。
●避けたい外発的動機づけ
内発的に子どものやる気を引き出すことを、「内発的動機づけ」という。
(これに対して、条件、比較、無理、強制などにより、外発的に子どものやる気を
引き出すことを、「外発的動機づけ」という。)
外発的動機づけが日常化すると、子どもは、ものごとに対して依存的になりやすい。
言われたことはするが、それ以上のことはしない。
あるいは言われないと、行動できない、など。
とくに条件が日常化すると、条件なしでは勉強しなくなる。
さらにこの条件は、年齢とともに、エスカレートしやすい。
幼児のころは、「30分、勉強したら、お菓子一個」ですむかもしれない。
しかし中学生や、高校生ともなると、そうはいかない。
「学年順位が10番あがったら、10万円」となる。
だから内発的動機ということになる。
子どものやる気を、子どもの内側から自然に引き出す。
そのための方法は、いくらでもある。
またそれを実践していくのが、教育、なかんずく幼児教育ということになる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW やる気 はやし浩司 動機づけ 内発型 外発型 動機づけの3悪
4悪 達成動機)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【家という、監獄】
+++++++++++++++
私の兄は、生涯、「家」という監獄に
閉じ込められた。
みなは、兄のことを、バカだと思っていた。
またそういう前提で、兄を見ていた。
「だから、しかたなかった」と。
しかしこれはまったくの誤解。
兄の感受性は私のそれよりも、鋭かった。
知的能力にしても、少なくとも姉よりは、
ずっと高かった。
そんな兄が、「家」という監獄に閉じ込められた
まま、昨年(08年)、他界した。
そう、兄にとっては、たしかに「家」は
監獄だった。
私にとっても、そうだった。
だから兄の苦しみが、私には、痛いほど、
今、よくわかる。
+++++++++++++++
●兄
みなさんは、「家制度」というものを、知っているだろうか?
知っているといっても、その中身を知っているだろうか?
「家」に縛られる、あの苦しみを知っているだろうか?
恐らく、今の若い人たちは、それを知らないだろう。
理解することもできないだろう。
自由であることが当たり前だし、自由というのは、自分が自由でなく
なったときはじめて、わかる。
それは空気のようなもの。
空気がなくなって、はじめて、そのありがたさがわかる。
自由も、また同じ。
●家制度
「家」に縛られる。
「家」あっての、「私」と考える。
江戸時代の昔には、「家」あっての「私」ということになる。
「家」から離れれば、無宿者(むしゅくもの)と呼ばれた。
街角で見つかれば、そのまま佐渡の金山送りとなった時代もある。
あるいは無頼(ぶらい)とか、風来坊(ふうらいぼう)という言葉もある。
少し意味はちがうが、「家」がなければ、定職につくのも、むずかしかった。
そのため(私)は、「家」を守ることを、何よりも大切にした。
「家」のために(私)が犠牲になることは、当然のことのように考えた。
ずいぶんと乱暴な書き方をしたが、大筋では、まちがっていない。
そういう前置きをした上で、私は、私の兄について書く。
●江戸時代
こう書くからといって、母を責めているのではない。
というのも、母が生きた時代には、まだすぐそこに江戸時代が残っていた。
私はそのことを、満60歳になったときに知った。
大政奉還によって江戸時代は終わったが、今から130年前のこと。
「130年」というと、若い人たちは、遠い昔に思うかもしれないが、
60歳になった私には、そうではなかった。
私の年齢の約2倍。
「2倍」と言えば、たったの2倍。
私の年齢のたった2倍昔には、そこにはまだ江戸時代が残っていた!
去年(08年)、私の母は、92歳で他界したが、母にしてみれば、
母が子どものころは、江戸時代はいたるところに残っていた!
江戸時代、そのものといってもよい。
●実家意識
そのため母がもつ、実家意識と、私たちがもつ、実家意識には、
大きなちがいがあった。
実家意識イコール、先祖意識と考えてよい。
母は容赦なく、私からお金を奪っていったが、母にすれば、
それは当然の行為ということになる。
あるとき私が、あることで泣きながら抗議すると母は、ためらうことなく
こう言った。
「親が実家を守るため、子(=私)の金(=マネー)を使って
何が悪い!」と。
母は、私から言葉巧みに土地の権利書を取り上げると、その土地を
転売してしまった。
土地を母名義のままにしておいたのが、悪かった。
●栄養不足
兄は、母の言葉を借りるなら、「生まれながらにして体が弱かった」。
母がそう思った背景には、母なりの理由がある。
長男の健一は、生まれるとまもなく、小児麻痺になった。
そして私が3歳のとき、日本脳炎で、死んでしまった。
そのあと、もう1人、兄がいたが、死産だった。
そのあと、もう一人の兄、準二が生まれた。
戦時中の貧しい時代のことで、栄養失調などというものは、あたりまえ。
国民病のようにもなっていた。
私が子どものころでさえ、砂糖水がミルクの代わりに使われていた。
私もよく飲まされた。
兄は、恐らくもっと多量に飲まされていたにちがいない。
それだけが原因だったとは言えないが、たしかに兄は、弱かった。
今で言う脳水腫のようなものを起こしたのではなかったか。
背も低かった。
おとなになってからも、身長は、150センチ前後しかなかった。
●長子相続
「家制度」は、「長子相続」が基本。
「長男が家を継ぐ」というのが、原則だった。
そのため父母はもちろんのこと、祖父母も、兄に大きな期待を寄せた。
同時に、兄に、スパルタ教育を試みた。
アルバムを見るかぎり、中学を卒業するころまでは、兄は、どこにでも
いるような、ごくふつうの子どもだった。
明るい笑顔も残っていた。
その兄がおかしくなり始めたのは、兄が17、8歳くらいからのこと
ではなかったか。
兄は、(跡取り息子)というよりは、(奴隷)に近かった。
もともと静かで、穏やかな性質だったが、それが父や母には気に入らなかった。
毎日のように兄は、父や母に叱られた。
怒鳴られた。
加えてやがて、家族からも孤立し始めた。
私とは9歳、年が離れていたこともある。
私は、兄といっしょに遊んだ記憶が、まったく、ない。
私は、父や母の関心が兄に集中する一方で、放任された。
私にとっては、それがよかった。
兄とは正反対の立場で、毎日、父や母の目を感ずることなく、遊んでばかりいた。
●心の監獄
今になって江戸時代の、あの封建主義時代を美化する人は多い。
悪い面ばかりではなかったかもしれないが、しかし封建主義時代がもつ(負の遺産)に
目を向けることなく、一方的に、あの時代を礼賛してはいけない。
家制度のもつ重圧感は、それを経験したものでないとわからない。
説明のしようがないというか、それは10年単位、20年単位でつづく。
いつ晴れるともわからない、悶々とした重圧感。
が、あえて言うなら、本能に近い部分にまで刷り込まれた、監獄意識に近い。
良好な家族関係、人間関係があるならまだしも、それすらないと、そこは
まさに監獄。
心の内側から、肉体を束縛する監獄意識。
この私ですら、そうだったのだから、兄が感じたであろう重圧感には、
相当なものがあるはず。
監獄から逃げる勇気もなかった。
その能力もなかった。
それ以上に、兄の精神は、20歳になるころには、すでに萎縮していた。
父は、親絶対教の信者。
母は、口答えすら許さない権威主義者。
そういう環境の中で、兄は、なるべくして、あのような兄になっていった。
●意識
が、意識というのは、おかしなもの。
私自身は戦後の生まれで、戦後の教育を受けた。
にもかかわらず、はじめてオーストラリアへ渡ったとき、そこで受けたのは、
ショックの連続だった。
日本でいう上下意識がなかった。
日本でいう家父長意識がなかった。
日本でいう男尊女卑思想がなかった。
もちろん長子存続意識もなかった。
さらにこんなことにも驚いた。
友人の家族だったが、年に2度も引っ越した。
オーストラリア人は今でもそうだが、収入が増えると、それに見合った
家に移り住んでいく。
「家を売り買いする」という意識そのものが、私の理解を超えていた。
「家」を売り買いするという意識そのものが、私には理解できなかった。
今から思うと、あのとき、その話を聞いて驚いたということは、それだけ
私の意識が、オーストラリア人のそれと、ズレていたことを示す。
●兄
兄は、自分で考える力すら、失っていた。
してよいことと、悪いことの判断すら、できなかった。
そのため常識はずれな行動が目立った。
こんなことがあった。
私が30歳のときのこと。
高校の同窓会があった。
私は恩師へのみやげということで、ジョニ黒(ウィスキー)を
用意して、もっていた。
が、その日の朝、見ると、フタが開けられ、上から3〜4センチくらい、
ウィスキーが減っていた。
兄の仕業ということはすぐわかった。
で、兄にそれを叱ると、悪びれた様子もなく、兄は、こう言った。
「ちょっと飲んでみたかっただけや」と。
一事が万事、万事が一事だった。
●マザコン
それで母の過干渉が終わったわけではない。
今にして思うと、ほかに類をみない、異常なまでの過干渉だった。
たとえば兄を、自転車屋という店に縛りつけたまま、一歩も、外に出さなかった。
友人も作らせなかった。
「おかしな連中とつきあうと、だまされるから」というのが、母の言い分だった。
兄は、そんなわけで生涯にわたって、給料なるものを手にしたことはない。
ときどき小遣いという名目の小銭をもらい、そのお金でパチンコをしたり、
レコードを買ったりしていた。
そんな母だったが、兄は、母の言いなりだった。
嫌われても、嫌われても、兄は母の言いなりだった。
何かあるたびに、兄は、こう言った。
「(そんなことをすれば)、母ちゃんが怒るで……」と。
母の機嫌をそこねるのを、何よりも、こわがっていた。
●母との確執
私が30歳を過ぎたころ。
兄は40歳になりかけていた。
そのころ、私は兄を、浜松へ呼びつける覚悟をした。
祖父が他界し、父も他界していた。
「母と兄を切り離さなくてはいけない」と、私は決心した。
すでに兄は、うつ病を繰り返していたし、持病の胃潰瘍も悪化していた。
内科の医師はこう言った。
「潰瘍の上に潰瘍ができ、胃全体が、まるでサルノコシカケのように、
なっています」と。
血を吐いたことも、たびたびある。
そういう兄を知っていたから、私は母と言い争った。
「兄を浜松へ、よこせ!」
「やらない!」と。
母は、兄を自分の支配化に置き、自分の奴隷として使うことしか考えていなかった。
心理学で言う、「代償的過保護」というのである。
「過保護」というときは、その裏に、親の愛情がある。
その過保護に似ているが、代償的過保護というときには、その愛情がない。
一時は、1週間にわたって、母と怒鳴りあいの喧嘩をしたこともある。
はげしい喧嘩だった。
が、母には勝てなかった。
兄は兄で、母の呪縛を解くことができなかった。
私は引き下がるしかなかった。
●母の愛
「愛」という言葉がある。
しかしこと私の母に関して言うかぎり、「愛」という言葉ほど、白々しい
言葉はない。
もっとも母は、「愛」という言葉は使わなかった。
「かわいい」という言葉を使った。
「準ちゃん(=兄)は、かわいい」
「私は準ちゃんを、かわいがっている」というような言い方をした。
母は、自分に従順で、口答えしない子どもが、「かわいい子」と言った。
そういう観点から見れば、私は、「鬼っ子」ということになる。
私は、ことあるごとに母に逆らった。
私のほうが生活の主導権を握っていたということもある。
母にはもちろん、兄にも、生活能力は、ほとんどなかった。
生活費は、すべて私が出した。
税金はもちろん、近親の人の香典まで……。
●泣き落とし
そこで母が私に使った手は、泣き落としだった。
母は、いつも貧しく、弱々しい母を演じた。
そういう話になると、いつも涙声だった。
(涙は、ほんとうは一滴も出ていなかったと思うが……。)
「母ちゃんは、近所の人が分けてくれる野菜で、生きていくから
心配しなくていい」というのが、母の口癖だった。
が、そう言われて、「はい、わかりました」と言う息子はいない。
私はこうして母に、お金を貢いだ。
実家へ帰るたびに、20万円とか30万円(当時の金額)という現金を、母に渡した。
●家族自我群
それでも私は自由だった。
浜松という土地で、好き勝手なことができた。
結婚し、3人の子どもをもうけることもできた。
そんな私でも、心が晴れたことは、一日もなかった。
本当になかった。
心理学の世界には、「家族自我群」という言葉がある。
無数の「私」が、家族という束縛の中で、がんじがらめになっている状態をさす。
それから生まれる呪縛感には、相当なものがある。
「幻惑」という言葉を使って、それを説明する学者もいる。
切るに切れない。
無視することもできない。
「私は知らない」と、放り出すこともできない。
それは悶々と、真綿で首を絞めるような苦しみと表現してもよい。
そんな中、母が私をだますという事件が起きた。
それについては、先にも書いた。
●家の犠牲
私は「家」の犠牲になった。
兄は、さらに犠牲になった。
生涯、「女」も知らず、結婚もせず、一生を終えた。
一度だけだが、兄にも結婚の話があった。
しかし母がそれを許さなかった。
「結婚すれば、嫁に財産を奪われてしまう」と。
で、ある日、私は兄を、浜松へ遊びに来たついでに、トルコ風呂へ連れて
いったことがある。
兄に「女」を経験させてやりたかった。
しかし入り口のところで兄は、固まってしまった。
「さあ、いいから、中へ入れ」と何度も促したが、兄は入らなかった。
そこがどういうところかも理解できなかった。
そう、そのころから、兄は、私の兄というよりは、私の弟という
存在になった。
さらに私の息子という存在になった。
●兄の死
こうして兄は、2008年の8月、持病を悪化させ、最後は胃に穴をあけられ、
肺炎で他界した。
作った財産は、何もない。
残した財産も、何もない。
あの「林家」という「家」に縛れられたまま、そこで生涯を終えた。
冒頭の話に戻るが、だからといって、母にすべての責任があるわけではない。
母は母として、当時……というより、自分が生まれ育った時代の常識に従った。
ここでいう「家制度」というのも、そのひとつ。
今でも、この「家制度」は、あちこちに残っている。
地方の田舎へ行けば行くほど、色濃く残っている。
そういう意識のない人たちからみれば、おかしな制度だが、そういう意識を
かたくなに守っている人も少なくない。
●家に縛られる人たち
私の知人に、D氏(50歳)という男性がいる。
父親との折り合いが悪く、同居しながらも、子どものころから、たがいに口を
きいたこともない。
父親は、きわめて封建的な人で、家父長意識がその村の中でも、特異とも
言えるほど、強い。
母親は、穏やかでやさしい人である。
そのため、一歩退いた世界から見ると、母親は、父親の奴隷そのものといった
感じがする。
が、D氏は、その「家」を離れることができない。
なぜか?
ここに(意識)の問題がある。
D氏をその家に縛っているのは、もちろんD氏の意識ではない。
D氏自身は、一日でもよいから、父親のもとを離れたいと願っている。
が、それができない。
それが家族自我群ということになる。
深層心理の奥深くから、その人を操る。
理性や知性の範囲を超えているから、自分でそれをコントロールすることは、
ほぼ不可能と考えてよい。
私も何度か、「親と別れて住んだらいい」とアドバイスしたことがあるが、
そういう発想というか、意識そのものがない。
ないというより、もてない。
「何十代もつづいた家だから」というのが、その理由である。
しかしはっきり言おう。
そういうくだらない考えは、私たちの時代で終わりにしたい。
「家」が大切か、「私」が大切かということになれば、「私」に決まっている。
「家を継ぐ」とか、「継がない」という発想そのものが、時代錯誤。
バカげている。
が、それがわからない人には、それがわからない。
D氏は死ぬまで、結局は、「家」に縛られるのだろう。
しかし先日、古里と決別した、私から一言。
「家意識なんて、棄ててしまえ!」。
「『私』を、鎖から解き放て!」。
そこは自由で、どこまでもおおらかな世界。
D氏よ、何を恐れているのか?
何を失うことを、心配しているのか?
あなたが自由になったところで、あなたは何も失わない。
あれこれと言う連中はいるだろうが、そういうバカな連中は相手にしなくてもよい。
相手にしてはいけない。
どうせ化石となって、消えていく運命にある連中なのだから……。
●兄へ
兄は、死ぬことで、「家」から解放された。
運命と言えば、それが運命だった。
またそれ以外、方法はなかった。
運命と闘い、それを切り開く能力もなかった。
本来なら、いちばんそばにいて、兄を助けるべき母が、それをはばんでしまった。
私のワイフは、よくこう言った。
「あなたの兄さんは、気の毒な人ね」と。
最近になって、つまり兄が死んでから、近所の人たちも、そう言うように
なった。
「あなたの兄さんは、気の毒な人だった」と。
その「気の毒」という言葉の中に、兄の人生のすべてが集約されている。
それが兄の人生だった。
(補記)
こうして兄のことを、包み隠しなく書くのは、兄のためである。
もしこのままだれも兄についての記録を残さなかったら、兄は、本当に
ただの墓石になってしまう。
兄だって、懸命に生きた。
苦しみながら生きた。
その記録を残すのは、私という弟の義務と考える。
今、同じような境遇で苦しんでいる人のために、一助になればうれしい。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep・09++++++++++はやし浩司
●ジョーク
「世界おもしろジョーク集」(PHP判)の中の1つを、
編集させてもらう。
+++++++++++++++
あるとき、釈迦が、ある村にやってきた。
家制度がしっかりと残っている村だった。
釈迦は、その村で、3日間、説法をすることになった。
(第一日目)
釈迦がこう言った。
「みなさんは、家制度というものを知っているか?」と。
すると、みなは、こう言った。
「知っていま〜す」と。
すると釈迦は、こう言った。
「そうか、それなら、何も話すことはない。今日の説法はおしまい」と。
村の人たちは、みな、顔を見合わせた。
そこでこう決めた。
「明日、釈迦が同じ質問をしたら、みな、知らないと答えよう」と。
(第2日目)
釈迦がこう言った。
「みなさんは、家制度というものを知っているか?」と。
すると、みなは、こう言った。
「知りませ〜ん」と。
すると釈迦は、こう言った。
「そうか、それなら、何を話しても無駄だ。今日の説法はおしまい」と。
村の人たちは、みな、顔を見合わせた。
そこでこう決めた。
「明日、釈迦が同じ質問をしたら、右半分の人は、『知っている』と
答え、左半分の人は、『知らない』と答えよう」と。
(第3日目)
釈迦がこう言った。
「みなさんは、家制度というものを知っているか?」と。
すると、右半分の人たちは、「知っていま〜す」と答えた。
左半分の人たちは、「知りませ〜ん」と答えた。
すると釈迦は、こう言った。
「そうか、それなら、右半分の人が、左半分の人に、家制度がどういう
ものか、話してあげてください。今日の説法はおしまい」と。
釈迦の3日間の説法は、それで終わった。
(以上、「世界おもしろジョーク集」を改変、編集。)
++++++++++++++++
●自己否定
少し不謹慎なジョークに仕立ててしまったが、そこは許してほしい。
こうした意識の奥深くに潜む意識の問題について書くのは、たいへんむずかしい。
本人自身にその自覚があれば、まだよい。
さらにそれに対する問題意識があれば、まだよい。
が、それすらないとなると、その説明すらできない。
「家制度」そのものが、その人の哲学(?)や、ものの考え方の基本になって
いることもある。
へたにそれを否定すると、その人にとっては、自己否定そのものにつながって
しまう。
「あなたの人生はまちがっていました」「あなたは無駄なものを大切なものと
思い込んでいただけです」と。
だからこのタイプの人は、抵抗する。
命がけで抵抗する。
そういうとき、決まって、「先祖」という言葉をよく使う。
「先祖あっての、あなたではないか」「その先祖を粗末にするとは何事か」と。
中に、「先祖を否定するあなたは、教育者として失格だ。
即刻、教育者としての看板をさげろ」と言ってきた女性(当時、35歳くらい)
がいた。
(この話は、ホントだぞ!)
私は何も、先祖を否定しているわけではない。
「教育者」を名乗っているわけでもない。
●D氏のばあい
先に書いた、D氏のばあい、盆供養のときは、位牌だけでも、
100個近く並ぶという。
昔からの家柄である。
そういう伝統を、D君の代で断ち切るというのは、D君自身にもできない。
できないというより、それをするには、大きな勇気がいる。
親戚の承諾も必要かもしれない。
が、こういうケースのばあい、不要な波風を立てるよりは、安易な道を選ぶ。
選んで、現状維持を保つ。
こうしてD氏自身も、やがて「家制度」の中に組み込まれていく。
そこで大切なことは、「私の代で、こうした愚劣な制度はやめにする」と
決意すること。
宣言すること。
子どもたちにそれを伝えて、よいことは何もない。
今度は、その子どもたちが苦しむことになる。
が、実際には、高齢になればなるほど、それができなくなる。
家制度そのものは、高齢者にとっては、けっこう、居心地のよい世界である。
家父長として、みなの上に、君臨できる。
そのためものの考え方も、どうしても保守的になる。
こうして再び、ズルズルと、家制度をそのままつぎの世代へと残してしまう。
つぎの世代はつぎの世代で、同じようなプロセスを経て、同じように考える。
●周りの人たち
そんなわけで周りの人たちが、その渦中で苦しんでいる人を、励まして
やらねばならない。
私も今回、古里と決別するについて、周りの人たちの励ましが、何よりも
大きな力となった。
ある友人は、こう言った。
「檀家なんて、やめてしまえよ」と。
また別の友人はこう言った。
「親が子どもを育てるのは当たり前のことだろ。感謝するとかしないとかいう
問題ではないだろ」と。
うれしかった。
また長野県のある地方では、自治体ぐるみで、そういった悪習と闘って
いるところもある。
香典の額を、一律、1000円と決めたり、葬儀での僧侶への布施の額を、
一律、5万円と決めるなど。
戒名もひとつにしているという(長野県S市)。
今、そういう動きが全国的に広がっている。
またその動きは、今後加速することはあっても、後退することはない。
あとは、私たちの勇気だけということになる。
みなが、一斉に声をあげれば、こうした愚劣な制度は滅びる。
それにしても、21世紀にもなった今、どうして長子相続制度なのか?
家制度なのか?
人間にどうして上下意識があるのか?
バカげていて、話にならない!
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 長子相続 家制度 家意識 家父長意識 封建制度 はやし浩司 私
の兄 先祖意識 親絶対教)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
【損得論】
●損と得
++++++++++++++++++
60歳をすぎて、「損と得」についての考え方が、大きく変わってきた。
「損とは何か」「得とは何か」と。
それをしみじみと(?)、心の中で思いやりながら、
「老人になるというのは、こういうことなのか」と思う。
「老人」といっても、使い古された、老いぼれた人のことではない。
少し照れくさいが、「円熟した人」をいう。
++++++++++++++++++
●何が損か
この世の中で、「損かどうか」を考えること自体、バカげている。
どんなにあがいても、「死」というもので、私たちは、すべてを失う。
この宇宙もろとも、すべてを失う。
「死」を考えたら、それほどまでの「大きな損」はない。
たとえばあなたが地球上の、ありとあらゆる土地を自分のものにしたとする。
北極から南極まで。
一坪残らず、だ。
が、死んだとたん、すべてを失う。
つまり「死」にまさる(?)、損はない。
これには、自分の死も、相手の死もない。
そのため「死」をそこに感ずるようになると、日常的に
経験する損など、何でもない。
損とは感じなくなる。
●「金で命は買えん」
たとえば私の友人の中には、数か月で、数億円も稼いだ人がいた。
その友人は、数年前、死んだ。
莫大な財産を残したが、死んだとたん、「彼の人生は何だったのか?」
となってしまった。
私の母ですら、死ぬ直前、こう言っていた。
「金(=マネー)で命は、買えん」と。
あれほどまで、お金に執着していた母ですら、そう言った。
●得
一方、「得」と思うことも多くなった。
昨日も、秋の空を見たときも、そう思った。
澄んだ水色の空で、白い筋雲が、幾重にも重なって流れていた。
それを見て、「ああ、生きていてよかった」と思った。
ただ「損」とちがって、「得」という感覚は、実感しにくい。
大きな青い空を見たからといって、大きく得をしたとは思わない。
反対に、小さな花を見たからといって、大きな青い空を見たときに感ずるそれに、
劣るということはない。
もちろん私も、金権教にかなり毒されている面もあるから、お金は嫌いではない。
たいていのばあい、金銭的な価値に置き換えて、ものの損得を考える。
たとえば予定外の収入があったりすると、「得した」と思う。
しかし同時に、そこにある種の虚しさを覚えるようになったのも事実。
「だから、それがどうしたの?」と。
●長生き
では、長生きはどうか?
長生きをすればするほど、得なのか、と。
が、これについても、最近は、こう考える。
「それが無駄な生き方なら、長生きしても、意味はない」と。
「生きることが無駄」と言っているのではない。
「どうせ生きるなら、最後の最後まで、意味のある生き方をしたい」と
いう意味で、そう言う。
もちろん、できれば、長生きしたい。
たった一度しかない人生だから、それは当然のこと。
問題は、どうしたら、意味のある人生にすることができるか、ということ。
●今のままで、よいのか
未来は現在の延長線上にある。
とするなら、今の生き方が、未来の生き方になる。
となると、「今のままでいいのか」となる。
今、意味のある人生を送っていない私が、この先、意味のある人生を
送れるようになるということは、ありえない。
言い換えると、今の生き方そのものが、大切ということになる。
「今日」という「今」ではなく、「この瞬間」における「今」ということになる。
「私は、この瞬間において、意味のある生き方をしているのか」と。
●命の換算
この話は前にも書いたので恐縮だが、テレビでこんな人を紹介していた。
ある男性だが、何かの病気で、2年近い闘病生活のあと亡くなった。
その男性について、妻である女性が、こう言った。
「がんばって生きてくれたおかげで、娘の家が建ちました」と。
つまり夫であるその男性が、死の病床にありながらも、がんばって生きて
くれたので、その年金で、娘のための家を建てることができた、と。
私はその話を聞いたとき、「夫の命まで、金銭的な価値に置き換えて
考える人もいるのだなあ」と驚いた。
まあ、本音を言えば、だれだってそう考えるときがある。
私もあるとき、ふと、こう思ったことがある。
「1年、長生きをして、1年、仕事がつづけられたら、○○○万円、
得をすることになる」と。
しかしこの考え方は、まちがっている。
もしこんな考え方が正しいというなら、私は自分の命すら、金銭的な
価値に置き換えてしまっていることになる。
仕事ができること自体が、喜びなのだ。
収入があるとすれば、それはあとからついてくるもの。
生きる目的として、収入があるわけではない。
●奇跡
さらに言えば、アインシュタインも言っているように、「この世に生まれた
ことだけでも、奇跡」ということになる。
(あなた)という人間が生まれるについても、そのとき1億個以上の精子が1個の
卵子にたどりつけず、死んでいる。
もしそのとき、隣の1個の精子が、あなたにかわって卵子にたどりついていたら、
あなたという人間は、この世には存在しない。
そのことは、二卵性双生児(一卵性双生児でもよいが)を見れば、わかる。
外の世界から見れば、(あなた)かもしれないが、それはけっして、(あなた)
ではない。
他人が見れば、(あなた)そっくりの(あなた)かもしれないが、けっして、
(あなた)ではない。
つまり私たちは、この世にいるということだけ、この大宇宙を手にしたのと
同じくらい、大きな得をしたことになる。
●統合性の確立
若いときは、生きること自体に、ある種の義務感を覚えた。
子育ての最中は、とくにそうだった。
働くことによって収入を得る。
その収入で、家族を支える。
しかし今は、それがない。
どこか気が抜けたビールのようになってしまった。
生きる目的というか、ハリが、なくなってしまった。
「がんばって生きる」とは言っても、何のためにがんばればよいのか。
そこで登場するのが、「統合性」ということになる。
(自分がすべきこと)と、(現実のしていること)を一致させていく。
それを「統合性の確立」というが、この確立に失敗すると、老後も、みじめで
あわれなものになる。
くだらない世間話にうつつを抜かし、自分を見失ってしまう。
そんなオジチャン、オバチャンなら、いくらでもいる。
あるいは明日も今日と同じという人生を繰り返しながら、時間そのものを無駄に
してしまう。
が、その統合性の確立には、ひとつの条件がある。
無私、無欲でなければならない。
功利、打算が入ったとたん、統合性は霧散する。
こんな話を、ある小学校の校長から聞いた。
●植物観察会
ある男性(80歳くらい)は、長い間、高校で理科の教師をしていた。
その男性が、今は、毎月、植物観察会を開いている。
もちろん無料。
で、雨の日でも集合場所にやってきて、だれかが来るのを待っているという。
そしてだれも来ないとわかると、そのまま、また家に帰っていくという。
その男性にとっては、植物観察会が生きがいになっている。
参加者が多くても、またゼロでも構わない。
大切なことは、その(生きがい)を絶やさないこと。
が、もしその男性が、有料で植物観察会をしていたら、どうだろうか。
月謝を計算し、収入をあてにしていたら、どうだろうか。
生徒数がふえることばかり考えていたら、どうだろうか。
同じ植物観察会も、内容のちがったものになっているにちがいない。
つまり、無私、無欲でしているから、その男性の行動には意味がある。
「統合性の確立」というのは、それをいう。
●変化
損か、得か?
それを考えるとき、これだけは忘れてはいけない。
今、ここに生きていること自体、たいへんな得をしているということ。
それを基本に考えれば、日常生活で起こるさまざまな損など、損の中に入らない。
そして損ということになれば、「死」ほど、大きな損はない。
それを基本に考えれば、日常生活で起こるさまざまな損など、損の中に入らない。
つまり生まれたこと自体、大きな得。
死ぬこと自体、大きな損。
私たちは、その得と損の間の世界で、ささいな損得に惑わされながら生きている・
・・・というようなふうに、このところ考えることが多くなった。
私自身が「死」に近づいたせいなのか。
それとも「生」の意味が少しはわかるようになったせいなのか。
どうであるにせよ、「損と得」について、私の考え方が大きく変わってきた。
この先のことはわからないが、人は老人になると、みな、そう考えるようになるのか。
それとも、私だけのことなのか。
どうであるにせよ、今は、自分の中で起こりつつある変化を、静かに見守りたい。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi
Hayashi 林浩司 BW はやし浩司 老後 損得論 損か得か 自己の統合性 統合性の確
立)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●教育費の公的支出割合
++++++++++++++++++++++++++++++
日本の公的支出割合は、OECD(経済協力開発機構)の
調査によれば、対GDP比において、日本は3・3%と、28
か国中、下から2番目だった(2009年9月9日)。
わかりやすく言えば、その分だけ親の負担が大きいということ。
「全教育費に占める私費負担の割合は、33・3%と、
韓国に次いで、2番目に高く、平均の2倍以上だった」(中日新聞)と。
++++++++++++++++++++++++++++++
●子ども大学生、親、貧乏盛り(When boys are Univ. students, Parents in Japan are the
poorest.)
++++++++++++++++++
8年前(2001年)に書いた
原稿を、再掲載。
++++++++++++++++++
子どもの教育費を考える法(学費を安くせよ!)
親が子どもの学費で苦労するとき
●親、貧乏盛り
少子化? 当然だ! 都会へ今、大学生を一人送ると、月々の仕送りだけで、毎月二七
万円(九九年東京地区私大教職員組合連合調べ、学費含む)(※)。が、それだけではすま
ない。アパートを借りるだけでも、敷金だの礼金だの、あるいは保証金だので、初回に四
〇〜五〇万円はかかる。それに冷蔵庫、洗濯機などなど。パソコンは必需品だし、インタ
ーネットも常識。となると、携帯電話のほかに電話も必要。入学式のスーツ一式は、これ
また常識。世間は子どもをもつ親から、一体、いくらふんだくったら気がすむのだ! そ
んなわけで昔は、『子ども育ち盛り、親、貧乏盛り』と言ったが、今は、『子ども大学生、
親、貧乏盛り』という。大学生を二人かかえたら、たいての家の家計はパンクする。
●親の負担が大きい日本
一方、アメリカでもオーストラリアでも、親のスネをかじって大学へ通う子どもなど、
さがさなければならないほど、少ない。たいていは奨学金を得て、大学へ通う。企業も税
法上の控除制度があり、「どうせ税金に取られるなら」と、奨学金をどんどん提供する。し
かも、だ。日本の対GNP比における、国の教育費は、世界と比較してもダントツに少な
い。欧米各国が、七〜九%(スウェーデン九・〇、カナダ八・二、アメリカ六・八)。日本
はこの一〇年間、毎年四・五%前後で推移している(UNESCO調べ)。大学進学率が高
いにもかかわらず、対GNP比が少ないということは、それだけ親の負担が大きいという
こと。日本政府は、あのN銀行という一銀行の救済のためだけに、四兆円という大金を使
った。それだけのお金があれば、全国二〇〇万人の大学生に、それぞれ二〇〇万円ずつの
奨学金を渡せる!
●もの言わぬ従順な民
が、日本人はこういう現実を見せつけられても、誰も文句を言わない。教育というのは
そういうものだと、思い込まされている。いや、その前に日本人の「お上」への隷属意識
は、世界に名だたるもので、戦国時代の昔から、そういう意識を徹底的にたたき込まれて
いる。いまだに封建時代の圧制暴君たちが、美化され、英雄化され、大河ドラマとして放
映されている! 日本のこの後進性は、一体、どこからくるのか。親は親で、教育といい
ながら、その教育を、あくまでも個人的利益の追求の場と位置づけている。世間は世間で、
「あなたの子どもが得をするのだから、その負担はあなたがすべきだ」と考えている。だ
から隣人が、子どもの学費で四苦八苦していても、誰も同情しない。こういう冷淡さが積
もりに積もって、その負担は結局は、子どもをもつ親のところに集中する。
日本の教育制度は、欧米に比べて、三〇年は遅れている。その意識となると、五〇年は
遅れている。かつてジョン・レノンが日本の税関で身柄を拘束されたとき、彼はこう叫ん
だ。「こんなところで、子どもを育てたくない」と。「こんなところ」というのは、日本の
ことをいう。彼には彼なりの思いがいろいろあって、そう言ったのだろうが、それからほ
ぼ三〇年。この状態はいまだに変わっていない。もしジョン・レノンが生きていたら、き
っとこう叫ぶに違いない。「こんなところで、孫を育てたくない」と。私も三人の子どもを
もっているが、そのまた子ども、つまりこれから生まれてくるであろう孫のことを思うと、
気が重くなる。日本の少子化は、あくまでもその結果でしかない。
(参考)
※……東京地区私立大学教職員組合連合の調査(一九九九年)によると、関東圏内の三一
の私大に通う大学生のうち、約九三〇〇人の学生について調べたところ、次のようなこと
がわ
かったという。親の平均年収 ……一〇三四万円(前年度より二四万円減)
受験費、住居費、学費、仕送りの合計金額 ……三二二万円
子どものために借金した親 ……二八・〇%(自宅外通学のばあい)
親の平均借り入れ額 ……一七六万円
教育費の負担が「たいへん重い」と答えた親……四四・六%
このため、子どもの学費は、親の年収の三一・八%を占め、平均仕送り額は、一二万一
〇〇〇円。そこから家賃の五万六九〇〇円を差し引くと、自宅外通学生の生活費は六万四
〇〇〇円ということになる(以上一九九八年度)。
(参考)
●かたよった日本の行政予算
これは2001年度、静岡県浜松市における予算案だが、それによれば、歳出のうち、
土木費が25・0%、民生費が19・5%、公債費が12・1%、教育費が10・3%、
衛生費が9・4%、以下総務費9・3%、商工費4・5%、となっている。
教育費が少ないのはともかくも、土木費が25%(4分の1)というのは、世界的にみ
ても異常としか言いようがない。家計にたとえるなら、月収50万円の人が、毎月、13
万円ものお金を家や庭の増改築に使っているようなものだ。こうしたいびつな予算配分が、
結局は子どもをもつ親の負担となってはね返ってくることを忘れてはならない。
+++++以上、2001年ごろ書いた原稿より(中日新聞掲載済み)+++++
この中で、1999年の調査結果を書いた。
ここに出てくる数字と、今回公表された数字を比較してみたい。
【1999年】
スウェーデン9・0、カナダ8・2、アメリカ6・8)。日本はこの10年間、毎年4・5%
前後で推移している(UNESCO調べ)。
【2006年】(今回、公表)
アイスランド……7・2%
デンマーク、スウェーデンとつづき、
日本は、2005年の3・4%より、さらに0・1%さがり、3・3%。
とくに大学などの高等教育費は、0・5%と、各国平均の1%の半分以下!
『子ども、大学生、親、貧乏盛り』の意味は、ここにある。
今回政権を取った民主党は、これを5%にするといっている。
おおいに期待したい。
が、同時に、こんなことも言える。
私などは国民年金しかないので、死ぬまで働くしかないと思っている。
が、その一方で、月額30万円前後の年金を手にして、優雅な生活を楽しんでいる
老人も多い。
そういう老人個人には、責任はないが、こんな偏(かたよ)った行政予算をしている
国は、OECDの調査結果を見てもわかるように、この日本だけ。
どうして元公務員たちの年金が、私たちの5倍近くもあるのか!
最近、私の友人はこう言った。
「この日本では、自営業など、バカ臭くて、そのうちだれもしなくなるだろう」と。
ホント!
江戸時代の士農工商という身分制度が、形を変えて、そのまま現代の世界に復活している。
「士」だけが特権階級を形成し、残りの93〜94%の民衆は、増税にあえぐ。
そのあたりから根本的に改善しないかぎり、結局はそのしわ寄せは、子どもをもつ
親にのしかかってくる。
それにしても、たったの3・3%とは!
その一方で、土木費が、25%!
どこの公共施設も、超の上に超がつくほど、立派。
豪華。
そんな施設の中で、何が、「育児相談会」だ。
笑わせるな!
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●9月11日
++++++++++++++++++
リバウンドが始まった?
旅行先で、ごちそうを食べたのが悪かった?
……おととい、恐る恐る体重計に乗ったら、
何と、62・5キロ!
2・5キロのオーバー。
たった、1日か2日で、2・5キロもオーバーとは!
あわてて食事制限+運動。
昨夜は、1時間ほど、汗をかいてサイクリングした。
で、今朝は、……60・1キロ。
ホ〜〜ッ!
++++++++++++++++++
●バカな人
そこにバカな人がいても、相手にしてはいけない。
そこにバカな人がいるということを、知るだけでよい。
そういうバカな人が、この世にいることを知るだけでよい。
つまりそういうバカな人もいることを前提で、ものを考え、行動する。
そこにいるバカな人を、1人や2人、相手にしても、世の中は何も変わらない。
相手にすればするほど、無駄なエネルギーを消耗する。
不愉快な思いをする。
無視して、あとは遠ざかる。
そしてその分、社会全体、日本全体をながめる。
自分の行動を決める。
その中でものを考え、ものを書く。
それが賢い生き方。
(注)「バカなことする人をバカという。頭じゃないのよ」(映画「フォレスト・ガンプ」)。
●妄想
(こだわり)と(妄想)。
密接に関連している。
こだわりが強くなればなるほど、妄想が生まれる。
さらに(うつ病)と(こだわり)。
密接に関連している。
うつ病がひどくなると、こだわりもひどくなる。
そのことばかりに、こだわり、悶々とした気分になる。(……らしい。)
うつ病というと、当人の問題だけと考える人は多い。
しかし周りの人たちに与える影響も、大きい。
その人がうつ病とわかっていれば、それでよい。
が、わからないと、周りの人たちが、それによって振り回される。
もちろんうつ病といっても、症状はさまざまだが……。
さらに高齢者になると、(うつ病)と(認知症)の問題が起きる。
うつ病から認知症になる人もいれば、反対に認知症からうつ病になる人もいる。
同時進行の形で、その両方になる人もいる。
そうした区別は、専門家でも、むずかしいそうだ。
要するに、(こだわり)をもつようになったら、要注意。
ただひたすら、気分転換、あるのみ。
何でもよい。
それぞれが自分に合った方法で、気分転換をする。
私のばあいは、映画を観に行ったり、温泉に入ったりする。
パソコンショップを歩き回るのもよい。
いちばん効果的なのは、運動。
それに買い物。
音楽をつづけて聴くのもよい。
草刈り機で雑草を刈ったり、畑を耕すのも楽しい。
言い忘れたが、もうひとつ効果的な方法がある。
気分がクシャクシャしたら、こうしてパソコン相手に文章を叩き出す。
それも楽しい。
読んでくれる人には、迷惑なことかもしれないが……。
(補記)
今、ふと、こんなことを思った。
こうしてパソコン相手に、文章を書けるのも、あと何年かな?、と。
頭の働きが鈍くなってきているのが、自分でもわかる。
集中力と根気が、つづかない。
それに油断すると、パソコンの使い方そのもので、迷うことがある。
アルツハイマー病でいう、(手続き記憶の喪失)というのかもしれない。
昨日までできたことが、今日になって、できなくなる、など。
この先、そういうことがふえてくるかもしれない。
あるいは本当に、認知症か何かになってしまうかもしれない。
今のところだいじょうぶとは思うが、……というのも、昨夜も中学生を相手に、
方程式の問題で、競争をしてみた。
私の完勝だった。
ほっとした。
が、発症したら最後。
そのあと数年で、頭は使い物にならなくなるという。
(アルツハイマー病については、前兆症状があり、さらに前兆の前兆症状というのも、
あるそうだ。)
今の私は、だいじょうぶかな?、と、何度も頭の中をさぐってみる。
「昨日の昼は、回転寿司屋で、3皿、食べた」
「昨日の夜は、きのこ弁当を食べた」
「中学生と解きあった方程式の問題は……」と。
若いころは、こんなこと、心配したこともなかった。
が、今は、そんな心配ばかりしている。
ああ、これも(こだわり)のひとつか?
これから居間へおりていって、ワイフとバカ話をしてこよう。
みなさん、おはようございます。
今日は、9月11日。
あの「9・11」の9月11日。
「9・11」という数字を見て、何も思い出さないようなら、あなたもあぶない?
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 9日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page019.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●つながり
++++++++++++++++++++
朝、パソコンを立ち上げる。
メールを読む。
つぎにHPやBLOGへの、アクセス数を
確認する。
ここまでで、5〜10分前後。
そのあと世界のニュースに目を通す……。
このころになると、頭の中が少しずつ、動き
始める。
私は血圧が低いこともあって、朝が苦手。
濃いお茶を飲んで、眠気を取り去る。
……こうして私の1日は始まる。
思いついたことを、書き始める。
しかしそれは同時に、不安との闘いでもある。
いつも文を書きながら、「こんなもの、だれが
読んでくれるだろう?」と迷う。
この文にしても、そうだ。
読んでも意味のない、ただの駄文。
自分でも、それがよくわかる。
目の前に見えるのは、パソコンの画面だけ。
その画面に向かって、孤独な闘いがつづく。
++++++++++++++++++
●T県のNさん(母親)より
そんな中、T県のNさんより、メールが届いていた。
少し前、子どもの相談にのってあげた人である。
うれしかった。
それをそのまま紹介させてもらう。
『……先生に相談にのっていただいてから、三ヶ月近くが経ちました。今、長男はとても
落ち着いています。暴力もほとんどなくなりました。本当に感謝しています。あの時、勇
気を出して相談にのっていただいてよかった、としみじみ思います。
今、私はとても子育てが楽しくなりました。そして長男をとてもいとおしく思います。も
ちろん、まだまだ問題がすべて解決したわけではありません。学校も嫌いだし、勉強も嫌
い、そしてゲームで負ければ怒ります。他のお母さんから見たら、問題ばかりで自慢でき
るような息子ではないかもしれません。でも、私はそれでいいと思えるようになりました。
勉強については、あきらめました。宿題を必要最小限なんとか怒らずにやるようになった
ので、それでよしとすることにしました。ゲームで負けると相変わらず怒り出すのですが、
そっとしておくとすぐに気持ちを切り替えて遊べるようになりました。
そして、私が重い荷物を持っているときには、すかさず手助けしてくれるようになりまし
た!こうしたほんの少しの変化が、とてもうれしいのです。
昨日は次男のトイレトレーニングにかかりきりで、遠くから「早く宿題やってね」と
時々言っていたのですが、あとで長男に「なんでママは今日怒ってばかりいるの?」
と聞かれました。怒ってはいなかったのですが、言い方がきつかったのかもしれませ
ん。でもそれを冷静に聞き流し、あとで私にそうやって言えるなんて、私よりずっと
大人だと思いました。
でも、一番変わったのは私なんだと思います。いつも「許して忘れる」を心にとめて
過ごしていたら、自然と怒ったりしなくなりました。私が長男を追い詰めていたのか
もしれませんね。今でも、もちろん心配事はたくさんありますが、心の中で「頑張っ
て」とつぶやきながら、私は私で頑張っていこうと思っています。次男も保育園に入
り、私も仕事を探すつもりです。これからは、自分の時間を大切にしていきたいで
す。
ほんとうにありがとうございました。先生、これからもお身体に気をつけて、たくさ
んの人の力になってください。すばらしいお仕事をされていて、尊敬しています。また
いつか、相談をするかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします……』
●それでじゅうぶん
私はNさんを知らないし、仮にどこかですれちがっても、そのまま通り過ぎてしまう
だろう。
何かのことでまたメールをもらえば、そのときはそのときで、返事は書く。
しかしそこまで。
生涯、会うこともないだろうし、もちろん関係を深めるということもない。
が、私はそこに、何というか、人生の切なさを感じる。
またそれが人生なのかなと思ってしまう。
数日前も、伊豆を旅して、いろいろな人に出会った。
話もした。
たがいに笑ったりもした。
しかし、やはりそこまで。
私はその場を去り、ここへ戻ってきた。
が、だからといって、そういう出会いが無意味と言っているのではない。
その切なさがあるからこそ、私はまたつぎの切なさを求めて、人と出会い、
メールを交換し、旅に出る。
言い換えると、人生は、その切なさの集まり。
その切なさが、無数のドラマを作る。
そのドラマに意味がある。
今回も、Nさんは、私をさして、「尊敬しています」と書いてくれた。
が、私は、そんな人間ではない。
まったく、ちがう。
Nさんが実物の私を見たら、がっかりして、ひっくり返ってしまうだろう。
が、それでも、うれしい。
どうしてだろう?
いったいこの(うれしさ)は、どこから来るのか?
ちょうど窓の外には、T県の方角が見える。
澄んだ水色の秋の空。
「あの空の遠くに、Nさんは住んでいるのだろうな」と、ふと思う。
この光と分子の織りなす世界で、ほんの少しだけだが、私とNさんと、心がつながった。
人との(つながり)を感じた。
私にとっては、それでじゅうぶん。
私のしていることで、喜んでくれた人がいた。
私のしたことが、役にたった人がいた。
それ以上、私は何を望むことができるのか。
何を望んでいるのか。
さあ、今日もがんばろう。
そこでだれかが待っていてくれる。
書き忘れたが、「切ない」ということは、「さみしい」ということではない。
「虚しい」という意味でもない。
人間も、そこに命の限界を感ずるようになると、その(切なさ)を楽しむことが
できるようになる。
私がここにいて、生きていること自体に、切なさを感ずることもある。
Nさん、ありがとうございました。
今日は、よい1日になりそうです。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【生命から生命へ】(From Life to Life)
We live and die and repeat it again and again, conveying out Life to other all living
creatures and things together with our consciousness.(後日、要推敲)
++++++++++++++
あなたの生命は、ほかのありと
あらゆる生命とつながっている。
過去から未来へと、つながっている。
すべての植物から動物へと、つながっている。
それがわかれば、あなたは
もう孤独ではない。
もしあなたに「死」というものが
あるとするなら、それはあなたの
「意識」の死に、過ぎない。
もっと言えば、意識の連続性が、
途切れるに過ぎない。
だから、もしあなたが意識の連続性を、
あなたの肉体を超えて感ずることが
できたら、あなたには、「死」は
ないことになる。
++++++++++++++
●生物の連続性
人は日々に死に、日々に生まれ変わる。
細胞の生死を考えれば、それがわかる。
死んだ細胞は、体外へ排出され、ときに
分子レベルにまでばらばらになり、また
別の生物や無生物の中へと取りこまれていく。
と、同時に、私たちは日々に、ほかの生物や
無生物から、新しい肉体を作り、生きている。
こうして私たちはありとあらゆる生物と
つながり、今というときを生きている。
これを「生物の連続性」という。
●命
では、死んだらどうなるか。
が、基本的には、「死」は存在しない。
その人個人の意識は途絶えるが、生命は、
姿や形を変え、別の生物の中に取りこまれて
生きていく。
虫かもしれない。
花や木かもしれない。
動物や、魚かもしれない。
ともかくも、生きていく。
この連続性を総称して、「生命」という。
●意識
個人は、その人の意識によって特定される。
「私は・・・」というときの「私」である。
しかしその私にしても、肉体のほんの一部
でしかない。
もっと言えば、脳の中を走り回る、電気的
信号の一部でしかない。
だからといって、「私」に意味がないというのでは
ない。
私が書きたいのは、その逆。
この「私」があるから、そこから無数の
ドラマが生まれ、人間の生活を、潤い豊かなものに
する。
もし「私」がなかったら、私たち人間は、そこらに
生える雑草のような存在になってしまう。
●死
では、「死」とは何か?
言うまでもなく、意識の途切れをいう。
その人の意識が途切れたとき、「私」は消える。
言うなれば、パソコンの電源を切るようなもの。
そのときから、見ることも、聞くことも、
感ずることもできなくなる。
しかし先にも書いたように、それで生命が
途切れるわけではない。
生物の連続性の中で、つぎつぎと新しい生物の
中に、生命は取りこまれていく。
あなたが過去から現在に至るまで、取りこんで
きたように・・・。
●再生
そんなわけで、「生命」を、あなたという個人の
中だけに閉じこめておくのは、正しくない。
またそういう視点で、あなたという「私」を見ては
いけない。
もっと具体的に話してみよう。
脳も含めて、上は髪の毛から、下は、足の爪まで、
私たちは長くて1年足らずで、すべてが作り替えられる。
古い肉体は、つねに便となったりして、外に排出される。
が、それは自然界でつねにリサイクルされ、無数の
生物の、一部となって再生される。
もちろんあなた自身の一部として戻ってくることもある。
●破壊と再生
こうした破壊と再生の中で、連続性をもつものが
あるとすれば、それが意識ということになる。
脳の中で、意識は、古い細胞から新しい細胞へと、
つねに伝えられていく。
あなたが子どものころの記憶があるとしても、
子どものころの脳細胞が、残っているからではない。
そのころの脳細胞は、とっくの昔に破壊されている。
今、「子どものころの記憶がある」と思いこんでいるのは、
ごく最近再生された、脳細胞の中に伝えられた電気的
信号にすぎない。
●瞬間移動(転送)
映画『スタートレック』の中に、よく「転送」という
言葉が出てくる。
これはある一定の場所から、別の場所に、瞬時に
移動することをいう。
SF映画の世界でのことだから、まともに考えるのも
どうかと思うが、その転送について、こんな議論がある。
「転送されてきた人間は、もとの人間と言えるか」
という問題である。
原理は、こうだ。
まずあなたという人間を、分子レベルにまで、バラバラに
する。
そのバラバラになったあなたを、電磁波か何かの(波)に
乗せて、別の場所に転送する。
そしてその別の場所で、もとどおりに、組み立てなおす。
そこであなたはこう考える。
見た目には、もとの人間と同じだが、しかしもとの人間は
一度死んだはず、と。
新しく再生された人間は、あくまでもまったく別の人間。
つまり転送を10回繰りかえせば、あなたは10回
死に、10回再生されたことになる。
●破壊と再生
人間の肉体は、転送という劇的な変化ではないにしても、
1年単位という時間の流れの中で、映画『スタートレック』の
中の転送と同じことを、繰りかえしている。
「劇的」というのは、映画『スタートレック』の中では、
すべてを瞬時にすることをいう。
一方、肉体のほうは、それぞれがバラバラに、長い時間をかけて、
徐々にする。
そこでもし、映画『スタートレック』の中の転送について、
あれは、「破壊」と「再生」を繰り返したもの、つまり
「一度死んで、再び、生きかえったもの」と考えるなら、
私たち自身も、同じことを繰りかえしていることになる。
「瞬時」にそれをするか、「1年」をかけてそれをするかの、
ちがいだけである。
●伝えられる意識
さらに……。
科学が進めば、(あなた)のコピー人間を作ることも、
可能になるだろう。
すでにクローン牛なども誕生している。
しかし意識は、どうか。
あなたのコピーは、あなたと同じ意識をもつだろうか。
今のところ、その答は、NO。
あなたのコピー人間は、ただのコピー人間。
たとえば私のコピーを作ったとしても、そのコピー人間が、
今の私と同じ感情をもつとはかぎらない。
というより、ありえない。
私のワイフを見て、私は逃げ回るかもしれない。
●コピー人間の意識
私が「私」と言えるのは、「意識の連続性」があるからにほかならない。
もし意識の連続性がなかったら、「私」はそのつど分断されてしまう。
たとえばクローン技術を使って、あなたのコピー人間を作ったとしよう。
見た目はもちろん、何から何まであなたと同じ人間である。
しかしそのクローン人間は、ここにも書いたように、「あなた」ではない。
意識の連続性がないからである。
同じように、先にも書いたが、あなたは日々に生まれ変わっている。
古い細胞は死に、新しい細胞が生まれる。
1年前のあなたは、どこにも残っていない。
言い換えると、今のあなたは、1年前のクローン人間といっても、さしつかえ
ない。
が、あなたはあなた。
そういうあなたは、「私は私」と言うだろう。
それが意識の連続性ということになる。
●親子
さらに言えば、親子の関係も、それに似ている。
親子のばあいは、1世代、つまり約30年をかけて、
親は自分のクローン人間を作る。
自分の子どもは、約30年をかけて作る、自分
自身のクローン人間とも考えられる。
顔や姿は、配偶者のそれと半々するということになるが、
それは大きな問題ではない。
それに意識、……このばあい、ものの考え方も、
あなたのそれに似てくる。
ただ親子のばあいは、クローン人間とはちがい、
個人差はあるだろうが、親子の間には、たしかに
意識の連続性がある。
●意識があるから私
こうして考えると、「意識」の重要性が、ますます
理解してもらえると思う。
もっと正確には、「意識の連続性」ということになる。
言うなれば、「意識の連続性があるから、私」ということになる。
「私」イコール、「意識」。
「意識の連続性」。
「意識の連続性」イコール、「私」と考えてよい。
●あやふやな意識
が、その一方で、その「意識」ほど、あてにならない
ものもない。
「私は私」と思っている意識にしても、そのほとんどが、
意識できない「私」、つまり無意識の世界で作られた
私でしかない。
意識している私は、無意識の世界で作られている私に、
操られているにすぎない。
その反対の例が、催眠術ということになる。
「あなたはキツネだ」という強力な暗示をかけられた
被験者は、目が覚めたあとも、キツネのように、
そのあたりをピョンピョンと、とび跳ねたりする。
つまり脳の中には、無数の暗示が詰めこまれていて、
それが私たちを裏から操る。
それを私たちは、「私の意識」と思いこんでいる。
・・・だけ。
意識には、そういう問題も隠されている。
●私の死
そこで再び、「死」について考える。
脳の中の意識は、脳細胞の中を走り回る電気的信号の
集合でしかない。
人間が霊的(スピリチュアル)な存在でないことは、認知症
か何かになった老人を見れば、わかる。
脳の機能が低下すれば、思考力も低下し、ついで、
意識の力も弱体化する。
「私」すら、わからなくなる老人も多い。
人間が霊的な存在であるなら、脳の機能に左右
されるということは、ありえないはず。
で、その電気的信号が止まったら、どうなるか。
それが「肉体の死」ということになる。
●すべてが消える
「死」についての説明は、これでじゅうぶんかも
しれない。
結論的を先に言えば、私たちは死によって、意識を
失う。
意識の連続性を失う。
だからこの大宇宙を意識している「私」すら、消滅する。
つまりこの大宇宙もろとも、消えてなくなる。
あなたが深い眠りの、そのまた数万倍、深い眠りに
陥った状態を想像してみればよい。
夢を見ることもない、深い眠りである。
(それでも、微量の意識は残るが・・・。)
それが「死」に近い状態ということになる。
では、「私」とは何か。
つまりそれが「意識」ということになる。
「意識の連続性」ということになる。
●意識
結論は、もう出ている。
「意識」イコール、「私」。
「私」イコール、「意識」ということになる。
が、「意識」だけでは足りない。
「私」を意識するためには、繰り返すが、そこに
「連続性」がなければならない。
意識だけなら、空を舞う蚊にすら、ある。
あの蚊に、「私」という意識があるとは、とても
思えない。
しかしその「私」は、努力によっていくらでも
大きくすることができる一方、ばあいによっては、
犬やネコどころか、虫のそれのように小さく
してしまうこともありえる。
人間は平等とはいうが、こと意識に関しては、
平等ということはありえない。
深い、浅い、の差はある。
またその(差)は大きい。
その(差)は努力によって決まる。
そうした努力を、釈迦は、「精進(しょうじん)」
という言葉を使って説明した。
●生命の伝達
そこで生きている人間の最後の使命はといえば、
「生命の伝達」ということになる。
「意識の伝達」と言い換えてもよい。
再び映画『スタートレック』の話に戻る。
もし肉体の転送だけだったら、別の肉体をもう一個、
作っただけということになる。
あなたのコピー人間を作っただけということになる。
そこで当然、意識の伝達が、重要な要素となる。
そうでないと、転送先で、それぞれが、何をしてよいか
わからず、混乱することになる。
本人も、どうして転送されたのかも、わからなくなって
しまうだろう。
与えられた使命すら、忘れてしまうかもしれない。
あなたに接する、相手も困るだろう。
(映画『スタートレック』の中では、この問題は
解決されているように見える。
しかしどういう方法で意識の連続性を保っているのか?
たいへん興味がある。)
そこで私たちは、生きると同時に、つねに意識の
伝達に心がけなければならない。
その意識の伝達があってはじめて、私たちは、
生命を、つぎの世代に伝えることができることになる。
●意識の消滅
個人の意識が途切れることは、こうした生命の
流れの中では、何でもないこと。
今、あなたが感じている意識しにしても、
あなたのほんの一部でしかない。
あなたの数10万分の1、あるいはそれ以下かも
しれない。
そんな意識が途切れることを恐れる必要はない。
●意識の伝達
それよりもすばらしいことは、あなたの生命が、
日々に、ほかの生物へと伝わっていること。
あなたの子どもに、でもよい。
ほかの生物が、日々にあなたを作りあげていくこと。
そうした生物ぜんたいの一部として、私がここにいて、
あなたがそこにいること。
つまりあなた自身も、無数の意識の連続性の中で
今を生き、そして無数の連続性を、かぎりなく
他人に与えながら、今を生きている。
●肉体の死
死ぬことを恐れる必要はない。
たとえばあなたはトイレで便を出すことを恐れるだろうか。
そんなことはだれも恐れない。
しかしあの便だって、ほんの1週間、あるいは1か月前には、
あなたの(命)だった。
その命が、便となり、あなたから去っていく。
また別の命を構成していく。
●意識の死
肉体は、1年程度で、すべて入れ替わる。
ただ同じように、意識も、そのつど入れ替わる。
このことは、1年とか、2年前、さらには10年前に書いた自分の文章を
読んでみればわかる。
ときに「1年前には、こんなことを書いていたのか?」と驚くことがある。
あるいは自分の書いた文章であることはわかるが、まるで他人が書いた文章の
ように感ずることもある。
さらに最近に至っては、まるでザルで水をすくうように、知識や知恵が、
脳みその中から、ざらざらとこぼれ落ちていくのがわかる。
それを知るたびに、ぞっとすることもある。
若い人たちには理解できないことかもしれないが、現在、あなたがもっている
知識や知恵にしても、しばらく使わないでいると、どんどんと消えてなくなって
いく。
ついでに、意識も、それに並行して、どんどんと変化していく。
何も、肉体の死だけが死ではない。
意識、つまり精神ですら、つねに生まれ、そしてつねに死んでいる。
●死とは
もし「死」が何であるかと問われれば、それは
意識の連続性の(途切れ)をいう。
しかし心配無用。
あなたの意識は、(思想)として、残すことができる。
たとえば今、あなたは私の書いたこの文章を読んでいる。
その瞬間、私の意識とあなたの意識はつながる。
私はあなたと、同じ意識を共有する。
たとえそのとき、私という肉体はなくても、意識は
残り、あなたに伝えられる。
●重要なのは、意識の連続性
反対に、こうも考えられる。
仮に肉体は別々でも、そこに意識の連続性があれば、「私」ということに
なる。
では、その意識の連続性は、どうすれば可能なのか?
ひとつの方法としては、SF的な方法だが、他人の意識を、自分の脳の
中に注入するという方法がある。
もっと簡単な方法としては、どこかのカルト教団がしているように、たがいに洗脳
しあうという方法もある。
が、自分の肉体にさえこだわらなければ、今、こうして私が自分の意識を
文章にする方法だって、有効である。
この文章を読んだ人は、肉体的には別であっても、またほんの一部の意識かも
しれないが、そこで意識を共有することができる。
それが意識の連続性につながる。
つまりこうして「私」は、無数の人と、意識の連続性を作り上げることに
よって、自分の「生命」を、そうした人たちに残すことができる。
もちろんそうした人たちも、また別の人たちと連続性を作り上げることに
よって、自分の「生命」を、そうした人たちに残すことができる。
人間は、こうして有機的につながりながら、たがいの生命を共有する形で、
永遠に生きる。
つまり「死」などは、存在しない。
繰りかえすが、個体として肉体の「死」は、死ではない。
●時空を超えて
さらに言えば、私という肉体はそのとき、ないかもしれない。
しかし時の流れというのは、そういうもの。
一瞬を数万年に感ずることもできる。
数万年を一瞬に感ずることもできる。
長い、短いという判断は、主観的なもの。
もともと時の流れに、絶対的な尺度など、ない。
寿命があと1年と宣告されても、あわてる
必要はない。
生き方によっては、その1年を100年にする
こともできる。
(年数)という(数字)には、まったく意味がない。
●大切なこと
大切なのは、今、この瞬間に、私がここにいて、
あなたがそこにいるという、その事実。
あなたの意識は、あなたの肉体の死とともに
途切れる。
しかしその意識は、かならず、別のだれかに
伝えられる。
こうしてあなたは、べつのだれかの中で、
生き返る。
それを繰り返す。
そこで大切なことは、本当に大切なことは、
よい意識を残すこと。
伝えること。
それが私たちが今、ここ生きている、最大の目的
ということになる。
●もう恐れない
さあ、もう死を恐れるのをやめよう。
死なんて、どこにもない。
私たちはこれからも、永遠に生きていく。
姿、形は変わるかもしれないが、もともと
この世のものに、定型などない。
人間の形だけが、「形」ではない。
また私たちの姿、形が、ミミズに変わったとしても、
ミミズはミミズで、土の中で、結構楽しく
暮らしている。
人間だけの判断基準で、ほかの生物を見ては
いけない。
そうそう犬のハナのした糞にさえ、ハエたちは
楽しそうに群がっている。
それが生命。
●日々に死に、日々に生まれる
私たちが日々に生き、日々に死ぬことさえわかれば、
最後の死にしても、その一部にすぎない。
何もこわがらなくてもよい。
あなたは静かに目を閉じるだけ。
眠るだけ。
それだけで、すべてがすむ。
あなたはありとあらゆる生物の(輪)の中で
生きている。
あなたが死んでも、その輪は残る。
そしてあなたはその輪の中で、この地球上に生命が
あるかぎり、永遠に生きる。
しかしそれとて何でもないこと。
なぜならあなたはすでに、毎日、日々の生活の
中で、それをしている。
繰りかえしている。
あとはその日まで、思う存分、生きること。
あなたという意識を、深めること。
つぎにつづく人や生物たちが、よりよく生きやすく
するために……。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 生命論 意識論 生命の連続性 090907)
(補記)
一気に書き上げた文章なので、随所に稚拙な部分、わかりにくい部分があるかもしれない。
今はこのままにし、しばらく時間をおいてから、推敲してみたい。
(文章の一部からでも、何かを感じとってもらえれば、うれしい。)
要するに私は、この原稿の中で、「死」を(肉体の死)と(意識の途切れ)に
分けて考えてみた。
肉体の死については、何も「死」だけが死ではない。
私たちは、毎日、死に、そして生まれ変わっている。
意識にしても、そうだ。
そこで重要なのは、(意識の途切れ)ということになる。
たしかに死によって、私たちの意識はそこで途切れるが、
だからといって、それで(意識)が死ぬわけではない。
現に今、あなたはこの文章を読んでいる。
読んだとたん、私の意識は、あなたの中に伝達されることになる。
あなたの中で生きることになる。
そして今度は、あなたは私の意識を土台に、さらに自分の意識を
発展させる。
こうして意識もまた、永遠に、生き残っていく。
そこで「死など、恐れる必要はない」と書いたが、それにはひとつの
重要な条件がある。
それは「今を、懸命に生きること」。
とことん懸命に生きること。
過去にしばられるのも、よくない。
明日に、今日すべきことを回すのも、よくない。
要するに、「死」に未練を残さないこと。
とことん燃やしつくして、悔いを明日に残さないこと。
あなたが今、健康であっても、またそうでなくても、だ。
それをしないでいると、死は、恐ろしく孤独なものになる。
人間は、基本的には、その孤独に単独で耐える力はない。
……と書きつつ、これは私の努力目標である。
いろいろ迷いや不安はあるが、とにかくその目標に
向かって進んでいくしかない。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●M町を去る(別記)
古い家だった。
家全体が、骨董品の倉庫のよう。
昔の人は、冠婚葬祭を自宅で、した。
そのときの道具が、一そろい、残っている。
奥の戸棚を開けると、古い木箱に入った道具類が、
山のように出てきた。
浜松へ持ち帰るとしても、たいへんな作業になる。
「どうしようか?」と考えているうち、GOOD IDEA!
道路脇並べて、近所の人たちに無料で、分けてやることにした。
++++++++++++++++++++
●モノを分ける
現在の貨幣価値になおして、時の祖父は、そうした道具類を
現在の価値で、何百万円も出して買ったのだろう。
茶碗といっても、本ウルシを塗った高価なもの。
金沢市の駅前のみやげもの店なら、1個、1万円前後で
売っているはず。
そういうものをビニールシートに並べる。
ほかに焼き物、花瓶、置物などなど。
「どうぞ自由にお持ち帰りください」という張り紙を張ったとたん、
4、5人の人たちが、そこに集まった。
最初は遠慮がちだったが、やがて大きな袋をもってくる人もいた。
うれしかった。
私からのプレゼントというよりは、私の祖父母、両親からのプレゼント。
祖父母や両親が、「気前のいい話やなあ」と、どこかで笑っているような
気がした。
●モノ
モノとは、所詮、そんなもの。
価値があるようで、ない。
あるとしても、思い出。
私の過去は、そうしたモンと、深くからんでいる。
それぞれのものを手に取ってみては、「ああ、これはあのときの
もの」と。
しかし時間的にも感傷に浸っている時間はない。
11時半から、実家の売買契約。
2時から、法事。
3時から、古物商との商談。
そして5時には、運送会社がやってくる。
●価値
古物の価値が、さがってきている。
たとえば切手にしても、古銭にしても、売り先を見つけるのさえ難しい。
ネットでオークションに出すという方法もあるが、そのための
時間がない。
ということで、そのまま宝の持ち腐れ?
そこで改めて、ふと考える。
私は先日、古いパソコンを、6〜7台、処分した。
「古い」といっても、10年ほど前のもの。
当時でもパソコンは、1台20万円前後はした。
ことパソコンに関して言えば、骨董的価値はない。
そのままゴミ。
となると、祖父が買った茶器類と、私の買ったパソコン類と、
どちらが(価値)があるか、と。
あるいは(価値)を考えること自体、まちがっているのか。
たとえば茶器にしても、プラスチック製のものよりは、ウルシ塗りの
もののほうが、作るのに手間がかかる分だけ、値段が高い。
値段が高いから、価値があるということになる。
しかしそこでハタと考えてしまう。
「だから、それがどうしたの?」と。
●見るモノと、使うモノ
一方、パソコンのほうは、それなりの(仕事)をした。
言うなれば骨董品のほうは、(見る)もの。
パソコンのほうは、(使う)もの。
(使う)という視点で価値を判断するなら、数年の1度しか
使わない茶器より、毎日使うパソコンのほうが価値がある。
(価値といっても、金銭的価値だが……。)
だから10年を経て、それが20万円で買ったものであったと
としても、棄てても悔いはない。
が、ウルシの茶器は、そうでない。
棄てることはできない。
が、骨董屋に売るとなると、二束三文。
だったら、近所の人たちに、無料で分ける。
そのほうが、ずっと気持ちがよい。
Hiroshi Hayashi++++++++SEP.09+++++++++はやし浩司
●9月X日、運命の日
+++++++++++++++++
現在の心境。
たいへん軽い。
刻一刻と、時が流れていく。
その音が、やさしいせせらぎのように、
心地よく心に響く。
うれしい。
9月X日。
私は、古里と決別する。
待ちに待った、その瞬間。
それがやってくる。
もちろん不安がないわけではない。
どんな別れにせよ、(別れ)というのは
そういうもの。
いつも不安がともなう。
あえて言うなら、『モヤのかかった
山の頂上に、朝日を見るような』
(シェークスピア)のような心境。
++++++++++++++++
●実家を売る
結局、間に立ってくれた人が、「自分でほしい」と言ってくれた。
譲渡価格は、問題ではない。
いくらでもよい。
とにかく買ってくれる人がいたら、それでよい。
そう思って、その人に、売買を一任した。
で、その人自身が、買ってくれることになった。
その人の言い値で売ることにした。
母に直接渡した現金の10分の1にもならない。
しかしそれで(過去)から解放されるなら、文句はない。
いうなれば、人生の(おまけ)。
バンザーイ!
●貧乏
私が実家を(重荷)に感じ始めたのは、小学5、6年生くらいの
ことではなかったか。
記憶は確かではないが、中学生になるころには、はっきりとそれを
自覚するようになった。
今にして思えば、そういう重圧感を作ったのは、母自身ということになる。
母は私に生まれながらにして、「産んでやった」「育ててやった」「親のめんどう
みるのはお前」と、言いつづけた。
それが母の教育の基本法だった。
加えてそのころから、稼業の自転車店は、ほとんど開店休業状態。
パンク張りの日銭で、何とかその日をしのいでいるという状態だった。
今になって実家は、町の「伝統的建造物」に指定されている。
大正時代の商家そのままという。
しかし何も好き好んで、伝統的建造物を守ったわけではない。
改築するお金もないまま、ズルズルと今に至っただけ。
言うなれば、慢性的貧乏。
その象徴が、私の実家。
わかりやすく言えば、そういうことになる。
●保護と依存
(この間、半日が過ぎた。
私は今、実家へ向かう電車の中にいる。
時は9月2日、午前7時40分。)
要するに保護と依存の関係。
それができてしまった。
保護する側はいつも保護の側に回る。
依存する側は、いつも依存する側に回る。
最初は感謝されることはあっても、それは一時的。
やがてそれが当たり前になり、さらに時間がたつと、相手、つまり
依存する側が、保護する側に請求するようになる。
「何とかしろ」と。
さらに時間がたつと、保護する側は、今度は、それを義務に感ずる
ようになる。
こうしてつながりそのものが、保護と依存の関係が結ばれたまま、
固定化する。
●解放
今の私の立場を一言で表現すれば、「何もかも私」という状況。
だれというわけではないが、みな、そう思っている。
私自身もそう思っている。
そういう中で、みなは、ジワジワと私に迫ってくる。
私はそれにジワジワと苦しめられる。
が、それが今日という日を境に、終わる。
私は何もかもから解放されたい。
何もかもから、解放される。
法事の問題、墓の問題も、あるにはある。
あるが、いくらでも先延ばしにできる。
●ドラマ
ところで昨日、郷里住むいとこと、2回、電話で話した。
どちらも1時間以上の長電話になった。
「明日、M町とは縁を切ってきます」と告げると、「それはよかったね」と。
で、私は自分の心にけじめをつけるつもりで、今までの心境を語った。
弁解とか、言い訳とか、悪口とか、そういうのではない。
今さら私が苦しんだ話など、だれも聞きたがらない。
話しても意味はない。
いとこはいとこで、自分の経験を、あれこれとしてくれた。
それが参考になった。
心に染み入った。
懸命に生きてきた人には、懸命に生きてきた人のドラマがある。
私にもある。
そのドラマが、今、光り輝く。
●社会的重圧感
金銭的負担感というよりは、社会的負担感。
負担感というよりは、重圧感。
40歳を過ぎるころから、私はそれに苦しんだ。
貪欲なまでに、私のお金(マネー)を求める母。
といっても、そのころになると、そのつど母は、私を泣き落とした。
一方、私は私で、いつしか、そういう母のやり方に疑念をもつようになった。
疑念をもちながら、それでも仕送りを止めるわけにはいかない。
それが社会的負担感を増大させた。
実家へ向かうたび、私はどこかで覚えた経文を唱えずして、帰る
ことができなかった。
●不安
が、不安がないわけではない。
親類がもつ濃密な人間関係は、ほかのものには換えがたい。
それを断ち切るには、それ自体、たいへんな勇気が必要。
断ち切ったとたん、そこに待っているのは、孤立感。
「私にはその孤立感と闘う力はあるのか」と、何度も自問する。
……というより、この10年をかけて、少しずつ、親類との縁を
切ってきた。
幸い、その分だけ、ワイフの兄弟たちとは、親しくさせてもらっている。
心の穏やかな、やさしい人たちである。
息子たちの結婚式など、そのつど、みな協力してくれた。
その温もりが、こういうときこそ、私を横から支えてくれる。
●真理
そう言えば、今朝、目を覚ましたときのこと。
私の心がいつもになく、穏やかなことを知った。
たいてい……というより、ほとんど毎朝、私は旅行の夢で目が覚める。
が、今朝はちがった。
夢の内容は忘れたが、あのハラハラした気持ちはなかった。
そのかわりに、郷里の人たちが、みな、小さな、どこまでも
小さな人間に思われた。
つい昨夜まで、心を包んでいたあの緊張感が、消えた。
「どういうことだろう?」と、自分に問いかけた。
いや、ときどき、そういうことはある。
あるひとつのことで、緊張感が頂点に達したとき、突然、
目の前に、別の世界が広がる。
ひとつの(山)を乗り越えたような気分である。
たとえば人を恨むことは、よくない。
しかし恨みも頂点に達すると、やがて心の水が枯れる。
枯れたとたん、その人を、別の心で包み込むことができる。
あマザーテレサも、同じようなことを言っている。
『愛して、愛して、愛し疲れるまで、相手を愛せよ』と。
私はそこまで高邁な心境になることはできないが、マザーテレサの
言葉には、いつも真理が隠されている。
●運命
そんなわけで、今、苦しみのどん底にいる人たちに、こんなことは
伝えられる。
どんな問題でも、相手が人間なら、時間がかならず解決してくれる、と。
解決してくれるだけではない。
『時間は心の癒し人』。
心も癒してくれる。
だからそこに運命を感じたら、あとは静かに身を負かす。
(運命)というのは、それに逆らえば、牙をむいて、その人に襲いかかってくる。
しかしひとたび受け入れてしまえば、尻尾を巻いて逃げていく。
もともと気が小さい。
臆病。
私もある時期、母を恨んだ。
心底、恨んだ。
しかし私の家に住むようになった直後のこと。
下痢で汚れた母の尻を拭いたとたん、その恨みが消えた。
「こんなバーさんを、本気で相手にしていたのか」と。
と、そのとき母は私にこう言った。
「お前にこんなことをしてもらうようになるとは思わないんだ」と。
それに答えて、私も、「ぼくも、あんたにこんなことをしてやるように
なるとは、思っていなかった」と。
まだ正月気分も抜けやらない、1月のはじめの日のことだった。
●こうして人生は過ぎていく
こうして人はやってきて、またどこかへと去っていく。
M町にしてみれば、私はただの通行人。
店先をのぞいて、そのまま通り過ぎる、通行人。
あの実家にしても、明日からは別の人が住み、別の生活が始まる。
みやげもの屋、もしくは町の案内所としては、最適。
実家は実家で、また別の人生を生きる。
あたかも何ごともなかったかのように……。
私「M町へ、再び行くようなことはあるだろうか」
ワ「……何か、あればね。今のあなたの気持ちとしては、もう
ないでしょうね」
私「何もなければいいけどね。行くとしても、素通りするよ」
ワ「そうね」と。
電車は、豊橋を過ぎると、少しずつ混み始めた。
ちょうどラッシュアワーに重なった。
「名古屋を過ぎれば、またすいてくるよ」と私。
不思議なほど、心は静かなまま。
フ〜〜〜ッと。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●夢判断
++++++++++++++++++++
夢判断というのは、たしかにある。
私にとっては、2009年9月2日は、心の大きな転機になった。
そのせいだろうと思うが、その日を境に、夢の内容が、がらりと変わった。
それまでは夢といえば、旅行先の夢ばかりだった。
どこかの旅館やホテルにいて、帰りのバスや飛行機の時刻を心配する
そんな夢ばかりだった。
おかしなことに、夢の、こまかい部分については、そのつど、ちがった。
同じ内容の夢を見ることは、ほとんどない。
が、9月3日は、忘れたが、旅行の夢ではなかった。
9月4日は、兄の夢。
9月5日も忘れたが、旅行の夢ではなかった。
9月6日、つまり今朝は、浜松の自宅に、生徒たちが遊びに来た夢。
夢の内容を判断するかぎり、私の心境は、大きく変化した。
++++++++++++++++++++
●深層心理
心の奥底にあって、人間の意思や意識をコントロールする。
それが深層心理ということになる。
人間のばあい、(人間だけにかぎらないのだろうが)、深層心理のほうが分量的にも、
はるかに大きい。
一説によれば、脳の中で意識として活動している部分は、脳全体の20万分の1
程度という。
何かの本でそう読んだ。
つまり私たちの意識は、その20万倍もの無意識や潜在意識によって支配
されている。
私が毎晩、ちがった夢を20年間見たとしても、365x20=7300。
20万倍には、遠く及ばない。
わかりやすく言えば、私たちの意識は、常に、無意識や潜在意識によって
支配され、コントロールされている。
私が旅行先の夢を見るのは、焦燥感、不安感、心配、不信感などが、ベース
になっているからと考えてよい。
が、それが消えた。
●墓参り
そのうち心境が変化するかもしれない。
しかし今の私には、墓参りをするという意識そのものがない。
祖父も、父も、墓参りだけは、したことがない。
墓参りした姿さえ、私の記憶にない。
理由はわからない。
が、墓参りを大切にしている人もいる。
人は、人それぞれだし、それぞれの思いの中で、墓参りをする。
私がしないからといって、それでもって他人のことをとやかく言っては
いけない。
が、同時に、自分が墓参りするからといって、私のことをとやかく言って
ほしくはない。
私は、私。
それでバチ(?)なるものが当たるとしたら、それは私のバチ。
あなたには関係のないこと。
ただ言えることは、合理的に考えれば、遺骨に霊(スピリチュアル)が
宿るということは、ありえない。
人間の肉体は、骨も含めて、常に新しく生まれ、そして死ぬ。
もし魂が宿るとしたら、むしろ脳みそということになる。
心臓でもよい。
しかし脳みそや心臓は、保存には適さない。
だから「骨」あるいは「髪の毛」ということになった。
言うなれば、人間のご都合主義が、「骨」にした。
●それぞれの思い
話はそれたが、墓参りを熱心にする人というのは、何かしらの
(わだかまり)が、心の奥にあるためではないか。
罪滅ぼし?
懺悔?
後悔?
うしろめたさ?
何でもよい。
こう決めてかかると、墓参りを熱心にしている人に対して失礼な
言い方になるかもしれない。
多くの人は、故人をしのび、故人を供養するために、墓参りをする。
「先祖を祭り、大切にするため」と主張する人もいる。
それはそれでわかる。
しかし私は墓参りも、自然体でよいのではないかと考える。
参りたいと思うときに、参ればよい。
もちろんそれぞれの思いに従えばよい。
罪滅ぼしであっても、また故人の供養でもよい。
ただ遺骨に、必要以上の意味をもたせることは、好ましいことではない。
もっと言えば、墓参りをすることによって、「今」そのものを見失って
しまう。
こんな女性(60歳くらい、当時)がいた。
その女性の母親が生きている間は、虐待に近い虐待を繰り返していた。
で、その母親は、ある寒い冬の夜、「ふとんの中で眠ったまま」(その
女性の言葉)、死んでしまった。
その女性の墓参りがつづくようになったのは、しばらくしてからのこと
だった。
一説によると、夜な夜な、母の亡霊が枕元に立ったからという。
あるいはその女性は、罪の意識に苛(さいな)まれたのかもしれない。
それで墓参りをするようになった(?)。
よくある話である。
●今が大切
死者を弔うことも大切だが、それ以上に、はるかに大切なことは、
「今」を大切にすること。
これは私の人生観とも深くからんでいるが、母を介護しているときにも、
それを強く感じた。
介護といっても、そのつど、多額の介護費用などがかかる。
救急車で病院へ一度運んでもらえば、救急車代は別としても、1回につき、
10万円前後の検査費、入院費、治療費がかかった。
しかしそういう費用が、惜しいとか、そういうふうに考えたことは一度も
ない。
「高額だな」と反感を覚えたことはあるが、それは医療体制に対しての
ものであって、母に対してではない。
しかし今、法事に、読経をしてもらうだけで、1回5万円ということに
ついては、矛盾というより、バカらしさを覚える。
信仰心のあるなしとは、関係ない。
まただからといって、母の死を軽んじているわけでもない。
この落差というか、(心の変化)を、どう私は理解したらよいのか。
同じように、私は、「今」を生きている。
懸命に生きている。
もし息子たちに、私やワイフを大切にしてくれる気持ちが少しでもあるなら、
今の私たちを大切にしてほしい。
死んでから、墓参りに来てくれても、うれしくはないし、またそんな
ことをしてくれても、私には意味はない。
またそれで私が地獄へ落ちるとしたら、仏教のほうがまちがっている。
カルト以下のカルト。
供養するかしないかは、あくまでも(心)の問題。
心があれば、毎日だって墓参りをすればよい。
また心があるなら、墓参りなどしなくても、どこにいても、供養はできる。
この3日間、いろいろと考えた。
私には、収穫の多い、3日間だった。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●決別、5日目
++++++++++++++++
古里と決別して、今日で5日目。
この4日間、いろいろあった。
そのせいか、今日になって疲れが
どっと出てきた。
ショックだったのは、むしろ
仲がよかった、K氏(59歳)が、
悪性リンパ腫になっていたこと。
血液のがんである。
今年で闘病生活も3年になるという。
知らなかった。
昨日、はじめて知った。
驚いたというより、3年間も
知らなかった私に、驚いた。
「最近はすぐれた抗がん剤も開発
され、数値をみながらのんでいれば、
何でもありません」と、K氏は笑っていた。
いっしょに笑いたかったが、私は
笑えなかった。
+++++++++++++++
●「私は健康だ」
「私は健康だ」と言うときには、そこにある種の優越感がともなう。
自分にはその気がなくても、相手によっては、それがイヤミに聞こえる。
とくに重病で苦しんでいる人には、そうだろう。
だから「私は健康だ」などとは、あまり人に言わないほうがよい。
それはちょうど、「私は金持ちだ」と言うのに似ている(?)。
その日の生活費に困っている人が聞いたら、どれほど不愉快に思うことか。
……といっても、つまり健康といっても、今、そうであるというだけで、
明日のことはわからない。
加齢とともに、不可逆的に健康は衰えていく。
仮に優越感をもったとしても、それは一時的。
大切なことは、今ある健康を、かみしめながら生きていくこと。
あとはその状態を、できるだけ、長く保つこと。
●苦痛
古里の話を書こうと思っていたが、健康論になってしまった。
話をもどす。
古里と決別して、先にも書いたように今日で5日目になる。
何かが大きく変わったように感ずる。
が、それが何であるか、今のところ、まだよくわからない。
平和になったというか、気が抜けたというか……。
心の緊張感は解けた。
正直に告白するが、実兄が死んだときも、実母が死んだときも、
私はホッとした。
実兄や実母の死を喜んだわけではない。
そんな気持ちは、みじんもなかった。
ただそれまでの重圧感には、ものすごいものがあった。
臨終が近づくにつれて、その重圧感が、さらに倍加した。
その重圧感が、スーッと消えた。
実のところ、実兄も実母も、それぞれ施設に入居していたから、
私への負担は、ほとんどなかった。
精神的負担も、ほとんどなかった。
ときに、「介護が、こんなに楽でいいのか」と思ったことさえある。
私が感じた重圧感というのは、実姉からのものだった。
実姉は、そのつど、狂ったように、私のところに電話をかけてきた。
それが苦痛だった。
受話器を取るたびに、手が震えた。
今にして思えば、姉は姉で、張りつめた緊張感の中で、もがき苦しんで
いたのだろう。
それはよくわかる。
わかるが、私には、どうしようもなかった。
実姉は、不満や不安をそのまま、私にぶつけた。
私は私で、包容力を失っていた。
が、それも今となっては、昔話。
1日ごとに、どんどんとそれが過去へ過去へと、遠ざかっていく。
●疲れ
講演の疲れ。
旅の疲れ。
それが今日になって出てきた。
睡眠薬の世話になっているわけでもないが、このところ毎日、9〜10時間
近く眠っている。
昼間も眠い。
そのつど、軽い昼寝をする。
寝心地は、よい。
どこにいても、気持ちよくうたた寝できる。
何よりも大きな変化は、悪夢から解放されたこと。
●今後のこと
今後のことは考えていない。
考えても、あま意味はない。
なるようにしか、ならない。
なり行きに任せる。
それしかない。
実家にまつわる問題は、すべて解決した。
「すべて」だ。
親戚づきあいも、今のところ、するつもりはない。
冠婚葬祭も、遠慮させてもらう。
その前に、だれも知らせてこないだろう。
そのかわりというわけでもないが、私の方のことも、だれにも伝えない。
「私が死んでも、親戚にはだれにも話すな」と、ワイフや息子たちには、
しっかりと伝えてある。
親戚など、今の私には、「クソ食らえ」(尾崎豊)、だ。
さみしい関係だが、仮面をかぶってつきあうのも、疲れた。
もうたくさん。
いや、それ以上に、私の人生も、刻一刻と短くなっていく。
そうそう、K氏の病名を聞いたとき、驚いたのには、
もうひとつの理由がある。
「そんな病気もあったのか!」と。
ひょっとしたら、病名の数のほうが、浜松市の人口(約80万)より
多いのではないか?
がんにしても、体の部位の数だけ、種類がある。
「病気から身を守る」といっても、どうやって守ればよいのか。
たとえて言うなら、浜松中の人たちが、みな悪党になったようなもの。
しかもみな、中身がちがう。
先日は、ほんの半時間ほどだが、視覚野の画像が乱れた。
半円形のチカチカした模様が、視野をじゃました。
あれはいったい、どういう病気によるものなのか?
言い換えると、私たちの健康は、細い糸でぶらさがっているようなもの。
その下では、無数の病気が、「おいで、おいで」と、手招きしている。
で、私はK氏にこう聞いた。
「どうして、その病気とわかったのですか?」と。
それについてK氏は、こう言った。
首の下のリンパ腺が腫れたこと。
胃の上に腫れ物ができたこと。
それで病院へ行ったら、悪性リンパ腫とわかった、と。
そして最後にこう話してくれた。
「おかしいと思ったら、検査だけは、どんどんと受けたほうがいいですよ」と。
しかし……。
おかしいと言っても、おかしなところだらけ。
一応、今のところ自分では健康とは思うが、中身はボロボロ。
何とかごまかしながら生きている。
だからやはり、検査は受けたくない。
受けても、しかたない。
20も30も、ゾロゾロと病名が出てきたら、どうするのか!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 7日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page018.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●英語のジョーク
++++++++++++++++++++
オーストラリアの友人のBob君が、こんなおもしろい
ジョークを集めてくれました。
(Thank you Bob!)
++++++++++++++++++++
先生「マリア、地図のところへ行って、北アメリカがどこにあるか、見つけてきなさい」
マリア「(指をさしながら)、ここです」
先生「そうです。では、みなさん、だれが北アメリカを発見したか、知っていますか」
生徒たち「マリア!!」
KIDS ARE QUICK:
TEACHER: Maria, go to the map and find North America.
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America?
CLASS: Maria.
先生「どうしてあなたはかけざんを、床の上でしているの?」
ジョン「だって先生が、テーブル(机、掛け算表)を使ってしてはいけないと
言ったから」
TEACHER: John, why are you doing your math multiplication on the
floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.
先生「グレン、あなたはワニは、どういうふうに綴るのですか」
グレン「KROKODIAL」
先生「あなたはまちがっている」
グレン「わかっている。でも、先生は、ぼくがどう綴るかを聞いたでしょ」
TEACHER: Glenn, how do you spell 'crocodile?'
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L'
TEACHER: No, that's wrong
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.
(I Love this kid)
先生「ドナルド、水の分子式を言いなさい」
ドナルド「HIJLLMNOです」
先生「何を言っているの?
ドナルド「だって、先生、先生は昨日、水は「H to O(HからOまで)と
言ったじゃない」
TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it's H to O.
先生「ウィニー、私たちが10年前にもっていなかった、重要なものを言いなさい」
ウィニー「私!」
TEACHER: Winnie, name one important thing we have today that we
didn't have ten years ago.
WINNIE: Me!
先生「グレン、どうしてあなたはいつも、そんなに汚れているの?」
グレン「先生より、ぼくのほうが地面に近いからです」
TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I'm a lot closer to the ground than you are.
++++++++++++++++++++++++++++++++
【名言集】
I CAN:
When I offend, I prefer it to be intentional.--Scott Adams
私は怒ったとき、よりい国際的になることを好む。
The last time I had a 36-inch waist was in the 8th grade.--John Madden
ぼくのウエストが、最後の36インチになったのは、中学2年生のときだ。
Drug misuse is not a disease; it is a decision, like the decision to move
out in front of a moving car.--Philip K Dick
ドラグの使用は病気ではない。それは心の決意の問題だ。
動いている車の前に飛び出すような決意だ。
++++++++++++++++++++++
FUNNY FORWARDS:
An invisible man marries an invisible woman. The kids were nothing to look
at either.
透明人間の夫が透明人間の妻と結婚した。
その子供たちは、何も見えなかった。
Two cannibals are eating a clown. One says to the other: 'Does this taste
funny to you?'
2人の人食い人種が、道化師を食べた。
1人がもう1人に言った。
「おもしろい味がしたかい?」
P.S. what do you call a fish with no eyes? A fsh!
目(アイ)のない魚(FISH)は、何と呼ぶか、知っているか?
答え……「FSH」
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●本音と建前
+++++++++++++++++++
学生時代、オーストラリアの人たちはみな、
私に親切だった。
あの人口300万人と言われたメルボルン市でさえ、
日本人の留学生は、私、1人だけ。
もの珍しさもあったのかもしれない。
が、あるとき、どういうきっかけかは覚えていないが、
こう感じたことがある。
「友人としてつきあう分については、そうかもしれないが、
一線を越えたらそうではないだろうな」と。
++++++++++++++++++++++
●社会的距離尺度(ボガーダス)
たとえば(結婚)。
(友人)としての範囲なら、親しく接してくれるオーストラリアの人たち。
しかしその範囲を越えて、たとえば(結婚)となったら、どうだろうか。
当時の状況からして、それはありえないことだった。
1970年当時、白豪主義は、残っていた。
日本人は、まだ第二級人種と位置づけられていた。
仮に相手がオーストラリア人であっても、第二級人種と結婚したばあい、
そのオーストラリア人も、第二級人種に格下げされた。
こうした距離感を、「社会的距離尺度」(ボガーダス)という。
つまり表面的には受容的であっても、内面では、否定的。
その距離感のことをいう。
日本的に考えれば、(本音)と(建前)ということになる。
●心の遊び
日本人には、うつ病の人は少ないと言われている。
その理由のひとつに、日本人の心がダブル構造になっていることが
あげられる。
(本音)と(建前)というのが、それ。
表と裏を、うまく使い分ける。
それが心に穴をあける。
一方、それに比較して、欧米人は、なにごとにつけ、ストレート。
日本的に本音と建前を使い分けると、「うそつき」というレッテルを
張られる。
その分だけ、心の(遊び)がない。
だからうつ病になりやすい。
●本音で生きる
が、できれば、日本人の私たちも、できるだけ本音で生きるように
したい。
本音と建前を分ければ分けるほど、外から見ると、訳の分からない民族
ということになる。
その典型的な例というわけでもないが、よく話題になるのが、日本人の
(笑い)。
よく電車に乗り遅れたような人が、プラットフォームで苦笑いするような
ことがある。
ああした(笑い)は、欧米人には理解できないもの。
最近ではぐんと少なくなったが、デッドボールを当てたピッチャーが苦笑いを
するのもそれ。
内心と表情が、別々の反応を示す。
いやなヤツと思っていても、ニコニコと笑いながら接する。
そういう場面は多い。
しかしそういう生き様は、時分自身を見苦しくする。
あとで振り返っても、後味が悪い。
●「自分の心を偽るな!」
平たく言えば、「どうすれば社会的距離尺度を、短くすることが
できるか」ということ。
で、私はここ1年ほど、子どもたちを指導しながら、こんなことに
注意している。
幼稚園の年中児でも、「君たちは、おっぱいが好きか?」と聞くと、
みな、恥ずかしそうな顔をして、こう言う。
「嫌いだよ〜」「いやだよ〜」と。
そこですかさず私は、真顔で、子どもたちを叱る。
「ウソをつくな!」「好きだったら、好きと言え!」
「自分の心を偽るな!」と。
2、3度、真剣にそう叱ると、子どもたちはみな、
「好きだよ〜」と、小さな声で答える。
つまり日本人独特の、本音と建前は、こうして生まれ、
子どもたちの心に根付く。
(少し大げさかな?)
●本音で生きよう
本音で生きるということは、勇気がいる。
しかしその分だけ、人生がわかりやすくなる。
すがすがしくなる。
自分を飾ったり、ごまかしても、後味が悪いだけ。
どうせ一回しかない人生。
だったら、思う存分、本音で生きてみる。
ものを書く立場で言うなら、ありのままをありのままに書く。
こう書くからといって、誤解しないでほしい。
読者あっての(文章)だが、私は、読者など、もうどうでもよい
とさえ思っている。
読んでくれる人がいるなら、それでよし。
読んでくれなくても、どうということはない、と。
どう判断されようが、私の知ったことではない。
大切なことは、こうして懸命に生きている人間がいること、
……過去にいたことを、何らかの形で、だれかに伝えること。
それができれば、御の字。
それ以上、何を望むことができるか?
話はそれたが、本音で生きるということには、そういう意味も
含まれる。
余計なことかもしれないが……。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●伊豆・熱川(あたがわ)温泉にて
+++++++++++++++++
今日は、講演のつづきで、伊豆の熱川温泉に泊まった。
きびしい海岸線にへばりついたような温泉街で、いたるところから白い蒸気が立ち上って
いるのがわかった。
ホテルに着くと私たちはすぐ、海岸へ出てみた。
やや荒い波が、黒っぽい砂浜に絶え間なく、打ち寄せていた。
何組のかの若い男女が、波と戯れていた。
私は、DVDカメラを回しつづけた。
泊まったホテルは、「ホテル・セタスロイヤル」。
「セタス」というのは、「クジラ座」という意味だそうだ。
駅からホテルまで運んでくれた運転手が、そう教えてくれた。
この地域は、何かのことでクジラと縁があるらしい。
9階の私たちの部屋から、そのまま太平洋が一望できた。
すばらしい!
ワイフは、「私は海が好き」と、子どものようにはしゃいでいた。
+++++++++++++++++++++
●セタスロイヤル
実名を出してしまったので、評価することはできない。
しかし熱川温泉では、海に面した、見晴らしのよさでは、最高のホテル。
各部屋から、太平洋が、視界が届く限り、端から端まで、一望できる。
加えて6階にある露天風呂がすばらしい。
広くて、美しい。
ただ露天風呂までの通路が長いのが、やや気になる。
寒い冬などは、それだけで体が冷えてしまうだろう。
が、長い通路を通りぬけて行くだけの価値はじゅうぶん、ある。
私たちはそのホテルの最上階、つまり9階に部屋にあてがわれた。
で、このところ私たちは、ほかにホテルがあっても、その土地へ行ったら、
できるだけ同じホテルに泊まるようにしている。
新しいところで冒険するより、勝手がよくわかったホテルのほうが、落ち着く。
2度目より3度目。
3度目より4度目のほうが、落ち着く。
次回、何かの機会で熱川温泉へ来るようなことがあれば、まちがいなくセタスロイヤルに
泊まるだろう。
●旅のよさ
人生を旅に例える人は、多い。
たしかに旅だ。
もう少し詳しく表現すれば、人生は、(時の旅)。
旅は、(位置の旅)。
時間と空間のちがいということになるが、今では、時間と空間は、物理学の世界では、
「同じ」と考える。
たとえば時間が止まれば、物体の移動も止まる。
時間が動き出せば、物体もまた動き出す。
見た目には静止していても、分子レベルでは、猛烈な勢いで動き出す。
私たちは位置を移動することによって、そこに時間の動きを感ずることができる。
わかりやすく言えば、(変化)を感ずることができる。
(時間の変化)を感ずることができる。
その時間の変化を感ずるために、旅をする。
●時間の変化
わかりにくいことを書いた。
理屈っぽくすぎて、「?」と思った人も多いことだろう。
つまり旅をすることによって、それまで止まっていた時計が、
再び動き出す。
時間の変化を感ずることができる。
もし旅をしなかったら、今日は昨日のまま過ぎ、明日は今日のまま過ぎる。
「マンネリ」という言葉も、そういうときの状態を表現するためにある。
わかりやすく言えば、そういうこと。
が、旅は、その時の流れに、ひとつの区切りを入れてくれる。
今日と昨日の間に、区切りを入れてくれる。
今日と明日の間に、区切りを入れてくれる。
今度の旅は、確実に、その区切りを入れてくれた。
●朝、5時に起床
朝、5時に目が覚めた。
昨夜は、午後9時半ごろ、それまでの疲れがどっと出たのか、そのまま眠ってしまった。
それで5時。
静かにカーテンをあけると、そこに再び、太平洋が現れた。
窓を開けると、潮騒の音が、部屋中に響いた。
空はほんのりと、ピンク色。
紫色の雲が、左から右へと、ゆっくりと流れているのがわかる。
その下を細いひだになった波が、手前へと流れている。
壮大な景色である。
水平線だけの、壮大な景色である。
私はDVDを回し、つづいてカメラのシャッターを切る。
午前5時26分。
日の出。
真っ赤な、小さな光点が、水平線から顔を出す。
●リバウンド?
伊東もよい。
稲取もよい。
しかしここ熱川もよい。
伊豆半島の東岸には、すばらしい温泉地が並ぶ。
近く、下田の市民文化会館で、講演をすることになっている。
そのときは、下田市に一泊するつもり。
楽しみ。
そうそう昨夜は料理で、一夜にして、3日分を食べた。
量的には、それくらいあった。
あとで体重計に乗るのがこわい。
おそらく63キロ台に戻っているはず。
私は食べたら、食べた分だけ太る。
今日は、がまんして、絶食。
(浴場にあった体重計に乗ってみたら、意外や意外!
体重は、60キロを切っていた!
「?」と思いながら、数回、量りなおしてみる。
私は講演期間中は、食事の量を極端に減らしている。
講演中に眠くなってしまう。
今日も、口にしたのは、稲荷寿司、数個だけだった。
リバウンドしていなかったことを、喜んだ。)
●心の整理
ワイフが楽しそうなのが、うれしい。
家の中で見るワイフと、旅先で見るワイフは、別人のよう。
昔から、「電車に乗っているだけで、楽しい」と、口癖のように言う。
一方、私は実家の問題が、解決した。
実家から解放された。
ついでに姉夫婦とも、xxした。
いろいろあった。
ありすぎて、ここには書けない。
それに書けば、いろいろと問題になる。
姉の娘が、ときどき私のHPをのぞいている。
のぞいては、内容を、あちこちに知らせている。
ただできるなら、もう私たちのことは、放っておいてほしい。
気になるのはわかるが、あなたがたはあなたがたの人生を生きればよい。
私の家の心配をするよりも、あなたがたの家の心配をしたほうがよいのでは・・・?
このままでは・・・?
この先のことは、あなたがたが、いちばん、よく知っているはず。
私が何も知らないと思っているのは、あなたたちだけ。
(わかりましたか、SRさん、それにMSさん!)
ともかくも、今は病気に例えるなら、病後の養生期。
ゆっくりと静養して、つぎの人生に備える。
●新しい人生
こうして私の新しい人生は、始まった。
太平洋に昇る朝日を見ながら、それを感じた。
老後なんて、私には関係ない。
これからが私の人生。
今まで苦しんだ分だけ、自由に、この大空をはばたいてみたい。
今日が、その第一歩。
2009年9月6日、日曜日。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●運命(Destiny)
++++++++++++++++++++
無数の(糸)がからんで、ときにその人の
進む道を決めてしまう。
社会の糸、家族の糸、生い立ちの糸などなど。
それを「運命」という。
が、「運命」は、自分で作っていくもの。
一見矛盾した考えに思う人もいるかもしれない。
自分の力では、どうにもならない力を運命という。
「しかしその運命は、自分で作るものとは、どういうことか」と。
しかしそのときは、こう考えたらよい。
その「糸」は、ふつうは見えない。
見えないが、自分のことがわかればわかるほど、
それが見えてくる。
それが見えるか見えないかは、その人自身の(視野の広さ)による。
視野さえ広めれば、そこにある(糸)が見えてくる。
糸さえ見えれば、自分で自分の運命をコントロールすることができる。
自分の運命を、自分で作ることもできる。
作り変えることもできる。
++++++++++++++++++++
●たとえば
たとえばこんな例で考えてみよう。
もちろんここに登場する母親は、架空の女性である。
いろいろなケースを、ひとつにまとめた。
●子どもの非行
最初に断っておく。
子どもが非行に走ったからといって、子育てに失敗したということではない。
今どき、非行など、珍しくも何ともない。
もう少しマクロな見方をすれば、まじめで(?)、何ごともなく青春期を過ごした
子どもほど、あとあと何かと問題を起こすことがわかっている。
あれこれと非行を経験した子どものほうが、のちのち常識豊かな子どもになる。
教育の世界では常識。
「教育がしにくい」というだけで、ほかに問題があるわけではない。
(だからといって、非行を奨励するわけでもないが……。)
●母親の視野
が、視野の狭い母親ほど、自分の子どもが何かの事件を起こしたりすると、
あわてふためく。
ギャーギャーと泣き叫んで、大騒ぎをする。
そして本来なら、軽く乗り越えられるような問題まで、より深刻にしてしまう。
こんな例で考えてみよう。
●3人も強制退学
その母親には、3人の子どもがいた。
上から、(男)(女)(男)である。
が、3人とも、高校生のとき、強制退学。
それぞれが傷害事件を起こした。
こういうケースのばあい、まず疑ってみるべきは、母親の育児姿勢。
1例とか2例なら、同じようなことがつづくことはある。
しかし3例ともなったら、原因は、環境にあるとみる。
なかんずく母親の育児姿勢にあるとみる。
が、残念なことに、その母親には、それを理解するだけの知的能力がなかった。
いや、自分では、「賢い、頭のいい女性」と思い込んでいた。
繰り返すが、子どもが強制退学になったからといって、「失敗」という
ことではない。
子どもたちに問題があったということでもない。
●夫の責任
子育てで何がこわいかといって、親の独善と独断ほど、こわいものはない。
その母親のばあいも、住んでいる世界そのものが、小さかった。
それに自分と同じレベルの人だけの世界で住んでいた。
が、それでいて、先にも書いたように、「私は賢い、頭のいい女性」と思い込んでいた。
で、こういうケースのばあい、そばにいる夫が妻を指導しなければならない。
しかしその夫も、趣味は、パチンコ。
これではたがいに、向上しあうことなど、夢のまた夢。
その女性は、いつもこう言っていた。
「子どもに教育をつけると、遠くへ行ってしまう。だから、損」と。
●レベルの高い人
母親は、つねに視野を広くする。
「視野を広くする」というのは、内面世界を豊かにすることをいう。
外面的な虚勢を張りあうことではない。
そのためには、つねに自分よりレベルの高い人と交際する。
これは恩師のTK先生が教えてくれたことである。
そしてできれば、……というより、同時に、自分の周囲からレベルの
低い人を遠ざけることも忘れてはいけない。
私もある時期、たいへん小ずるい男性と交際したことがある。
気がついてみると、私自身も、たいへん小ずるいものの考え方をしていることを知った。
人間というのは、こうしてたがいに感化しあう。
●長女、二男
長男が傷害事件を起こしたとき、その母親は、ガミガミというより、ギャンギャンと
子どもを叱った。
来る日も来る日も、子どもを叱った。
「私は苦労してあんたを育てた」「塾の送り迎えで苦労した」「親の恩を忘れたのか」
「世間に顔向けができない」と。
長女はと二男は、同時期に暴走族に加わった。
暴走族同士の抗争事件を引き起こし、警察に逮捕。
そのまま高校は強制退学。
再びその母親は、ガミガミというより、ギャンギャンと子どもを叱った。
来る日も来る日も、子どもを叱った。
●子どもは家族の代表
こういう話を見聞きすると、私はすぐこう思う。
「責められるべきは母親のほうであって、子どもたちではない」と。
子どもは家族の(代表)にすぎない。
それがわかるか、わからないかは、親の視野の広さによる。
が、たいへん悲しいことに、その母親には、その視野の広さがなかった。
ウソと虚栄のかたまり。
ひとつのウソをごまかすために、つぎのウソをついた。
あとは、その繰り返し。
子どもたちが強制退学になったことについても、「学校が正しい判断をしなかった」
「相手の子どもが悪い」「うちの子は、たまたま事件に巻き込まれただけ」と主張した。
その結果、子どもたち自身も、ますます自分を見失っていった。
●不幸の連鎖
長男と長女は、そのまま家出。
二男はしばらく家を出入りしていたが、母親は、「近所に恥ずかしい」という理由で、
それを許さなかった。
で、それから10年。
現在、長男と二男は、離婚。
これについても、「離婚したから、子育てで失敗した」と書いているのではない。
問題は、そのあと。
それぞれ2人の子ども(その女性の孫)がいるが、養育費すら満足に払えない状態が
つづいている。
これについても、その女性は、「(孫を)相手の嫁に取られたのだから、養育費など
払う必要はない」とがんばっている。
調停員が、「あなたは連帯保証人になっている」と、いくら説明しても、その女性には
それを理解する能力さえない。
●失敗
もしこういうケースで、「失敗」という言葉を使うとしたら、子どもたちが退学
させられたり、良好な家庭を築けなかったことではない。
離婚にしても、いまどき、何でもない。
「失敗」という言葉を使うとしたら、子どもたちの能力を、じゅうぶん、
引き出せなかったこと。
よき家庭人として、自立させられなかったこと。
ついでに言えば、孫たちの養育費すら払わず、責任逃れをしていること。
そういう無責任な人間になってしまったこと。
で、こうした一連の(流れ)を、外から見ると、そこに一本の(糸)があることが
わかる。
その糸が順につながって、その女性の現在の状況を作りあげている。
●自分で作る運命
その女性は、たぶん心のどこかで、自分の運命をのろっているかもしれない。
最初の話にもどるが、その女性が現在の状況になったのは、(なった)というよりは、
(作り出した)のは、その女性自身の育児姿勢にある。
自ら(糸)を作り、自らその(糸)に巻き込まれていった。
が、自分を見つめる視野そのものが狭い。
だからそういう(糸)があることにさえ、気づいていない。
私が知るかぎり、その女性は、口がうまく、不誠実だった。
言っていることのうち、10に1つも、本当のことがない。
そういう女性だった。
しかしその女性がそういう女性になったのは、その女性の生まれ育った家庭環境に
あった。
視野を広めていくと、そういうことまでわかるようになる。
●運命と闘う
そこにある運命と闘うためには、まず自分の視野を広くすること。
視野が広くなればなるほど、そこに(糸)が見えてくる。
その糸さえわかれば、自分でその糸をほぐすことができる。
運命の糸を、ほぐすことができる。
ではどうしたらよいか……ということをわかってもらいたかったから、
架空の女性だが、1人の女性を例にあげて、考えてみた。
私たちは、その反対のことをすればよい。
それが運命と闘う方法のひとつということになる。
(今日の教訓)
そこに運命があるなら、視野を広くせよ。
文化に親しみ、教養を深くせよ。
運命は、それを恐れれば、キバをむいてあなたに襲いかかってくる。
しかし一度受け入れてしまえば、向うからシッポを巻いて逃げていく。
不誠実、愚かさは、視野を狭くする。
その視野の狭さが、やがてあなたを袋小路に追いつめる。
あなたは運命に翻弄され、暗闇の中で、もがき、苦しむ。
あとは、あなたの勇気だけ。
それさえあれば、霧に包まれた原野の向うに、一本の道が見えてくる。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●9月4日
+++++++++++++++++++++++
古里と決別した。
実家を売り払い、家財を処分した。
かなりのモノが残ったが、それはそのままにしておいた。
つぎに入居する人のための、置き土産。
+++++++++++++++++++++++
●損論
わずかな財産だった。
モノは山のようにあったが、お金にはならなかった。
数十枚もあった着物が、全部で、たったの2万円。
漆(ウルシ)塗りの食器も、10数箱もあったが、一部を除いて、近所の人に
分けてやった。
「ほしい方はどうぞ!」と書いたら、みなが、もち帰っていった。
中には、大きな袋に入れて、もち帰っていった人もいた。
損?
損といえば、損。
が、私がした損は、そんなものではない。
たとえて言うなら、数千万円も損をした人が、10万円や20万円の損に
こだわるようなもの。
それよりも私は、実家のことで、自分の人生そのものを、犠牲にしてしまった。
失われた時間は、戻ってこない。
その「損」と比べたら、10万円や20万円の損など、なんでもない。
それよりも私は、こうして実家から解放された。
その解放感のほうが、うれしい。
金銭的な価値で計算することはできないが、今から20年も前だったら、
1億円でも高くない。
つまりあのとき、だれかが、「1億円出してくれたら、お前の重荷を代わりに担いで
やる」と言ったら、私は1億円を出しただろう。
そのときすでに私は、合計すれば、それ以上のお金を、実家に貢いでいた。
●財産
私はそうした財産を処分しながら、何度もこう思った。
祖父の時代から、父の時代。
そして兄の時代へと、3代つづいた自転車店だったが、その「3代」で、残ったものは、
何だったのか?、と。
ときどき、祖父や父や兄たちが、必死になって守ろうとしてきたものは、
何だったのか?、と。
35坪足らずの土地に、古い家屋。
私はその家で生まれ育ったが、その私だって、何だったのか?、と。
わかりきったことだが、モノ、つまり財産のもつ虚しさを、改めて感じた。
●未練
ワイフも、私の意見とまったく同じだった。
故郷を自分の中から消すということは、一度、自分自身を、(無)に
しなければならない。
未練が残ったら、故郷を消すことはできない。
そのときもし、実家に残っているモノを見ながら、そこに自分の過去を
重ねるようなことをすれば、故郷を去ることはできない。
何もかも棄てるというのは、そういう意味。
「惜しい」と思ったとたん、それは未練に変わる。
未練が残れば、前に向かって歩けない。
未練は、心を、うしろ向きに引っ張る。
だから心の中を、一度、無にする。
ある女性は、漆の食器を、大きな袋に詰めながら、私にこう聞いた。
「本当にいいのですか?」と。
つまり「本当に、もらってもいいのですか?」と。
私はそのつど、笑みを浮かべながら、「どうぞ」「どうぞ」を、繰り返した。
買えば、一個、1万円はくだらない。
お椀の模様にしても、手彫りで、その溝に、金箔が埋め込んである。
それがつぎつぎと消えていくのを見ながら、私はある種の快感を覚えていた。
言うなれば、古里を蹴飛ばすような快感だった。
●夢
その翌朝。
つまり今日、私は兄の夢を見た。
私は実家のあるゆるい坂道を、実家に向かって歩いていた。
そのときふと横を見ると、兄がいっしょに歩いていた。
ニコニコと笑っていた。
うれしそうな顔だった。
黄色いTシャツを着ていた。
私は、兄を、右手で抱いた。
兄といっても、いつからか、私の弟のようになっていた。
小さな体に、頼りない顔をしていた。
私は兄に、こう言った。
「仇(かたき)は、取ってやったぞ」と。
それを聞いて、兄は、さらにうれしそうに笑った。
私は夢の中だったが、涙で目がうるんだ。
●家の奴隷
兄は、一家の主人というよりは、家の奴隷だった。
母にしばられ、家にしばられ、社会を知ることもなく、この世を去った。
生涯において、母は、兄を、内科以外の病院へは連れていかなかった。
無知というよりは、兄を「家の恥」と考えていた。
晩年、母の認知症が進んだこともあり、(実際には、老人性のうつ病だったかも
しれない)、兄は母の虐待を受けるようになった。
一度、ワイフと2人で実家を見舞うと、兄は、何が悲しかったのか、
私の顔を見るやいなや、ポロポロと、大粒の涙をこぼした。
私はその涙を、私のハンカチで拭いてやった。
今にしてみれば、唯一の、それが、心残りということになる。
どうしてあのとき、私は兄を浜松へ連れてこなかったのか。
その気になれば、それができたはず。
あのときを思い出すたびに、胸が痛くなる。
が、迷ったのには、それなりの理由がある。
兄には、おかしな性癖があった。
私の目を盗んでワイフに抱きついたり、ワイフの入浴中に、風呂の中に、
勝手に入ってきたりした。
その性癖を、兄は、自分ではコントロールできなかった。
●総決算
その兄の夢が、私の人生の総決算かもしれない。
実家への思いを、それで断ち切ることができた。
兄も、それで断ち切ることができた。
一抹のさみしさがないと言えば、ウソになる。
しかしそれ以上に、実家から解放されたという(ゆるみ)のほうが、
大きい。
長い旅が終わって、気が抜けたような状態。
緊張感そのものが、消えた。
私はその陶酔感に浸りながら、何度も何度も、肩の力が抜けていくのを覚えた。
●世間体
母は母で苦しんだ。
それはわかる。
しかし母の人生観が、ほんの少しちがっていたら、その(苦しみ)の
中身もちがっていたことだろう。
私たちの人生も、大きく変わっていたことだろう。
母が悪いというよりは、母はあまりにも通俗的だった。
自分の人生というよりは、「世間体」の中で生きていた。
いつもそこに他人の目を気にしていた。
その通俗性の中で、母は、自分を見失ってしまっていた。
通俗的になればなるほど、何が大切で、何がそうでないか、それがわからなくなる。
晩年の母は、仏具ばかり磨いていたが、私はそこに、哀れさというよりは、
もの悲しさを感じていた。
●「まんじゅう……1個、80円」
実家を整理しているとき、兄の残したノートが出てきた。
その1ページに、「まんじゅう……1個、80円」とあった。
その日、どこかでまんじゅうを1個買って、食べたらしい。
それが80円、と。
それを見たとき、ぐいと胸がふさがれるのを感じた。
貧しい生活。
慎ましやかな生活。
1個80円のまんじゅうまで、ノートに書きとめていた。
それをワイフに話しながら、ふと、こう漏らした。
「ぼくたちのしたことは、まちがっていなかったね」と。
母は、そのつど、私から、お金を(まきあげていった)。
額は計算できないが、相当な額である。
そういったお金は、実家の生活費だけではなく、母の実家へと流れていった。
もう一か所、別のところへ流れていき、残ったお金は、母の通帳の中へと消えた。
10数年ほど前だが、現金だけで、母は、3000〜4000万円程度は
もっていたはず。
その一部を、兄は母からもらいうけ、それでまんじゅうを買って食べていた。
兄は生涯にわたって、給料らしい給料を手にしたことはなかった。
いつも「小遣い」と称して、小額のお金を、母から受け取っていた。
それだけ。
兄は、自閉傾向(自閉症ではない)はあったかもしれないが、頭はよかった。
65歳で私の家に来たときも、小学3〜4年生の算数の問題を、スラスラと
解いてみせた。
●のろわれた家系
母が守ったものは、何だったのか。
守ろうとしたものは、何だったのか。
よくわからないというより、あまり考えたくない。
母は母で、自分の人生を懸命に生きた。
それが正しいとか、正しくないとか、そういう判断をくだすこと自体、まちがっている。
母は母でよい。
が、全体としてみれば、「林家」は、(「家(け)」と家付けで呼ぶのも、
おこがましいが)、(のろわれた家系)である。
ひとつの例外もなく、どの家族も、深い不幸を背負っている。
みな、それぞれ、必死にそれを隠し、ごまかしている。
が、人の口には戸は立てられない。
他人は気づいていないと思っているのは、本人たちだけ。
みな、知っている。
知って、知らぬフリをしている。
●象徴
私には、その象徴が、兄だったように思う。
いつしか兄が、そうした不幸を、一身に背負っているように感じるようになった。
だから兄が死んだときも、その通夜のときも、私はうれしかった。
兄が死んだことを喜んだのではない。
私以上に、重い苦しみを背負い、兄は、もがいた。
健康でそれなりの仕事をしている私だって、苦しんだ。
兄の感じた苦しみは、私のそれとは比較にならなかっただろう。
「家」という呪縛感。
重圧感。
母の異常なまでの過干渉と過関心。
それでいて、それに抵抗する力さえなかった。
つまり兄は、死ぬことで、その苦しみから解放された。
自分の運命に翻弄されるまま、またその運命と闘う力もないまま、この
世を去っていった。
最後は、やらなくてもよいような治療を受け、体中がズタズタにされていた。
食道や胃に穴をあけ、そこから流動食を流し込まれていた。
動くといけないからと、体は、ベッドに固定されたままだった。
一度、見舞いに行くと、私の声とわかったのか、目だけをギョロギョロと
左右に振った。
三角形の小さな目だった。
兄は死ぬことで、その苦しみからも解放された。
私はそれがうれしかった。
が、それだけではない。
●犠牲になった兄
兄は、林家にまつわる(のろい)を、一身に背負っていた。
いや、私が兄だったとしても、何も不思議ではない。
兄が、私であったとしても、何も不思議ではない。
たまたま生まれた順序がちがっていただけ。
で、もし反対の立場になっていたら……。
あの兄なら、私のめんどうをみてくれたことだろう。
収入の半分を、私に分け与えてくれただろう。
兄は、私より、ずっと心の温かい、やさしい人間だった。
その兄が(のろい)のすべて背負って、あの世へ旅立ってくれた。
私はそれがうれしかった。
だから祭壇に手を合わせながら、私はこうつぶやいた。
「準ちゃん(=兄名)、ありがとう」と。
●礼の言葉
葬儀が終わったとき、私は参列者にこう言った。
「今ごろ、兄は、鼻歌でも歌いながら、金の橋を、軽やかに渡っているはずです」と。
それについて、その直後に、寺の住職が、「そういうことはまだです。
四九日の法要が終わってから決まることです」と言った。
つまり「まだ、極楽へ渡ってはいない」と。
もともと『地蔵十王経』という偽経を根拠にした意見だが、何が四九日だ!
私の人生は61年。
兄の人生は69年。
アホな「十王」どもに、人生の重みがわかってたまるか!
兄は、あの夜、まちがいなく、金の橋を渡って、極楽へと旅立った。
●終焉
こうしてあの「林家」は、終わった。
が、すべてがハッピーエンドというわけではない。
問題は残っている。
残っているが、これからはそのつど、蹴飛ばしていけばよい。
私の知ったことではない。
いまさら誤解を解きたいなどとは思わない。
●運命
最後に、これだけは、ここで自信をもって言える。
もしあなたが運命に逆らえば、運命は、キバをむいてあなたに
襲いかかってくる。
しかし運命というのは、一度受け入れてしまえば、向こうから尻尾を
巻いて逃げていく。
もともと気が小さくて、臆病。
そこに運命を感じても、おびえてはいけない。
逃げてはいけない。
受け入れる。
そしてあとはやるべきことをやりながら、時の流れに身を任す。
あとは必ず、時間が解決してくれる。
つまりこうして今まで、おびただしい数の人の人生が流れた。
あたかも何ごともなかったかのように……。
準ちゃん、ぼくももうすぐそちらへ行くからな。
またそこで会おう!
(補記)(のろい論)
私はここで(のろい)という言葉を使った。
しかしスピリチュアル(=霊的)な、のろいをいうのではない。
ひとつの大きな運命が、つぎつぎと別の運命の糸を引き、ときとして
それぞれの家族を、翻弄する。
それを私は、(のろい)という。
ふつうの不幸ではない。
ふつうの不幸ではないから、(のろい)という。
が、それは偶然によるものかもしれない。
たまたまそうなっただけかもしれない。
しかし私はそうした(不幸)に間に、一本の糸でつながれた、
運命を感ずる。
それについて書くのは、ここではさしひかえたい。
まだ生きている人も多いし、みな、それぞれの運命を引きずりながら、
懸命に生きている。
私とて例外ではない。
ある時期、私は、心底、そっとしてほしいと願ったときもあった。
けっして、問題から逃げようとしたわけではない。
どうにもならない袋小路に入ってしまい、身動きできなくなってしまった
ときのことだった。
しかしそういうときにかぎって、事情も知らないノー天気な人たちが、
あれこれと世話を焼いてくる。
わずか数歳、年上というだけで、年長風を吹かしてくる。
その苦痛には、相当なものがある。
私はそれを身をみって、体験した。
だから、……というわけでもないが、もしその人が、今、苦しんで
いるなら、そっとしておいてやることこそ、重要ではないか。
もちろん相手が求めてくれば、話は別。
そうでないなら、そっとしておいてやる。
それも気配りのひとつ。
思いやりのひとつ、ということになる。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 10月 5日号
================================
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page017.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●幻覚
今日、はじめて、私は(幻覚)なるものを見た。
子どもたち(小4生徒)たちにワークをさせていたときのこと。
シーンと静まり返っていた。
そのとき私は腕組みをして、目を伏せていた。
たぶん、そのとき眠ってしまったのだと思う。
ほんの瞬間のできごとだった。
目をさますと同時に、ななめ右前の子どもを見た。
見たというより、目に入った。
そのときのこと。
その子どもの背後に、黒いスーツを着た男が立っていた。
その男が、見た瞬間、くるりと体を回すと、そのままドアのほうへ
音もなく消えていった。
私は思わず声をあげた。
「どちらさんですか?」と。
今から思うと、それは幻覚だった。
脳の中で、夢と現実が、ごちゃまぜになった。
が、私はワイフにそれを話すまで、それが幻覚だったとは思わなかった。
あとでワイフに電話をして、そういうものを見たと話すと、ワイフは、
「ヘエ〜、あなたは幻覚を見たのね」と言って笑った。
幻覚?
もしそうなら、私は生まれてはじめて、幻覚を見たことになる。
あるいは脳みそが、とうとうおかしくなり始めたのか?
死ぬ直前の母も、よく幻覚を見ていた。
理屈の上では、視覚野を通して入ってきた情報と、夢として見る
情報が、脳のどこかで交錯したと考えられる。
実に奇怪な経験だった。
で、その話を子どもたちにすると、私が真顔だったせいもあるが、
何人かが、「先生、こわい!」と言い出した。
「本当にこわいのか?」と聞くと、「こわい」と。
1人の子ども(男児)は、体を小刻みに震わせていた。
「冗談かな?」と思ったが、本当に震わせていた。
いつもは大胆な言動で、みなを笑わす子どもが、である。
それを見て、「そういうこともあるんだ」と思った。
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●人間不信
++++++++++++++++++
ゆらゆらと揺れるカーテン。
その向こうに、乾いた庭の落ち葉が見える。
台風が、現在、太平洋上を、関東地方に向かっているという。
湿り気を帯びた、あやしげな風。
それがパタパタと、庭をせわしく走り抜けている。
だれもいない朝。
ワイフは、午前中はクラブに出かけて、今はいない。
時間は、先ほどから止まったまま。
私はぼんやりと時の流れに身を任す。
++++++++++++++++++
●自業自得
「人間不信」というと、(私)の問題と考える人は多い。
まちがってはいない。
しかし「人間不信」には、もうひとつの意味が含まれる。
相手の人から見て、私は、どう見られているかという問題である。
「相手の人は、私を信じているか」と。
人は、他人を信じ、同時に、他人に信じられてこそ、「人間不信」という問題を
克服することができる。
他人に信じられない人が、己の人間不信を嘆いても、それは身勝手というもの。
そういうのを、言葉はきついが、『自業自得』という。
●孤立感
今、ふと我に返る。
私の周りには、だれもいない。
私はひとりぼっち。
孤独ではないが、孤立。
孤立感。
この孤立感は、いったい、どこからくるのか。
再びゆらゆらと揺れるカーテン越しに、庭の落ち葉を見る。
土の色と化した、葉っぱの死骸。
それがところどころで、小さな山を作っている。
それを見ていると、孤立感が、カプセルとなって、私をすっぽりと包む。
●基本的不信関係
「他人を信じられない」と嘆いても、意味はない。
「他人に信じられない」と嘆いても、意味はない。
だいたい私は、私自身を信じていない。
ふわふわとした人生観。
焦点のぼやけた哲学観。
だれにでもシッポを振る、捨て犬のような根性。
「私は私でいたい」といくら願っても、そのつど、世の動きに、そのまま流されてしまう。
原因は、基本的不信関係。
心理学では、そう説明する。
乳幼児期の貧弱な家庭環境が、私をして今のような私にした。
これは生まれついた、脳みそのシミのようなもの。
簡単には取れないし、また取れるようなものでもない。
本能に近い部分にまで、刷り込まれている。
●心の傷
だから私には、(その人)がよくわかる。
『同病、相、憐れむ』といったところか。
私に似た人に出会うと、「ああ、ここにも、心のさみしい人がいる」と。
一見、朗らかで、明るい。
快活で、幸福そう。
しかしそれは仮面。
精一杯、無理をしている。
そういう人を見ながら、私は、いつもこう思う。
「この人は、自分の心の傷に気がついているのだろうか」と。
あるいは傷があることにさえ、気がついていない?
「かわいそうな人だ」とは、思うが、どうしようもない。
私自身だって、どうしようもない。
●信じられるのは、お金だけ
私はよい夫を演じているだけ。
よい父親を演じているだけ。
ワイフにしても、私を信じていない。
息子たちとなると、さらに私を信じていない。
私は、自己愛者。
愛他的自己愛者。
自分勝手で、自己中心性が強い。
プラス、わがまま。
心の中身も、さみしい。
いまだに「信じられるのは、お金だけ」と。
そんな人生観を崩せずにいる。
だからみんな、去っていく。
楽しそうな顔をしたまま、去っていく。
●希望
ゆういつの救いは、パソコン。
こうしてパソコンに向かって、心の内を書く。
真新しいパソコンで、キーボードに触れているだけで、気持よい。
その気持よさに陶酔しながら、孤立感をまぎらわす。
このパソコンの向こうには、私に共鳴してくれる人もいるはず。
数は少ないが、「私もそうだ」と思ってくれる人もいるはず。
今すぐには無理かもしれない。
しかし何か月か、何年かを経て、いつかどこかで、だれかが共鳴してくれるかもしれない。
「文」には、そういう「力」がある。
私にとっては、それが希望。
孤立感を癒す、ゆいいつの方法。
●自分の中のボロ
しかしどうして私は、こうまで人に裏切られてばかりいるのか。
「人を信じよう」と思ったとたん、そこで裏切られてしまう。
相手は、最初から私をそういう人間と思って、近づいてくる?
それとも最初から、私をまともな人間と思っていない?
そんな人間関係に、ボロボロとまではいかないにしても、もう疲れた。
「信じられたい」と思いつつも、その努力にも限界がある。
私ももうすぐ、満62歳。
このところザルから水がこぼれ出るように、人々が私から去っていく。
それが実感として、よくわかる。
あの人も、この人も……と。
理由がわかっているだけに、私としてもなす術(すべ)もない。
「歳を取る」ということは、こういうことかもしれない。
自分を支える気力そのものが弱くなる。
孤立に弱くなるというのではない。
自分の中のボロが、そのまま表に出てきてしまう。
それが周りの人たちを、遠ざけていく。
●捨て身
「今日、1日だけでもいいから、ワイフを信じてみよう」と、今、思った。
だまされてもいい。
裏切られてもいい。
・・・ワイフは、そういうことはしない。
それはわかっているが、こうなれば捨て身で、ワイフと接してみよう。
気を張れば張るほど、疲れるだけ。
ワイフも疲れる。
「信じてもらおう」などと思う必要はない。
「信じてやろう」と気を張る必要もない。
ただひたすら、「捨て身」。
何も考えない。
何も求めない。
こうしてぼんやりと、時の流れに身を任す。
どうせ今の私には、それしかできない。
それしかすることもない。
そうそう心なしか、庭を行き交う風が、強くなったように思う。
カーテンの揺れが、それに合わせて、大きくなった。
さあて、今日もこうして始まった。
まだ朝のニュースは見ていないが、今ごろは選挙一色のはず。
自民党が歴史的敗北を期した。
……となってみると、今まで、あんな党がどうして50年間も、
日本に居座っていたのか、居座ることができたのか、
その理由がよくわからない。
2009年8月31日(月曜日)
Hiroshi Hayashi++++++++AUG.09+++++++++はやし浩司
●980円の時計(脳の中の脳)
++++++++++++++++++
近くのショッピングセンターでは、毎月
30日に、「みそか市」というのが開かれる。
この日は、商品を選んで特別に安く、ものが
売られる。
1万円の自転車とか、6000円の掃除機とか、など。
その中に、9800円のソーラーバッテリーで
動く腕時計(電波時計)というのがあった。
ググーッと物欲が湧いてきた。
が、ここで「待ったア!」。
++++++++++++++++++
●作られる意識
最近の脳科学の進歩には、めざましいものがある。
その中のひとつが、これ。
実は(意識)というのは、それを意識として意識する前に、
脳の別のところで、つまり無意識の段階で、その意識の原型が作られる。
私たちが「意識」と呼んでいるのは、実はその無意識に操られてできた意識
ということになる。
もう少しわかりやすく説明しよう。
●物欲
私はその腕時計がほしくなった。
腕時計など、この10年以上、身につけたこともないのに、ほしくなった。
で、ワイフに「あとで、この時計を買いに行こう」と誘った。
が、実はこのときすでに、脳の別のところでは、「買わない」という意識が
作られていた。
もちろんそれは無意識の世界でのこと。
無意識の世界で、別の反応が起きていることなど、私には知る由もない。
意識の世界では、「ほしい」「買いたい」「買いに行こう」という意識が働く。
●無意識の世界の反応
で、ショッピングセンターに出向く。
時計売り場に立つ。
時計を見る。
「どこかジジ臭い」と、私は思った。
「重そうだ」と、私は思った。
で、結論は、「買わない」。
……と書くと、「どうして無意識の世界の反応が、あらかじめ君には
わかったのか?」という質問が出てくるかもしれない。
私は無意識の世界では、「どうせ店に行っても買わないだろう」と反応していた。
無意識の世界での反応だから、意識の世界で、それがわかるはずがない。
わかったとたん、それは無意識ではなくなる。
●訓練
ところが、である。
少し自分の脳みそを訓練すると、無意識の世界での反応が、おぼろげならも、
自分でわかるようになる。
そのときも、そうだった。
コマーシャル(DMチラシ)を見たとき、私は意識の世界では、それを
「ほしい」と思った。
が、同時に、脳の別のところで、モヤモヤとした感覚が、それをじゃました。
それは「迷う」という反応とは、ちがう。
意識の世界では、はっきりと「買う」という反応を示していた。
が、そのモヤモヤとした感覚の中に、「買ってはだめ」とか、「買ってもむだ」とか
いう(思い)が、あるのを感じた。
言葉ではない。
感覚的な反応である。
それが無意識の世界の(反応)ということになる。
●嘘発見器
私は実物を見たことがない。
嘘発見器なるものに、触れたこともない。
しかし映画などでは、よく見かける。
その嘘発見器だが、今では、脳の奥深くで起きる反応を見分けることが
できるそうだ。
だからいくら意識的に嘘をついても、脳の別のところが、別の反応をそてしまう
ため、それを嘘と見抜いてしまう。
そこで……。
ここからはあくまでも映画で知った話だが、一流のスパイともなると、嘘発見器を
だます技術を身につけるのだそうだ。
本当かどうかは知らないが、もしそういう訓練があるとするなら、それは無意識の
世界をだます訓練ということになる。
が、そういうことはありえることだと私は思う。
訓練すれば、無意識の世界をコントロールし、ばあいによっては、だますこと
もできる。
その反対の側位にある反応が、催眠術ということになる。
●催眠術
催眠術については、今さら、改めて、ここに説明するまでもない。
あの催眠術を使えば、心の奥の奥、深層心理までコントロールすることが
できる。
こんな実験を、私は、直接、目撃したことがある。
実験者(催眠術師)が、被験者(女性、30歳くらい)にこういう暗示を与える。
「あなたは目をさましたあと、隣の部屋に行って、ハサミをもってくる」と。
で、そのあと被験者は催眠術から解かれ、我に返る。
が、そのあとのこと。
被験者は席を立ち、隣の部屋に行こうとする。
それを見ていたほかの人が、「どこへ行くのですか?」と聞くと、
「ちょっと、隣の部屋まで……」と。
そこで「どうして隣の部屋に行くのですか」と聞くと、
「ハサミを取りにいくのです」と。
「なぜ、ハサミを取りにいくのですか?」
「あら、……どうしてかしら?」
「ハサミで何を切るのですか?」
「でも、ハサミを取りにいかなきゃ……」と。
その女性は、自分の意思でハサミを取りに行くようにみえた。
が、実際には、他人によって作られた(暗示)に、操られていただけ。
ハサミが、なぜ必要なのか、それについては、まったく考えていなかった。
●もうひとりの「私」
乳幼児期(0〜2歳)から幼児期前期(2〜4歳)にさしかかってくる
と、子どもは、「いや」という言葉を連発するようになる。
母「お外へ行こうか」
子「いや」
母「じゃあ、おうちの中で遊ぼうか」
子「いや」と。
そういう子どもの反応を観察していると、子どもの意思というよりは、
子どもの意思そのものが、さらに奥深い意識によって操られているのがわかる。
何も考えず、条件反射的に「いや」と言う。
子どもの心の中で、自立に対する意識が芽生え始めているためと考えてよい。
その意識が、親の言いなりになることに対して抵抗する。
同じような現象がおとなの世界でも、見られる。
私のワイフでも、虫の居所が悪くなったりすると、何かにつけて拒否的な態度
を示すようになる。
私への嫌悪感が、ワイフを裏から操る。
「あれもいや」「これもいや」となる。
●残った物欲
……ということで、9800円のソーラー電波時計は買わなかった。
が、ここでまた別のおもしろい反応が、脳の中で起きた。
視床下部の指令を受けて、ドーパミンが放出された。
そのドーパミンが、線条体を刺激した。
私の線条体の中には、物欲に反応する受容体ができあがっている。
「何かほしい」と思うと、それを自分の意思で止めることがむずかしくなる。
アルコール中毒の人が、酒のコマーシャルを見たときのような反応が、脳の
中で起きる。
ニコチン中毒の人が、タバコの煙をかいだときのような反応が、脳の中で
起きる。
それが何であれ、この反応が一度起きると、簡単には止められない。
そのモノがほしくなる。
とくに私は、デジモノに弱い。
9800円の時計については、買うのをやめたが、「時計がほしい」という気持ちは、
そのまま残った。
そこで私がしたことは、その横にある、安物の時計を買うことだった。
値段は、980円。
10分の1の値段。
ベルトが布製の、けっこうしゃれた時計だった。
色は茶と白と黒の組み合わせ。
小ぶりで、軽いのも、気にいった。
で、買った。
その日は、一日、その時計を腕につけて遊んだ。
こうして物欲を満たし、やがて私の脳は、落ち着きを取り戻した。
Hiroshi Hayashi++++++++AUG・09++++++++++はやし浩司
●9月の抱負
+++++++++++++++++
明日から9月。
講演の季節。
私は最近、講演に招かれると、できるだけ
先方の地で、そのまま旅館に泊まるようにしている。
来週は、F県のN町と、伊豆半島のA温泉で、
それぞれ一泊することになっている。
楽しみ……というより、そういう楽しみを
用意しておくと、心もはずむ。
講演旅行も、ずっと楽しくなる。
言い忘れたが、私はいつもワイフを連れて行く。
ワイフの趣味は、旅行。
それを満足させてやるのも、夫の役目。
++++++++++++++++++
●料理は最低
N町の旅館では、鮎の塩焼きが出るという。
A温泉では、伊勢海老の姿焼きが出るという。
結構な料理だが、私たち夫婦は、基本的には小食。
回転寿司でも、2人で、7〜8皿が限度。
ときには、6皿。
それ以上は食べられない。
だから旅館を予約するときも、料理はいつも最低の料理を注文する。
追加料理は、なし。
不要。
そのかわり、風呂の設備のよい温泉を選ぶ。
湯質がよければ、文句なし。
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【熟年離婚】(17% of old couples have been divorced now in Japan)
●ふえる熟年離婚
厚生省大臣官房統計情報・人口動態統計課の「人口動態調査」によると、昭和25年から
平成7年までの間に、離婚率は、4・6倍になったという。
その中でも、結婚生活20年以上の熟年夫婦の離婚率は、3・5%から、16・9%に
まで上昇しているという。17%といえば、ほぼ5組に1組ということになる!
実は、私の知人の中にも、今、離婚の危機に立たされている人が、何人かいる。しかし
そういう人たちと会って話をしてみると、どこまでが冗談で、どこから先が、真剣なのか、
わからなくなってしまう。そのわからなさこそが、この熟年離婚の特徴の一つかもしれな
い。
知人「もう、5年も、セックスレスだよ」
私「本当かあ!」
知人「寝室も別々だよ」
私「本当かあ!」
知人「だからさ、オレにも、愛人がいてさ」
私「本当かあ!」
知人「家内も、今ごろは、どこかの大学生と、飲み歩いているよ」
私「本当かあ!」と。
そんな調子で、会話がかみあわなくなってしまう。が、それでいて、その奥さんからは、
こまめに礼状が届いたり、電話がかかってきたりする。離婚の雰囲気など、どこにも感じ
させない(?)。
で、それを話題にする私のほうも、疲れた。私の実感では、「離婚する」「離婚する」と、
騒ぐ人ほど、離婚しない。本当に離婚する人は、静かに、だれにも悟られずに、離婚する
……ということか。
その熟年離婚には、大きな特徴がある。今までの経験をまとめてみると、こうなる。
(1)夫の知らないところで、妻側が、先に離婚の決意をかためてしまう。
(2)それまでは表面的には、従順で、家庭的な妻であることが多い。
(3)夫の職業は、ほとんどが会社勤めのサラリーマン。会社人間であることが多い。
(4)夫は、まじめタイプ。むしろ、家庭思い。家族思い。家庭サービスもしている。
(5)共通の趣味や、目的がない。休日などは、バラバラの行動をすることが多い。
(6)妻側から離婚を申し出られると、夫は、「どうして?」と、ろうばいしてしまう。
(7)子どもの結婚など、子育てが終わったときなどに、離婚しやすい。
ほかにもいろいろあるが、実は、私たち夫婦も、あぶない。しかし私のように、「あぶな
い」「あぶない」と思っている夫婦は、離婚しない。それを知っているから、「多分、だい
じょうぶだろう」と、自分では、そう思っている。
そこでこうした熟年離婚を防ぐには、どうしたらよいかということになる。が、それと
て、つまり、「防ぐ」という発想とて、一方的に、夫側の勝手にすぎない。夫としては、離
婚されたら困るかもしれない。しかし一方の当事者である、妻側は困らない。離婚を望ん
でいる。
だから「防ぐ」という発想そのものが、夫側のものでしかない。妻側にすれば、「どうす
れば、離婚できるか」。さらには、「どうすれば、夫の束縛から解放されて、自分らしい人
生を、もう一度、生きることができるか」ということが、問題なのだ。
事実、熟年離婚する妻たちは、こう言っている。「残りの人生だけでも、私らしい生き方
を、してみたい」と。だから、「防ぐ」という発想そのものが、そぐわない。そういう妻た
ちにとっては、かえって迷惑になる。
そこで、これはあくまでも夫側の立場の意見だが、熟年離婚を防ぐためには、とにかく
『協同意識』をもつしかないのではないかということ。共通の目的が無理なら、趣味でも
よい。たがいに、たがいの心の補完をしあうような活動をしなければいけない。土日にな
ると、夫は、ひとりで魚釣り。妻は、テニス仲間と旅行……というのでは、あぶないとい
うこと。
で、私たち夫婦も、その熟年離婚の予備軍のようなものだから、偉そうなことは言えな
い。しかし最近、私は、こう思う。
夫は、夫で、妻の生きがいを、いっしょにさがし、育ててやる。それが熟年離婚を防ぐ、
最大の方法ではないか、と。「私は夫だ。お前らを食わせてやっている」という発想では、
熟年離婚されても、文句は言えない。
そう言えば、離婚の危機にある(?)と思われている、冒頭にあげた知人たちは、どの
人も、どこか権威主義的。夫意識が強すぎるのでは? 「男は仕事だけしていれば、一人
前」「それでじゅうぶん」「妻は家庭に入って、家事をすればよい」と、日常的に、そんな
ふうに考えているような感じがする。つまり、そういう発想をする夫ほど、あぶないので
は?
今夜もワイフに、「おい、今じゃあ、5組に1組が熟年離婚する時代だそうだよ。20年
間も結婚生活をしていてね……」と話すと、ワイフは、どこか感慨深げ。「じゃあ、私たち
も……」と言いそうな雰囲気だった。うちも、あぶないなア〜。
【補記】
どうせ17%も、熟年離婚するなら、そういう熟年離婚を、積極的に考えなおしてみた
ら、どうだろうか。夫婦も、いつまでも「結婚」というワクにとらわれないで、自由に、
自分たちの時間を楽しむとか……。そういう発想で、たがいの関係を、もう一度、つくり
なおす。
もっと言えば、「結婚」という概念を、一度解体した上で、つくりなおす。こういう時代
になったのだから、いつまでも、旧態依然の結婚観にしがみついているほうが、おかしい
のかも?
Hiroshi Hayashi++++はやし浩司
●疑似・熟年離婚
++++++++++++++++++
9月x日、私は故郷のM町と、絶縁する。
言うなれば、「熟年・離縁」。
故郷と言いながら、私にとっては、腐れ縁。
思いも枯れた。
未練も枯れた。
言い残すことは、何もない。
いろいろ言いたいことはある。
あるが、今さら言いたくもない。
言ったところで、何も変わらない。
説明しても、どうせわからないだろう。
どうにもならない。
いや、それ以上に、私の人生も、秒読み段階に入った。
だからきれいさっぱり、自分の心の中から消す。
だから「熟年・離縁」。
++++++++++++++++++
●熟年離婚
人は時として、ひとつの人生を生きながら、別の人生を経験する。
ひとつの例が、「熟年離婚」と「熟年・離縁」。
まったくちがうようで、中身は同じ。
心の動きは同じ。
今、私は熟年・離縁を経験しながら、他方で、熟年離婚を経験しつつある。
が、どうか心配しないでほしい。
私とワイフが離婚するわけではない。
そのつもりもない。
あくまでも「熟年・離縁」。
つまり人の心は複雑なようで、ときに、定型化することができる。
似たような例を経験しながら、それをもとに別の経験を定型化することができる。
わかりやすく言えば、私は今、熟年・離縁を経験しながら、「熟年離婚もこんな
ものだろうな」と、想像することができる。
●なぜ離縁?
いつかゆっくりと、それについて書くときがやってくるだろう。
今はまだ、そのときではない。
話せば長くなる。
要するに、失望の連続。
裏切られることはあっても、何もよいことはなかった。
が、「それでも……」と思って、故郷にしがみついてきた。
私なりに(縁)を大切にしてきた。
つまりそれも限界に来たということ。
だから離縁!
もっとも私は故郷を離れて、40年以上になる。
正確には44年!
いまだに故郷にしばられるほうがおかしい。
おかしいが、しばられた。
ずっとしばられた。
その呪縛感には、相当なものがあった。
だから今の気持ちは、「もう、たくさん!」
●香典抜き
もちろんきっかけは、ある。
私はずっと絶壁のフチに立っていた。
その私を背中から、どんと押すような事件があった。
「事件」というのも、大げさに聞こえるかもしれないが、事件は、事件。
ワイフは、「あの男のやりそうなことね」と言った。
わかってはいるが、私の背中を押すには、じゅうぶんなパワーがあった。
何と、私の肉親の葬儀のとき、間に立って、香典抜きをしていた親類がいた。
ほかの親類から預かった香典を、自分の懐(ふところ)に入れていた。
それは「浩司君、ところで……」という話から、始まった。
「こんなこと聞きにくいのだけど、ぼくが出した香典、君に届いているだろうか?」と。
私が「届いていない」と答えると、声にもならないような声を出して、その人は
「ハア〜」と言って、驚いた。
そのまま黙ってしまった。
こうした香典抜きが、いかに親戚関係を破壊するものか、葬儀を経験したことのある人
なら、わかるはず。
私はその親戚づき合いが、つくづくいやになった。
愛想(あいそ)も尽きた。
「あのNS氏というのは、そういう男ですよ。私も、さんざんだまされた。
しかしそこまでやるとはねエ……!」と私。
●熟年離婚
つまらない話を書いたが、そういう意味では、(貧乏)というのは、恐ろしい。
金銭的な貧乏が、時として、その人の心まで貧しくする。
私「まあ、私は無視します。あんな男、相手にしたくありません。定職ももたず、かわ
いそうな男です」
相「しかし、ぞっとするような話です……」
私「だから葬儀のあと、あなたのところに電話を入れていたのですね」
相「そうだったのか。そうだったんだ。浩司君とぼくが、連絡を取り合っていないか、
それを確かめるために、ね」
私「ハハハ、そこまでやるとはねエ……」と。
で、そのとき私は、理解できた。
熟年離婚を申し出る、妻の気持ちが、である。
グググッと怒りが増幅し、それが頂点に達したとき、突然、急に、心の中がすっきりする。
許したのではない。
受け入れたのでもない。
「もうどうでもいいや」というニヒリズムが、心を満たす。
そのとたん、ス〜ッと、心がすっきりする。
●熟年離婚に至るまで
そこで自分なりに心の中を整理してみる。
そして自分が熟年・離縁に至った過程を、熟年離婚のそれに当てはめて考えてみる。
つぎのが、それである。
(1)疑問期…「これでいいのか」という疑問をもち始める。
(2)反復期…疑問と否定を繰り返す。
(3)確認期…「これでいい」という確信をもちはじめる。
(4)決断前夜…身辺の整理を始める。
(5)決断期…未練をふっきり、決別を決断する。
最大の問題は、「悪人としての顔を、どう吹っ切るか」ということ。
私を悪く思っている人を、心の中で、どう処理するかということ。
イギリスの格言に、『2人の人によい顔はできない』というがある。
どちらか一方の人によい顔を見せることはできても、もう一方の人にまで
よい顔を見せるのはむずかしい。
どちらかに好かれれば、どちらかに嫌われる。
嫌われることを恐れていたら、ときとして、真の友を失うこともある。
熟年離婚についていえば、自分の最後の時間を失うことになる。
内容について考えてみよう。
ただしこれは、先にも書いたように、私の(熟年・離縁)をもとにして
書いたものであり、(熟年離婚)には、そのまま当てはまらないかもしれない。
「似ている?」という点で、私自身が経験した(熟年・離縁)をもとに、
熟年離婚を考えてみた。
(1)疑問期…「これでいいのか」という疑問をもち始める。
現状への不信感がつのる。(夫への不信感がつのる。)
重苦しい日々がつづく。(悶々たる日々がつづく。)
やがてその原因や理由に気づくようになる。(なぜ、そうなるか、それを考える。)
現状を打開しようとする。(空漠とした日々に耐えられなくなる。)
(2)反復期…疑問と否定を繰り返す。
「これでいいいのか」という疑問。(「夫婦というのは、どういうものか」と悩む。)
「これでいい」「しかたない」という否定。(自分を納得させる。)
(怒り)と(絶望感)でもよい。(妥協と衝突を繰り返す。)
その2つが、交互に心の中に現れては消える。
家族、親類、社会……もろもろの「糸」にからまれる。(とくに子どもの問題。)
もがく。
苦しむ。
(3)確認期…「これでいい」という確信をもちはじめる。
苦しんだ分だけ、心が研ぎ澄まされてくる。(ものごとを割り切るようになる。)
拾い出すものと、棄てるものを、選び分ける。(みなによい顔ができないことを知る。)
それらを天秤にかけながら、取捨選択を繰り返す。(居直る。)
「みなにいい顔はできない」ことを知る。
(4)決断前夜…身辺の整理を始める。
身辺の整理を始め、同時進行の形で、心の準備を整える。(覚悟を決める。)
未練の燃焼。(思い残すことがないよう、準備する。)
後悔しないことの確認。
前に向かって進む勇気の確認、(うしろを見ない。振り返らない。)など。
(5)決断期…未練をふっきり、決別を決断する。
過去を消し、未来だけを前に置く。
行動として、それを表現する。(離婚を申し出る。)
●2人の人によい顔はできない
どんな形であるにせよ、また人知れずそれをしたところにせよ、
それをよしとしない人は、かならず現れる。
そういった人にとっては、理由など、何でもよい。
(自分たちから去っていくこと)自体が、悪であり、まちがっているという
ことになる。
似たような現象は、カルト教団でもよく見られる。
カルト教団にしてみれば、去っていくこと自体、まちがっているということに
なる。
理由があるとしても、あとから理由、つまりこじつけすぎない。
「あいつは親の面倒すら、ロクに見なかった」
「親の一周忌すら、簡単にすませた」
「私への借りを踏み倒した」などなど。
いろいろ理由をこじつけて、あなたを非難する。
自分から去っていく人間を肯定することは、そのまま自己否定につながる。
だから(去られる側)は、周囲を巻き込んで、援軍を求める。
熟年・離縁を覚悟する人は、そうした人たちすべてとも縁を切る。
誤解を解くという方法も残されているが、それには相当のエネルギーが必要。
また残された時間は、それほどない。
だから、「思いたければ、勝手に思え」という方法で、居直る。
居直るしかない。
「すべてを断ち切る」という覚悟をもつしかない。
●悪役一筋
たとえば私は、親類の中では、悪役だった。
遠くに住むことをよいことに、母は、私を悪役に仕立てた。
何かつごうの悪いことがあると、すべて私の責任にした。
その中でも、最大の問題が、祖父が残し遺産の相続問題。
祖父が他界し、数年後に父が他界した。
祖父は3筆の土地を残した。
その土地を自分名義のものするため、母は、私を悪役に仕立てた。
「私は遺産などいらないが、息子の浩司がうるさいから、判を押してくれ」と。
親戚中に泣きついた。
つまり私がうるさくて困っているから、遺産相続放棄の書類に判を押してくれ、と。
が、私はそういうことを母がしているとは、まったく知らなかった。
また遺産相続について、私が口を出したことは、一度もない。
結局母は、自分の思い通りに、ことを運んだ。
同時に、私は、悪者になった。
誤解と言えば誤解だが、私自身も、最終的には利益を享受するという点で、
それ以上のことは、何も言えなかった。
また当時の私にしてみれば、いくら誤解を解くためとはいえ、親の悪口を言うことは
許されないことだった。
私は沈黙を守った。
叔父の1人に顔面を数発殴られたこともあるが、それでも沈黙を守った。
●熟年・離縁
しかしこれも人生。
私の人生。
世の中には、もっと複雑で、不愉快な運命を背負って生きている人がいる。
またそういう人の方が、多い。
みな、それぞれが、それぞれの運命を背負いながら、懸命に生きている。
私もそうだし、あなたもそうである。
その(懸命さ)こそに、生きる意味がある。
無数のドラマも、そこから生まれる。
私の母にしても、一時は、私は母を恨んだ。
心の水が枯れるまで、恨んだ。
しかし今はちがう。
「母は母で、あの時代を懸命に生きた」という思いの方が優勢である。
かく言う私だって、たいした人生を送っているわけではない。
偉そうなことを言える立場ではない。
もし私が母と同じ立場に置かれたら、私もやはり母と同じことをしていただろう。
それを考えると、どうも自信がもてない。
で、9月X日。
私は故郷のM町と、縁を切る。
怒っているからでも、また不愉快に思っているからでもない。
人生には、結末というものがある。
その準備として、縁を切る。
私の故郷は、ここ浜松市である。
それをさらに確固たるものにするため、縁を切る。
だから今、さばさばとした気持ちで、
本当にさばさばとした気持ちで、こんな歌を歌う。
「♪さらば、ふるさと、さらば、ふるさと、ふるさと、さらばあ〜」と。
(ただし歌のような涙は、一滴も出ない!※)
恐らく熟年離婚をして夫のもとを去っていく妻も、似たような気持ではないか。
夫には、理解できないかもしれないが……。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 熟年離婚 熟年離縁 熟年・離縁)
(注※:補記)
♪『故郷を離るる歌』(ドイツ民謡)
園の小百合、撫子、垣根の千草、
今日は汝(なれ)を眺むる最終(おわり)の日なり。
おもえば涙、膝をひたす、さらば故郷(ふるさと)。
さらばふるさと、さらばふるさと、故郷さらば。
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●衆議院議員選挙(8月30日)
++++++++++++++++++
浜松7区。
3人の立候補者がいる。
順に、
(1)現職の、片山S氏衆議院議員・元官僚・自民党)
(2)前職の、城内M氏・元官僚・元自民党)
(3)新人の、斉木T氏・元アナウンサー・民主党)
+++++++++++++++++++++
今日(29日)までの予想によれば、この7区だけは、週刊誌によって、みな、ちがう。
片山氏優勢というのもあれば、城内氏優勢というのもある。
新人の斉木氏について言えば、「新人」ということで知名度が低い。
しかし「民主優勢」の流れに乗って、他の2人の候補者に肉薄しつつある。
こういうとき、浮動票の王様を自称する私は、むずかしい選択に迫られる。
浮動票層には、浮動票層としての、プライドがある。
哲学もある。
その第一。
自分の入れる票は、死に票にしたくない。
ぜったい敗れるとわかっている候補者には、貴重な一票は入れない。
その第二。
浮動票は、言うなればバランス票。
バランス感覚を重要視する。
本来なら、今回のように、自民党ベタ負けとわかっているというときには、
自民党に一票を入れるということも、当然、考える。
民主党のベタ勝ちというのは、浮動票層の望むところではない。
またそれは日本の民主主義制度にとっても、よくない。
が、今回は、異変が起きた。
「激戦区」というよりは、「混戦区」。
片山氏と城内氏は、いうなれば同じ穴のムジナ。
城内氏は、もともと自民党。
当選すれば、自民党に復帰する。
自民党系の票は、片山氏と城内氏の2人で、分け合う形になる。
こうなれば、斉木氏有利!
一方、城内氏と斉木氏の関係も、それに似ている。
城内氏は、地元では人気度が高い。
片山氏と一対一の一騎打ちになれば、今回は、城内氏が勝つはず。
これに対して斉木氏は、民主党優勢の流れに乗っている。
反自民党の票は、城内氏と斉木氏の2人で、分け合う形になる。
こうなれば、片山氏有利!
つまり三つ巴の混戦状態。
地元の雰囲気からすると、(あくまでも私の印象だが……)、
城内氏が有利、そのあとを、片山氏と斉木氏が猛追しているといった
ところか。
が、自民党の片山氏に票を入れても、死に票になる。
今回は、当選は無理。
そこで城内氏に入れるか、斉木氏に入れるか……?
そのとき第一に考えるのが、城内氏が元自民党であること。
(繰り返すが、当選すれば、当然、自民党に復帰。)
斉木氏が民主党であること。
自民党か民主党かということになれば、今の流れからすれば
民主党ということになる。
が、先にも書いたように、城内氏の支持基盤は固い。
となると、最終的にそれを決めるのは、私たち浮動票層ということになる。
つまり、投票率。
投票率で決まる。
投票率が高ければ高いほど、斉木氏(民主党)に有利になる。
(一方、投票率が低ければ低いほど、片山氏に有利になる。)
現在までの予想によれば、明日のこの7区の投票率は、80%近くになると言われて
いる。
ということは、斉木氏が、がぜん有利ということになる。
では、どう判断したらよいのか。
(1)バランス感覚が働かない
今回の選挙で特徴的なのは、本来なら働くはずのバランス感覚が、
働かないということ。
AS首相は、昨日、「自民党の支持率が低いのは、今までの自民党に責任が
ある」というような発言をした。
これなどは、言い逃れもよいところ。
AS首相という人は、自分のことがまるでわかっていない。
わかっていないから、鉄槌を加えてやるしかないということになる。
AS首相は、こう述べている。
『……自民党にとって、今回の衆院選で、与党が「3分の2」を失うというのは早くから
の既定路線だった。AS首相は衆院解散後「与党で過半数なら、引き続き信任をいただい
たことになる」と、事実上の勝敗ラインを過半数の241議席に設定した』と。
(もしここで自民党が善戦したということにでもなれば、AS首相の続投
が決まってしまう。
それだけは生理的にも、許せない。)
……ということで、私は明日の投票率をにらみながら、だれに一票を入れるかを
決める。
投票率速報をにらみながら、夕方遅く投票所に向かうつもり。
投票率が低いようであれば、XX氏。
投票率が高いようであれば、YY氏。
同時に片山氏だけには、勝たせたくない……。
(GOOD NEWS)
今回の選挙で、自民党が大敗北を期したとしたら、自民党の派閥そのものが
消滅することになる。
あの悪名高い、派閥政治の終焉。
親分(領袖)が落選する。
資金の流れも、止まる。
族議員も消える。
つまり派閥そのものが、成り立たなくなる。
これだけでも、とてもすばらしいことだ。
どこかのタブロイド紙は、「日本の革命」と書いていたが、まさに「革命」。
「革命」と言うにふさわしい。
明日、その日がやってくる。
(付記)
総選挙の結果は、
(1)城内M氏が、小選挙区で当選。
(2)斉木T氏は、小選挙区で落選したものの、比例区で当選。
(3)片山S氏は、落選。
投票率が予想外に低く、70%に届かなかった。
Hiroshi Hayashi++++++++AUG 09++++++++はやし浩司
●日本の総選挙(General Election of Japan, Farewell to the Rotten Politics of Japan!)
We feel something has been changing rapidly and dynamically. We hope this would be
the end of rotten politicsof Japan.
+++++++++++++++++++
昨夜は、眠い眼(まなこ)をこすりながら、
夜遅くまで、選挙報道をテレビで見ていた。
結果は、みなさんご存知の通り。
民主党が、最終的に308議席。
自民党が、119議席。
民主党の完全圧勝で終わった。
これからは、30代を中心とした若い人たちが、
政治の中心を担うことになる。
すばらしいことである。
言い換えると、今までの自民党政治は、あまりにも
ドロドロしかった。
薄汚かった。
カネと権力。
言うなれば、腐敗したゴミの山。
それがその底流で、渦を巻いていた。
今回の総選挙は、一応、それを一掃してくれた。
これから先のことはわからないが、民主党政権の
これからに、強く期待したい。
がんばれ、民主党!
+++++++++++++++++++
●AS首相
それにしても醜いのが、AS首相。
この場に及んでも、自分の責任を認めるどころか、安倍首相、福田首相の辞任劇を、
敗因の理由にあげている。
自分だって、国民の審判を受けて総裁になり、総理大臣になったわけではない。
そのAS首相が、そう言う。
そのおかしさ。
今回の敗因の理由の第一は、もちろん、AS首相、彼自身にある。
それを棚に上げて、テレビ画面に向かって、さかんに「自民党の3分の2の支持を得て、
総裁になった」と主張していた。
「私には責任はない」と言わんばかりの口調である。
自己矛盾もはなはだしい。
本来は、選挙までの暫定内閣として発足したAS内閣。
そのAS内閣のAS首相は、そのつどああでもない、こうでもないという理由を
こじつけて、政権の座に居座った。
その見苦しさ。
つまりその結果が、今回の総選挙ということになる。
本来なら自民党内部でさえ、袋だたたきにあってもしかたない立場。
ところがその袋叩きする人すら、今の自民党には、いない。
AS首相は記者の質問に答えて、「政治は大きなうねりの中で、よいときもあれば、
悪いときもある」というようなことを言っていた。
が、それはどうか?
へたをすれば、自民党は、このままバラバラになってしまうだろう。
もともと主義主張、つまり正義が(柱)にある党ではない。
金(マネー)と権力。
この2つだけで、これから先、どうやって自民党をひとつにまとめていくつもりなのか。
先ほどざっと世界の報道記事に目を通してみた。
世界中が、速報の形で、日本の総選挙の結果を伝えていた。
「日本は今、大きな転換期を迎えた」というのが、おおかたの見方である。
そう、今、日本は、大きく変わりつつある。
この流れは、もうだれにも止められない!
(8月31日記)
Hiroshi Hayashi++++++++AUG.09+++++++++はやし浩司
最前線の子育て論byはやし浩司(090901)
●米朝平和協定・絶対阻止!(Down with the Peace Treaty between USA and North
Korea)
+++++++++++++++++
今日から9月。
9月1日。
ときに書きたいことが枯渇することがある。
書きたいことが何もなくなり、ただぼんやりと
時間を過ごす。
が、今朝はちがう。
書きたいことが、山のようにある。
あれも、これも、と。
どこから手をつけてよいのか、わからない。
++++++++++++++++++
●米朝平和協定(We should never accept or admit the "Peace Treaty between USA and
North Korea, which would bring Japan the greatest political damage.)
++++++++++++++++++
日本よ、民主党政権よ、どんなことがあっても、
米朝平和協定なるものの締結だけは、阻止しろ!
ぜったいに結ばせてはならない。
これは日本の死活問題。
もしアメリカと北朝鮮の間で、「米朝平和協定」
なるものが結ばれたら、それこそ日本はそのあと、
たいへんなことになる。
まさに北朝鮮に言いなり。
言いなりになるしかない。
北朝鮮の核兵器におびえながら、日本は、莫大な戦後補償費
なるものを絞り取られる。
「金を出せ」「出さなければ、戦争だ」と。
わかるか?
米朝平和協定が結ばれたら、アメリカ本土が攻撃され
ないかぎり、いくら北朝鮮が日本を攻撃しても、
アメリカは、それに対して手も足も出せなくなる。
つまりそれこそが、北朝鮮のねらい。
つまりこの時点で、こと北朝鮮に関するかぎり、
日米安保条約は死文化する。
「アメリカと北朝鮮が仲良くなればいい」という
ような単純な問題ではない。
またこれはそういう問題ではない。
北朝鮮の立場で、ものを考えてみれば、それがわかる。
北朝鮮にとっては、在日米軍は、まさに目の上のタンコブ。
在日米軍が日本に駐留しているかぎり、北朝鮮は
日本に対して、何もしかけることができない。
そこで「米朝平和協定」ということになる。
また今回、鳩山内閣が組閣されるについて、TJ氏
(私の三井物産時代の元同僚)が、首相の顧問団に
加わることになった。
TJ氏は、かねてより、「対米追従外交反対」を
唱えている。
行き過ぎたアメリカ追従主義にも問題がある。
あるが、しかし現実には、日本の平和と安全は、アメリカ軍
によって守られている。
この事実は、(現実)であり、だれにも動かしがたい。
それを忘れてはならない。
けっして理想主義に突っ走ってはいけない。
聯合ニュースは、つぎのように伝える(09年8月31日)
+++++++++++以下、聯合ニュース+++++++++++
【ソウル8月31日聯合ニュース】北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル)総書記が、北朝
鮮の緊張状態を緩和し戦争の危険を取り除く問題は「米国がわが共和国に対する敵対視政
策を捨て、朝米(米朝)間で平和協定を締結してこそ解決できる」と述べたと、北朝鮮の
対外用放送、平壌放送が31日に報じた。ただ、金総書記がいつどこで、こうした発言を
したかについては明らかにされなかった。
平壌放送は1999年9月29日にも、金総書記が「戦争の危険を取り除き平和を担保
するには、われわれと米国間で平和協定を締結し平和保障体系を策定するべき」だと述べ
たと伝えている。(聯合ニュース)
+++++++++++以上、聯合ニュース+++++++++++
アメリカには、北朝鮮を攻撃する意図など、最初からみじんもない。
ないことを知りつつ、「平和協定」の締結を求める。
その理由は、ここに書いたとおりである。
繰り返す。
米朝平和協定の締結は、どんなことがあっても、日本は阻止しろ!
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●「明治維新以来の大変革」
++++++++++++++++
今回の総選挙について、外国のメディアは、
おおむねつぎのように伝えている。
オーストラリアの(ジ・オーストラリアン紙)の
記事を紹介する。
++++++++++++++++
【ジ・オーストラリア紙より】
(翻訳は、Lingoes)
Pivotal moment in Japan's history(日本の歴史のターニングポイント)
Greg Sheridan, Foreign editor | August 31, 2009
Article from: The Australian
YUKIO Hatoyama's victory is a pivotal point in modern Japanese history.
鳩山由紀夫氏の勝利は近代日本の歴史において極めて重要なポイントです。
And when Japan pivots, the consequences for Australia are enormous.
Hatoyama and his Democratic Party of Japan promise to break down the influence of Japan'
s
s
all-powerful bureaucracy and put power into the hands of politicians.
そして、日本が枢軸、オーストラリアの巨大されている結果。
鳩山氏と民主党の政治家の手に渡って、日本のすべての強力な官僚制とputの力の影響を打
破す
破す
る日本の約束。
They also promise to reverse the crippling fertility decline, which has led to Japan's
population
population
starting to decrease, to seek a more independent foreign policy, to redistribute money and
spending power to the consumer and most of all to normalise Japanese politics - to create
a
a
competitive two-party system. It's a grand sweep of history, to wipe away the post-war
settlement
settlement
under which Japan has changed government just once since the mid-1950s.
彼らはまた、日本の人口が減少し始めてつながっている壊滅的な出生率低下は、逆に、消費
者に
者に
お金と購買力を再配布して、すべてのほとんどは日本の政治を正常化する-競争力を作成す
るた
るた
めに複数の独立した外交政策を追求することを約束二大政党制。これは、歴史のポストの下
で日
で日
本は1回以来、政府が変更されて戦争の和解をぬぐうための壮大な掃引、の1950年代半ば。
It could be as big and bold and thunderingly significant as the last two great Japanese
pivots -
pivots -
the Meiji Restoration in the late 1800s and the post-war economic revival.
Both of those pivots had colossal consequences for Australia.
これは大きくて大胆かつthunderinglyの最後の2つの偉大な日本の枢軸として大きな-明治維
新
新
後、1800年代後半に、戦後の経済復興ことができる。
両方のこれらのピボットのオーストラリアの巨大な影響をもたらした。
The Meiji Restoration modernised a previously feudal society. But Japan took on some of
the
the
most unpleasant aspects of modernisation - such as colonialism and militarism. The Meiji
Restoration led to the industrial and military behemoth Australia fought in World War II.
明治以前は封建社会の近代化。しかし、日本のいくつかの近代化の中で最も不快な側面をし
た-
た-
植民地主義や軍国主義など。明治維新オーストラリア二次世界大戦に参戦した産業や軍事巨
大に
大に
つながった。
The post-World War II restoration, when Japan embraced defeat and took all the
opportunities an
opportunities an
enlightened US dominance provided, was also of profound importance to Australia. Japan's
economic growth in the second half of the 20th century, more than any other external
factor,
factor,
powered Australian economic growth.
後の日本が敗戦を受け入れて悟りを開いた米国の独占提供するすべての機会だった二次世
界大
界大
戦の修復も、オーストラリアへの深い重要なものでした。 20世紀の後半に日本の経済成長
は、
は、
他の外部的な要因より、電源がオーストラリアの経済成長率よりも。
So we have our war legends because of the Japanese, and we also have our contemporary
prosperous Australian society because of the Japanese.
Japan is still Australia's largest export market. It is still the biggest Asian investor in
Australia.
Australia.
And because the US strategic position in Asia depends utterly on Japan, Tokyo is still the
most
most
important player in regional security for Australia.
How will Hatoyama make things different?
だから我々は戦争をするための伝説、日本語、また日本語のための私達の現代的な豊かな
オース
オース
トラリアの社会にしている。
日本はオーストラリア最大の輸出市場である。まだオーストラリアではアジア最大の投資家で
あ
あ
る。とはアジアでの米国の戦略的位置は全く日本に依存し、東京がまだオーストラリアの地域
の
の
安全保障の中で最も重要なプレーヤーです。
どのように鳩山氏は物事を一味違ったものでしょうか?
Some of his economic populism is dangerous. Some of it opposes the market-based reforms
that Japan's economic system, which has its brutally efficient parts and its astonishingly
bureaucratic and inefficient parts, still needs.
いくつかの彼の経済的ポピュリズムは危険です。それのいくつかは、市場は反対に、その残酷
な
な
効率的な部品とは、驚くほど、官僚主義や非効率な部分が日本の経済システムは、まだその
ニー
ニー
ズに改革した。
In some areas, Hatoyama has not so much repudiated the ruling Liberal Democratic Party
as
as
simply made a takeover bid for some of its constituencies, offering for example the same
antique
antique
protection to Japan's wildly expensive and inefficient agricultural sector as the LDP has
done.
done.
Hatoyama himself began his political career in the LDP, and one of the dangers of the new
situation is that the DPJ simply inherits the LDP's patronage system of politics and
perpetuates
perpetuates
the iron triangle - of bureaucrats, business leaders and politicians scratching each other's
backs.
backs.
But Japan hungers for change. Japan's last successful prime minister, the redoubtable
Junichiro
Junichiro
Koizumi, already tried to push greater power to politicians and away from the bureaucracy.
This
This
process, if Hatoyama completes it, would make Japanese politics more transparent,
competitive
competitive
and nimble in its responses.
一部の地域ではそれほど単純に、いくつかの選挙のための買収提案を行ったとして、例えば、
自
自
民党の行っているとしての日本の非常に高価で、非効率的な農業部門には、同じアンティーク
な
な
保護を提供する自民党を否定、鳩山しています。
鳩山氏自身は、自民党内の政治的キャリアを開始し、1つの新たな状況の危険性については、
民
民
主党は、単に政治の自民党の庇護のシステムを継承し、鉄の三角形の官僚は、ビジネスリー
ダー
ダー
や政治家が互いの背中スクラッチ-を永続させています。
しかし、変化は、日本ハンガー。日本の最後に成功した首相は、恐るべき小泉純一郎首相
は、す
は、す
でに政治家に大きな力をプッシュするとの距離は官僚から試みた。このプロセスは、場合、鳩
山
山
氏は、それが完了する、日本の政治の透明性を作ると競争し、その応答に軽快。
But it is hard to read Hatoyama's policy pronouncements. He has softened earlier
opposition to
opposition to
free trade agreements, such as the one Canberra is trying hard to negotiate with Tokyo.
Hatoyama will certainly never give total free access for Australian farmers to the Japanese
food
food
market, but he might be prepared to move enough to make an FTA of some kind a
possibility.
possibility.
Hatoyama wants a more independent foreign policy for Japan. In the past this was code for
Japan seeking a more equal alliance with the US.
しかし、鳩山氏の政策の公式見解を読むことは難しい。彼は、1つのキャンベラなどのハード東
京都と交渉するとしている自由貿易協定に、以前の野党軟化しています。
鳩山氏は、確かに日本の食品市場、オーストラリアの農民のための合計の無料アクセスを提
供す
供す
ることはありませんが、彼に移動する準備かもしれないFTAのいくつかの種類の可能性を確認
するのに十分。
鳩山氏は日本の複数の独立した外交政策を望んでいる。過去には、この日本のコードでは、
米国
米国
との対等な協力関係を求めていた。
But the irony was that greater independence allowed Tokyo to do more things that
Washington
Washington
wanted, such as dispatching troops to peacekeeping operations, making the US-Japan
alliance
alliance
reciprocal, or supporting the US military logistically in the war on terror.
Hatoyama has opposed Japan's refuelling ships engaged in the conflict in Afghanistan.
But he won't stop the practice immediately. He will let the current arrangements run their
course
course
until early next year and simply then plans not to renew the relevant legislation.
しかし皮肉なことに一層の自立東京より多くのものは、ワシントンなど、平和維持活動に軍隊を
派遣するなどやりたいことができたの日米同盟は、相互に、または論理学対テロ戦争で米軍
の支
の支
援を行っていた。
鳩山氏は、日本の給油発送アフガニスタンでの紛争に従事して反対している。
しかし、彼はすぐにその習慣をやめることはありません。彼は、現在の取り決めは来年初めま
で、
で、
そのコースを実行し、単純にしてできるようになる関連法規を更新しない方針だ。
But all this is a work in progress. It could all change. The DPJ, though it contains
fundamental
fundamental
internal divisions on the US alliance, will not threaten the alliance fundamentally.
Hatoyama will want to get on well with the Obama administration and co-operate, especially
on
on
issues such as climate change and the shaping of the G20 summit process as the key
instrument to respond, at the policy co-ordination level, to the global financial crisis.
Hatoyama will almost certainly continue close co-operation with Canberra as well.
しかし、これは進行中の作業です。これはすべての変更があります。民主党はしかし、これは、
韓米同盟関係を根本的に内部分裂が含まれて根本的に同盟を脅かすことはありません。
鳩山氏も、オバマ政権と共同で、問題は特に、気候変動などとして動作するとうまくやってする
必要がシェーピングポリシーのコーディネーションのレベルには対応するキーの楽器として、
G20首脳会談のプロセスのグローバルな金融危機。
鳩山氏は、ほぼ間違いなくキャンベラとも緊密な協力を継続されます。
It is instructive to examine the experience of the late Roh Moon-hyun in South Korea. Roh,
whose presidency finished last year, came to office with a background in radical labour union
law
law
and was a harsh anti-American and well to the left of the Korean political spectrum. He
looked
looked
much more radical than Hatoyama.
これは、後半に盧大統領はムーンの経験は、韓国の大統領を調べることは有益です。盧大統
領は、
領は、
その大統領は、昨年完成のオフィスに過激な労働組合法の背景に来て、過酷な抗され、また、
韓
韓
国の政治的スペクトルの左側にあるアメリカ。彼は多くの急進的な鳩山も見えた。
But in office he negotiated a free trade agreement with Washington and sent thousands of
Korean troops to Iraq, essentially to make sure the alliance with the US stayed healthy.
Hatoyama's other big foreign policy challenge is integrating China into Asia-Pacific and
regional
regional
institutions.
しかし、オフィスで彼はワシントンとの自由貿易協定を交渉し、イラクへの韓国軍の何千もの送
信、本質的に確認して、米国との同盟関係を健全に宿泊された。
鳩山氏の他の大きな外国の政策課題、アジアの中に中国に統合されて太平洋地域機関。
A centre-left leader is expected to get on well with China, but as Kevin Rudd shows, this
doesn't
doesn't
always work out. Further, when Japan has self-confident prime ministers with strong
political
political
bases, they tend to squabble with China.
Almost everyone in Japan, and almost everyone in the world concerned with Japan, wants
Hatoyama to produce key changes.
But they also want him to produce key continuities.
He may not get the balance right. He won't please everyone. But we may be witnessing
another,
another,
gigantic, Japanese pivot.
中心リーダー左だけでなく、中国との上を取得するが、期待されてケビンラッドを示し、これは
常にうまくされません。さらに、日本が強力な政治的拠点と自信の首相が、彼らは中国と口論
す
す
る傾向にある。
世界は日本との関係で日本では、ほとんどみんな、ほぼ全員が、鳩山氏は主要な変更点を生
成す
成す
る望んでいる。
しかし、彼らも彼のキーの連続性を生成します。
彼は正しいバランスを得ることはできません。彼は全員を満足されません。しかし、我々は、日
本ピボット別の、巨大な目撃されることがあります。
++++++++++++++++++++
●オーストラリアの友人たちからも、メールが届いている。
Hi Hiroshi,
Interesting times in Japanese politics!
(日本の政治に、興味深いことが起きている。)
What do you think about it.?
(君は、どう思うか。)
One of our local commentators has the opinion that this is an event in
Japanese history as important as the Meiji Restoration & the Economic
miracle after WW2.
ぼくたちの地方のコネンテイターは、今回の選挙結果は、明治維新や、戦後の
高度成長というあの奇跡に匹敵するほど、日本の歴史には重要なできごとである
と述べている。
Cheers,
バイ
B
+++++++++++++++++++++
G'day mate,
(やあ、こんにちは!)
I am interested to know what you think about the election result. I guess the important
thing is
thing is
politicians think about the nation first.
D
今回の選挙結果について、君がどう考えているか、興味をもっている。
重要なことは、政治家が、国家をまず第一に考えることだと思う。
++++++++++++++++++++++++
【民主党政権へ】
世界の期待は大きい。
こうした期待を裏切らないよう、どうかがんばってほしい。
(090901記)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
・
・
・
・
・
*********************************
彡彡人ミミ 彡彡彡彡彡
| ⌒ ⌒ | MM ⌒ ⌒ MM
q 0―0 MMMMM ∩ ∩ MM m
(″ ▽ M ⌒ ⌒ M″ v ゛)/ ̄)
凸/Σ▽乃q ・ ・ p ̄Σ▽乃 ̄` /
\ /(″ ▽ ゛)\ 厂 ̄偶
===○=======○====================
子育て最前線の育児論byはやし浩司 09年 10月 2日号
================================
10月2日……1260号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━――――――――――――――
★★★★★★★★★★HTML版★★★★★★★★★★★
マガジンを、カラー版でお楽しみください。(↓)をクリック!
http://bwhayashi2.fc2web.com/page016.html
メルマガ(6万3000誌)の中で、2008年度、メルマガ・オブ・ザ・イヤーに
選ばれました!
********安全は確認しています。どうか安心して、お読みください*****
【1】(子育てのこと)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●子どもは、家族の「代表」
++++++++++++++++++++
子どもは、家族の「代表」。
代表にすぎない。
今では、それは、常識。
子どもに何か問題があったとしても、
それは子どもだけの問題ではない。
家族全体の問題。
そのように、考える。
またそのように考えないと、子どもの問題は
解決しない。
しかしそれだけでは足りない。
足りないという話を、今までの経験を交えながら
書いてみたい。
+++++++++++++++++++
●優等生
その母親(当時60歳)は、自分の息子(33歳)をさして、「うちの子ほど、
すばらしい息子はいない」と言った。
自分の息子をさして、「すばらしい」と言う親は、珍しい。
外国では多いが、日本では珍しい。
そこで私はその息子氏に会ってみたくなった。
が、その日は、その直後にやってきた。
ある葬儀に出たときのこと。
その息子氏は母親のそばに寄り添うように、そこに座っていた。
「ああ、これがあの息子か」と、私は思った。
思いながら、私はその息子氏にあれこれと話しかけてみた。
が、第一印象は、言うなれば、完璧に近いほど、マザコン。
穏やかで、おとなしいが、覇気がなく、静か。
私が話しかけても、はにかむだけ。
満足な返事もない。
どこかの電気会社の下請け企業で、技術者として働いているということだった。
私「仕事はどう?」
息「うん、まあまあ」
私「暑いときは、たいへんだね」
息「うん、ふふふ……」と。
●同一性の確立
親はそれぞれの思いをもって、子育てを始める。
自分の夢や理想、思いを子育てに凝縮させる。
自分なりの(子ども観)をもつ人も多い。
それ自体は、悪いことではない。
が、親が思い描く子ども観を、子どもに押し付けてはいけない。
「求める」ことまではしても、押し付けてはいけない。
それが度を越すと、過干渉となる。
その息子氏は、母親の過干渉で、人格そのものまで、押しつぶされてしまっていた。
思春期前期から、思春期にかけて、自我の同一性の確立に失敗した。
私は、そう判断した。
だから人格の「核」がない。
「この人は、こういう人だ」という(つかみどころ)を「核」という。
その「核」がない。
軟弱で、ひ弱。
たしかに(いい人)だったが、それだけ。
面白みがない。
迫力もない。
●過干渉
原因は、ここにも書いたように、母親にあった。
口うるさい人だった。
葬儀の席だったが、そんなとことでさえ、こまごまとしたことを、矢継ぎ早に
指示していた。
「あの扇風機を、こちらに向けなさい」
「ざぶとんを、あの人に出しなさい」
「お茶をわかしてきなさい」と。
息子氏は、黙ってそれに従っていた。
つまりこうした親子のリズムが、その息子氏をして、そのような息子にした。
が、ここで最大の問題は、息子氏のことではない。
母親自身にその自覚がないということ。
先にも書いたように、母親自身は、そういう息子を、「すばらしい子ども」と誤解して
いた。
●病識
精神病の世界にも、「病気意識(病識)」という言葉がある。
「私はおかしい」「へんだ」と思っている人は、まだ症状が軽い。
しかし「私はだいじょうぶ」「何でもない」とがんばる人ほど、症状は重い。
まったく病識のない人さえいる。
同じように、自分の子どもの問題点に気がついている母親は、まだよい。
指導ができる。
そうでない母親は、指導そのものが、できない。
たとえば年中児(4〜5歳児)でも、親の過干渉が原因で、精神そのものまで
萎縮してしまったような子どもがいる。
けっして少なくない。
10人のうち、1人はいる。
程度の差も含めれば、10人のうち、2〜3人はいる。
しかしそういう子どもの親ほど、「うちの子どもはできがいい」と思い込んでいる。
またそういう子どもにしようと、無理をしている。
で、その一方で、ほかの子どもを、「できの悪い子ども」として、排斥してしまう。
自分の子どもから遠ざけてしまう。
●極端化
小さな世界に閉じこもり、自分だけの世界で、子育てをする親がふえている。
以前はそれを「核家族」と呼んだ。
今は、「カプセル家族」と呼ぶ。
このタイプの家族は、大きく2つに分けられる。
(1)親たち自身が高学歴で、外の世界の価値を認めない。
(2)親たち自身が低学歴で、外の世界の価値を理解できない。
どちらであるにせよ、一度カプセルの中に入ってしまうと、その狭い世界で、
自分だけの価値を熟成させてしまう。
結果として、独善的になったり、社会から孤立化したりする。
これがこわい。
一度カプセルの中に入ってしまうと、同じ過保護でも極端化する。
過干渉でも極端化する。
これが子育てそのものを、ゆがめる。
●A君(小2)の例
A君は、幼児期のときは、まだ明るかった。
何かの勉強をしていても、楽しそうだった。
が、小学校へ入学したとたん、表情が暗くなった。
もともと勉強が得意ではなかった。
言葉の発達も遅れ気味だった。
そのため母親が、かかりっきりで、A君を指導した。
A君は、月を追うごとに、やる気をなくしていった。
私の教室でも、フリ勉(勉強をしているフリをする)、
ダラ勉(ダラダラと時間ばかりかけて、何もしない)、
時間つぶし(ほかの作業をして、時間をつぶす)などの症状が見られるようになった。
こうなると、つまりこの時期に一度、こうなると、症状は、ずっとつづく。
「直る」のは、ほぼ不可能とみてよい。
(ますます勉強から遠ざかる)→(無理な家庭学習が日常化する)の悪循環の
中で、症状は、ますますひどくなる。
それ以上に、学校での学習量がふえる。
学校での勉強が追いかけてくる。
A君はその負担に、ますます耐えられなくなる。
●迷い
こういうケースでは、親にそれを告げるべきかどうかで悩む。
親にそれだけの問題意識があればよい。
が、そうでないケースのほうが多い。
「まだ何とかなる」「うちの子にかぎって……」「やればできるはず」と。
それにこの時期、「過負担を減らしましょう」と言うことは、親にしてみれば、
「勉強をあきらめなさい」と言うに等しい。
親がそれを受け入れるはずがない。
とても残念なことだが、親というのは、行き着くところまで行かないと、自分では
気がつかない。
これは子育てというより、家庭教育のもつ宿命のようなもの。
私の立場では、自分のできる範囲で、また自分の世界で、(最大限)、指導するしかない。
この世界には、『内政不干渉の大原則』という原則もある。
で、実際問題として、この時期、それを親に告げると、私のほうにはその意図が
なくても、親は、「拒否された」ととる。
そのまま私のところを去っていく。
●いい子論
話を戻す。
そんなわけで、「いい子論」は、家庭によって、みなちがう。
子育ての目標がちがうように、みなちがう。
冒頭に書いた息子氏について書く。
母親は、かなり権威主義的なものの考え方をする人だった。
「親絶対教」の信者でもあった。
「先祖」「親孝行」という言葉をよく使った。
ものの言い方が威圧的で、一方的だった。
一見穏やかで、やさしそうな言い方をする人だったが、それは仮面。
息子氏や、ほかの娘たちが口答えでもいようものなら、烈火のごとく、それを叱った。
「親を粗末にするヤツは、地獄に落ちる」が、その母親の口癖だった。
息子氏はそういう環境の中で、ますます萎縮していった。
で、悲劇は、その数年後に起きた。
妻のほうが、一方的に離婚を宣言し、子どもを連れて、家を出てしまった。
息子氏の母親は、息子氏の妻(嫁)を、はげしくののしった。
が、そういう面もなかったとは言わない。
いろいろあったのだろう。
しかし離婚を宣言した妻の気持ちも、よくわかる。
「あの息子と、あの姑(しゅうとめ)では、だれだって離婚したくなる」と、
私は、そのときそう思った。
●では、どうするか
「まず、自分を知る」。
それが子育てにおいては、必須条件ということになる。
この世界では、無知は罪悪。
無知であることを、居直ってはいけない。
そのためには、もしあなたの生活がカプセル化しているなら、風穴をあけ、
風通しをよくする。
もしそれでも……ということであれえば、私が用意した「ママ診断テスト」を
受けてみてほしい。
(私のHPより、「最前線の子育て論」→「ママ診断」へ。)
平均的な母親たちと、どこがどうちがうかを知ることができる。
平均的であればよいということにはならないが、自分の子育てを、ほかの人と
比較することはできる。
つぎに、たとえば学齢信仰、学校神話、出世主義、権威主義に毒された子育て観を
改める。
世界も変わった。
世間も変わった。
しかし子育ての基本は、変わっていない。
子育ての基本は、1000年単位、2000年単位で、繰り返されるもの。
その原点に立ち返る。
というのも、子どもというのは、子ども自身が自ら伸びる(力)をもっている。
あらゆる動物や、植物がそうである。
その(力)を信じ、その力を(引き出す)。
それが子育ての原点ということになる。
言うなれば、子育ての原理主義ということか。
しかし何かのことで迷ったら、そのつど原点に立ち返ってみる。
意外とその先に、「道」が見えてくるはず。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
子育ての原理主義 無知は罪悪 萎縮する子ども 過干渉 いい子論 はやし浩司
よい子論 覇気のない子供 家族の代表 代表論 子供の問題)
【2】(特集)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●温泉の注意書き
+++++++++++++++++++
このところ毎週のように、温泉街のひとつに
ある温泉浴場に、足を運んでいる。
最近オープンしたばかりの、温泉浴場である。
そこでのこと。
毎回のように、注意書きがふえているのに
気がついた。
最近見たのには、こうあった。
「おむつ、尿取りパッドなどを使用している
方の入浴は、ご遠慮ください」と。
おむつというのは、赤ん坊のそれをいう。
それはわかる。
尿取りパッドというのは、老人のそれをいう。
それも一応、わかる。
わかるが、40代、50代の女性でも、
日常的に尿漏れを起こしている人は多い。
(男性は少ないと思うが・・・。)
しかしこれから先は、こういう注意書きが、どんどんと
ふえてくるのでは・・・?
要するに、「老人の入浴は、遠慮してくれ」と。
++++++++++++++++++++++
●嫌われる老人
このところどこへ行っても、老人の姿が目立つようになってきた。
温泉だけではない。
映画館でも、バス旅行でも、そしてレストランでも・・・。
通りをふらふらと歩いている老人も、目立つようになってきた。
やがて75歳以上の、後期高齢者の数が、人口の3分の1、つまり
3人に約1人になると言われている。
そうなったとき、私たち老人族は、どう扱われるのか。
想像するだけで、さみしくなる。
老人は、老人特有の臭いがする。
いわゆる「加齢臭」というのである。
映画館へ入ったようなとき、それがプンと臭うときがある。
そういう臭いがすると、(私たち自身も老人の仲間なのだが・・・)、即、席をかわる
ようにしている。
が、それは明日の、私たち自身の問題でもある。
やがて映画館の入り口にも、こういう注意書きが並ぶようになるかもしれない。
「加齢臭のある方の入場は、お断りします」と。
が、それはしかたないとしても、マナーの悪い老人が多いのも事実。
気力が弱くなるせいか、自分で自分を律することができなくなる。
痰を吐く。
服装がだらしなくなる。
入浴の仕方が、いいかげんになる。
態度が横柄になる。
マナーを守らなくなる。
もちろん加齢臭を放つ。
つい先日は、コンビニで、ウンチを漏らしたまま歩いている老人を見かけた。
ズボンの後部が、下痢か何かで、べっとりと汚れていた。
そういう老人が、コンビニで買い物をする!
世の中がそういう老人を受け入れてくれればよい。
「老人というのは、そういうもの」と理解してくれればよい。
が、そうは寛大ではない。
寛大でないことは、若い人たちのBLOGを読めば、よくわかる。
「昨夜、車をぶつけられた。相手は70のクソジジイだった」とか何とか。
「老人」というだけで、白い目で見られる。
差別される。
こうした傾向は、今後加速することはあっても、減速されることはない。
●新たな老人問題
今はまだ、社会のほうも遠慮している。
表だって、老害論を説く人は少ない。
しかしこうした(やさしさ)も、いまや、風前のともしび。
そのエネルギーは、爆発寸前といってもよい。
温泉にしても、映画館にしても、バス旅行にしても、さらにレストランにしても、
そのうち年齢制限が設けられるようになるかもしれない。
「65歳以上の方は、ご遠慮ください」とか、なんとか。
さらに深刻な問題として、(事実、そうなりつつあるが・・・)、がんなどの重病の
ばあい、ある一定年齢以上の老人は、治療そのものを拒否されるようになってきた。
私の実母も、実兄も、そして義兄も、それを経験している。
自分がそういう立場になったら、どうするか?
いさぎよく死ぬか?
その覚悟は、できているか?
今のままでは、あと10年を待たずして、全国の火葬場は、飽和(満員)状態に
なるという。
今の今でさえ、夏場や冬場には、3〜4日待ちというのは、当り前。
そこで東京都では、大型船を改造して、船そのものを火葬場にする構想まで考えられて
いる。
火葬場ですら、そうなのだから、そうなれば、老人は、満足な治療すら
受けられなくなる。
さらに一歩進んで、「もう、死んでください」となるかもしれない。
●老人よ、自分の存在価値を高めよう!
こうした老人問題に対処するためには、老人自身が、自分の存在感を高めることでしか
ない。
わかりやすく言えば、(価値ある老人)になること。
若い人たちから見て、「老人は必要な存在なのだ」と思ってもらえるような老人になること。
名誉や地位や財産ではない。
過去の名誉や地位をぶらさげれば、かえって嫌われるだけ。
(価値)である。
(存在価値)である。
そのための努力を怠ってはいけない。
代替的な方法として、「お金を貯める」という方法もあるかもしれない。
お金で老後を買う。
あるいは息子や娘に依存するという方法もあるかもしれない。
息子や娘にめんどうをみてもらう。
しかしこうした方法では、今度は、私たち自身の(生きがい)を満たすことはできない。
それについては、すでに何度も書いてきたので、ここでは省略するが、
やはり結論は、ここにくる。
「私たちは私たちで、自分の存在価値を高めるしかない」である。
+++++++++++++++++++++++++++
●親と子、意識のズレ
+++++++++++++++++
私が母に嫌われていると知ったのは、
私が40歳も過ぎてからではなかったか。
それまでは、そう思っていなかった。
母の気持ちを、みじんも疑わないでいた。
「母は、私を好いているはず」と。
しかも嫌われたのは、私が高校2、3年生のころ。
そのころの、私は、「荒れた」。
気持ちがすさんでいた。
親というより、「家」そのものが、私には
負担だった。
居場所もなかった。
それに自分が進むべき方向さえ定まらなかった。
やや遅い思春期だったが、たぶん、母には、
それが理解できなかったのだろう。
数日おきに、「親に向かって何てこと言う!」
「うるさい、このバカヤロー!」と、まあ、
よく覚えていないが、そういうような言い争い
をよくしたと思う。
母は、悪玉親意識が強かった。
親風をよく吹かした。
が、それでも私は幻想を抱いていた。
「親だから……」という幻想である。
「親だから、どんなことがあっても、私を嫌う
はずがない」と。
しかしいつしか母は、私を恨むようになった。
私が結婚したことについても、そうだった。
「浜松の嫁に、息子を取られた」と、
親類にはもちろん、近所の人たちにまで、
泣きついていた。
+++++++++++++++++++++
●似たような話
冒頭に書いたのは、私と私の母についての話である。
しかし似たような話は多い。
たまたま今日も、耳にした。
こういう話である。
Aさん(女性、40歳くらい)は、現在、近くの特別養護老人ホームで介護師を
している。
その女性が話してくれた。
ひとりの老人(女性、80歳)がいるのだが、その老人は、ことのほか、自分の娘
(50歳)を嫌っている。
どう嫌っているかについては、ここに書いても意味はない。
が、介護師をしているその女性には、それがよくわかる。
が、肝心の娘には、それがわからないらしい。
「自分が見舞いに来たことで、母親は喜んでいるはず」と思い込んでいる。
しかしその女性(80歳)は、娘が見舞いに来るのを、何よりもいやがっている。
●思い込み
だれにでも、(思い込み)というのはある。
一般的には、自己中心性の強い人ほど、思い込みがはげしい。
一度、「こうだ」と思い込んだら、そのワクから抜け出せない。
私「そういうのをありがた迷惑というんだよ」
ワ「そうね。でもその女性(50歳)には、わからないのよ」
私「どうしてだろ?」
ワ「親だから、娘の自分が見舞いに行けば、喜ぶはずと思い込んでいるのね」
私「……う〜ん、そういうケースは多いよ。ぼく自身が、そうだったからね」と。
(思い込みのはげしさ)という点では、よくストーカーが例にあげられる。
ストーカー行為を繰り返す男性にせよ、女性にせよ、(思い込み)から始まる。
「相手は、自分のことをきにかけているはず」
「相手は、自分のことを好きなはず」
「嫌っているフリをしているだけ」と。
親子の間でも、似たような(思い込み)が、起きることがある。
ここに書いた女性(50歳)も、その1人ということになる。
●なぜ、起きるか
こうした思い込みは、なぜ起きるか。
ほかによくある例が、うつ病タイプの人の思い込み。
このタイプの人は、ひとつのことにこだわり始めると、そのことばかり考えるようになる。
脳みそのカベに、そのことがペタリと張り付いたような状態になる。
その結果、取り越し苦労、ぬか喜びを繰り返す。
繰り返しながら、どんどんと深みにはまっていく。
では、私のばあいは、どうだったか。
ひとつには、これはずっとあとになってからワイフが教えてくれたが、私はかなりの
マザコンだったということ。
学生時代、野口英世の母、シカの手紙を読んで、涙をこぼしたことさえある。
窪田聡の『かあさんの歌』は、日本が誇る名曲と思っていたこともある。
森進一の歌う、『おふくろさん』でも、そうだった※。
しかし自分が親になってみて、急速に、私の中のマザコン性は、消えていった。
というより、仕事を通して、マザコンタイプの子どもたちを観察するうち、自分の中の
マザコン性に気がついた。
そのマザコン性は、乳幼児期の刷り込みによって、作られる。
人間にも、ある種の鳥類に見られるのと同じ、(刷り込み)があることが、わかってきた。
0歳から生後7か月前後までの期間と言われている。
この時期を、とくに「敏感期」と呼ぶ人もいる。
子どもは、こうして作られた(刷り込み)を基盤に、成長する。
成長しながら、修正する。
その鍵を握るのが、父親ということになる。
イギリスでは、『母親は子どもを産み育てるが、父親は、子どもに狩の仕方を教える』
と教える。
父親の役目は、(1)母子関係の是正と、(2)社会性の構築である。
が、その父親の存在感が薄いと、子どもは(刷り込み)を修正できないまま、マザコン化
する。
私のばあい、父親の存在感がきわめて薄い家庭に、生まれ育った。
●隠れマザコン
私「自分の中から、マザコン性が抜けないかぎり、親、とくに母親に対して、幻想を
もちつづけるだろうね」
ワ「理想の女性像を、母親に求めるわけね」
私「そう。だから、マザコンタイプの男性のばあい、離婚率が高いと言われている」
ワ「理想像を求められたら、妻だって疲れてしまうわ」
私「そう、まったく、そのとおり」と。
そのマザコン性が、子どもの側の心を盲目にする。
書き忘れないうちに書いておきたいことがある。
ふつう「マザコン」というと、「男性」を想像する人は多い。
しかし女性にも、マザコンは多い。
(ひょっとしたら、男性より女性のほうが多いかもしれない。)
男性のマザコンは目立つが、女性のマザコンは、同姓であるという点で目立たない。
たとえば母親と娘がいっしょに風呂に入っていても、それを「おかしいこと」と思う人
は少ない。
私は女性のマザコンを、「隠れマザコン」と呼んでいる。
●容赦なかった、私の母
私の母は、そういう母だったから、私からお金を(まきあげる)のは、平気だった。
「取る」とか、「奪う」などというようなものではなかった。
「まきあげる」。
容赦なかった。
長男が生まれたときも私のアパートへやってきて、母は、貯金全額を、
もって帰っていった。
私は私で、マザコンだったから、そういう母の行為をみじんも、疑わなかった。
母は、そのつど言葉巧みに、こう言った。
「私が、あなたの代わりに、貯金しておいてやる」と。
ワイフはそういう母を、薄々疑い始めていた。
が、私は、「ぼくたちがもっているより、安全だから」と、そのつどワイフを説得した。
そういう関係が、それからあと、25年以上もつづいた。
●その女性(50歳)
冒頭にあげた女性(50歳)のばあい、「自分は母親に好かれている、すばらしい
娘」と思い込んでしまっている。
母親への依存心も、その分だけ、強い。
自分が本当は嫌われているにもかかわらず、それすら客観的に判断することもできない。
そのため、自分勝手な行動を繰り返す。
その仕方は、被害者を追いかけ回す、ストーカーと、そっくり。
どこもちがわない。
で、この話には、つづきがある。
……というか、ここまで現在形で書いたが、実は、過去の話である。
最近(09年の春)、その女性(50歳)の母親が、他界した。
それについて、その女性(50歳)は、こう言っているという。
「施設に入れないで、私がめんどうをみてやればよかったア」と。
そして母親が他界したあと、毎週のように墓参りをしているという。
その女性(50歳)は、いまだに自分のことが、まるでわかっていない。
恐らく死ぬまで、自分の(思い込み)に気づくことはないだろう。
(はやし浩司 家庭教育 育児 育児評論 教育評論 幼児教育 子育て はやし浩司
マザコン 自己中心性 親の気持ちがわからない娘 刷り込み 敏感期 思い込み 思い
込みの激しい人 人の心がわからない人)
(注※…日本には、この種の「マザコン・ソング」が多い。
母親を実際以上に美化し、たたえ、そしてそこに理想的な女性像を織り込む。
すべてを許し、すべてを受け入れてくれるような女性である。
しかしそんな女性(=母親)など、どこにもいない。
いるはずもない。
本能的な母性愛というのは、子どもに対してのものであり、夫に対してのものではない。
またそういう女性を求めてはいけない。
もし「どうしても……」と考えるなら、どこかの寺の観音様でも拝んでくればよい。
……というのは言い過ぎかもしれない。
が、夫の側にマザコン性が強すぎると、その分だけ妻側に負担感がます。
この負担感が、夫婦関係そのものを、ぎくしゃくさせる。
おかしくする。
「マザコン男性の離婚率は高い」というのは、そういう理由による。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司
BW はやし浩司 マザコン マザコン夫 離婚率)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●8月29日
++++++++++++++++++
暑いといえば、暑かった。
しかし全体としてみれば、異常なほど、
涼しい夏だった。
その夏も、もう終わり?
気象庁の発表によれば、9月に入れば、
今度は残暑がきびしくなるとか。
今日は、8月29日、土曜日。
振り返ってみるが、今月も、何かと
あわただしく過ぎていった。
それだけ。
何かをやり残したという実感が、
ほとんど、ない。
たった今、大きなあくびが、出た。
このあくびが、この8月を象徴して
いる。
「これではいけない」と、気を引き締める。
やりたいことは、そこに山のようにある。
が、どれから手をつけたらよいのか、
わからない。
今日も、忙しい1日になりそう。
がんばるしかない。
自分の体に、ムチ打って……。
みなさん、おはようございます。
++++++++++++++++++
●老害問題(価値ある老人をめざして)
+++++++++++++++++++
やがて……というより、もうすぐ、「老害」
という言葉が、日常的に使われるようになる。
現に今、若い人たちの老人を見る目が、
大きく変わりつつある。
「そこにいる老人」から、「そこにいては
いけない老人」へと大きく変わりつつある。
彼らの目に映る老人の姿そのものが、ちがってきた。
今後、私たち老人を見る、若い人たちの目が、
きびしくなることはあっても、やさしくなることはない。
が、ともすれば私たちは、老人の立場で、
自分たちの未来をどう守ればよいか、
それだけを考えやすい。
しかし本当の問題は、高齢化社会を
どうすれば守れるかではない。
どうすれば若い人たちに受け入れられる老人に、
私たちがなれるか。
それが本当の問題。
こうした問題を総合して、「老害問題」と、
私は呼ぶ。
+++++++++++++++++++
●健康な老人
もう30年近くも前のこと。
当時の三世代同居家庭の若い母親たちを対象に、私は、
祖父母(=同居の舅、姑)に何を望むかというアンケート調査をしたことがある。
その結果、第一の答が、「健康であること」であった。
(ついでに、第二が、「子どもの教育に口出しをしないこと」。)
今、調査をしても、同様の結果が出ると思う。
私たち老人族は、第一に、健康でなければならない。
そのための努力を怠ってはいけない。
老人の問題は、その老人だけの問題ではない。
家族全体の問題である。
「迷惑をかけないからいい」という問題ではない。
(老人が同居している)ということ自体が、みなに迷惑をかけている。
もっと言えば、私たちが老人であること自体が、みなに迷惑をかけている。
つまり老人の問題は、自分のためというよりは、家族全体の「和」
のための問題と考えるべき。
こんなことを言う人がいた。
「親の介護が3年つづくと、兄弟姉妹はメチャメチャになる」と。
先日、健康診断に行ったら、そこにいた看護士の女性が、そう教えてくれた。
つまり介護問題はこじれやすく、それが原因で、兄弟姉妹関係がメチャメチャになる。
そういうケースが多い、と。
老人というのは、できるだけギリギリまで健康でいて、死ぬときは、さっさと死ぬ。
それが理想ということか?
要するに、家族には迷惑をかけない、ということ。
老人問題は、それに始まって、それに終わる。
……とまあ、書くのは簡単なことだが、実際には、そのようにうまくはいかない。
「死ね」と言われても、死ねるものではない。
さりとて生きていくのも、むずかしい……。
多くの老人は、最後は、「死ぬこともできないから、生きている」という状況に
追い込まれる。
わかっていても、どうしようもない。
それ以上に、私たちは無力。
加齢ともに、さらに無力になっていく。
●勤労寿命
人間には3つの寿命がある。
(1)絶対寿命、(2)平均寿命、それに(3)健康寿命。
絶対寿命というのは、その年齢を超えて生きることはないという寿命をさす。
現在、満130歳が、絶対寿命と言われている。
それ以上の年齢を生きた人はいない。
平均寿命については、すでにみなさんご存知のとおり。
問題は、健康寿命。
ふつう平均寿命から、10歳を引いた年齢が、健康寿命と言われている。
満84歳が平均寿命なら、健康寿命は、満74歳ということになる。
死ぬまでの、最後の10年は、病魔との闘いということになる。
そのため平均寿命を延ばすことも大切だが、健康寿命を延ばすことのほうが、
もっと大切。
健康というのは、(病気のない)状態をいう。
もう少しつっこんで言えば、(死の恐怖を感じない)状態をいう。
で、さらにこれら3つに、もうひとつ寿命を加えるとしたら、(4)勤労寿命というのも
ある。
いくら健康でも、庭いじりと、孫の世話だけで、老後を過ごせといっても無理。
老人には老人の生きがいが必要。
(生きがい)なくして、長い老後を生き延びることはできない。
その(生きがい)となると、働くことを考えるのが、いちばんわかりやすい。
働くことによって、私たちは社会とのつながりを維持することができる。
その働ける限界を、「勤労寿命」という。
勤労寿命は、健康寿命からさらに10年を引いた年齢をいう。
健康寿命が、満74歳なら、満64歳ということになる。
●徴兵制
これから書くことは極論ということは、私もよく承知している。
あくまでもひとつの(例)として理解してほしい。
その上で、私は、こう考える。
現在、世界で、徴兵制を敷いていない国は、そうはない。
とくにこのアジア地域で、徴兵制を敷いていない国は、この日本だけ。
だからといって、徴兵制を敷けということではない。
それに賛成しろというのでもない。
しかしこの日本が、かろうじて平和を維持できているのは、日本人がそれだけ平和的
であるからではない。
平和を守っているからでもない。
さらに言えば、日本人のもつ哲学観が、それだけすぐれているからでもない。
戦後、65年の長きにわたって、日本が平和を守れたのは、たまたまアメリカ軍という、
世界最強の軍隊が、日本に駐留しているからにほかならない。
あるパキスタン人(友人)は、こう言った。
「日本が核武装していないだってエ? とんでもない。そう思っているのは、君たち
だけだ。君たちの国には、アメリカ軍が駐留しているではないか」と。
つまり日本以外の世界の人たちは、「日本は核武装している」と、思っている。
核武装していないと思い込んでいるのは、この日本人だけ。
『核の傘』というのは、そういう意味である。
日本の平和というのは、言うなれば薄氷の上に立った楼閣のようなもの。
さらに言えば、日本という国は、丸裸のうさぎのようなもの。
で、こうした事実を冷静に積み重ねていくと、その先に浮かび上がってくるのが、
「徴兵制」ということになる。
その徴兵制について、たとえばこんな徴兵制はどうか。
「満60歳になったら、5年間、徴兵義務を負う」と。
これに対して、「老人に戦争は無理」と思う人も多いかと思う。
しかしそれは、使用する武器の問題。
年齢の問題ではない。
老人用に、携行する武器を軽くするとか、いくらでも方法はある。
今では戦争の仕方も、大きく変わってきた。
戦闘機は無理でも、戦車くらいなら、私でも操縦できる。(……と思う。)
それに若い人たちを戦場へ送るよりは、はるかに合理的。
若い人たちには、(未来)という人生がある。
が、私たち老人には、すでに(過去)という人生しかない。
若者が死ぬか、老人が死ぬかと問われれば、私たち老人が死んだ方がよい。
もし「満60歳になったら、5年間、徴兵義務を負う」ということになったら、
私たち老人を見る若い人たちの目も、少しは変わってくるのではないだろうか。
徴兵制を例にあげたが、これはあくまでも(例)。
老人たちにも、しなければならないことがある。
できることがある。
それが(老人)ということになる。
●老害問題(私たちが老害にならないために……)
私は(老害問題)を考えるたびに、そこにあのユダヤ人問題を重ね合わせてしまう。
第二次大戦前のドイツと、現在の日本は、よく似ている、と。
戦前のドイツには、ユダヤ人たちが、1千万人単位で住んでいた。
そういうユダヤ人たちが、ドイツ社会に同化することもなく、自分たちの宗教をもち、
自分たちの言葉で話した。
ドイツの経済を牛耳るようになった。
もちろんドイツが迎えた人たちではなかった。
そのほとんどは、今で言う、違法難民であった。
その結果、こうした事実が、あの忌まわしい、ユダヤ人虐殺へとつながっていく……。
問題は、あれほどまでに高い文化を誇った、ドイツで、そういう虐殺事件が起きたという
こと。
多くの日本人は、「日本人は、あんな残虐なことはしない」とか、「日本人の私たちは
ちがう」と思っている。
しかし本当に、そうか?
そう断言できるか?
ユダヤ人虐殺事件はともかくも、これからの日本で、似たような事件が起きないか、
私はそれが心配でならない。
3人に1人が、75歳以上の後期高齢者になったとき、ひょっとしたら、老人排斥運動
が始まるかもしれない。
表立った行動をする人はいないだろうが、人々の心の奥深くで、それは静かに進行する。
現に今、医療機関において、後期高齢者に対する治療拒否などの問題が、起きつつある。
●やるべきことを見つけよう!
老人たちよ、けっして今の立場に安住してはいけない。
安住したまま、若い人たちを、上から見下ろしてはいけない。
老人たちだけの別世界を作り、自分たちをその中に隔離してはいけない。
たとえばこんな光景を想像してみるとよい。
あるみやげものセンターに、一台の大型のバスが止まった。
見ると、60歳以上の老人たちが、ゾロゾロとバスを降りてくる。
どこかの観光地を回ってきた団体である。
一方、みやげものセンターでは、20代、30代の若い人たちが、声を張り上げて、
こう連呼する。
「いらっしゃいませ!」と。
せわしく動き回りながら、老人たちの落とすお金を、ねらっている……。
こういう光景が、ごく日常的なものになったとき、はたして私たちは、それを
望ましい社会の姿と言ってよいのだろうか。
もちろん老人には老人の言い分がある。
それはよくわかる。
わかるが、しかしそうした言い分だけでは、若い人たちが感じ始めている矛盾を、
溶かすことはできない。
老人は老人で、自分たちが生きてきた人生を、若い人たちに還元していかねば
ならない。
「命」を、還元していかねばならない。
「還元」という言葉は、藤沢市に住むI先生が教えてくれた言葉である。
すばらしい言葉だ。
知恵や知識を伝え、人生の先輩として、どう生きるべきかを伝えていく。
それをしてはじめて、私たちは、「老人」と胸を張ることできる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 B
W はやし浩司 命の還元 老人問題 はやし浩司 老害)
W はやし浩司 命の還元 老人問題 はやし浩司 老害)
【3】(近ごろ、あれこれ)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●分かっていないのは、だれ?
++++++++++++++++++++
NIKKEI NEWSは、
つぎのように伝える。
『麻生太郎首相は25日、宮城県多賀城市で街頭演説し「政治はばくちじゃない。(民主党
に)ちょっとやらせてみようか、というのは違う話だ。全く優先順位が分かっていない人
が多すぎる」と、いら立ちを見せた。報道各社が衆院選情勢調査で自民党の劣勢を伝えて
いることが背景にあるとみられる』(Nikkei NEWS 09年8月26日)
++++++++++++++++++++
●方向音痴
「もう、いやだ」「たくさん」というのが、浮動票層の本音。
選挙もせず、政権をたらい回しにし、あれこれと理由にもならない理由をこじつけて、
政権の座に居座りつづけている……。
そういうAS首相に、生理的嫌悪感すら覚える。
むしろ浮動票層の私にしてみれば、いまだにAS内閣の支持率が、20%前後も
あるということのほうが、驚き。
だれが、いつ、どこで、AS首相を支持した?
裏工作に裏工作を重ね、自分で勝手に総理大臣の椅子を手にしただけではないのか?
まったく分かっていないのは、AS首相本人。
「この怒り、どこに向かうべきか」(尾崎豊「卒業」)。
本来なら、行き過ぎた民主党支持に対して、ブレーキをかけるのが、私たち浮動票層
の役目。
ふつうなら、「民主党のひとり勝ちはよくないぞ!」と。
しかし今度ばかりは、そのブレーキが働かない。
理由の第一は、AS首相自身にある。
民主党は300議席以上を確保するだろうと言われている。
が、このままでは、300議席ではなく、320議席以上。
そういう数字も視野に入ってきた。
ところで、私とワイフは、年間、49万円近い国民健康保険料を支払っている。
7回に分けて支払っているので、1〜2か月ごとに7万円!
もうすぐ国民年金が手に入る年齢になるが、国民年金は、月額6万3000円。
わかるか?
たったの6万3000円。
2人で、13万円弱!
国民年金など、国民健康保険料だけで、吹っ飛んでしまう。
こんなバカげた国が、どこにある。
……と、みなが、思い始めている。
今に、自営業を営む人は、ひとりもいなくなるぞ!
この怒り、どこに向かうべきか!
それが今度の総選挙ということになる。
Hiroshi Hayashi++++++++AUG.09+++++++++はやし浩司
●意識vs無意識
++++++++++++++++++++++
簡単に説明してみよう。
まず、意識を、(意識)と(無意識)に分ける。
今どき、こんな単純な分け方をする人はいないが、ここではそうする。
つまり(今、意識している意識)を、(意識)という。
それに対して、意識できない意識、それを(無意識)という。
(意識)というのは、わかりやすい。
今、あなたは考えたり、思ったりしていることが、(意識)ということになる。
では、無意識とは何か。
それがわかりにくい。
平たく言えば、それ以外の、表に出てこない意識を、(無意識)という。
これを簡単に図示すると、つぎのようになる。
――――
意識
====
無意識
――――
意思として自覚する(意識)。
意識として自覚しない(無意識)。
今は、そう考えて、話を先に進める。
ここで、それぞれの強弱を、仮に3段階に分けてみる。
するとそれぞれの組み合わせは、9通りになる。
(意識が強くて、無意識が強い人)、(意識が強くて、無意識が中くらいの人)、
(意識が強くて、無意識が弱い人)……、と。
その中でもわかりやすいのを、3通り、ここに書き出してみる。
(1)(意識・強)−(無意識・強)……精神力の強固な人
(2)(意識・中)−(無意識・中)
(3)(意識・弱)−(無意識・弱)……精神力の軟弱な人
そこでさらに一歩、話を進めてみる。
たとえば(意識が強くて、無意識が弱い人)と、反対に(意識が弱くて、
無意識が強い人)を考えてみる。
(4)(意識・強)−(無意識・弱)……臨機応変に自由に行動できる人
(5)(意識・弱)−(無意識・強)……がんこで、融通がきかない陽と
たとえば、たいへんがんこな子どもがいる。……いたとする。
一度、こうと言い出したら、テコでも動かなくなるタイプである。
たとえばこんな子ども(年中児)がいた。
幼稚園でも、自分の座る席が決まっていた。
それ以外の席には、座らなかった。
先生がいくらていねいに指導しても、「ぼくは、この席!」と譲らなかった。
ズボンもそうだった。
毎日、幼稚園へはいていくズボンが決まっていた。
「青いズボン」と決めると、毎日、そればかりをはいて、幼稚園へ出かけた。
母親が、いくらほかのずぼんを勧めても、それは、はかなかった。
こうした(こだわり)は、自閉傾向(自閉症児のことではない)のある子どもに、
共通して見られる症状である。
いわゆる(根性)とちがうところは、(理由)がないということ。
理由もなく、「この席でないといやだ」とか、「青いずぼんでないといやだ」とか言って、
カラにこもる。
このタイプの子どもは、(意思の力)というよりも、その子どもを裏から操る、
(無意識の力)のほうが、強いということになる。
先の分類法によれば、(5)の(意思・弱)−(無意識・強)というのが、それに当たる。
●(意識・強)−(無意識・弱)
反対に、意識が強く、無意識の力が弱いばあいは、どうか。
このばあいは、意識できる意思が強く、無意識の世界からの影響を受けないので、
臨機応変に、自分で考えて、自由に行動する。
無意識の世界から、いろいろな命令があがってきたとしても、それすらも、自分の
意思でコントロールしてしまう。
ただ誤解していけないことは、無意識の力が弱いからといって、それだけ無意識の
世界が狭いということではない。
脳のもつキャパシティは、同じと考えてよい。
●発達段階
これらのことは、子どもの発達段階を観察してみると、納得がいく。
いわゆる3〜4歳期の、幼児期前期の子どもを観察すると、(言われたことをきちん
と守る)という習性があるのがわかる。
何か母親が言ったりすると、「幼稚園の先生がこう言ったから」と、かたくなに
言い張ったりする。
最初にきちんとした形で入った情報を、絶対的と思い込む。
そのため、この時期は、(しつけ)がしやすい。
エリクソンは、「自律期」と呼んでいるが、それはそういう理由による。
しかしその幼児でも、満4・5歳を過ぎると、なにごとにつけ、急に反抗的に
なってくる。
母親が、「新聞をもってきて!」などと言うと、「自分のことは自分でしな」などと
言い返したりする。
つまり(決められたこと)を、自由な意思で、コントロールするようになる。
上記の分類法によれば、(4)の(意識の力が強くなり)−(無意識の力が弱くなった)
状態を考えればよい。
●思考の融通性
思考の融通性は、(意識の力)と(無意識の力)の強弱によって決まる。
意識の力が強く、無意識の力が弱ければ、融通性があるということになる。
これを(a)の人と呼ぶ。
反対に、意識の力が弱く、無意識の力が強ければ、融通性がきかなくなる。
ものごとに、よりこだわりやすくなる。
これを(b)の人と呼ぶ。
が、それはあくまでも相対的な力関係に過ぎない。
意識の力が弱い人でも、さらに無意識の力が弱ければ、融通性のある人ということに
なる。
このばあいは、軟弱な印象を、人を与える。
覇気がない。
何か指示すると、だまってそれに従ったりする。
同じ融通性がある人といっても、(a)の人のような、強い意識の力を感ずることはない。
●応用
この分類法を使うと、子どもの様態が、より明確に区分できるようになる。
たとえば、かん黙児の子どもについて言えば、(意識の力が弱く)−(無意識の力
が強い)ということから、上記(5)のタイプの子どもと位置づけられる。
反対に、AD・HD(注意力欠陥型多動性児)のばあいは、(意識の力が強く)−
(無意識の力が弱い)ということから、上記(4)のタイプの子どもと位置づけられる。
このことは年齢を追いかけながら、子どもを観察してみると、よくわかる。
たとえばかん黙児の子どもにしても、AD・HD児にしても、加齢とともに、症状が
緩和されてくる。
自己管理能力が発達し、自分で自分をコントロールするようになるためである。
で、そのとき、かん黙児の子どもにしても、(がんこさ)はそのまま残ることは多い。
一方AD・HD児のばあいは、もちまえのバイタリティが、よいほうに作用して、
自由奔放な子どもになることが多い。
モーツアルト、チャーチル、エジソン、さらには最近では、あのアインシュタインも、
子どものころ、AD・HD児だったと言われている。
●無意識の世界
話はぐんと変わるが、ダメ押し的な補足として、こんなことを書いておきたい。
催眠術という「術」がある。
あの催眠術を使って、被験者に、たとえば「あなたはキツネになった」と暗示をかけると、
あたかもキツネになったかのように、ピョンピョンとはねたりする。
こうした現象は、(意識の世界)が、(無意識の力)に支配されたことによって起こると
考えると、わかりやすい。
意識の世界で、いくら「私はキツネではない」と思っても、無意識の力の前では、
無力でしかない。
それだけ無意識の世界の力が強力であるとも考えられるが、言い換えると私たちは、
意識の力と、無意識の力の、絶妙なバランスの上で行動しているということになる。
意識の力だけで行動していると思っても、常に無意識の力の影響を受けている。
しかし意識の力だけで行動しているわけではない。
無意識の力だけで行動しているのでもない。
それをわかりやすくするために、上記(1)〜(5)の仮説を立ててみた。
「私」をよりよく知るための、ひとつのヒントにはなる。
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hay
ashi 林浩司 BW はやし浩司 無意識 意識 意識vs無意識論 意識の強弱)
Hiroshi Hayashi++++++++AUG 09++++++++はやし浩司
●学問のすすめ(福沢諭吉)
(未完成原稿)
++++++++++++++++++++++
いまだに学問を否定する人が多い。
それには、驚かされる。
本当に驚かされる。
学問無用論すらある。
(「学歴無用論」ではない。「学問無用論」である。)
「学問」という言葉に問題があるなら、「学識」
でもよい。
重要なのは、学識。
いくら学歴や学問を否定しても、学識まで
否定してはいけない。
++++++++++++++++++++++
●福沢諭吉
あの福沢諭吉は、こう書いた(『学問ノススメ』)
『天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と言えり。されば天より人を生ずるに
は、万人は万人皆同じ位にして、生れながら貴賎上下の差別なく、万物の霊たる身と心と
の働きをもって天地の間にあるよろずの者を資り、もって衣食住の用を達し、自由自在、
互いに人の妨げをなさずして、おのおの安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。されど
も今広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあり、
富めるものあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たるは、
何ぞや。その次第甚だ明らかなり』と。
『学問のすすめ』については、ウィキペディア百科事典には、つぎのようにある。
『・・・原則的にそれぞれ独立した17つのテーマからなる、初編から十七編の17の分
冊であった。 1872年(明治5年2月)初編出版。以降、1876年(明治9年11月
25日)十七編出版を以って一応の完成をみた。その後1880年(明治13年)に「合
本學問之勸序」という前書きを加え、一冊の本に合本された。その前書きによると初出版
以来8年間で、合計約70万冊が売れたとの事である』(ウィキペディア百科事典より抜粋)
と。
●1872年(明治5年2月)
1872年(明治5年2月)というから、2009−1872=137年前ということ
になる。
遠い昔に思う人もいるかもしれないが、137年というのは、私の年齢(61歳)に
してみれば、たったの2倍強にすぎない。
で、この137年の間に、教育、教育を取り巻く環境、人々の教育観は大きく変わった。
といっても、明治の昔にはどうであったか。
それについては、ただ想像するだけでしかない。
が、手掛かりがまったくないかというと、そうではない。
私のばあい、子どものころを思い出せば、その片鱗をかぎ取ることができる。
●学歴時代
学問を鼓舞するために、学歴が利用された。
あるいは江戸時代の身分制度を、別の形で温存させるために、学歴が利用された。
明治の終わりですら、東大生のほとんどが、華族、士族、豪商の子弟たちで占められた。
(詳しくは、別のところで……。)
そういういきさつはあるが、結果として、世界に名だたる学歴制度というの
が、日本に生まれた。
私が子どものころには、「学卒」、つまり大学卒と言われる人たちは、
それだけで一目置かれた。
ところが身近にいる人というと、学校の教師か、医者くらいなもの。
そのため学校の教師や、医者は、飛びぬけた存在だった。
「学校の先生がこう言った」と言うだけで、親たちですら、黙った。
●高学歴時代
それが今では、さらに一歩進んで、大学などというのは、当り前。
修士号か博士号をもっていないと、一人前に扱われないという時代になった。
それがさらに一歩進んで、今はもう、学歴をぶらさげて生きる時代ではない。
「学歴より中身」というわけである。
この意見には異論はない。
まさにそうあるべきだし、またそれが正しい方向ということになる。
が、こうした(流れ)に対して、その一方で、学問そのものを否定する人が多いのには
驚かされる。
(学歴の否定)が、一足飛びに、(学問の否定)につながっている(?)。
若い人を中心に、しかも中高校生あたりにも、そのように考える子どもは多い。
これには驚かされる。
●勉強より部活
たとえばこの浜松市あたりでも、約60%前後の中学生は、受験勉強すらしていない。
たいはんは、「部活でがんばって、推薦で高校へ入る」などと考えている。
「有名進学校なんか入ると、勉強でしごかれるから、いや」などと言う子どもも多い。
つまり頭から、勉強、つまり学問を否定してしまっている。
が、このことと、(学歴の否定)とは、まったく別問題である。
学歴というのは、あくまでも結果。
しかしいくら学歴を否定しても、学問、つまり学識まで否定してはいけない。
またそういう考え方は、まちがっている。
●50歳
満50歳前後になると、その人のそれまでの生きざまが、そのまま集約され、表に
出てくる。
それまでにどんな生き方をしてきたかが、大きな(ちがい)となって表に出てくる。
こんなことがあった。
それまでにほぼ20年ぶりに、X氏という名前の男性(私と同年齢)と会った。
通りで会って、そのまま喫茶店に入った。
しばらくは会話がはずんだが、そのあとがつづかない。
どんなことをしているのかと聞くと、X氏は、こう言った。
「趣味は、プロ野球の実況中継を見ること。
天気のよい日は魚釣り。
雨の日は、パチンコ・・・」と。
そういう生活が積み重なって、X氏は、X氏のような人物になった。
●学識
学識のある人からは、学識のない人がよくわかる。
が、学識のない人からは、学識のある人がわからない。
それはちょうど山登りに似ている。
どんな小さな山でも登ってみると、意外と視野が広いのがわかる。
下から見上げているときは、それがわからない。
だから学識のない人は、自分に学識がないことに気づかない。
「私も平均的だ」とか、「ふつうだ」とか、思ったりする。
だからといって、私には、学識がある。
X氏には学識がないと言っているのではない。
学識のあるなしは、相対的なもの。
学識のある人でも、さらに学識の高い人から見れば、学識の低い人ということになる。
恩師のTK先生から見たら、私など、いまだにヒヨコ以下かもしれない。
●学識の否定
その学識を否定する。
そうでない人には、信じられないような話だが、実際には、そういう人もいる。
ある人は、こう言った。
「林君、いくら偉くなっても、死ねばおしまいだよ。
10年もすれば、総理大臣ですら、忘れさられる」と。
名誉や地位についてはそうかもしれない。
しかし名誉や地位にしても、あとからついてくるもの。
その前に立つのが、(学識)ということになる。
学識は残る。
人から人へと、(心)の形で残る。
(そう言えば、たった今、インターネットを通して、こんなニュースが飛びこんで
きた。
あのおバカ首相が、またまた大失言。
昨日は、どこかで、「貧乏人は結婚するな」式のことを言った。
今日は、豪雨の被災地で、こう言った。
「引き続き捜索にあたっている方々が努力しておられると思うが、ぜひ遺体が
見つかるように今後とも努力をしていただきたい」と。
「行方不明者」と言うべきところを、「遺体」と言った。
あきれるというよりも、あのAS首相をながめていると、「学識とは何か」、
そこまで考えさせられる。)
名前を残すか、残さないかということになれば、AS首相は、確実に名を残す。
「自民党を解体した、最後の総理大臣」として。
つまり学識のあるなしは、名を残すかどうかということとは、関係ない。
あくまでも個人の問題。
個人の(知的世界)の問題。
●雲と泥
福沢諭吉は、「知的世界」の重要性を説いた。
なかんずく、「知的世界の広さ」の重要性を説いた。
『学問ノススメ』という本は、そういう本である。
『……今広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあ
り、富めるものあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥との相違あるに似たる
は何ぞや。その次第甚だ明らかなり……』と。
「人間はみな、同じ。同じだが、人によって、雲と泥ほどのちがいがある」と。
そのちがいは、何によって生まれるか。
それが、言わずと知れた、「学識」ということになる。
つまり学ぶことを忘れたら、人間は「サル」(福沢諭吉)になりさがる。
そこで……。
いきなり結論ということになるが……。
さあ、あなたも本を開こう。
考えよう。
そして文を書こう。
それは遠くて険しい道かもしれない。
しかしほんの少しでも視野が広がれば、あなたはそれを喜びに感ずるはず。
その喜びは、ほかのありとあらゆる喜びにまさるものであることを知るはず。
そしてそれこそが、人間が人間であるという証(あかし)ということになる。
●補記
福沢諭吉の時代から、ほぼ140年。
人間を取り巻く知的環境は、大きく変わった。
が、その分だけ、人間が賢くなったかといえば、それは疑わしい。
たとえばそのあと、日本人にしても、福沢諭吉が説いたように、もっと
知的世界を広め、磨いておけば、あの太平洋戦争はなかったかもしれない。
現在にしてもそうだ。
21世紀に入って10年にもなるのに、どうして今、武士道なのか?
福沢諭吉らは明六社に参画し、封建時代の清算を試みた。
が、それはきわめて中途半端なもので終わってしまった。
あるいはそれにつづく軍国主義の台頭とともに、しぼんでしまった。
ついでながら、たいへん興味深いのは、福沢諭吉が、あの『忠臣蔵』を、
批判しているということ。
たいした批判ではないのだが、当時としては、たいへんな批判だったにちがいない。
『学問ノススメ』の中の「赤穂不義士論」が、それである。
その中で福沢諭吉は、『国法の貴きを論ず」において、赤穂浪士の討ち入りは私的制裁で
あって正しくないと論じている。さらに、浅野内匠頭が切腹になったのに吉良上野介が無
罪になったことの不当性を、本来は幕府に訴えて、裁判により明らかにすべきであると論
じている』(第6編、ウィキペディア百科事典より抜粋)と。
これに対して、猛烈な批難の嵐が巻き起こった。
「義士を、批判するとは何ごとぞ!」と。
福沢諭吉は、「こうげきばり ちやうじやう ゑんきん けふはくじやう たうらい
ちうこく しんぺん あやう ばあい」(=攻撃罵言の頂上を極め、遠近より脅迫状の到来、
友人の忠告など、今は、ほとんど、身辺も危うきほどの場合に迫れり)」と書き残して
いる。
わかるかな?
赤穂の浪士たちは、暗殺劇を試みるのではなく、正々堂々と裁判で闘えばよかった
と福沢諭吉は説いた。
まさに正論である。
この正論に対して、福沢諭吉は、身の危険を感ずるほどの脅迫にさらされた。
『しんぺん あやう ばあい(身辺も危うき場合に迫れり)』と。
今でも、毎年12月を迎えると、『忠臣蔵』が、顔を出す。
NHKの大河ドラマとしても、繰り返し取り上げられている。
が、『忠臣蔵』が問題というのではない。
この(進歩のなさ)こそが、問題なのである。
140年を経た今でさえ、何も変わっていない。
それが問題なのである。
学識を磨くには、日々の鍛錬あるのみ。
立ち止まったとたん、学識は後退する。
(注:中途半端な原稿のまま、発表します。推敲、校正は、また後日します。ごめん!)
09年8月26日記)
(はやし浩司 家庭教育 育児 教育評論 幼児教育 子育て Hiroshi Hayashi 林浩司 B
W はやし浩司 学識論 福沢諭吉 赤穂浪士論 忠臣蔵)
W はやし浩司 学識論 福沢諭吉 赤穂浪士論 忠臣蔵)
Hiroshi Hayashi++++++++Sep.09+++++++++はやし浩司
●新しい試み(WEBCAMERAを使って、YOUTUBEに直接アプロード)
<object width="480" height="385"><param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/DXlPZOKLgbU&hl=ja&fs=1&color1=0xe1600f&color
2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen"
value="true"></param><param name="allowscriptaccess"
value="always"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/DXlPZOKLgbU&hl=ja&fs=1&color1=0xe1600f&color2=
0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always"
allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
++++++++++++++++++++
インターネットの世界には、「YOU STREAM」
というサービスがある。
これは言うなれば、私設の放送局のようなもので、
これを使うと、話したことが、リアルタイムで
HPなどにアプロードできる。
みなさんに楽しんでもらえる。
が、問題がある。
せっかくアプロードしても、1年を待たずして、
削除されてしまう。
(あるいは半年くらいか? 確かめていない。)
しかしこれでは使い物にならない。
一方、YOUTUBEのほうは、今のところ、10年前に
アプロードした動画も、そのまま残っている。
今後のことはわからないが、今のところ、息が長い。
が、これにも問題がある。
カメラに向かって話したことを、直接アプロード
する方法もあるらしいが、何度試しても、うまくいかない。
(どこかに操作ミスがあると思うが、それがよくわからない。)
そこで今は、一度、ビデオカメラに動画を収めて、
編集したのち、YOUTUBEにアプロードしている。
が、これには、けっこう時間がかかる。
10分程度の動画をHPに載せようとすると、
編集するのに、5〜8分。
ファイル変換に、3〜4分。
アプロードするのに、7〜8分。
どんなにはやくやっても、計30分前後もかかって
しまう。
そこでいろいろ考える。
手元に「防犯24時」というソフトがある。
XPパソコン時代に購入したもので、今でも
使えるかどうかわからない。
しかしこの「防犯24時」には、撮った動画を
即、ファイル化してくれる機能がついている。
それを使えば、あとはYOUTUBEにアプロード
するだけ。
そうすれば、毎朝、文章ではなく、生の
声で、「みなさん、おはようございます」と
話しかけることができる。……はず。
試してみない手はない。
朝のルーティーン(日常行事)が終わったら、
さっそく試してみたい。
アプロードした動画は、別枠で新設した
BLOG上で、公開するつもり。
ともかくも、8月27日。
みなさん、おはようございます!
今日はやや湿った空気。
どこか肌寒さを感じるが、心地よい。
もうすぐ9月だなあと、今、そう思った。
+++++++++++++++++++
(追記)
たった今、WEBCAMERAを使って、
直接動画を、YOUTUBEにアプロードしてみた。
今度は、うまくできた。
が、音声がうまく録音できない。
マイク自体の性能が悪いのか?
設定が悪いのか?
どうであるにせよ、あとは小さな問題。
よかった!
……と、自分で喜んでいる。
ハハハ。
+++++++++++++++++++++
(追記2)
結局、5回トライアルしてみた。
音声が録音されない原因はよくわからないが、マイクは、ヘッドフォンのもの、
スピーカーは外付けの大型のものを、それぞれ使っている。
それが原因ではないか?
……ということで、いろいろ試行錯誤の結果、やっと満足に録画、録音できるように
なった。
この日記に添えて、YOUTUBEでのあいさつ、第一号をBLOGに公開してみる。
ホ〜〜ッ!
Hiroshi Hayashi++++++++AUG.09+++++++++はやし浩司
●60キロ(肥満論)
+++++++++++++++++++
体重が60キロになった。
(4か月前には、68・5キロ!)
喜んでいたら、義兄も60キロという。
妻の義姉も、60キロという。
見ると、義兄のほうは、丸々と太っている。
腹もポカリと丸く突き出ている。
「兄さんが、……それで60キロ?」と驚いていると、
「そうだと」と。
横にいた義姉も、「私もよ・・・」と言った。
それを聞いて、笑った。
同じ60キロといっても、太り方は、さまざま。
義兄のばあいは、小さな相撲取りといった風。
メタボリック。
見た感じでは、70キロ以上。
一方、義姉は、典型的なずん胴(ごめん!)。
私のばあいは、このところ骨と皮だけといった
風になってきた。
同じ60キロなのに、どうしてみな、太り方が
ちがうのだろう?
義兄と私は、身長は、それほど変わらない。
++++++++++++++++++++
●太り方
「りんご太り」とか、「洋ナシ太り」とかいう言葉がある。
内臓脂肪の付き方で、太り方がちがってくるそうだ。
「りんご太りのほうはよくないが、洋ナシ太りはよい」とか、言う。
正確には・・・
リンゴ型肥満(内蔵脂肪型)・・・ビール腹とも言われる。
中年男性に多い太り方。
内臓につく脂肪は生活習慣病を引き起こしやすいと同時に、
体内で悪玉物質の量を増やすので、糖尿病、脳梗塞、高血圧など、
成人病にかかる確率も、非常に高くなるといわれている(All About HP)。
洋ナシ型肥満(皮下脂肪型)・・・お尻、下腹、太ももなど下半身を中心に脂肪がつき、
女性に多く見られる太り方。
皮下脂肪は妊娠や出産時のエネルギー源となるため、あまり減らしすぎても危険だが、
皮下脂肪が蓄積されて代謝されないままでいると、セルライトができやすくなるので
注意が必要(同HP)。
そこで私は、そもそも「りんご」とか「洋ナシ」という言葉が、日本人の体形には
合っていないのではないかと思うようになった。
りんご太りは、「たぬき太り」「太鼓腹太り」「すいか腹太り」と言い換えればよい。
洋ナシ太りは、「ずん胴太り」「短足太り」「アヒル太り」と言い換えればよい。
アメリカで見る洋ナシ太りの人は、見るからに、それとわかる。
体の前部と後部の両方に、お尻がついているといった風。
日本人には、ああいう体形の人は、珍しい。
(最近、ふえてきたようには思うが・・・。)
要するに、肥満は健康に悪いということ。
太り方は、そのあとの問題ということになる。
そこで私の哲学。
『食べたら損(そこ)ねるのか、食べなければ損(そん)なのか』。
結局は、そこへ行きつく。
よけいに食べれば、損(そこ)ねる。
食べたら、損(そん)なのである。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
はやし浩司のホームページ http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
***********************************
このマガジンがお役にたてそうな人が、あなたのまわりにいませんか?
よろしかったら、どうか、このマガジンのことを、お友だちの方に
話していただけませんか?
よろしくお願いします。 はやし浩司
***********************************
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
まぐまぐプレミア版(有料版)のお申し込みは……
http://www2.wbs.ne.jp/~hhayashi/page141.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. *※※
.※※ ***※
.*※※…※}※**
. **++ ※))
. {※}※※ /
. ※*… /mQQQm
.**/| |Q ⌒ ⌒ Q Bye!
. = | QQ ∩ ∩ QQ
. m\ ▽ /m〜= ○
. ○ 〜〜〜\\//
.=================================
.みなさん、次号で、またお会いしましょう!
.=================================
|
